
東京の片隅で、女手一つで薬局を営んできた吟子。手塩にかけた娘・小春が結婚することになって、寂しいやら、うれしいやら、複雑な気持ちだ。
一つ気がかりは、所在のわからない不出来な弟・鉄郎。小春の名付け親にもなっているが、立派な叔父とは到底言い難い。酒を飲んでは失敗を繰り返し、厄介者扱いされてきた。きっと小春の晴れ姿を見たいだろうが、所在がわからないのではしようがない。
結婚式当日、小春の幸せな笑顔が曇る。突然、おじちゃんはやってきた。そして、案の定披露宴を酒でめちゃめちゃにしてしまう。顰蹙そのものだが、さすがの鶴瓶!このときの話芸がうますぎ。
詰まんないスピーチ聞かせられるより、よっぽどおもろいと思ったのだが、そうもいかないらしい。台風でも巻き起こしたかのようにした、鉄郎は兄から絶縁状を突きつけられ、また消える。
家族の縁は切れそうで、切れない。ごんたくれで、どうしようもなくて、半径1m以内には来ないで!と思っても、そうはいかない。親と子のように、無条件でつながっている絆とは違う。断つことは出来ない同士のような、親友のような、同じ根っこを持つ、それが兄弟の絆のようなものか。
ごんたくれの弟は、また姉に面倒をかけ、今度こそ姉にも愛想をつかされるが、姉が見捨てることはなかった。しかし、再会した弟は、病に侵され余命いくばくもなかった・・・。
鶴瓶のうまさが光る、光る、光る。落語家なのか、司会者なのか、役者なのか、この人は一体何なんだろう・・・と悩むところだが、才能がありすぎて、器用貧乏だったのかもしれない。
少々特異な風貌で、見た目にインパクトが強かったのだが、そのインパクトが薄くなってからの映画で見せる演技は絶品だ。自分が要求されてることをわかりきってる。そして、それを見事に伝える力量はなかなかだ。
普通に高座にあがった鶴瓶師匠の落語をぜひ聞きたいのだが、聞けるのかな。
先日、伊勢谷祐介と対談している番組を見たのだが、自分の本業はあくまで落語。いままでいろんなことをしてきたが、そのいろんなことが今の自分の身になってる。それが落語に生かせる。無駄なものは何もなかった・・・みたいなことを言ってたのだが、こうなったら見たいのは、聞きたいのは落語だ。ぜひ落語を!
物語は、家族に一人くらいはいる厄介な奴。こればっかりはどうしようもない。まったくもう!!と思いながら、実際のところ、当の本人が一番困っているのかもしれない。人並みなことをやろうと思っても、やれない自分を歯がゆく思っているのは、自分だ。そのことを改めて感じた。
もう一つは、いかに死ねるか。誰しも迎える死にいかに向き合うか。向き合うことが出来るか。尊厳ある死を迎えることが難しい世の中になっているのは、根本的におかしいのではないかと思わせる昨今の状況。人間誰しもが、必ず迎える死にたいして、監督の一つの憧憬のようなものを感じた。
さて、相変わらずのお化け女優。吉永小百合嬢。平成も22年にもなったが、この人が出た瞬間、その場は昭和になる。いつまでも昭和だ。あの空気は一種異様にも感じられるほど、時間が止まってる。それがいいのか悪いのかはあたしには判断不能。それにしても、あの髪型はないんではないのかと・・・・。
絶品は、加藤治子でしたね。嫁姑のやりとりは、山田節ならではでしょう。
と言うことで、鶴瓶のタレントぶりをはたまた堪能できる一品ですが、あたしは普通の人の加瀬君でありがとうございましたです。
上映は、1月末からです。
どうぞ、足をお運びください。
◎◎◎
「おとうと」
監督 山田洋次
出演 吉永小百合 笑福亭鶴瓶 蒼井優 加瀬亮 小林稔侍 森本レオ 茅島成美 ラサール石井 佐藤蛾次郎 池乃めだか 田中壮太郎 キムラ緑子 笹野高史 小日向文世 横山あきお 近藤公園 石田ゆり子 加藤治子
一つ気がかりは、所在のわからない不出来な弟・鉄郎。小春の名付け親にもなっているが、立派な叔父とは到底言い難い。酒を飲んでは失敗を繰り返し、厄介者扱いされてきた。きっと小春の晴れ姿を見たいだろうが、所在がわからないのではしようがない。
結婚式当日、小春の幸せな笑顔が曇る。突然、おじちゃんはやってきた。そして、案の定披露宴を酒でめちゃめちゃにしてしまう。顰蹙そのものだが、さすがの鶴瓶!このときの話芸がうますぎ。
詰まんないスピーチ聞かせられるより、よっぽどおもろいと思ったのだが、そうもいかないらしい。台風でも巻き起こしたかのようにした、鉄郎は兄から絶縁状を突きつけられ、また消える。
家族の縁は切れそうで、切れない。ごんたくれで、どうしようもなくて、半径1m以内には来ないで!と思っても、そうはいかない。親と子のように、無条件でつながっている絆とは違う。断つことは出来ない同士のような、親友のような、同じ根っこを持つ、それが兄弟の絆のようなものか。
ごんたくれの弟は、また姉に面倒をかけ、今度こそ姉にも愛想をつかされるが、姉が見捨てることはなかった。しかし、再会した弟は、病に侵され余命いくばくもなかった・・・。
鶴瓶のうまさが光る、光る、光る。落語家なのか、司会者なのか、役者なのか、この人は一体何なんだろう・・・と悩むところだが、才能がありすぎて、器用貧乏だったのかもしれない。
少々特異な風貌で、見た目にインパクトが強かったのだが、そのインパクトが薄くなってからの映画で見せる演技は絶品だ。自分が要求されてることをわかりきってる。そして、それを見事に伝える力量はなかなかだ。
普通に高座にあがった鶴瓶師匠の落語をぜひ聞きたいのだが、聞けるのかな。
先日、伊勢谷祐介と対談している番組を見たのだが、自分の本業はあくまで落語。いままでいろんなことをしてきたが、そのいろんなことが今の自分の身になってる。それが落語に生かせる。無駄なものは何もなかった・・・みたいなことを言ってたのだが、こうなったら見たいのは、聞きたいのは落語だ。ぜひ落語を!
物語は、家族に一人くらいはいる厄介な奴。こればっかりはどうしようもない。まったくもう!!と思いながら、実際のところ、当の本人が一番困っているのかもしれない。人並みなことをやろうと思っても、やれない自分を歯がゆく思っているのは、自分だ。そのことを改めて感じた。
もう一つは、いかに死ねるか。誰しも迎える死にいかに向き合うか。向き合うことが出来るか。尊厳ある死を迎えることが難しい世の中になっているのは、根本的におかしいのではないかと思わせる昨今の状況。人間誰しもが、必ず迎える死にたいして、監督の一つの憧憬のようなものを感じた。
さて、相変わらずのお化け女優。吉永小百合嬢。平成も22年にもなったが、この人が出た瞬間、その場は昭和になる。いつまでも昭和だ。あの空気は一種異様にも感じられるほど、時間が止まってる。それがいいのか悪いのかはあたしには判断不能。それにしても、あの髪型はないんではないのかと・・・・。
絶品は、加藤治子でしたね。嫁姑のやりとりは、山田節ならではでしょう。
と言うことで、鶴瓶のタレントぶりをはたまた堪能できる一品ですが、あたしは普通の人の加瀬君でありがとうございましたです。
上映は、1月末からです。
どうぞ、足をお運びください。
◎◎◎
「おとうと」
監督 山田洋次
出演 吉永小百合 笑福亭鶴瓶 蒼井優 加瀬亮 小林稔侍 森本レオ 茅島成美 ラサール石井 佐藤蛾次郎 池乃めだか 田中壮太郎 キムラ緑子 笹野高史 小日向文世 横山あきお 近藤公園 石田ゆり子 加藤治子










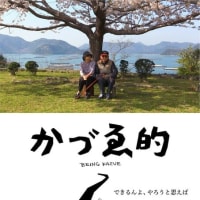
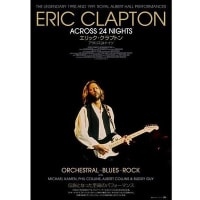
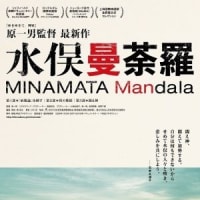
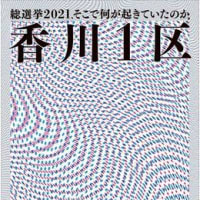






でも私はこの脚本が全面的にダメでした。古過ぎるです…。
それがサユリストにはたまらないんでしょうね、きっと。
そういった人たちには、絶対に必要な映画なんすよ、こういうのは。
蒼井優ちゃんが、ハマってたのが、発見でした。やっぱ女優さんですね。
TB&コメント、ありがとうございましたm(__)m
山田監督、現代劇は久しぶりだということですが、
この種のテイストは逆に時代劇仕立てにした方が、
感情移入がしやすいかも。
鶴瓶は鶴瓶で特に演技らしい演技ではないですが、
彼のは落語というより、座布団の上で漫談って感じですね(笑)
師匠にお前は落語なんかせんでえぇと言われていた
あのねのねあがりですから(笑)
ま、それでも見せるのは監督のうまさだなあと改めて感じましたが。
市川監督の「おとうと」に対するオマージュと言うことで、今回はこれでいいとは思います。
鶴瓶サンですが、自分的にはかなり自身ありそうでしたよ。自分は落語家なんだ!って。
なモンで、いっそう見て見たいと思ったのでした。
観終わって心の中でかみしめました。
私は多分、古いタイプの人間なんでしょうね。
知らず知らずのうちに、鶴瓶さん演じるてっちゃんに、自分の姿を重ねて見ていました。
ホスピスの所長(小日向さん)や千秋さん(石田ゆり子)の「もう少しで、楽になるからね~」に涙を堪え切れませんでした。
ラストの加藤治子さんのセリフも、優しかったですね・・。
私にとっては、何年に1本出会えるかどうかの、心に残る映画となりました。
母にせがまれて連れて行ってきました。
感想はsakuraiさんとほぼ同じかな~
鶴瓶さん上手いですね~
「ディア・ドクター」とはまた違った
ほとんど素の落語のノリのような演技もありましたが
ラストの息を引き取るときの演技は凄かったです。
そして吉永小百合。
う~ん,いつも同じキャラしか演じないというのは
名女優といえるかどうか・・・・
ま,あのお方は存在そのものが奇跡みたいなものなので
それもアリなんでしょうね。
>この人が出た瞬間、その場は昭和になる。いつまでも昭和だ。
同感,同感!
それがいいのかどうかは,やはり人それぞれの感じ方でしょうね。
同じようなお顔と雰囲気の韓国女イ・ヨンエさんは
「親切なクムジャさん」で見事新境地にも挑戦されましたが
吉永さんはもうこのお年では無理でしょうし・・・。
>「こういう映画を観たかったんだ・・」
そう感じられることができたのは、よかったですね。
テーマがきちんとしていて、ぶれがないのがこの監督の持ち味だと思うのですが、それが素直に出ていたと思います。
だれしもが迎える死ですが、その死を尊厳をもって迎えさせたい・・・というホスピスの方々の気持ちも、とっても良かったです。
実際にモデルの施設も、あんな感じなんでしょうかね。
老いて、ますますさかんな山田監督!まだまだ良作を生み出す勢いを感じました。
ちゃんとお母さん孝行して、見習え・・・・ません。なは。
今度、「花のあと」がいかがでしょうか。
しっとりとした味わいでしたよ。
鶴瓶さんは、本当にうまいですよね。
すっかり役者になってしまいましたが、あの結婚式の独壇場は、落語家ならでは・・と思いました。
彼の落語、聞いたことないもんで、一度聞いてみたいです。
吉永さんは、本当に存在が奇跡みたいな人ですから、あのままでいいんでしょうね。
あの人に別のキャラを求める人はいないでしょうから。彼女には普遍の吉永小百合を演じてもらう。
それが吉永さんの生きる道でしょう。
イ・ヨンエさんねぇ。なるほど。
昔っから、学級委員長!みたいなのがぴったりの人でしたから、あのパターンへの挑戦は見事でしたね。
“それを言ったら映画が成り立たない”というだろう。でもある観客を「見るに耐えない」思いにさせておいて、映画が成り立ってもらっては困るのだ。
以上、大方の賛同は得られないことは承知で。