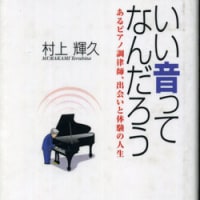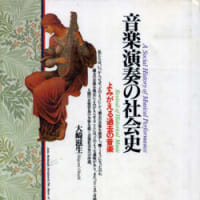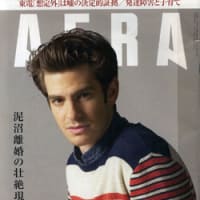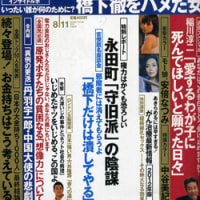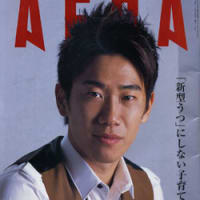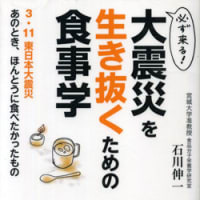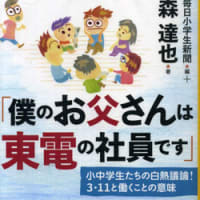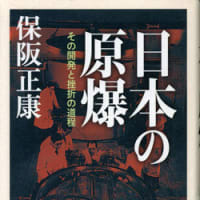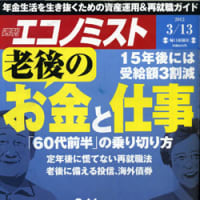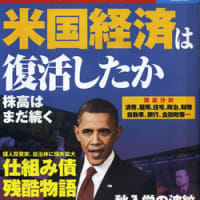『戦後日本の歴史-1945~1970-下』
藤井松一、大江志乃夫・著/青木書店1971年、1973年5刷
日本に限らず書かれてありました。たとえばキューバ革命。

曽野綾子、執筆拒否で協力。下「」引用。
「一組合役員の配置転換に端を発し、即日ロックアウトと組合役員一五人の解雇をもって争議にはいった「主婦と生活」社争議は、大宅壮一、亀井勝一郎、曽野綾子、有吉佐和子ら文芸家協会員三五○人の執筆拒否、広範な雑誌不買運動の展開、出版労協や全印総連の支援にささえられて、懲戒解雇の撤回、被解雇者はいったん依願退職ののち嘱託として再雇用される、など、組合側に有利な条件で妥結し、三一八日ぶりに解決した。-略-」
 index
index
--「六○年安保」。
三木武夫の脱落により反主流派の力はいちじるしく落ちたという。
岸刺される。下「」引用。
「右翼の老人が岸首相を官邸で刺し、傷をおわせた。傷ついた体をかつがれて岸の“引退の花道”であった。」
「農業基本法の成立」1960年。
アフリカの年といわれた1960年。
「原水禁運動の分裂」中国系vsソ連系の対立。下「」引用。
「しかし翌年の第八回大会では、会期中にソ連がおこなった水爆実験にたいし、「いかなる国の核実験にも反対」との立場から、大会の名で抗議せよという社会党系と、ソ連は平和勢力であり、抗議すべきではないとの大会主流派とが全面的にはげしく衝突し、あとの主張が通った。こうした混乱は六三年の大会にもちこされ、国際会議でも中国系とソ連系のはげしい論議が交わされ、また社会党・総評は参加せず、べつの集会をもつこととなった。六四年にはいるとり、状況は前年の米ソ合意による部分核停条約の評価の分裂、中国の核実験にたいする態度の対立を加えて、いよいよ複雑となった。」
 index
index
“核の傘” 下「」引用。
「ベトナム戦争の激化とともにアメリカの日本にたいする軍事的要求は大きなものとなった。六四年十一月十二日、日本国民の声を無視して佐世保に米原潜が入港したのを皮切りとして、六五年には原潜の佐世保入港は六回に及び、しかも八月にはサブロック搭載の原潜を寄港させた。十一月には、原子力空母エンタープライズの第七艦隊配属が発表され、政府はその寄港要請があったばあいは原潜寄港に準じて安全性を確認した上で寄港を認めるとの非公式態度を決定した。」
「核ならし」の政策。下「」引用。
「原潜寄港はしだいに周期を早め、日米を米原子力艦隊の基地とするために、日本国民の“核アレルギー”をなくしていこうとする、日米両国政府の「核ならし」政策であると考えられた。」
「エンタープライズ反対闘争」1968年。
倉石発言1968年2月。下「」引用。
「倉石農相は記者会見で、「なにしろ軍艦や大砲を背景に持たなきゃだめだよ。日本の憲法は他国の誠意と信義に信頼してと前文は書いてあるが、これじゃ、親鸞上人の他力本願だ……。佐藤首相も“平和憲法を守る”なんて口では言っているが、腹のかなではくすぐったいんじゃないか。こんなバカバカしい憲法を持っている日本は、他国のなさけにすがって生きるメカケみたいなもんだ……。日本も原爆もって三○万人の軍隊であったら……」と、発言した。現職の官僚が公務員の憲法尊重擁護の義務を規定した憲法第九九条に違反して、公然と憲法を誹謗し、核武装を説いたのであるから、世論の反撃はきびしかった。世論を背景として、野党は結束して倉石罷免を要求し、予算審議を急ぐ政府はついに倉石農相を辞任させた。」
 index
index
 index
index
 目次
目次


藤井松一、大江志乃夫・著/青木書店1971年、1973年5刷
日本に限らず書かれてありました。たとえばキューバ革命。

曽野綾子、執筆拒否で協力。下「」引用。
「一組合役員の配置転換に端を発し、即日ロックアウトと組合役員一五人の解雇をもって争議にはいった「主婦と生活」社争議は、大宅壮一、亀井勝一郎、曽野綾子、有吉佐和子ら文芸家協会員三五○人の執筆拒否、広範な雑誌不買運動の展開、出版労協や全印総連の支援にささえられて、懲戒解雇の撤回、被解雇者はいったん依願退職ののち嘱託として再雇用される、など、組合側に有利な条件で妥結し、三一八日ぶりに解決した。-略-」
 index
index--「六○年安保」。
三木武夫の脱落により反主流派の力はいちじるしく落ちたという。
岸刺される。下「」引用。
「右翼の老人が岸首相を官邸で刺し、傷をおわせた。傷ついた体をかつがれて岸の“引退の花道”であった。」
「農業基本法の成立」1960年。
アフリカの年といわれた1960年。
「原水禁運動の分裂」中国系vsソ連系の対立。下「」引用。
「しかし翌年の第八回大会では、会期中にソ連がおこなった水爆実験にたいし、「いかなる国の核実験にも反対」との立場から、大会の名で抗議せよという社会党系と、ソ連は平和勢力であり、抗議すべきではないとの大会主流派とが全面的にはげしく衝突し、あとの主張が通った。こうした混乱は六三年の大会にもちこされ、国際会議でも中国系とソ連系のはげしい論議が交わされ、また社会党・総評は参加せず、べつの集会をもつこととなった。六四年にはいるとり、状況は前年の米ソ合意による部分核停条約の評価の分裂、中国の核実験にたいする態度の対立を加えて、いよいよ複雑となった。」
 index
index“核の傘” 下「」引用。
「ベトナム戦争の激化とともにアメリカの日本にたいする軍事的要求は大きなものとなった。六四年十一月十二日、日本国民の声を無視して佐世保に米原潜が入港したのを皮切りとして、六五年には原潜の佐世保入港は六回に及び、しかも八月にはサブロック搭載の原潜を寄港させた。十一月には、原子力空母エンタープライズの第七艦隊配属が発表され、政府はその寄港要請があったばあいは原潜寄港に準じて安全性を確認した上で寄港を認めるとの非公式態度を決定した。」
「核ならし」の政策。下「」引用。
「原潜寄港はしだいに周期を早め、日米を米原子力艦隊の基地とするために、日本国民の“核アレルギー”をなくしていこうとする、日米両国政府の「核ならし」政策であると考えられた。」
「エンタープライズ反対闘争」1968年。
倉石発言1968年2月。下「」引用。
「倉石農相は記者会見で、「なにしろ軍艦や大砲を背景に持たなきゃだめだよ。日本の憲法は他国の誠意と信義に信頼してと前文は書いてあるが、これじゃ、親鸞上人の他力本願だ……。佐藤首相も“平和憲法を守る”なんて口では言っているが、腹のかなではくすぐったいんじゃないか。こんなバカバカしい憲法を持っている日本は、他国のなさけにすがって生きるメカケみたいなもんだ……。日本も原爆もって三○万人の軍隊であったら……」と、発言した。現職の官僚が公務員の憲法尊重擁護の義務を規定した憲法第九九条に違反して、公然と憲法を誹謗し、核武装を説いたのであるから、世論の反撃はきびしかった。世論を背景として、野党は結束して倉石罷免を要求し、予算審議を急ぐ政府はついに倉石農相を辞任させた。」
 index
index index
index 目次
目次