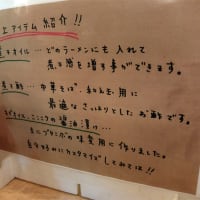『痣丸』の頼朝様を描き直してみました。よしよし、前のの百倍似てる。
このマンガで頼朝の耳が大きいのは、何か理由があるのでしょうか。「釈迦と劉備の再来」という設定だったりして。
実はこのシリーズは「その5」で終了する予定だったのですが、間が空いてしまったので仕切り直します。年を跨いでしまうのも何なんで。取りあえず今ある写真はこれでおしまい~。

中伊豆。冷川の里にある「頼朝腰掛け石」。
これは、年来の私のナゾなのです。この遺跡自体は名前の通りでエピソードも頼朝石によくあるたぐいの物なのですが、この看板が立っている場所から辺りを見渡しても、何も無い。
丁度2年ぐらい前に、この看板が気になって、頼朝石を求めて付近を探し回ったことがあります。見つからなかった。でも味のある竹林や道祖神やワサビ畑が多く、それ以来大好きな里になりました。…が、やっぱり看板のある位置に何かあるべきですよねえ。

看板の立ってる付け根。もしかしてこの土の下に頼朝石があるのか?
ナゾ。
そこから冷川峠へ。
現在「中伊豆バイパス」(通行料金360円。高い)が中伊豆町と伊東市南部を短距離で結んでいるのですが、このバイパスとトンネルは昭和53年に開通したもので、当然頼朝の時代にはありませんでした。バイパス開通以前に使われていたのは「冷川峠」。実はこのブログでは「頼朝の時代に韮山から伊東に行くには、主に亀山峠と冷川峠があった」とたびたび述べていますが、正確に言うと冷川の道も大昔にはありませんでした。ウィキペディアによると冷川の開通は明治36年で、それ以前は「柏峠」と呼ばれる場所を通っていたのです。当然、頼朝が歩いていたのも柏道のはずです。なのになぜこのブログでは「柏峠」の名前を使わないのかというと、この道は現在はもう無名の道で、言っても誰も分からないからです。
前から疑問に思っていました。この峠道は伊東のどこに出るのかと。前にもここから伊東へ行こうとしたことがあったのですが、その時は2tトラックだったので途中で挫折してしまいました。なので、今日こそこの道を突き詰めてみようと思って。

冷川峠の最高地点の少し手前に、柏峠との分岐点があり案内板もあります。
柏峠には、曾我物語での「奥野の狩り」での逸話と伊東仏現寺の「天狗の詫び証文」の故事があり、「伝説好き」には欠かすことのできないスポットです。
冷川峠全体が木が深く生い茂り、神秘的な道路ですが、とりわけこの柏峠への入口のある場所が最も杉が高く「ここだったら天狗が出てきてもおかしくないな」と思わせます。

「柏峠、ここから2km」「伊東近道」の道標が。

東伊豆でよく見かける束帯姿の道祖神です。右側の台座に何が載っていたのか気になる。
ところが柏峠に入って少し行くとこんな光景に。


こんなんじゃ天狗は出ないよ~。(雰囲気的に) 天狗には杉か松が必須。
しかし「奥野の狩りの時に柏峠で頼朝を囲んで伊豆・相模・武蔵の武士が華やかな祝宴をおこなった」という逸話には、こういう景色の方が似合う気がします。全域で椎茸がたくさん栽培されていました。
道は細く、心配になりながら2kmほど進むと、突如として道が行き止まり。あれ?

なんだよー。伊東への近道なんじゃなかったのかよー。
引き返しますが、車が通れそうな脇道は無く、解せない気持ちのまま冷川峠まで戻って伊東に向かいました。
自転車で柏峠踏破を実行した方がおられました。なるほど。
伊東では八重姫関係の遺跡を。
伊東は大好きな町ですけど、その地の伝説はあまりよく知りません。八重姫についても普通にネット収集で知ることのできるぐらいしか分かりません。図書館に行けばたくさんの見知らぬ伝説が蒐集できると思うし、伊東という場所は逸話がまた豊富そうな町なのです。今後の課題としましょう。
まず向かったのは、「日暮(ひぐらし)の森」。
伊東に棲んでいた頃の頼朝が逢い引きの場としていたのが「音無神社」でしたが、その八重姫が来るまで時間潰しをしていたというのがここなのです。頼朝が日が暮れるまで待っていたから「日暮らし」で、これは完全な頼朝地名です。

ひぐらしの森の碑。
森と書いてあるのに住宅地の中心にあり、森なんかでは全然ありません(笑)。結構分かりづらいのであらかじめ地図で場所を確かめとかないと絶対に迷うでしょう。適当には巡り着けない位置です。駐車場はありません。路駐。
現在は森としての面影は一切ありませんが、明治の中頃まではちゃんとした大きな森だったそうですよ。「日暮神社」がありますが、この神社の創建年代は不明です。頼朝の頃はあったのでしょうか。でも他に相当する場所が無いので、「この建物の影で頼朝は息を潜めて日の暮れるのを待ったんだ」と夢想することにしときましょうね。
(※こちらのサイトさんによると、頼朝の時代の建物の遺構が確認されているそうです)

祭神は誉田別命(=応神天皇)。おお、八幡神のことだ。
ここから音無神社は120mで、音無神社から伊東祐親の屋敷と推定されている物見塚公園までは700mです。「そんなに近いんなら最初からこの日暮の森を待ち合わせ場所にすればいいじゃん」と思うのですが、何か理由があったのだと考えましょう。
実は日暮神社と音無神社の間には松川が流れているんですよね。八重姫はこの川を渡れないことになってたんじゃないか。実は、伊東の町は「曾我兄弟の仇討ち」の発端となった出来事によって、領地が二分されていたんです。“本来の伊東の支配者”である工藤祐経と、“汚く土地を奪い取った”祐経の叔父の伊東祐親と。本来は伊東庄全体が祐経のものだったはずなのですが、「伊東の地を両者で半分に分けるべし」という祐親に有利な裁定をくだしたのは平清盛で、だから祐親法師は死ぬまで清盛に忠節を尽くすこととなりました。半分にわけられた領地のうち、工藤祐経の取り分がどこからどこまでだったのかは明らかではありません。が、上述のことから「その境界線は松川だったのじゃないのか」と私は思うのです。多分現在伊東駅のあるあたりは昔は低地の氾濫原で、一番暮らしやすい久須美の高台のあたりは祐親が取ったのだと思う。…もちろん伊東に流されてきた頼朝は湿地帯の蛭の多い、通称「北の小御所」に住まわされたのだと思う。それはわざと祐経の領地内で祐親は「清盛から命ぜられているから」という名目で祐経の領域内にも監視を届かせるようにしたのだと思う。すべては祐経への嫌がらせのために。←全部私の夢想ですが。(※祐経の弟の祐茂は宇佐美に住んでいるので祐経の住居も宇佐美じゃないかとする考え方もありますが、私はその説は採りません)

松川
音無神社
祭神は豊玉姫命。
頼朝と八重姫が忍び逢いをしていたとき「伊東氏の屋敷に近いために一切無言であ~んなことやこ~んなことをしたから音無神社」という…のかと思いきや、実は神社の命名には頼朝は関与していないようですね。豊玉姫は竜宮城の姫君なのですが、旦那さんはイジワルな海幸彦の弟として有名な心優しい山幸彦命。出産するときに姫は夫に「絶対見ないでくださいね」と念を押したのに、好奇心に負けた夫が産屋を覗いてしまい、巨大なワニがいたので夫は小さな叫び声を上げる。すると妻は「み~た~な~」と言って夫を頭からバリバリ食べてしまったということです。この故事を記念して「しゃべっちゃいけない=音無神社」となったのだと。なんでやねん。それだったら普通は「見ちゃいけない=冥神社」「妻の言いつけは聞かなければいけない=絶対服従神社」でしょう? このとき産まれた子供がウガヤフキアエズ神(=神武天皇の父)です。
奇祭「尻摘み祭り」が有名で、これは女の尻が三度の飯より好きだった頼朝に由来してると思うのですが、「好き放題暗闇の中で周りの人のシリを触りまくれる」と有名になって、数年前だか数十年前だかに実際にけしからん事件が起こったので、しばらく中止を余儀なくされたのだそうです。現在は「尻相撲」に力を入れていて、尻をつねるのは禁止となっているらしい。意外とネットで検索してもそのことには言及されてないことが多いので、わくわくしながら11月10日に祭りを見に来て、禁止と言われてガッカリしてしまう人も多いと思う。頼朝もあの世でがっかりだ。でもそもそもは貴方が元凶だ。

こちらも「音無の森」と表記されていますが、森では全然無いです。
しかし境内が広く巨木が点在しているので、太古に深い森だった様子を想像するのは容易です。

「玉樟神社」の小祠がありました。祭神は源頼朝・八重姫。「八重姫がこのあたりに千鶴丸を祀った」という話も聞いたことあるんですけど、それもここでしたっけ?

わお!! 愛らしい。

有名な「奉納された底が抜けたひしゃく」。
なんでも安産のための祈願だそうですが、なんで底を抜いた柄杓? ネットで調べてみると、これを見た人は同じくみんな首を捻っています。何かエロい意味がありそうですが。どうしても千鶴丸が海の中から可愛らしく「ヒシャクをよこせ~~、ヒシャクが欲ちいの~~」と泣きながら叫んでいる姿が脳裏に浮かんできてしまいます。この神社では「境内で種のあるミカンを食べると子供を授かる」とも言いますので、…穴を開けた○○の寓意? 柄杓の柄は太くて長い方がいいとか? 頼朝の考えることはわからん。大丈夫ですよ、貴方の鯨は小さくありません。
隣りに伊東家代々の墓の並ぶ最誓寺があったのですが、うっかり行くの忘れてました。伊東祐親も河津三郎も八重姫も別の場所に墓があるというのに、最誓寺には誰の墓があるんですか?
続きまして、河津三郎と曾我兄弟の墓がある東光寺。
河津三郎つながりで「相撲の守護神」としても名高いそうです。

が、私は曾我物語では工藤祐経・祐茂応援派だし、スモウ神は野見宿禰を尊崇してますので、ここは軽く。曾我兄弟の首塚へ行く長い階段には石仏が盛りだくさんで、石仏好きな私は心癒されました。


続いて近くにある楠見神社へ。
ここには頼朝が伊東館から逃げる時に隠れたという、大楠の巨大な洞があります。


さすがにでかい。本当に中に人が入れそう。逃げている最中に面白半分にこんなのの中に入ったら、見つかった時に逆に慌てて引っ掛かって出られなくなりそうですが。推定樹齢は800年~3000年までまちまち。
この神社の立地が絶妙で、頼朝が逃げたルート、身を隠しながら必死でまろびでた様子を想像すると感無量です。
続きまして、祐親法師の墓。

東光寺の正面の高台の上の住宅街のただなかにあり、「なんでこんな辺鄙な」と思うのですが、愛する嫡子・河津三郎の墓といい物見塚公園といい、全部やけに見晴らしの良い高台の上にあって「祐親はこういう場所が好きだったんだな」「意外とスカッとしたいい奴だったのかも」と思わせます。頼朝も憎い祐親の遺体をちゃんと伊東に届けてやって彼の希望通りの場所に埋葬してやるなんて、案外優しいじゃん。

傍らに祐親お手製の歌の碑がありましたが、、、 達筆すぎて読めん。三笠山?
続きまして、伊東市役所にある物見塚公園。

祐親のことはどうでもいいのでスルー、、、 しようとしましたが、銅像好きにはこれは何度見てもたまらん。かっこいい~~。


三代目物見の松。

ここからみはらかす伊東の町は絶景です。写真じゃわかりませんけど。
続いて隣りにある仏現寺へ。
この寺は「伊東館の鬼門に当たる場所に建てられた毘沙門堂」が母体だそうです。

が、伝説好きにはそれ以上に気になるのが、各種妖怪本やテレビには必ず出てくる「柏峠に出た天狗」の「天狗の詫び証文」と「天狗のヒゲ」がこの寺にあるということでした。…でも午後5時半頃、、、誰もいない。ててててて天狗様~~。こちらのブログさんを見ると、頼んでも本物を見せてくれることはないですが、詫び証文の写しをくれるそうです。それから、「天狗の詫び状羊羹」があるそうです。
最後に、河津三郎が暗殺されたという八幡野の「血塚」に向かいます。

が、まだそんなに遅い時間じゃないのに灯りが無いので真っ暗。別荘地で高い杉の木だらけですもんなあ。車のライトで照らした入り口が上のような感じ。ここから数百m歩かないといけません。車はここまでなのでライトでは照らせない。

15mほど歩いて、フラッシュで写真を撮ったんですが、上のような感じだったので「こりゃダメだ」と思って断念しました。だって通路の石畳すらフラッシュ無しだとまったく見えない。また来よう。べべべべべべつに怖かったわけじゃないんだからねっ。懐中電灯を車に常備するべきですね。