
久しぶりに2日間も休みが貰えたので、「溜まってる日記を次々と消化させるぞー」と意気込んでいたら、親が「温泉でも行くか?」と言うからどうせ近くの日帰り温泉だと思って「オッケー♪」と答えてから「どこに行くの?」と問うと、下部温泉だという。山梨県です。遠いよ、日帰りはしんどいよ、と躊躇しているともちろん日帰りじゃなくてお泊まりですってさ。親は最近変な会員制の旅館巡り企画に手を出してまして、格安で泊まれる代わりに年に数十回のペースで各地の旅館を巡らないとモトが取れないらしい(11月に行った越前旅行もソレでした)。もちろん費用は親が全部出してくれるというのです。気持ちの悪い状態のママで宙ぶらりんとなっている多々のブログ記事のことは気になりましたが、でもやっぱり信玄公の隠し湯のことも捨てがたいし、結局「うん」と答えちゃった。・・・・ところが、明日の今日で宿の予約が簡単に取れるわけもなく、やっぱり下部は満杯だったそうで、代わりに伊東の温泉に行くことになった・・・・・・
結果オーライ。ラッキ~
もちろん、この旅は私にとって「伊豆の伝説の頼朝巡り」の一環です。
前の一巡では見逃してしまっていた場所が多かったですからね。

午後3時ぐらいに伊東に着いたのですが、親をホテルに置いて早々に私は一人で車を出す。向かうのは伊豆高原にある富戸です。
伊豆高原は世にも珍しい場所でして、高原なのに海がある。この富戸港が以前1年ぐらい私の仕事場だったことがありまして、伊豆の国市の自宅からここに赴くたびに、「なんと美しい海なんだろう~」と毎回嘆息していたのでした。大好き。
海の景色と同じくらい独特なのが、港町の風情です。なんと文字通りに海に面しているのに高原地帯の趣なのです。落葉樹と溶岩性大地と細い山道。通勤していた頃から度々その桃源郷のような光景を写真に撮ろうと幾度と無く試みていたのですが、どうにも巧くいかないので今日もあきらめる。
さて、ここにも頼朝伝説がひとつあります。
源頼朝と伊東の領主・祐親法師の3女との間に生まれた嬰児に関する伝説。
曾我物語では激怒した祐親によって幼児は伊東の町の真中を流れる松川の上流で沈められたことになっているのですが、伊東の伝説では、3才児の遺体は川を流れて海に出、海流に流されて富戸の海岸に打ち上げられたことになっているのです。松川の河口と富戸海岸ってかなり遠いぞ。


当地の伝説では、海流に遙々15km流されてきたこの幼児を、富戸海岸でつりをしていた釣り人が発見して、崖の上で乾かして丁重に葬ったということにされています。その幼児がとんでもない高価な衣服を着ていたので釣り人はその遺体の身分が気になっていろいろ調べてみたところ、頼朝の子らしいということが明らかになったのだという。頼朝ものちに子を発見してくれたこの男のことを知り、称賛の言葉と生川(なまかわ)という姓を与えたそうです。
近くに、頼朝がこの死んだ自分の子を祀った「富戸三島神社」があります。

富戸の町はきわめて独特なつくりをしています。きわめて細い坂道と地形の高低差で出来た町。働いていた頃は一帯を難儀して走り回っていたのですが、そういえばスーパーうわみつじの陰に小さな神社があったことは気が付いていた。でもまさかこれが頼朝ゆかりの神社だったなんて思いもよらなかった。

小さな神社ですが、彫り物がやたらと見事です。
また、さらにこの本殿に接着するような形で細長い巨大な歩廊とお籠り堂というか公民館みたいな巨大な建物が付属していまして、この土地にとってこの神社がどういう位置づけなのかが気になる。ちょっと変わった神社です。

子供を流したとき、沈めた人間はかわいそうに思って近く(伊東市鎌田町)の八幡神社の境内に生えていた橘の小枝を子供の両の手に握らせましたが、富戸海岸に流れ着いたときに子供はまだその小枝を握りしめていたそうです。村人はその小枝をここに植えましたがそれはすぐ枯れ、惜しんだ村人がもう一度植えたら今度は見事に根付いたそうです。(再生の神話?) ただし現在あるこの木は3代目(?)らしい。
注目すべきなのは、ここで頼朝は死んだ自分の子供を「若宮八幡」として祭り、また神社を三島神社としたことです。私が「頼朝は自分を三島明神もしくは蛭子神と同一視していたと思う」という説を遙か遙か大昔に唱えたことがありましたよね。(どこで言ったんでしたっけ)。若宮八幡といえばふつうは八幡神(応神天皇)の息子(仁徳天皇)のことを指すのですが、別の人になっている例も全国には多々あります。
ただし、この富戸の三島神社自体は奈良時代からここにあったと看板には書かれており、頼朝はたまたま自分の息子が上がった近くにあった三島社に「若宮八幡」を足しただけとこと。看板には続けて「この富戸三島神社は頼朝が流人時代に遙拝した十七社のうちのひとつである」と書かれています。
気になったのはこの神社の壁には「鹿島踊り」の歌詞の額縁が飾られていたこと。鹿島踊り自体は謎の風習なのですが、全国に結構見られる伝統芸能でして、静岡では島田大祭のものが有名ですが、伊豆でもこれを伝えている所はこれまた多い。
でもよく考えてみれば鹿島大神というのは記紀のタケミカヅチ神のことで、三島神の本体とされるヒトコトヌシ神とは不倶戴天の敵じゃん。下総の鹿島大社の正面がタケミナカタ神を祀る信濃の諏訪大社を睨むような形で建てられている、とかいう話を思い出します。(※注;こちらのサイトさんには、「鹿島踊りが伝わっている地域には出雲神を祀っている場合が多い」と書かれています)
で、鹿島踊りとは地区によって大漁祈願とか、悪霊退散とか、疾病退散とか、航海安全とか、全然違う意味を願われていますが、とりわけ伊豆の富戸においては、ここが全国でも有数の海坊主伝説の中心地であるという事も留意すべきです。
なお、上掲の伊東市の看板には「千鶴丸」に「ちづる」とルビを振っていますよ。岩波書店版の曾我物語では「せんつる」なのに。「万寿(まんじゅ=頼家)」、「千幡(せんまん=実朝)」、「一幡(いちまん=頼家の子)」に対応しているんだと思うんですけど、伊東市では「ちづる」とするのが公式見解。
神社の裏には伊東市の名木と書かれた「たぶの木」がありました。以前行った伊東の町中の「音無神社」にもありましたよね、タブのでかいのが。なにげに頼朝と関係のある植物なのでしょうか。

さて、3年ぐらい前に富戸の海岸を仕事で流していた頃、海岸沿いにとても気になっていたスポットがありました。なんやら岸壁に展望台らしきものが立っているのですが、ゼンリンの地図でもそこに至る道が載っていないという謎のスポット。のちに、千鶴丸の産衣石についての情報を調べていたところ、どうやらその謎の展望台の所にそれがあるらしいという。今回意を決してそこに行ってみました。どこに車を止めるんだか分からないほどの小路の果てにあります。まさに絶界の港町・富戸らしいスポットであります。
ほんとにね、「こんなところ入っていいんか」という街路を入っていくんです。でもその先はちゃんとしたちょっとした公園になっているので心配ご無用です。徒歩15分先の海岸に車を停め小路を抜け行ってわたしが入って行ったとき、入口付近で犬を連れて散歩している地元民らしき方に「なんだこいつ」「不審者だ」「怪しいぜこの男」的にじろりと見られて(被害妄想)路地を突き進んだのに、でもその先には観光客らしき若い女性たちがたくさん戯れていてかなり脱力したのでした。駐車場も無いのにどこから湧いたのだこの人たちは。まあ、ここは城ヶ崎に次ぐ絶景スポットなのですね。
岩の岬(御根もしくはう根というそうです)の先にはこぢんまりと城ヶ崎桜が乱れ咲いており、その先にありました。「産衣石」と「若宮八幡」です。

神社は、わたしがこよなく憧れるALABAMAさんは「竜宮神社」と呼んでおられますが、小さな祠です。でもこんな小さな岬なのに盛り上がった石段の上にある。なぜだか旗を掲揚する長いポールが2本も立っています。何の時に使うんでしょう。(特別な祭礼があるのだなきっと)

この産衣石。明らかに火山岩で、しかも表面の灰白色のざらざらした腐食しやすい部分と内部の黒い光沢のある堅い部分の2層に分かれているのが見て取れて、周囲の岩と違うのが分かるのですが、なにやら上部に人の手でコンクリで何かを立てようとしたらしい構造があることがわかります。これなに?



「2時間サスペンスの名所」として有名なのは隣の城ヶ崎ですが、富戸のここでもそれより小規模ですが極めて優れた絶景を眺めることができます。柱状節理。海が深い碧。
ここに千鶴丸が流れ着いたのですね。ジャジャッ、ジャジャッ、ジャジャジャーーン。最初犯人とされたのは松川の上流で彼を沈めたことが目撃された伊東祐親の郎党でしたが、名探偵・稗田礼次郎の巧みな推理により真犯人は別にいてそれは当初被害者だとみなされた意外な高貴な人物だということが明らかになったのでした。キーとなるのは時刻表トリックならぬ海流時刻表トリックです。大体3歳児なのに産着を着ているのがおかしいじゃん。最後に厳かに哀しい真相を告げてから馬上より相模川に身を投げる連続殺人の真犯人(実は彼は女性でした)。
千鶴遺産はこのくらいにして、次は以前探索しそびれた、八幡野の「河津三郎の血塚」に行きます。
ここは隔絶された別荘地にあって、「関係者以外の無断進入を禁ずる」の看板が随所に立てられているのですが、申し訳ないけど無視して進むことにします。ゴメンナサイ。

よし、これだけ明るければ大丈夫。
って、前来たときは車のライトが届く範囲まで進んだんですが、その先に遙か深い闇が延々続いている気がして「こりゃだめだ」と思って引き返したんでした。
ところが、明るい今になって来てみれば、前回引き返した地点のほんの先に目的のものがあった。ほんのちょっとのものだったのだよ~~



でもこの血塚、確かに何か禍々しい感じがします。
何かのオカルト本にも「無念に殺された武者の怨念が~」とか書かれていた気がするナ。
ここで殺された河津三郎とは伊東領主・伊東祐親の長男で、強力で知られのちに相撲の神にまでなった人ですが、彼の父祐親が無惨に所領を奪った伯父の遺児(工藤祐経)の雇ったスナイパーによってここで殺されました。暗殺者たちも狙うんなら当の本人の祐親にすればいいのに。で、十数年後に河津三郎の息子たち(曾我兄弟)が仇討ちとしてなぜか源頼朝を狙い、間違って工藤祐経を殺してしまうのです。この事件はほんとわけわからん。
この塚の目の前が広大な竹林で、冬の風が吹き付けるたびに何かが叩きつけられる音がぱしっぱしっと鳴る。
が、とにかく雰囲気があるので、一方で心安らぐ場所であるのも間違いない。
「どうしてこんなに心が安らぐんだろう?」と思って、塚の前の小道をどんどん遡ってみたらその理由が分かった。

塚の横に看板があったのですが、この道は現在の海沿いの国道が出来る前は、下田街道の本道が通っていた場所だったんですって。
通常ならば、そのような場所は地域起こしの名のもとにそれっぽい改修をなされてチープに売り出されるのが常で、実際この場所も伊東市によって「なんとかの散歩道」とかの整備をされかけたらしいのですが、何らかの理由でそれが中止されたらしい。この道も途中で行き止まりになっています。
しかし、そのおかげでこの付近には一切の開発がなされてなく、静寂。この石垣はわざとらしいですけどね。でも許容範囲です。
「鎌倉時代の街道ってこんなかんじだったんだな」と改めてしみじみしました。
河津の三郎はこの近くを馬で家まで帰ろうとしていたときに、木の陰から狙撃されたんですね。
この付近にあるという実際の狙撃点、“椎の木三本”も結局どこにあるのか良く分からなかったですけど。
・・・さて続けて、「八幡野」という地名の語源となった「来宮八幡神社」に行ってみました。異邦神である来宮神と武神である八幡神が一緒に祀られているという珍しい神社で(普通にある合祀という形ではなくて、並列された別々の一級神が同一の社殿で祀られているという扱い)、これまた「頼朝が自らを異訪神としてみなしている」という私の説を証立てたかったんですが、行ってみても何の証拠も無かったので、今回は解説をパスします。
雰囲気は良かったですよ。狛犬がやたらたくさんありました。
冒頭の狛犬の写真はここのものです。
・・・で、つづけて本日のメインイベント!
伊東市吉田にある「吉田家」です!
数ある家系ラーメンのうち、わたくしが「もっとも美味しい」と信じてやまないお店。
吉田家とは藤原北家勧修寺流の公家で、初代関東申次吉田経房や後の三房の一人吉田定房を輩出し、後に嫡流は甘露寺家、庶流が中御門家・坊城家・万里小路家・勧修寺家・穂波家・岡崎家・芝山家・清閑寺家などと名を変え、現在も存続しております。
なんといってもね、キャベツがね、キャベツが!!

今回はチャーシューメン(950円)に玉子(50円)をトッピングしてみました。
朝から何も食べていないわりにそんなにお腹も空いていなかったので普段ならタマゴなんて付けないのですが、そういえばここのタマゴは現在主流の味付半熟玉子ではなくただの普通のユデタマゴだったな~と思い出し、写真に撮りたくなって注文してみました。うん、普通のゆで卵です。味は染みていません。
以前にも書きましたが、店内が異様に見晴らしが良いので、かつては「怒声で有名」とされたが今では丸くなった(らしい?)というおやっさんと若い衆らのほのぼのしい掛け合い、2つの寸胴の中身、麺切りは若い衆に全部任すが盛りつけのコーディネートはおやっさんがやっている様子などをただただ黙って見つめて麺が出てくるまで待つしかありませんでしたが、これがきわめて楽しい。
吉田家のラーメンは一般に「しょっぱい」と評されることが多く、わたしもそう感じたことが多々あるのですが、この日の一口目は抜群に美味かった。なんという調和! なんという攻撃力! なんというシャクシャクするキャベツ!
チャーシューも麺の旨みも抜群です。こんなにウマかったっけ。
う~~ん、山岡家の百倍うえです。

が、最後の方にはやっぱりしょっぱくなっていました。
塩だれは下の方にたまっていたんですね。











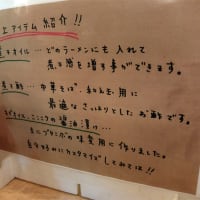








ウチはネコがいるので一人旅でも無理っぽいです。ペット同伴可能の宿も増えましたが、ネコという生き物そのものがあまり移動を好みません。『夏への扉』のピートなど「よく慣らしたものだ」と感心します。ペットホテルもネコには馴染みにくい場所でしょうしねぇ。
たとえ費用が親持ちでも、親子旅行というのは親孝行になるんじゃないですか?
ウチは旅行どころか二親そろって身体が不自由でしたから(というか親子仲は激悪でありました)、親の身体の自由が利く時の孝行旅行をオススメしますよ。
ラヴクラフトは「ギリシャ行きてー!」と手紙に書いていますが、本人はあまり生まれ故郷から出ていないんですよね。生涯に5~6度くらいでしたか(バス旅行で行ったニューオーリンズはそこそこ遠出になりますか)。
オーガスト・ダーレスとも一度も会ってないそうですね。
本人は元々旅行好きだったようで、旅行者が旅先でえらい目に会う作品もあったりしますが。
あぁ、この人も大のネコ好きでありました。
(アイドルだったダンセイニ卿はイヌ好き。私はどちらも飼った事がありますが、よく考えたら動物好きの子どもが飼いそうな生き物は一通りこなしてました^^)
作家や画家が旅の空に身を重ねてないと創作の池が飢えるということは良く分かるのですが、同じく芸術創作家として音楽家が業務のひとつとして旅(@演奏旅行)が不可欠としているのはどうしてだろうと思います。
旅と創作源はそれほど密接な関係があるものだろうか。旅により偉大な音楽を生み出した作家としてモーツァルトとメンデルスゾーンとチャイコフスキイがいます。ベートーヴェンとバッハは頭の中だけで旅が出来た人ですが、私のこよなく愛するヘンデルは実益を兼ねて(=ヨーロッパ中を歌が得意な絶世の美女を求めて)旅することを敢していた人で、対するようにシュウベルトはご近所旅行だけを無邪気に楽しんでいた人でした。
漫画家さんはどうなんでしょう。むかしの少女漫画のコミックを読んでいると、3分の1スペースに取材と称していろんなところに遊びに行ってる様子だけが思い起こされるんですけど。(特に遠藤淑子の3分の一が面白かった)
j.kさんもどうか存分に旅行をなされますように。
猫だってきっと旅は好きですよ。
私の舘山寺にもぜひ来てくださいまし。
・・・といえども私の店だってまだペット同伴を受け入れてないんですよねえ。
伊豆にはペットの宿もたくさんあったのに~