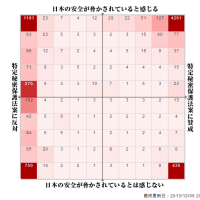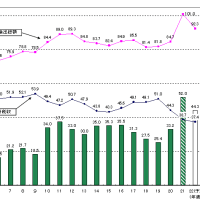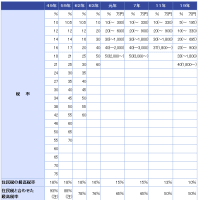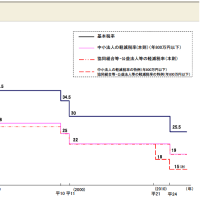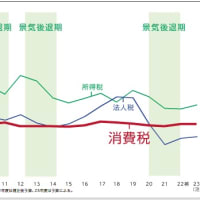はいは~い
別にのんきは忘れてたわけじゃないんですよ。
最近のキーワード検索で、意外とこの「狐と狸」のお話に対して検索をかけてくれてる人がいるので、狐編のみで放置してるのは申し訳ないな・・・
と思いまして。
改めて狐編にとりかかろう、と思いましてございます。
ってことで、「狐(きつね)と狸(たぬき)のばかし合い~狐編~」。
狐(きつね)と狸(たぬき)のばかし合い~狸編~の続きです。
さてさて。↑前回の記事では、「狸」とは、もともと中国から漢字として輸入された時「たぬき」ではなく、「やまねこ」であった事。
当時の日本には「やまねこ」なんて動物は存在しなかったので、当時の日本人たちが、「やまねこ」という動物を想像して、良く似た動物を総称で「狸」と呼んでいた
のだということ。後に現在の「たぬき」のイメージが「狸」という漢字に定着して「狸=たぬき」となったのだということ。
そしてさらに、中国で元々「たぬき」をあらわしていた「貉」と言う漢字は、日本では「狸」という漢字にその立場を奪われ、元々日本で得体のしれない、人間などに
化ける妖怪の総称であった、「むじな」という読みを与えられてしまった事。
これが混同されて狸(たぬき)に人を化かすイメージがついたのではないか、というのんきの予想をご紹介いたしましたね。
そして、古来、「たぬき」という動物に対しては、森羅万象を象徴する、神聖な生き物として日本人には受け入れられていたのに、仏教の伝来とともに到来した「狐」
によってその神聖な立場を奪い去られてしまい、森羅万象の象徴として、「特別な力を持った生き物」というイメージのみが残ってしまったのではないか、と言う事。
また、元々神聖な立場であったので、比較的人々に愛着のある生き物として受け入れられていったのではないか・・・ということを前回の記事ではお示ししましたね。
ではでは。一方の「狐」。前回の記事では、「本来神の使いであるはずの狐に、なぜあれほどずる賢いイメージが定着してしまったのか。」
と記してしまいました。そう。あたかも「仏教」でいう「狐」そのものが神聖なイメージである、と言うように記してしまいましたが、若干、事情は異なるようです。
元々、「狐」に対して神聖な神の使いとしてのイメージが持たれていたのは仏教よりも日本の神道。「稲荷神」の使いとしての狐(白狐)であったようです。
全国の稲荷神社でお祭りされていますね。
弥生時代。大陸から伝来された稲作は、田に水を溜めることによって行われますね。
ところが、肝心の田に穴をあけ、この稲作を邪魔する動物がいました。「ネズミ」です。
このネズミをとらえ、退治する生き物。それが「狐」や「狼」だったんです。日本の食生活を支える稲作です。狐や狼は農民たちにとってありがたい存在であった、
と言うことでしょう。
さて。この農民たちの思想をうまく利用したのが大和朝廷。朝廷は、地方の農民たちの事を「狐」と呼んで蔑視していたらしいのですが、朝鮮からの渡来民族である
「秦氏」が、元々農民たちが「山の神」「田の神」を祀っていた神社を、五穀豊穣の神である「稲荷神」を祀る神社として作り変えてしまいました。
土着農民たちの神を祭る神社の象徴であった「狐」は、そのまま稲荷神の眷属としておさまってしまった・・・と言うのが狐に神格が備わるようになった流れなのだそう
です。(Wikiより)
この流れは、なんだかインドでドラヴィタ人をアーリア人が支配する為に用いた手法とよく似ていますね。
さてさて。では、「本来神の使いであるはずの狐に、なぜあれほどずる賢いイメージが定着してしまったのか。」というお話。
実は、ここに仏教のお話が絡んできます。仏教のお話なんですが、そのルーツはやはり「ヒンドゥー教」に起因します。
ヒンドゥー教のお話はぜひ、のんきの宗教観~総集編でご覧下さいませ。
狐にずる賢いイメージを植え付けた張本人(張本神かな? )は、「荼枳尼(ダキニ)天」と呼ばれる仏教の神様。
)は、「荼枳尼(ダキニ)天」と呼ばれる仏教の神様。
日本に持ち込んだのは空海(弘法大師の事ですね。 )。空海が持ち込んだ「真言密教」の中では、荼枳尼(ダキニ)天は、Wikiによると、
)。空海が持ち込んだ「真言密教」の中では、荼枳尼(ダキニ)天は、Wikiによると、
『荼枳尼は胎蔵曼荼羅の外金剛院・南方に配せられ、閻魔天の眷属となっている。半裸で血器や短刀、屍肉を手にする姿であるが、後の閻魔天曼荼羅では金嚢に似た小袋
を持つようになる。さらに時代が下ると、その形像は半裸形から白狐にまたがる女天形へと変化し、荼枳尼”天”と呼ばれるようになる。また、辰狐王菩薩(しんこおう
ぼさつ)、貴狐天王(きこてんのう)とも呼ばれる』
という風に記されています。不思議ですね~。 元々、『半裸で血器や短刀、屍肉を手にする姿』であった荼枳尼(ダキニ)天。なんだか、とっても凶悪なイ
元々、『半裸で血器や短刀、屍肉を手にする姿』であった荼枳尼(ダキニ)天。なんだか、とっても凶悪なイ
メージですよね。それが、後に『半裸形から白狐にまたがる女天形へと変化し、荼枳尼”天”と呼ばれるようになる』にまでなるのです。
『辰狐王菩薩(しんこおうぼさつ)』とか、『貴狐天王(きこてんのう)』とか、なんだか当初の凶悪なイメージとはかけ離れた存在に変化していますよね。
どうしてなんでしょう。
さてさて。『荼枳尼(ダキニ)天』とは一体何者なのか。では、なぜ彼女が「狐」に対して『狐にずる賢いイメージを植え付けた張本人』なのか。
「狐」が「狸」から神格を奪うほどまでに日本で神格化されたのはなぜなのか。
次回、「狐(きつね)と狸(たぬき)のばかし合い」、続編をお楽しみに~~
日本の未来は明るい!!








帰りしにクリックを・・・
あなたの1票が、のんきのブログを沢山の方に知っていただく力になります^^

別にのんきは忘れてたわけじゃないんですよ。

最近のキーワード検索で、意外とこの「狐と狸」のお話に対して検索をかけてくれてる人がいるので、狐編のみで放置してるのは申し訳ないな・・・
と思いまして。

改めて狐編にとりかかろう、と思いましてございます。

ってことで、「狐(きつね)と狸(たぬき)のばかし合い~狐編~」。
狐(きつね)と狸(たぬき)のばかし合い~狸編~の続きです。
さてさて。↑前回の記事では、「狸」とは、もともと中国から漢字として輸入された時「たぬき」ではなく、「やまねこ」であった事。
当時の日本には「やまねこ」なんて動物は存在しなかったので、当時の日本人たちが、「やまねこ」という動物を想像して、良く似た動物を総称で「狸」と呼んでいた
のだということ。後に現在の「たぬき」のイメージが「狸」という漢字に定着して「狸=たぬき」となったのだということ。
そしてさらに、中国で元々「たぬき」をあらわしていた「貉」と言う漢字は、日本では「狸」という漢字にその立場を奪われ、元々日本で得体のしれない、人間などに
化ける妖怪の総称であった、「むじな」という読みを与えられてしまった事。
これが混同されて狸(たぬき)に人を化かすイメージがついたのではないか、というのんきの予想をご紹介いたしましたね。

そして、古来、「たぬき」という動物に対しては、森羅万象を象徴する、神聖な生き物として日本人には受け入れられていたのに、仏教の伝来とともに到来した「狐」
によってその神聖な立場を奪い去られてしまい、森羅万象の象徴として、「特別な力を持った生き物」というイメージのみが残ってしまったのではないか、と言う事。
また、元々神聖な立場であったので、比較的人々に愛着のある生き物として受け入れられていったのではないか・・・ということを前回の記事ではお示ししましたね。

ではでは。一方の「狐」。前回の記事では、「本来神の使いであるはずの狐に、なぜあれほどずる賢いイメージが定着してしまったのか。」
と記してしまいました。そう。あたかも「仏教」でいう「狐」そのものが神聖なイメージである、と言うように記してしまいましたが、若干、事情は異なるようです。
元々、「狐」に対して神聖な神の使いとしてのイメージが持たれていたのは仏教よりも日本の神道。「稲荷神」の使いとしての狐(白狐)であったようです。
全国の稲荷神社でお祭りされていますね。

弥生時代。大陸から伝来された稲作は、田に水を溜めることによって行われますね。

ところが、肝心の田に穴をあけ、この稲作を邪魔する動物がいました。「ネズミ」です。
このネズミをとらえ、退治する生き物。それが「狐」や「狼」だったんです。日本の食生活を支える稲作です。狐や狼は農民たちにとってありがたい存在であった、
と言うことでしょう。
さて。この農民たちの思想をうまく利用したのが大和朝廷。朝廷は、地方の農民たちの事を「狐」と呼んで蔑視していたらしいのですが、朝鮮からの渡来民族である
「秦氏」が、元々農民たちが「山の神」「田の神」を祀っていた神社を、五穀豊穣の神である「稲荷神」を祀る神社として作り変えてしまいました。

土着農民たちの神を祭る神社の象徴であった「狐」は、そのまま稲荷神の眷属としておさまってしまった・・・と言うのが狐に神格が備わるようになった流れなのだそう
です。(Wikiより)
この流れは、なんだかインドでドラヴィタ人をアーリア人が支配する為に用いた手法とよく似ていますね。

さてさて。では、「本来神の使いであるはずの狐に、なぜあれほどずる賢いイメージが定着してしまったのか。」というお話。
実は、ここに仏教のお話が絡んできます。仏教のお話なんですが、そのルーツはやはり「ヒンドゥー教」に起因します。
ヒンドゥー教のお話はぜひ、のんきの宗教観~総集編でご覧下さいませ。
狐にずる賢いイメージを植え付けた張本人(張本神かな?
 )は、「荼枳尼(ダキニ)天」と呼ばれる仏教の神様。
)は、「荼枳尼(ダキニ)天」と呼ばれる仏教の神様。日本に持ち込んだのは空海(弘法大師の事ですね。
 )。空海が持ち込んだ「真言密教」の中では、荼枳尼(ダキニ)天は、Wikiによると、
)。空海が持ち込んだ「真言密教」の中では、荼枳尼(ダキニ)天は、Wikiによると、『荼枳尼は胎蔵曼荼羅の外金剛院・南方に配せられ、閻魔天の眷属となっている。半裸で血器や短刀、屍肉を手にする姿であるが、後の閻魔天曼荼羅では金嚢に似た小袋
を持つようになる。さらに時代が下ると、その形像は半裸形から白狐にまたがる女天形へと変化し、荼枳尼”天”と呼ばれるようになる。また、辰狐王菩薩(しんこおう
ぼさつ)、貴狐天王(きこてんのう)とも呼ばれる』
という風に記されています。不思議ですね~。
 元々、『半裸で血器や短刀、屍肉を手にする姿』であった荼枳尼(ダキニ)天。なんだか、とっても凶悪なイ
元々、『半裸で血器や短刀、屍肉を手にする姿』であった荼枳尼(ダキニ)天。なんだか、とっても凶悪なイメージですよね。それが、後に『半裸形から白狐にまたがる女天形へと変化し、荼枳尼”天”と呼ばれるようになる』にまでなるのです。
『辰狐王菩薩(しんこおうぼさつ)』とか、『貴狐天王(きこてんのう)』とか、なんだか当初の凶悪なイメージとはかけ離れた存在に変化していますよね。
どうしてなんでしょう。

さてさて。『荼枳尼(ダキニ)天』とは一体何者なのか。では、なぜ彼女が「狐」に対して『狐にずる賢いイメージを植え付けた張本人』なのか。
「狐」が「狸」から神格を奪うほどまでに日本で神格化されたのはなぜなのか。
次回、「狐(きつね)と狸(たぬき)のばかし合い」、続編をお楽しみに~~

日本の未来は明るい!!






帰りしにクリックを・・・

あなたの1票が、のんきのブログを沢山の方に知っていただく力になります^^