政府をば縛りて民のしあはせを図るためにぞ憲法のある
いつしかぞ小沢一郎のまだしもに見ゆる世にとはなりにけるかも
*
日本国憲法が施行されて今日がちょうど60年目です。
いまや確信的改憲論者が首相となり、任期中に改憲をめざすと公言しています。
さらにこの首相はアメリカでブッシュ大統領に、明文的な改憲以前に「集団的自衛権」に関して解釈改憲をめざすことをも、事実上約束してきました。
アメリカといっしょに世界中でイラク戦争のようなことを行えるよう、危険きわまりないさらなる一歩を踏み出すためです。
ぼくは2年前に、ある雑誌に「「戦争違法化」と日本国憲法―通説を疑う―」という文章を書きました。
その中で、「集団的自衛権」に関してもその問題性について触れました。
一部を省略して掲載しますので、ご検討いただければ幸いです。
*
「戦争違法化」と日本国憲法―通説を疑う―
はじめに
日本国憲法の平和主義がその基本的条項と共に投げ捨てられようとしている。しかも、従来の一国主義的な護憲論ではそれを防ぐだけの十分な説得力を国民や生徒の中で持ち得なくなっている。日本国憲法の平和主義を守り抜くためには、それを日本の歴史や日米関係史の中だけでなく、広く世界史的な視野と文脈の中でとらえ、きたえ直すことが強く求められている。もちろん、そうした努力も始まってはいる。その代表的なものは、第一次世界大戦以降の「戦争違法化」の歴史の中に日本国憲法の平和主義をとらえ直そうとするものである。また、一部では一九二〇年代アメリカの「戦争違法(非合法)化運動」との関連を追求する動きもある。この小論では、「戦争違法化」と日本国憲法の平和主義の関係に関する通説を「戦争違法化運動」も視野に入れて再検討し、その克服すべき問題点を指摘したい。一社会科教師が日本国憲法の平和主義を授業でどう取り扱うかを試行錯誤する中で学び、考えたことである。見当はずれの恐れがないとは言えないが、敢えて問題を率直に提起したい。
一、今も正戦論の時代ではないのか?
戦争の歴史については、正戦論→無差別戦争観→戦争違法化と整理するのが近年の通説となっている。しかし、生徒にそう教えながらも、こうした整理が果たしてどこまで正確なのかという疑問を持つようになった。通説とはちがって、実は現在に至るまで姿を変えながら正戦論が一貫して生きており、それを克服することこそが現代平和主義の最大の課題なのではないのかという疑問だ。それを決定的にしたのが、ダグラス・ラミスの「正戦論」(『憲法と戦争』晶文社、二〇〇〇年、所収)である。ラミスはこう言っている。「正戦論とはなんだろう。簡単に言えば、戦争は不正で犯罪である場合もあれば、正義で合法である場合もある、という説だ。平和主義者にとってこの説は変に聞こえるかもしれないが、正戦論はとても説得力のある説だということを理解するのは重要だ。世界の人びとのほとんどはそれに説得されているし、世界の政治的法的制度のほとんどは正戦論に基づいている。近代国家(わずかの例外を除いて)の理論的基礎になっているし、国連憲章を含めて国際法の基盤でもある」。「正戦論は戦争を合法とする一番強い論理である。したがって、これを論破しないと絶対平和主義は成り立たない論理なのだ」。ラミスはさらに「積極的平和?」(『講座 戦争と現代 5 渡辺治・和田進編 平和秩序形成の課題』第一章。大月書店、二〇〇四年)でも、同様の指摘を展開している。ラミス自身は明言していないが、こうした指摘には正戦論→無差別戦争観→戦争違法化という近年の通説への強い批判が明らかに内包されている。
二、正戦論から無差別戦争観へ?
通説では、ウェストファリア条約以降、第一次大戦に至るまでの戦争観は、いっさいの戦争の正・不正を問わずに合法とみなす「無差別戦争観」だと整理される。(中略)
三、無差別戦争観から戦争違法化へ?
上述のように、第一次大戦に至るまでの「無差別戦争観」といわれる時代も、内実は各国家の個別正戦論の自由競争と植民地主義的正戦論の時代だったとすれば、国際連盟以降の戦争違法化といわれる時代についても疑問が生まれる。結論から言えば、戦争違法化の歴史と概念には正戦をめぐって決定的に異なる二つの潮流があったのではないかということだ。第一は、侵略戦争は違法化しても、国際連盟や国際連合などの国際機構による制裁戦争と各国の自衛戦争を正戦として国際法が公認する流れである。第二は、一九二〇年代のアメリカで広範に展開された戦争違法(非合法)化運動(outlawry of war movement)が求め、日本国憲法に結実された、人類史上初めて国家と国際レベルの一切の戦争を(正戦も)否定する流れだ。前者は戦争の部分的違法化プラス正戦論である。全面的戦争違法化の後者と一括りにするのは正しくないだろう。
<戦争違法化運動とは>
戦争違法化運動は第一次大戦後に、弁護士サーモン・レヴィンソン(Salmon Levinson)が提唱し、思想家ではジョン・デューイが、政治家ではボーラー(Borah)上院議員が中心となって展開した広範な大衆的市民運動である。日本では久野収が一九六二年に先駆的に紹介したが(「アメリカの非戦思想と憲法第九条」『中央公論』一九六二年一月号。『憲法の論理』筑摩書房、一九八九年、所収)、近年河上暁弘によって精力的に研究・紹介されるまでは(「日本国憲法第九条成立の思想(上・下)「戦争非合法化(outlawry of war)」思想を中心に」『専修法研論集』二五・二六号、一九九九・二〇〇〇年。「憲法第九条の源流=「戦争非合法化(outlawry of war)」思想―資料と解説」『専修法研論集』二八号、二〇〇一年。「戦争「制度」の非合法化と日本国憲法の平和主義」『専修法研論集』三二号、二〇〇三年)ほとんど知られることがなかった運動である。
レヴィンソンのアイディアは、アメリカ合衆国の州同士の紛争解決法をモデルに、まず自衛戦争・侵略戦争を問わず国際紛争の解決法としての戦争という制度そのものを違法化し、国家間の紛争解決は連邦最高裁に相当する国際最高裁判所の裁定に委ねて各国が厳密に従うというものであった。戦争違法化運動は、ごく初期を除けば自衛戦争だけでなく国際連盟による制裁戦争も認めなかった。したがって、アメリカの国際連盟加入にも反対した。
このように、思想や信念としての戦争絶対否定だけでなく、国家や国際間での制度としての戦争絶対否定は、日本国憲法で突如現れた占領下での非現実的空論ではなかった。その起源は、第一次大戦の惨禍を踏まえた一九二〇年代の戦争違法化運動によって提起された現実的思想であった。
<不戦条約と自衛権>
一九二八年に成立した不戦条約は、米仏二国間不戦条約をというフランスのブリアン外相からの提案をアメリカのケロッグ国務長官が多国間不戦条約として逆提案したことから生まれた。実はこうしたブリアンとケロッグの動きは、この戦争違法化運動の大きな盛り上がり抜きにはありえなかったのである。ブリアンが米国での戦争違法化運動の高揚を知って、最初の提案を敢えて米国政府ではなく米国市民に対して行ったことは案外知られていない。これに応えた戦争違法化運動の参加者を中心とする米国市民の広範な声を背景に、ボーラー上院議員らがケロッグを動かしたのだ。だから、戦争違法化運動の参加者は不戦条約の成立には大いに期待した。しかも、成立した不戦条約の条文には戦争の放棄とあるだけで、制裁戦争や自衛戦争の除外が明記されているわけではない。多くの米国市民はこれで世界から戦争がなくなると本気で信じた。
ところが、市民の知らない外交交渉の場ではフランスやイギリスなどの政府から自衛戦争の除外要求が出されていた。英国政府に至っては、本国だけでなく植民地・勢力圏に対するどんな干渉に対しても自衛戦争をする権利があると露骨に主張した。結局アメリカ政府は、不戦条約は各国の固有の(inherent)自衛権と自衛戦争かどうかを判断する権利を一切損なうものではないという立場を固め、そうした趣旨の政府公文を各国政府に回して条約正文を骨抜きにしてしまう。米国政府も中南米やフィリピンなどの植民地・勢力圏の確保という帝国主義的利害を持っていたことが、その深因であろう。他の列強政府もむろん同様であった。一般に日本政府は不戦条約の批准に際して「人民の名において」という規定だけにこだわったと言われるが、実際には日本政府も植民地・勢力圏の確保の障害にならないかどうかに重大な関心を払っていた。
戦争違法化運動をバネにした不戦条約の成立を機に、列国政府はかえって各国家の個別正戦論の自由競争を国際的に公認してしまった。後にジョン・デューイはこれが各国のナショナリストとミリタリストへの妥協によるものだったと指摘しているが、戦争違法化にとってはまさに致命的な妥協であった。こうして、第二次大戦前の戦争違法化の流れといわれるものの実態は、違法化したのは侵略戦争だけで、逆に国際連盟による制裁戦争と各国の自衛戦争を新たに正戦として公認するものだった。しかも、この違法化された侵略戦争の中に植民地征服戦争が入るかどうかも微妙であった。前述のイギリスの要求などは、過去の植民地征服戦争は違法とみなさないで新たな植民地征服戦争だけを違法とみなすもの、と言ってよいかもしれない。この偽善的なダブルスタンダードは、後に後発帝国主義国の日独伊が「持たざる国」の不満を叫んで国際連盟を脱退した最大の口実でもあった。しかし日独伊も不戦条約からは脱退しなかったから、公然と侵略戦争をするわけにはいかなかった。例えば日本は中国侵略を「事変」の名において拡大し、アジア・太平洋戦争を「自存自衛」の名において正当化せざるを得なかったのである。連合国側も日独伊のファシズムの侵略に対する自衛の名において戦争を拡大した。
国際連盟による制裁戦争は国際連盟の分裂によってまったく機能せず、不戦条約を機に正戦として国際的に公認された自衛戦争の名において当の不戦条約は踏みにじられ、結局は破滅的な第二次大戦に至ったのであった。
四、国連憲章・日本国憲法と戦争違法化
第二次大戦後の国際連合を中心とする戦争違法化の流れも、基本的にはこの延長上にある。しかし、日本国憲法の戦争放棄はむしろ挫折した戦争違法化運動の流れの延長上にあると見るべきだろう。従来の通説的理解においては、この点のちがいがほとんど明確にされてこなかった。
国連憲章は二次にわたる世界大戦の惨禍を踏まえ、一切の侵略戦争と侵略的な武力行使、武力による威嚇をも禁止した。しかし、他方で国連軍による制裁戦争を最終的な唯一の正戦として公認し、それが実行されるまでの暫定措置として国連憲章五一条で自衛戦争も正戦と認めた。国際連盟と比較すれば、制裁戦争規定はいっそう強化拡大され、自衛戦争規定はいっそう限定されたと言えるだろう。
<国連憲章五一条と個別的・集団的自衛権>
しかし、国連憲章五一条は同時に、自衛戦争の根拠として個別的自衛権だけでなく新たに集団的自衛権を認め、不戦条約に付された米国政府公文などの文言を踏襲してそれらを国家の固有の(inherent)権利だと表現した。そのことによって限定されたはずの自衛戦争規定は、一面ではかえって拡大されてしまった。この集団的自衛権という規定は国連憲章策定の最終段階で、安保理事会常任理事国の五大国の分裂で集団安全保障体制が機能しないことを恐れた米州諸国の要求によって挿入されたと言われる。明らかに米ソ冷戦を予期して、集団安全保障に逆行する旧来の軍事同盟による安全保障を担保するための規定であった。この危険な鬼っ子はその後現実にNATOとワルシャワ条約機構という軍事同盟の対峙を生み出して、国連の集団安全保障体制を食い尽くしてしまった。
ところが、現在高まっている改憲論の最大の理論的根拠のひとつは、この矛盾に満ちた国連憲章五一条にあると言っても過言ではない。多くの改憲論者は、この五一条を引いて自衛権(right of self-defense)は国家の固有の権利(inherent right)であり、国民の正当防衛権(英語ではこれもright of self-defenseで、自衛権と区別しない)と同様の国家の自然権(natural right)だと主張している。しかも国連憲章五一条は個別的だけでなく、集団的自衛権も国家の固有の権利だと認めているではないか。だとすれば、そうした国家の自然権を奪うことは誰にもできないはずだ。今こそ集団的自衛権を含めて自衛権を明記して行使できるよう改憲せよ、というのである。
<国家の固有の権利としての自衛権とは>
このもっともらしい議論の最大のポイントは、自衛権を国家の固有の権利(inherent right)だとする規定の理解にある。だが、なぜか多くの論者はそこを見過ごしている。
ラミスが一九八三年以来核心をついて指摘しているように、「国家は奪うことのできない権利を持たない」、「それを持つのは国民のみ」(「国家の権力から国民の権力へ―英文日本国憲法を読む」『思想の科学』一九八三年一月号。『ラディカルな日本国憲法』晶文社、一九八七年、所収)なのだ。奪うことのできない固有の自衛権(正当防衛権)を持つのは国民だけであって、国家の自衛権は国民が与え、かつ奪うことのできるものにすぎない。国際法が自衛権を国家の固有の権利(inherent right)だと規定してきたのは、これまでほとんどの国民(peoples)が自明のように国家に対して自衛権を与えてきた結果の慣習的表現と理解すべきだろう。“inherent right”を、フランスが“droit naturel(自然権)”、中国が「自然権」と訳しているのも同じことだ。しかし、同じことばでも文脈が違えば意味も違う。民主的政治・国家理論の大原則を変えない限り、国家が基本的人権と同じ意味での、奪うことのできない固有の権利や自然権を持つなどということはありえない。日本国憲法でいえば憲法前文で言う「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し」という、国民主権を前提にした社会契約論的な民主的国家像の根幹に関わる問題だ。理論的には社会契約的国家観を否定して、国家に永遠の生命を与える国家有機体説か、独立した人格を与える国家法人説に立つかどうかを意味する。
国家に自衛権があるとすれば、唯一それは国民の固有の自衛権(正当防衛権)に基づき、国民による「厳粛な信託」がある場合に限られる。しかも、その場合でも厳密な意味ではそれは国家の権利ではない。なぜなら、本来、権利は国民しか持つことのできないものだからだ。国家の権利というのはあくまでも擬制にすぎない。正確には国民の「厳粛な信託」によって生じた国家の統治権(rulling power, sovereignty)、権限(power and authority)、または権力(power)と言うべきものであろう。
おわりに
これもラミスが鋭く指摘したように、日本国憲法はアメリカ占領権力が日本の旧支配層から奪った権力を、一時的に同盟を結んだ日本国民に譲渡した「占領革命」の記録でもある。日本の旧国家から戦力と交戦権を実力で奪ったのはアメリカ軍と占領権力だが、日本国民は「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し」て、第九条で新たな国家に一切の戦力と交戦権を与えなかったのである。しかも、日本国憲法が成立したときにはすでに国際法によって侵略戦争は違法化され、国連軍による制裁戦争と暫定的自衛戦争が正戦とされていた。したがって、その時点で放棄できる戦争とは後者の制裁戦争と自衛戦争だけであった。その上、国連軍による制裁戦争は個別国家の交戦権に基づくものではないから、国家の交戦権は自衛戦争をする自衛権と同義であった。したがって、交戦権の放棄は自衛権の放棄を意味していたのである。
現在、改憲論者たちは全面改憲を目指して国連憲章五一条を認めるのかどうかと一点突破の攻勢をかけてきている。国家の「固有の権利」と「集団的自衛権」などの意味を歴史的文脈の中で徹底的に再吟味した、的確な反論が必要だろう。ところが不思議なことに、護憲派の中でも国連憲章五一条の規定自体の意味を問題にする政治学者や憲法学者は圧倒的に少数派である。政党に至っては皆無だ。第九条についても、とくに戦争違法化運動と不戦条約成立の歴史を縦糸に、民主的政治・国家理論の原則を横糸にして再定義することが不可欠であろう。その際、正戦論→無差別戦争観→戦争違法化という通説の再検討は避けて通れないのではないか。敢えて問題を提起した所以である。



















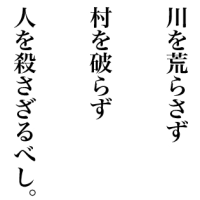






憲法は国を規制するのがその本質だ、という考え方、同感ですが「美しい国」というおかしな言葉を意図的にか使っている人には理解できないか・しようともしないでしょう。
それは安倍たちの問題ではなく今の日本を広く覆う状況だと思うとちょっと前の時代が一体どうして?と驚きます。
であるからこそ、面倒でも根っこの考え方をしっかりしておかないといけないと思いました。
人為的構築物である国家に自然権なんかあるかよと、前から漠然とは思っていたのですが、髭彦さんの文章を読んで納得がいきました。ありがとうございます。
言及されているダグラス・スミス『憲法と戦争』を、つい数日前、地元の図書館で借り出してきたところです。一緒に借りた姜尚中『日朝関係の克服』、丸谷才一『ゴシップ的日本語論』から先に読み出したので(丸谷氏の文章論的護憲論も傾聴に値します)まだページを開いていないのですが、これから心して読みます。
長い拙文をお読みの上、さっそくのコメント、ありがとうございます。
いつもお二人の名文に教えられるばかりでしたので、ちょっぴりお返しができたかもしれません。
それにしても、ぼくが書いたような憲法理解が元アメリカ海兵隊員の政治学者ラミス以外にほとんど見当たらないのは、どうしたことでしょうか。
したがって、その時点で放棄できる戦争とは後者の
制裁戦争と自衛戦争だけであった。
その上、国連軍による制裁戦争は個別国家の交戦権に基づくものではないから、国家の交戦権は自衛戦争をする自衛権と同義であった。したがって、交戦権の放棄は自衛権の放棄を意味していたのである。>
日本国憲法が発布された歴史的状況をこのように簡潔に実証的に検証できること、目から鱗が剥げ落ちた!!
長い連休から帰って、これが目に付いたものの、家の工事、仕事に追いまくられて、なかなか読めませんでした。昨日、勤務先から速達で、麻疹のために1週間の休講の知らせ。思いがけない時に今日から4連休、まづこれを読もうと。
ありがとう。
こういうことを教えてもらえる青少年達に幸あれ。
拍手しながら読ませて頂きましたが、私の悪い頭では、通り過ぎてしまうので、コピーさせて頂き、大きな文字でもう一度、拝見いたします。
<国家に自衛権があるとすれば、唯一それは国民の固有の自衛権(正当防衛権)に基づき、国民による「厳粛な信託」がある場合に限られる。しかも、その場合でも厳密な意味ではそれは国家の権利ではない
総理になると、勘違いがひどくなるのでしょうか。
このあと憲法がどうなるかは、結局ぼくたちのような名もない多くの<国民>が<市民>としてどのような判断と行動を選択するかにかかっているのだと思います。
拙文がせめてそのほんの一助にでもなればいいのですが。
国家の「固有の権利」と「集団的自衛権」などの意味を歴史的文脈の中で徹底的に再吟味した、的確な反論・・・多くの国民が関心を持てば、護憲派の政治家、学者のみなさんも頑張って下さるのではないかという期待を込めて、許可を得られれば、髭彦さんのこの文章(問題提起)を友人知人にも広めさせて頂きたいのですが。
ここで、お名前を伺うわけにもいきませんので、出典を調べさせて頂き・・・。
ご迷惑なら、読ませて頂いたということで、留め置きます。
わたしも興味深く拝読させていただきました。
<このあと憲法がどうなるかは、結局ぼくたちのような名もない多くの<国民>が<市民>としてどのような判断と行動を選択するかにかかっているのだと思います。>
上記引用、そのとおりですね。
こうした言挙げは、自身の無力を痛感している無名者には眩しく痛いです。しかしながら認識は相当範囲で共有していますし、私自身は冷笑主義者にはなれないヒューマニストです。偽善者にもなれませんが。
ご労作に敬意を表し、深いところで痛みを分かち合っていますという思いを寄せたいと、コメントいたしました。
自分を律することが前提、それが制度や環境といった全体に反映する健康なシステムが、さまざまな分野であらためて模索されてほしいものです。
シンプルにやりなおしができないものか、という感じ。戦争するんじゃなくて、なんといいますか、くにづくり、つまり、人育て。それも少子化対策とかではなく、オトナの改造。教育者、学校の建て直しからでしょう、というのが、実体験からのわが悲鳴です。
かつての「運動」とは異なるカタチでないと時代的に有効とは思えませんが(そのあたりは感覚に世代差があるかもしれません。)、ネットの活用の功罪についてもあわせて考え込んでしまいます。
軽薄で冷酷な言葉を浴び、撒き散らしてきた現代っ子のひとりとして。
お写真もお歌もますます素敵です!
最近では柳と石畳。
夏風邪などおめしになりませんよう、お元気で。
ただし定年までは基本的に職場の友人にも内緒のブログですので、お手数ですが下記のアドレスにメールを下さるか、NDL-OPACの雑誌記事検索で調べていただくかしていただけませんでしょうか。
よろしくお願いします。
GZA01761@nifty.com