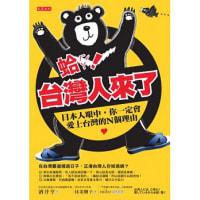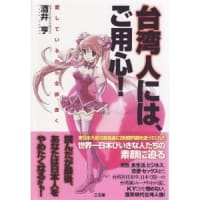なんども指摘していることだが、「倒扁運動」はそれ自体は訴えの内容も行動方式もおかしい。
たとえば、選挙で選ばれた大統領を任期途中で辞めろとか、道徳性などという封建的な概念を持ち出すところもおかしい。そもそも、そもそも赤い服を全員が着たり、やっていることが中国共産党のゲリラ戦術そのものだし、参加者もどうみても外省人反動派が主体で、04年に連戦が負けた後の国民党反動派の抗争の延長という感じだ。合法的な手段である罷免が成立しなかったからといって街頭抗争という手段に訴えるのは選挙をやっている民主国家にあるまじきこと。
ただし、冷静に見ていると、彼女ら・彼ら自身の意図とは別に新たな効果とか意味が出てきていると思う。
一つは、議院内閣制移行に向けた改憲論が民進党や国民党の一部に台頭してきたこと。もう一つは台湾意識の伸張である。
まず、議院内閣制については、従来民進党や国民党など主要勢力は否定的だった。
もっとも、中華民国憲法本文の制度設計では、大統領は議員団である国民代表大会による間接選出であり、その憲法上の権限はフランス並みでかなり限られたものだったのだが、蒋介石時代には憲法は運用停止で大統領独裁、さらに民主化以降は総統直接選挙にしたことから、大統領権限は強くなる一方で、実質大統領制に近い半大統領制(二重首長制)となってきた。
同じような歴史的背景や経緯を持つ韓国も似ている。
ただ、ここに来て民進党や国民党にも内閣制に変更しようという声が台頭しつつある。
これはある意味では、「倒扁」運動がもたらした効果かも知れない。
というのも、「倒扁」運動は陳水扁には道徳的に問題があるとして(この場合の道徳というのが蒋介石が持ち込んだシナ封建思想であるのは問題だが)、国の最高権力者には道徳性が必要だと訴えていること。さらに、道徳的に問題があるなら、最高権力者はそのつど交代させるべきであると主張しているからである。
ところが、普通は国民の直接選挙で選ばれた大統領には、「問題があるから辞めさせる」ということはありえない。大統領を選んだのが議会と同じく国民である以上、任期途中で大統領に国民のある部分が不満を感じても、それで辞めさせられるわけがない。そもそも大統領制や半大統領制は、そんな制度設計にはなっていない。
そういう点では、「倒扁」運動側の訴えは(半)大統領制という制度を理解していないっ非常識だということができる。
ただし、かといって、彼らの言っていることをさらに根源的に考えてみると、なるほど、彼らは必ずしも大統領制にこだわっていないことがわかる。
つまり、大統領には最高の道徳性を求めるとともに、最高権力者は常に適格性が判断され、民意や議会の動向によって交代させることが可能だという思想が垣間見える。
だとすると、これを満足するシステムは、議院内閣制しかない。
典型的にはドイツやイタリアに見られるのだが(最近はフィンランドもこれに移行しつつある)、大統領はあくまでも儀礼的な存在で実質権限はないが、高度の道徳性(この場合の道徳性はシナのそれではなくて、近代的なそれ)が要求される。ドイツのヴァイツゼッカーが好例だ。
首相は一義的には国会(あるいは国会だけ)に責任を持ち、国会から不適格を認定されたら、解散することもできるが、辞任しなければならない。
まさに「倒扁」運動側の要求にぴったりではないか?
もちろん、「倒扁」運動側の中核部分に入っている勢力は、国民党反動派であり、彼らは馬英九を08年の総統にと考えているはずだ。
だが、「倒扁」運動の要求を論理的に見ていくと、08年の総統選挙などいっそのこと廃止して、大統領は立法院と地方議会の代表からなる間接選出として儀礼的な存在にして、行政権力はすべて国会が選出する首相が持つという方式が適していることになるのだ。
もちろん、これは国民党反動派とその代表格である馬英九にとっては望ましくない制度であり、彼らが権力を握る希望は限りなくゼロになってしまうのであるが、とにかく「倒扁」運動が求めていることを素直に解釈すれば議院内閣制に移行して、総統選挙を廃止するしかないことになる。
しかも、実際、大統領選挙や(半)大統領制というのは、もともと国論を単純に二分し、二極化対立を生む一方で、行政と立法が異なる政党が占めた場合国政の麻痺や不安が続きやすい。
だから、米国をほぼ唯一の例外として、大統領制や半大統領制は安定しないシステムとなる。米国の場合は政党が弱く、政党の対立構造が明確ではないから、それでも機能するが、大抵の国では国政不安定化が、大統領独裁化を招くか、あるいは議院内閣制に移行するケースが多い。
特に台湾のように、藍緑対立、族群対立などの単純に分化しやすい問題を抱えているところでは、そもそも(半)大統領制は禁じ手なのである。
もちろん、台湾の場合は中国の脅威など軍事安保的な要素から、統帥権を明確にし強い大統領権限への欲求があるのは確かだし、だからこそ民主化以降も強い大統領権限が保持されてきたのだが、ただそれだけに着目して、恒常的な国政の安定を犠牲にするのは、結果的には安全保障も阻害される。実際、兵器購入予算が国民党の嫌がらせで通らないのが現実である。(ただし私自身は兵器によって安全保障という発想は時代遅れだと見ているが、それはともかく)。
しかも、藍緑のクリーヴィッジは実際には国家アイデンティティや族群のクリーヴィッジを反映していない。緑側が台湾独立ないし本土派であることは明確であっても、藍の全体が中国統一志向だとはまったくいえないからである。国民党の立法委員89人の中には、少なくとも20人は台湾本土派がおり、地方派閥出身なら中国志向とはいえないと考えるとすれば実に65人くらいは本土派とみなしうるからである。
しかも桃園県長の朱立倫は血統的には外省人とはいえ、思想は本土派に近く、さらに他の多くの国民党所属の県市長も本土派が多い。
だとしたら、現在の藍緑の対立は、本来台湾にある統一・独立の対立がそのまま反映されているのではなく、それが歪曲されたうえに抽象化され、実質的にはそれほど変わらない国民党本土派と民進党との間で政党の名前による溝を作り、さらにそれが抽象化された次元での対立を激化させているといえる。要するに、実質的な意味がないのである。
それを生んでいる制度的な欠陥は、大統領直接選挙と大統領権限が強い半大統領制にある。
議院内閣制に移行させれば、議会にも責任感も生まれ、さらに極端な対立や主張は敬遠され、中道的で協調的な勢力や政治家を主体に、そうした人物が行政のトップになりやすい。
もしそうでないことがわかれば、首相に不信任をつきつけて辞めさせることはいつでも可能である。
立憲君主国のほとんどは議院内閣制であり、さらに(半)大統領制に失敗した民主国家の多くが議院内閣制に移行したのは、議院内閣制がいかに安定的で穏健な性質を持っているかを物語っているといえる。
確かに国家元首を国民が直接に選び、選ばれた彼・彼女に強い権限を持たせるという現在の台湾の制度は、それが下からの民主化の流れの中で勝ち取られたという点も含めて、それ自体としては民主主義の極致ともいえる。しかし、いかんせん(半)大統領制は制度設計に無理が多すぎる。しかも台湾住民の多くは対立に疲れつつあるのだ。
そういう点では、「倒扁」運動が意図しなかった実質的な効果として、内閣制移行のための憲法論議が高まりつつあることは、結果的には良かったといえるかもしれない。
それから、台湾意識の伸張というのは、「倒扁」運動の本質や中核を考えれば意外な感じがするかもしれない。しかし、これも「倒扁」運動の過程では意外にも観察されたことである。
確かに、「倒扁」運動では、外省人保守派・反動派の参与が目立ったし、「台湾国人民は雨を恐れない」と叫んだ「倒扁」運動本部幹部が会場からブーイングを浴びる一方で、「中国人」「中華民国万歳」と叫んだ外省人政治家や芸能人は拍手を受けるなど、「倒扁」運動の色彩は、従来の国民党反動派集会の延長であり、深藍色が濃いといえる。
ところがである。
一方では、穏健な形での台湾主体・本土性の主張も、実は浸透し、使われているのである。
たとえば、「北原山猫」という深藍系統の原住民のポップスバンドがいて、今回も集会に参加していた。ところが、彼らの歌の中には原住民の各部族の名前が散らばれていて、それは北原山猫そのものの政治性を無視すれば、台湾独自性の突出と原住民に対する再認識につながるものである。
また、テレビ中継を見ていると、会場でよく流れた歌としては、台湾語の「望春風」「黄昏的故郷」「媽媽請li也保重」、北京語の「美麗島」「緑島小夜曲」など、かつては党外や民進党がよく歌ったものが多かった。まずこれが10年前なら間違いなく外省人や国民党系の集会では排斥され、民進党の集会だと思われたはずである。それが今回は外省人にも何の抵抗もなく受け入れられていた。
さらに15日のデモの最後には施明徳は「台湾の自由、民主、人権、平和、主権のため」の運動だと演説で表明した。それを外省人も多いはずの観衆も拍手を送っていた。
ひょっとして、「倒扁」運動本部の一部は、「倒扁」を叫ぶことで、深藍を引き寄せて、彼らに台湾主体性を徐々に植え付けることを狙っているのでは?と思えるシーンが多いのである。施明徳も長年の女と物への浪費から金に困って国民党の買収を受けたという噂があるとしても、それでも美麗島事件以前からの筋金入りの台湾本土派であり、今回の発言の端々にもその色彩は否定できない。また、王麗萍は今回「台湾国」と叫び、呂秀蓮系の「台湾心会」の地方幹部も務めていて独立派であることは間違いないし、簡錫[土皆]も左派独立派ともいえる思想を持っていて、台湾本土社民主義政党の立ち上げを狙っていることは知られている。だから、この間も民進党関係者が、施明徳などへの批判とは対照的に簡に対する批判は微妙に避けているように見える点でも、実は面白い構成になっているのだ。
これまでこうした緑系統が「倒扁」運動本部に入っていることを一部の軽率なメディアは「緑の中も分裂していて、陳水扁は孤立化している」と書いてきたが、実に皮相的な見方だといわざるを得ない。
そもそも街頭運動を展開しても陳水扁を辞めさせられるわけがないことは、深藍の人間だってわかっている。それでもこの運動に引き寄せられ、台湾語の歌や「台湾の主権」という施明徳の言葉に何の抵抗も覚えなくなっていくことで、結果的には台湾意識を知らず知らずに植えつけられているといえまいか?
もちろん、「倒扁」運動本部の幹部がそこまで策略を練って考えているというのは考えすぎだろう。多分、緑系の幹部の多くは単に陳水扁が嫌いなだけでやっていると考えられる。しかし、結果的な効果を見ると、外省人反動派が台湾語の歌や台湾主権なる言葉に何の抵抗も感じることなく、それらを受け入れている光景は実に意味深長だといえる。
これが、初めから民進党政権や緑陣営が企画したイベントや集会だったら、深藍の反動派は受け入れようとはしなかったに違いない。ただ、「陳水扁辞めろ」と叫ぶ集会だからこそ、本来は拒絶してきたはずの台湾本土の価値をも受け入れてやすくなっているのである。
「倒扁」運動本部の幹部の思いや想定、あるいはこれを民進党叩きの道具に利用しようと考えている反動派政治家たちの思惑とは裏腹に、実は今回の運動で、深藍や外省人反動派の民衆も着実に台湾本土の価値を受け入れるようになっているのだ。
これは逆に台連あたりも「利用」すべき方法かも知れない。つまり、わざと「陳水扁は不適格で辞めろ」と叫び、アホな反動派を引き付けて、徐々に台湾本土の価値を吹き込み、洗脳していくのである。
実際現在台連かそれに近い緑系の外省人知識人の中には以前は、外省人の典型の深藍だったのが、一挙に民進党を通り越して台連や強い独立派となっている例が多い。黄光芹がそうだし、周玉寇がそうだ。
だとすれば、深藍の連中は、伊達に「中華民国」という強い国家民族意識を持っているだけに、意外に簡単に、深緑、強い独立派の信者になることは可能だろう。
後世の歴史は、「倒扁」運動を深藍勢力が台湾本土の価値を受け入れ、台湾にアイデンティファイするための通過儀礼だったと記すかも知れない。
台湾は策謀を練っても常に裏目に出たり、逆の効果が発揮される社会である。だからこそ中国共産党の統一工作も裏目に出ることが多いのだが、現時点で見ると、今回の「倒扁」運動もその一つになっているといえる。
そういう点では、どうせ陳水扁は辞めさせられないし、馬英九の評判も低下するし、内閣制論も高まってくるだろうし、「倒扁」運動は続けてもらったほうがいいかも知れない(笑)。
たとえば、選挙で選ばれた大統領を任期途中で辞めろとか、道徳性などという封建的な概念を持ち出すところもおかしい。そもそも、そもそも赤い服を全員が着たり、やっていることが中国共産党のゲリラ戦術そのものだし、参加者もどうみても外省人反動派が主体で、04年に連戦が負けた後の国民党反動派の抗争の延長という感じだ。合法的な手段である罷免が成立しなかったからといって街頭抗争という手段に訴えるのは選挙をやっている民主国家にあるまじきこと。
ただし、冷静に見ていると、彼女ら・彼ら自身の意図とは別に新たな効果とか意味が出てきていると思う。
一つは、議院内閣制移行に向けた改憲論が民進党や国民党の一部に台頭してきたこと。もう一つは台湾意識の伸張である。
まず、議院内閣制については、従来民進党や国民党など主要勢力は否定的だった。
もっとも、中華民国憲法本文の制度設計では、大統領は議員団である国民代表大会による間接選出であり、その憲法上の権限はフランス並みでかなり限られたものだったのだが、蒋介石時代には憲法は運用停止で大統領独裁、さらに民主化以降は総統直接選挙にしたことから、大統領権限は強くなる一方で、実質大統領制に近い半大統領制(二重首長制)となってきた。
同じような歴史的背景や経緯を持つ韓国も似ている。
ただ、ここに来て民進党や国民党にも内閣制に変更しようという声が台頭しつつある。
これはある意味では、「倒扁」運動がもたらした効果かも知れない。
というのも、「倒扁」運動は陳水扁には道徳的に問題があるとして(この場合の道徳というのが蒋介石が持ち込んだシナ封建思想であるのは問題だが)、国の最高権力者には道徳性が必要だと訴えていること。さらに、道徳的に問題があるなら、最高権力者はそのつど交代させるべきであると主張しているからである。
ところが、普通は国民の直接選挙で選ばれた大統領には、「問題があるから辞めさせる」ということはありえない。大統領を選んだのが議会と同じく国民である以上、任期途中で大統領に国民のある部分が不満を感じても、それで辞めさせられるわけがない。そもそも大統領制や半大統領制は、そんな制度設計にはなっていない。
そういう点では、「倒扁」運動側の訴えは(半)大統領制という制度を理解していないっ非常識だということができる。
ただし、かといって、彼らの言っていることをさらに根源的に考えてみると、なるほど、彼らは必ずしも大統領制にこだわっていないことがわかる。
つまり、大統領には最高の道徳性を求めるとともに、最高権力者は常に適格性が判断され、民意や議会の動向によって交代させることが可能だという思想が垣間見える。
だとすると、これを満足するシステムは、議院内閣制しかない。
典型的にはドイツやイタリアに見られるのだが(最近はフィンランドもこれに移行しつつある)、大統領はあくまでも儀礼的な存在で実質権限はないが、高度の道徳性(この場合の道徳性はシナのそれではなくて、近代的なそれ)が要求される。ドイツのヴァイツゼッカーが好例だ。
首相は一義的には国会(あるいは国会だけ)に責任を持ち、国会から不適格を認定されたら、解散することもできるが、辞任しなければならない。
まさに「倒扁」運動側の要求にぴったりではないか?
もちろん、「倒扁」運動側の中核部分に入っている勢力は、国民党反動派であり、彼らは馬英九を08年の総統にと考えているはずだ。
だが、「倒扁」運動の要求を論理的に見ていくと、08年の総統選挙などいっそのこと廃止して、大統領は立法院と地方議会の代表からなる間接選出として儀礼的な存在にして、行政権力はすべて国会が選出する首相が持つという方式が適していることになるのだ。
もちろん、これは国民党反動派とその代表格である馬英九にとっては望ましくない制度であり、彼らが権力を握る希望は限りなくゼロになってしまうのであるが、とにかく「倒扁」運動が求めていることを素直に解釈すれば議院内閣制に移行して、総統選挙を廃止するしかないことになる。
しかも、実際、大統領選挙や(半)大統領制というのは、もともと国論を単純に二分し、二極化対立を生む一方で、行政と立法が異なる政党が占めた場合国政の麻痺や不安が続きやすい。
だから、米国をほぼ唯一の例外として、大統領制や半大統領制は安定しないシステムとなる。米国の場合は政党が弱く、政党の対立構造が明確ではないから、それでも機能するが、大抵の国では国政不安定化が、大統領独裁化を招くか、あるいは議院内閣制に移行するケースが多い。
特に台湾のように、藍緑対立、族群対立などの単純に分化しやすい問題を抱えているところでは、そもそも(半)大統領制は禁じ手なのである。
もちろん、台湾の場合は中国の脅威など軍事安保的な要素から、統帥権を明確にし強い大統領権限への欲求があるのは確かだし、だからこそ民主化以降も強い大統領権限が保持されてきたのだが、ただそれだけに着目して、恒常的な国政の安定を犠牲にするのは、結果的には安全保障も阻害される。実際、兵器購入予算が国民党の嫌がらせで通らないのが現実である。(ただし私自身は兵器によって安全保障という発想は時代遅れだと見ているが、それはともかく)。
しかも、藍緑のクリーヴィッジは実際には国家アイデンティティや族群のクリーヴィッジを反映していない。緑側が台湾独立ないし本土派であることは明確であっても、藍の全体が中国統一志向だとはまったくいえないからである。国民党の立法委員89人の中には、少なくとも20人は台湾本土派がおり、地方派閥出身なら中国志向とはいえないと考えるとすれば実に65人くらいは本土派とみなしうるからである。
しかも桃園県長の朱立倫は血統的には外省人とはいえ、思想は本土派に近く、さらに他の多くの国民党所属の県市長も本土派が多い。
だとしたら、現在の藍緑の対立は、本来台湾にある統一・独立の対立がそのまま反映されているのではなく、それが歪曲されたうえに抽象化され、実質的にはそれほど変わらない国民党本土派と民進党との間で政党の名前による溝を作り、さらにそれが抽象化された次元での対立を激化させているといえる。要するに、実質的な意味がないのである。
それを生んでいる制度的な欠陥は、大統領直接選挙と大統領権限が強い半大統領制にある。
議院内閣制に移行させれば、議会にも責任感も生まれ、さらに極端な対立や主張は敬遠され、中道的で協調的な勢力や政治家を主体に、そうした人物が行政のトップになりやすい。
もしそうでないことがわかれば、首相に不信任をつきつけて辞めさせることはいつでも可能である。
立憲君主国のほとんどは議院内閣制であり、さらに(半)大統領制に失敗した民主国家の多くが議院内閣制に移行したのは、議院内閣制がいかに安定的で穏健な性質を持っているかを物語っているといえる。
確かに国家元首を国民が直接に選び、選ばれた彼・彼女に強い権限を持たせるという現在の台湾の制度は、それが下からの民主化の流れの中で勝ち取られたという点も含めて、それ自体としては民主主義の極致ともいえる。しかし、いかんせん(半)大統領制は制度設計に無理が多すぎる。しかも台湾住民の多くは対立に疲れつつあるのだ。
そういう点では、「倒扁」運動が意図しなかった実質的な効果として、内閣制移行のための憲法論議が高まりつつあることは、結果的には良かったといえるかもしれない。
それから、台湾意識の伸張というのは、「倒扁」運動の本質や中核を考えれば意外な感じがするかもしれない。しかし、これも「倒扁」運動の過程では意外にも観察されたことである。
確かに、「倒扁」運動では、外省人保守派・反動派の参与が目立ったし、「台湾国人民は雨を恐れない」と叫んだ「倒扁」運動本部幹部が会場からブーイングを浴びる一方で、「中国人」「中華民国万歳」と叫んだ外省人政治家や芸能人は拍手を受けるなど、「倒扁」運動の色彩は、従来の国民党反動派集会の延長であり、深藍色が濃いといえる。
ところがである。
一方では、穏健な形での台湾主体・本土性の主張も、実は浸透し、使われているのである。
たとえば、「北原山猫」という深藍系統の原住民のポップスバンドがいて、今回も集会に参加していた。ところが、彼らの歌の中には原住民の各部族の名前が散らばれていて、それは北原山猫そのものの政治性を無視すれば、台湾独自性の突出と原住民に対する再認識につながるものである。
また、テレビ中継を見ていると、会場でよく流れた歌としては、台湾語の「望春風」「黄昏的故郷」「媽媽請li也保重」、北京語の「美麗島」「緑島小夜曲」など、かつては党外や民進党がよく歌ったものが多かった。まずこれが10年前なら間違いなく外省人や国民党系の集会では排斥され、民進党の集会だと思われたはずである。それが今回は外省人にも何の抵抗もなく受け入れられていた。
さらに15日のデモの最後には施明徳は「台湾の自由、民主、人権、平和、主権のため」の運動だと演説で表明した。それを外省人も多いはずの観衆も拍手を送っていた。
ひょっとして、「倒扁」運動本部の一部は、「倒扁」を叫ぶことで、深藍を引き寄せて、彼らに台湾主体性を徐々に植え付けることを狙っているのでは?と思えるシーンが多いのである。施明徳も長年の女と物への浪費から金に困って国民党の買収を受けたという噂があるとしても、それでも美麗島事件以前からの筋金入りの台湾本土派であり、今回の発言の端々にもその色彩は否定できない。また、王麗萍は今回「台湾国」と叫び、呂秀蓮系の「台湾心会」の地方幹部も務めていて独立派であることは間違いないし、簡錫[土皆]も左派独立派ともいえる思想を持っていて、台湾本土社民主義政党の立ち上げを狙っていることは知られている。だから、この間も民進党関係者が、施明徳などへの批判とは対照的に簡に対する批判は微妙に避けているように見える点でも、実は面白い構成になっているのだ。
これまでこうした緑系統が「倒扁」運動本部に入っていることを一部の軽率なメディアは「緑の中も分裂していて、陳水扁は孤立化している」と書いてきたが、実に皮相的な見方だといわざるを得ない。
そもそも街頭運動を展開しても陳水扁を辞めさせられるわけがないことは、深藍の人間だってわかっている。それでもこの運動に引き寄せられ、台湾語の歌や「台湾の主権」という施明徳の言葉に何の抵抗も覚えなくなっていくことで、結果的には台湾意識を知らず知らずに植えつけられているといえまいか?
もちろん、「倒扁」運動本部の幹部がそこまで策略を練って考えているというのは考えすぎだろう。多分、緑系の幹部の多くは単に陳水扁が嫌いなだけでやっていると考えられる。しかし、結果的な効果を見ると、外省人反動派が台湾語の歌や台湾主権なる言葉に何の抵抗も感じることなく、それらを受け入れている光景は実に意味深長だといえる。
これが、初めから民進党政権や緑陣営が企画したイベントや集会だったら、深藍の反動派は受け入れようとはしなかったに違いない。ただ、「陳水扁辞めろ」と叫ぶ集会だからこそ、本来は拒絶してきたはずの台湾本土の価値をも受け入れてやすくなっているのである。
「倒扁」運動本部の幹部の思いや想定、あるいはこれを民進党叩きの道具に利用しようと考えている反動派政治家たちの思惑とは裏腹に、実は今回の運動で、深藍や外省人反動派の民衆も着実に台湾本土の価値を受け入れるようになっているのだ。
これは逆に台連あたりも「利用」すべき方法かも知れない。つまり、わざと「陳水扁は不適格で辞めろ」と叫び、アホな反動派を引き付けて、徐々に台湾本土の価値を吹き込み、洗脳していくのである。
実際現在台連かそれに近い緑系の外省人知識人の中には以前は、外省人の典型の深藍だったのが、一挙に民進党を通り越して台連や強い独立派となっている例が多い。黄光芹がそうだし、周玉寇がそうだ。
だとすれば、深藍の連中は、伊達に「中華民国」という強い国家民族意識を持っているだけに、意外に簡単に、深緑、強い独立派の信者になることは可能だろう。
後世の歴史は、「倒扁」運動を深藍勢力が台湾本土の価値を受け入れ、台湾にアイデンティファイするための通過儀礼だったと記すかも知れない。
台湾は策謀を練っても常に裏目に出たり、逆の効果が発揮される社会である。だからこそ中国共産党の統一工作も裏目に出ることが多いのだが、現時点で見ると、今回の「倒扁」運動もその一つになっているといえる。
そういう点では、どうせ陳水扁は辞めさせられないし、馬英九の評判も低下するし、内閣制論も高まってくるだろうし、「倒扁」運動は続けてもらったほうがいいかも知れない(笑)。