<初舞台だよ!>
公演名をフルネームで書くと「三代目家元 梅茂都陸平二十三回忌追善」。
ムム。舞踊と舞の違いもわからない私が、ナンデそんなところに?
「梅茂都(うめもと)」とは上方舞の一つの流派で、四代目家元後継者となる
ことを先日発表した愛之助さんが、この日初めて舞台を勤めるという。
せっかくの機会なので行ってみた。
|
この日は梅茂都梅咲さんをはじめとする梅茂都流一門の人々はもちろん、日本
舞踊を代表する各流の人々も、二代目梅茂都扇性さん振付の作品で舞う(一部
を除いて)という趣向だった。
梅茂都と同じ上方舞の主要流儀の家元も参加され、吉村輝章さん、井上八千代
さんはその流儀で、山村若さんは梅茂都流でそれぞれ舞を披露された。
そして最後に登場したのが愛之助さん。
この日も「蝉しぐれ」昼の部を終えての舞台!
あくまでも個人的な印象だけれど、愛之助さんの梅茂都での初作品は歌舞伎の
動きと梅茂都流の振付を融合したような舞台だった。歌舞伎を知っている人に
はなじみのある題材で、「松嶋屋ーーーっ!」なんて声もかかったしね!(笑)
追いかけ五枚銀杏に梅の御紋も加わった、今の愛之助さんの立場を象徴するか
のような演目。いつか歌舞伎の興行で梅茂都の舞を上演したいと語っていたの
が、すぐにでも実現しそうな気がしましたよー♪
<梅茂都ってどんな舞?>
一日中ただ見ていただけで、梅茂都の何かがわかるワケもなく(グスン)。
(参考サイト:上方舞 梅茂都梅衣華の世界
9/26追記:ブログに訪問させて頂いた事がきっかけで山村若伸紀様が上方舞
について下のコメント欄に説明を寄せてくださいました。山村若伸紀様のサイ
トはこちら。ブログはこちらです。)
司会の桂文我さんがしゃべっておられたことを思い出して書いてみよう。
梅茂都の作品には生き物がよく登場するそう。この日も猫、鼠、蛙が出てきて
独特のお茶目な動きを楽しませていただいた。
(愛之助さんが舞う演目も<狐>だったんですよね!)
また、他の流派の方たちに梅茂都の特徴を尋ねたところ、多かった答えは・・・
<振りが細かい><艶っぽい>とのこと。
私が見ても、目線や首から上の動きが柔らかく艶っぽいと感じたし、物事の情景
が目に浮かぶような細やかな振付は上方歌舞伎の和事に通じるように思えた。
<狐忠信再度の旅って?>
そんな前フリがあって、ようやく愛之助さんの「狐忠信再度の旅」へ。
ここまでで相当見疲れしていたが、愛之助さんが登場するとシャキッ!(笑)
ちなみにこのお話、「義経千本桜」の四の切の後日談だそう。ほお~。
ネットで調べても出てこないってことは、梅茂都のオリジナルだろうか?
しかも、ここまでずっと長唄だったのが、この演目だけ義太夫に。
浄瑠璃はなんと! 豊竹咲大夫さんと咲甫大夫さん。
愛之助さんを見つつ、咲大夫さんの絞り出すような声にシビれ、咲甫大夫さん
のハリのある声にビシバシ反応し、三味線の音色を感じながらの贅沢な舞台♪
以下、長々と。初見の上にイヤホンガイドもないため多々まちがいだらけだと
思うが、書かないよりは書いたほうがいいかな、ということで。
(特に、狐忠信なのか本当の忠信なのか、混乱している箇所あり。)
●「狐忠信再度の旅」(きつねただのぶにどのたび) 片岡愛之助
作曲:初代鶴澤道八 振付:二代目梅茂都扇性
(義太夫 浄瑠璃:豊竹咲大夫、豊竹咲甫大夫 三味線:鶴澤燕三、鶴澤清旭)
於 国立文楽劇場 9月22日(日)
あらすじ(ご注意:勝手に解釈したもので、内容は全く自信ありません!!)
旅支度の忠信。秋の風景を見ているうちに源平の戦いを思い出す。かと思えば、
狐忠信、人間の子供が遊んでいる姿を見て故郷に残してきた子を思い出してし
まう。そこで、鼓を出して戯れる狐忠信。鼓を見ると嬉しい気持ちが隠せない
様子。だが、ふと思う。これは初音の鼓。義経様から頂いたもので、その時に
「源九郎」の名も賜った。でも、この鼓の皮は我が父と母。畜生といえども親
を想う気持ちは人間と同じと、涙を流す源九郎狐(狐忠信)。ひとまず故郷に
帰る決意をする。忠信様(?)とは再び吉野で会いましょう、おさらば、と別
れを告げて。(約30分間)
緞帳が上がって現れたのは定式幕。太鼓の音も聞こえる。
幕があいて、舞台セットは秋の田舎の風景。
稲架をくぐるように向こうから忠信(愛之助さん)が登場。
顔は白塗り、スキッと美しい歌舞伎メイク。
黒の着物に荷を背負った旅姿。髪型は義経千本桜の忠信ふう。
出てくるなりいきなり見得が決まるので「松嶋屋ーーっ」の声がかかる。
(あれ、まるで歌舞伎や~♪ 松嶋屋!って、ここは楳茂都やっちゅうねん。)
2匹の蝶がヒラヒラ~。それを見て手を前に出し、ピョン、ピョンと追いかけ
たりして遊ぶ。(ってことは狐のほうの忠信?)
前に出てきたり、動きの中で小さな見得がピシピシ入る。
辺りを見渡せばすっかり秋景色、紅葉もしている。
~赤い木は源氏 白い木は平家~♪(浄瑠璃の声)
木を源平の武士になぞらえて、回想モードの表情。(←これは人間の忠信?)
思い出すのは屋島の戦い。小さな船で漕ぎ出たが波が高く・・・。
このあたり歌に合わせて舞の振付が入っている。
たとえば、扇子を使って船を漕ぐ動きや、手に持った扇をパッと放し片手で持
ち替えたり、すり足のように横に移動したり(和風ムーンウォーク?)。また、
扇を使って春風や波を表現したり。
素敵~!!と思ったのは那須与一になって矢を射る振り。右耳の横で弓を構え、
パッと矢を放った瞬間に指がピシッと伸びて、目が矢を追う。
着物を赤に替えて、狐忠信。人間の子供が戯れている光景を見て感傷モードに。
故郷に残した妻や子を思う表情になる。(憂い顔にウットリ~。)
ここで、鼓が登場!
急に嬉しそうな顔になり、ピョンピョン跳ね回る。鼓を跳び越えてきて見得を
決めたりもする。それが本当の狐の姿になる。
(愛之助さんは隠れ、作り物の狐が登場。狐人形は耳が動いたり、口がパクパ
クしたりしてカワイイの!)
白のフサフサした四の切の狐の衣装を着て、愛之助さんが再登場。耳もある。
すんごいウレシそうな顔をして、鼓といっしょに戯れる振りがお茶目で可愛い!
身軽な動きでジャンプし続けたり、鼓の横で寝っころがって手足を曲げたまま
バタバタさせる仕草が可愛いすぎる~♪
すわったままチョコチョコ走るのは歌舞伎の源九郎狐の動き。その場で四つ足
のままクルクル回るところで拍手!!
後ろ向きにすわったまま、海老ぞりになりながら鼓をつかんで、拍手!!
その鼓の紐を口にくわえて前を向く。
鼓をおしいただく動作を2回。これは義経に鼓をもらった時の回想?
初音の鼓を見て親を思い出し、すごく悲しそうな顔。顔に手をやり涙を流す。
狐の衣装から(ぶっ返りのような)白の着物に早替え。
(しばしおさらば!と浄瑠璃の声。)
その場でグルグル回ったり、見得がいっぱいの、ほとんど歌舞伎みたいな見せ
場が続く。一番最後も見得を決めて、大拍手~!!
以上。
愛之助さんの梅茂都でのデビュー、立派に勤めておられたと思います。
舞の事も歌舞伎の事も知らない私なんかが言うのもおこがましいのですが。
明日は最後の文四郎。狐忠信を脱いだ松竹座の舞台を私も楽しんできま~す。















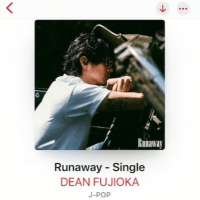
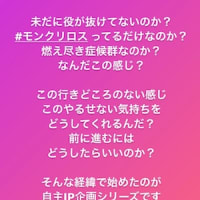
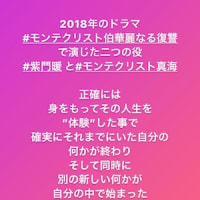


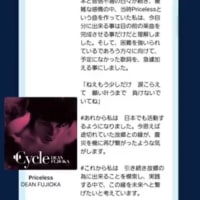











そう、あの梅茂都流の家元就任のニュースには驚いたもんです。
いよいよ本格的にそちらの方の活動も始まったのですね。
狐忠信のその後というのは、また愉快ですね。歌舞伎ファンにも取っ付きやすい演目ですね。
歌舞伎もまだそんなに分からない私には、舞踊はまた更に遠い感じがするものなのですが、こういうものから入っていくと面白くなるのかもしれないですね。
ちなみに歌舞伎での愛之助さんの狐忠信も見てみたいなぁ、なんて思ったりもしました。(^-^)
しまった~。f(^_^;
ムンパリさん、調べ物までされて、本当に頭が下がります。
やはりこの姿勢にも愛之助さんへの「愛」を感じましたよん♪
そうなんですよ。舞踊と舞があるんですよ。今まで私もそんなことぜーんぜん知りませんでした(汗~)。
調べ事っていうのは、今回の演目が梅茂都流のオリジナルかどうか知りたかったんです。義太夫を演じられた人たちを見て、文楽作品なのかな?と思ったので。個人的な興味ですけどね~。
源九郎狐は私もとっても好きなキャラなので、あの衣装を着た愛之助さんが見られて嬉しかったです~♪ ぜひ歌舞伎のほうでも演じてほしいですよね! 宙乗りとかもありますしね。
「狐忠信再度の旅」は、「義経千本桜」四段目通称「忠信」をパロディ化した作品だそうです。
江戸時代から明治大正までの素浄瑠璃の流行を背景に成立した曲に振りを付けたものと考えられる。。。と物の本に書いてありましたので、歌舞伎の「忠信」とは少々異なるようですね。
原作が静との道行きなのに対し、この曲は初音の鼓を譲り受けた後の狐忠信一人の道行になってます。
ですから「再度」と言うことらしいですね。
日本舞踊は、基本歌舞伎舞踊の舞踊部分であるのに対し、舞は能の流れを汲んだものです。
日本舞踊という名称自体、明治に西洋舞踊が入ってきてからの対語として生まれたようなところがあり、日本舞踊として固まってきたのは、明治時代以降になります。
舞は能の「仕舞」が発展し、その後武士の台等と共に武士の一般教養として広まり、その時には能役者の舞ではない教養としての舞(幸若舞等)として広まり、江戸時代に町人たちの間(上方)の一般教養として発展しました。
よく芸者さんたちの踊りを例に挙げられますが、特に大阪は船場のいとさん、こいさんの教養、行儀見習いの意味で一般市民に広まってきたものです。
ですので日本舞踊が「舞台で踊る」を基礎としているのに対し、地唄舞は「部屋の中(座敷)で舞う」事に重きを置いたものと言うことになります。
でも昔はやはり舞踊家ですから上方歌舞伎の振り付けなどもしていたと言うことなので、そう言う役者さんの踊りと、芸者さんたちの踊りとお嬢さんたちの踊りの三通りがあると考えていただけたらよいかと思います。
こんな説明でお分かりになったでしょうか?
説明下手ですみません。
うわ~!わざわざこちらにお越しくださったのですね。どうもありがとうございます。そのうえ大変詳しくてわかりやすい説明を頂き、恐縮し感激しております。
今回なぜ文楽の太夫さんがおられたのか、なぜ「再度」というタイトルなのか、疑問がいっぺんに解けました。やはり素浄瑠璃が先にありき、なのですね! 狐忠信一人で再び、なのですね! 納得でございます~♪
時代劇で信長が舞う「幸若舞」はそのような流れの中にあるんですねえ! 船場のいとさん、こいさんの教養というのは映画「細雪」の台詞につながりますね♪ とてもよくわかりました。
> 地唄舞は「部屋の中(座敷)で舞う」
先日拝見した「座敷舞 道成寺」ですが、歌舞伎でよく見るのとは全然違っていました。舞台ではなく、座敷で舞うからそのような振りになるのですね。
ということは、やはり愛之助さんの今回の舞は座敷用とは考えられないですから、もしかしたら元々歌舞伎用に振付されたものかも、と思えてきました。のぶき様が書かれていたように、私も次回は愛之助さんによる地唄舞をじっくり拝見したいです。
この記事の<梅茂都ってどんな舞?>の参考サイトとして、山村若伸紀さまのページとブログを追記させて頂きますね! このたびは本当にありがとうございました。
咲甫さんが大夫を勤めたと教えていただいた時は、
ホンマに気絶しそうでした(苦笑)
急に決まったのでしょうか?ね。
それにしてもわざわざ東京から…ですもん!
レポを読ませていただくと、ホントに楳茂都流と関係あるの?と
思ってしまう出し物ですね。それでも歌舞伎とは違うんですね。
ある意味貴重かもしれない愛之助さんの狐忠信、観たかったです!
舞踊と舞の違い。
>日本舞踊が「舞台で踊る」を基礎としているのに対し、
>地唄舞は「部屋の中(座敷)で舞う」
コメントでののぶき様の言葉に納得しました。
これから私も少しずつ楳茂都流の舞について勉強させていただきたいと思います。
私も当日知ってビックリ。こらぁ知らせなアカンやろ!と。
大夫さんお二人とも、翌日はすぐに東京に戻られたんでしょうね! そこまでしてわざわざ愛之助さんのデビューに?と思って調べてみたんだけど、今回の演目の作曲者、初代鶴澤道八さんって、どうやら咲甫大夫さんにものすごく縁の深い人のようですよ~♪
狐忠信、今回のが歌舞伎用に振付されたものなのかどうかは、ぜひぜひ家元後継者にお聞きしたいですが~(笑)。初舞台を勤められた感想なり説明をどこかで目にする機会がありますように!