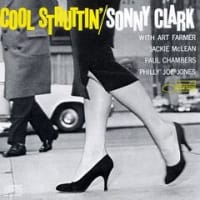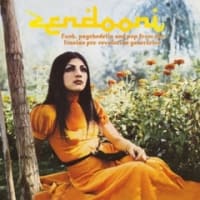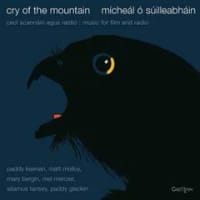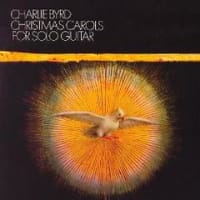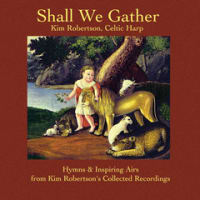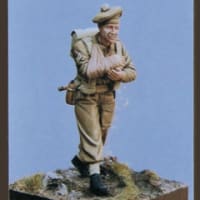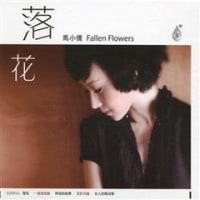当時、というか今でもあるんでしょうが、東京は新宿御苑の近くに御苑スタジオという音楽スタジオがあって、そこが、はっぴいえんど御用達の場所だった。音作りとかも、そこに籠もってやっていた。で、私達がバイトでやっていたのは、そのスタジオに行ってアンプ類を借りだし、車に積んでライブ会場に運び、ステ-ジに設営し、ライブが終わったらそいつを再び車に乗せ、御苑スタジオに返す、というのがメインの仕事だった。(時期的には、「風街ろまん」制作期とほぼ重なる?)まあ、ほかに細かい仕事もあったんだけど、いちばん情けないのは、大嫌いな岡林信康(注)のコンサ-トのビラ配りでしたね。まあ、それはこの場合、関係はない。
(注)私が通った高校というのが、「これから進学校に成り上がろう」との学校側の野望(その後、挫折)に沿って集められた、半端なエリ-ト意識の持ち主ばかりが通う、学生運動と反戦フォ-クの牙城とも言える所で、高校当時の私と言えば、以前書いたように、その真っ只中で落ちこぼれのロック少年を孤独にやっていたわけで、それは風当たりも強かった。当然、「学友諸君」の崇拝の対象だった岡林など、嫌悪の対象でしかなかったのであります。
私はそのスタジオで、はっぴいえんどの新曲のリハ-サルに偶然立ち会った事がある。と言っても時間にしてほんの数分程度のものだったが。大滝詠一がスタジオとガラス1枚隔てた調整卓のある場所に座り、バンドのメンバ-というよりはディレクタ-然として、スタジオの中の3人にこまごまと指示を出していたのが印象的だった。もっとも、「大滝の曲は大滝が主導権を握る」という事だったのかもしれないが。ちなみにその「ウッドストック」調?の曲、「はっぴい」のどのアルバムにも収録されていない。没曲だったのかと思うと、もっと気を入れて聞いておけば良かったと反省したりする。
こうして昔のことを思い出し思い出し書いていると、「あの頃、結構面白い場面に出くわしたり立ち会う機会があったのに、それに積極的にかかわりもしなかったし、きちんと記憶にとどめてもいない。惜しいことをしたなあ」と、ザンキの念に耐えない。馬鹿な私は、あの貴重な日々を「わ-いわ-い、まいにちおんがくだらけでうれしいな、わ-い!」と、浮かれ騒ぐだけで浪費してしまったのだ、振り返れば。
数少ない「記憶にある決定的瞬間」は、例えば以下のようなものしかない。
(はっぴいと岡林が開演前の会場で音合わせをしていたのだが、その過程でマイク&マイクスタンドが一式、足りないことが分かった。我々バイト軍団に「あれだけ取りに、もう一度スタジオに引き返すのかよ-」とウンザリ気分が走った。と、大滝詠一が岡林の抱えたフォ-クギタ-の前に置かれたマイクスタンドを掴み、「これ、いらないっスよね。これ、使いましょう」と言ったのであります。皆は、「ああ、そう言えばそうだよな、それはいらね-や、ああなるほど、それを使えばいいや、そうだそうだ」と頷いて一件は落着したのだが、「どうせ俺のギタ-は役に立ってね-よ」と怒った岡林はギタ-を投げ捨て、マイクを握って唄いだした。はっぴいえんどをバックに唄いだした頃の岡林は、初めはギタ-を抱えて歌っていたが、ある日を境にマイクのみを握って歌うようになる。そうなる瞬間を、私は目撃したのだ)
ああ、くだらない。こんな事しか覚えていないのだ、私は。
Y.Nさんが紹介しておられる、なぎら氏の「はっぴいは巧いバンドだった」証言と、M.Oさんのご覧になった、パッとしないはっぴい&岡林の図、必ずしも矛盾はしません。しばらく真近にいた者として証言しますが、そもそもはっぴいえんどのライブ、面白いものではありませんでした。(1曲だけ例外あり。後述)ましてや、必ずしも音楽的に近しいものがあるとは言えない岡林の、どれだけやる気を出していたか怪しいバッキング(なにしろ「これいらないっスよね」だ)ですから。
今にして思えば彼等、「自分たちはレコ-ディング・バンドである」との自負に自縄自縛となっていたのではないか。ある程度のテクニックはありながら、それをライブでは、どう生かすか、そのすべを知らなかった。知らなくても構わないと信じていた。彼等はその結果、「ライブ」そのものを持て余し、客にどうアピ-ルすべきか分からなくなっていた様な気がする。彼等よりずっと不器用で、あれしか出来なかったのでは?と思える「初期のはちみつぱい」の演奏が、にもかかわらず妙な妖気を放っていたのとは対照的な姿だった。
と、勝手なことを言えるのは、上で述べかけた「1曲の例外」があるから。それは、ライブに於ける「はいからはくち」という曲の存在である。当時の野音の客席には、何のスリクをやっているのか知らないが、ステ-ジの演奏とは無関係にその場に寝ころがり、自分一人のサイケデリック・ワ-ルドに入ってしまっているヒッピ-氏が、必ず何人かはいたものだが、はっぴいが「はいからはくち」を始めた途端、そんな連中が起き上がり、「イエイ!」とか喚いて踊りはじめた、なんて光景を私は一度ならず見ている。実際、妙に快調な「乗り」を、はっぴいえんどは、あの曲を演奏するときのみ、例外的に見せてくれたのだ。
ご存じの通り「はいからはくち」は、軽佻浮薄な若者風俗を自虐的な戯画として描き出した曲である。つまり、「ロックン・ロ-ルだぜっ!」と盛り上げた後、「なんちゃって!」で済ますことの可能な曲なのである。そんな無責任性を内包する故にこの曲は、はっぴいのメンバ-を、「レコ-ディング・バンド」の自負から、つかのま解放し、彼等なりのどさくさ紛れのロック魂を炸裂させたのだ、と私は考える。また、その瞬間を何度も目撃しているからこそ、私はあえて断言するのである。「はっぴいえんどのステ-ジは、一曲の例外を除いて、面白いものではなかった」と。
妙なこだわりを捨ててド-ンと行っちゃえば良かったのに、と言うのは今の時代の感性です。当時は、各自が自分のメンタリティを守るために、そんなこだわりに入り込んだりもせずにはいられない、トンチンカンな未踏の時代だったのだ、とでも言っておこうか。