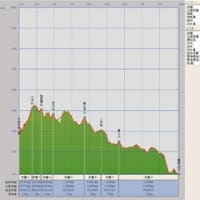目黒の自然教育園から恵比寿のガーデンプレイスへ散歩
今日は格別暑い日でした。
予報では35℃と云っていましたが、多分それ以上では・・・。
目黒駅まで電車で、そして帰りも恵比寿駅から電車で帰りました。
もう、暑くて、暑くて、歩く元気は出ませんでした。
歩いたルートは下の赤線です。5kmぐらいでしょうか。
何時もの地形図ソフトの調子が悪く、市販の地図を下敷きにして作りました。
さて、パンフレットによると、
「自然教育園の生い立ちは、今から400~500年前の豪族の館から始まります。
江戸時代は、高松藩主松平頼重の下屋敷となり、
明治時代は陸・海軍の火薬庫、
大正時代には白金御料地へ 歴史を重ねてきました。
この間は、一般の人が立ち入ることが出来なかったため、
この地に豊かな自然が残されました。
昭和24年(1949)に天然記念物および史跡に指定され、一般に公開されるようになりました。」
とありました。
入口近くには、ヤブランが静かに、私を迎えてくれました。
そして、水生植物園の辺りには、ミソハギが背伸びして迎えてくれました。
しかし、表示板は多いが、殆ど花は咲いていませんでした。そういう暑い時期なのです。
花は少ないが、大木がうっそうと茂り、その巨大さに圧倒されました。
武蔵野の面影をそのまま残していて、起伏も多く、また溜池もあちこちにありました。



ちょっと横途にそれて思うに、
小田原城攻略直後、秀吉にiいわれ、開らけた駿府から、この未開の地・江戸に移された家康や家臣の心中は如何でしたでしょう。
しかし、やや長い目で見て、結果は家康の勝ちになりましたね。
江戸に移封したのは、秀吉の読み違いと思いますが・・・。「歴史」の面白いところです。
巨木の立ち並ぶ園内を歩いていると、「マツ林の移り変わり」という掲示板がありました。
「この林は1950年頃にはまだ若いマツ林でした。
しかし、自然教育園になって、下刈りなどの手入れを止めると
ウワミズザクラ・イイギリ・ミズキなどの落葉樹やスダジイ・タブノキなどの常緑樹がマツ林の下に育ってきました。
1963年頃には、マツは下から育ってきた落葉樹の高木に光をうばわれて枯れ始めました。
今ではその落葉樹も、成長が遅かった常緑樹が高くなるにつれて下枝などが枯れ始めています。
やがてこの林は、長い年月の間には、スダジイなどの常緑樹林へ変わっていきます。
このように、林が時間と共に変化していくことを『遷移』といい、
遷移が進んで変化の少ない安定した林を『極相林』といいます。」
また、別の所には「コナラ林」の説明板がありました。
「昔から詩や歌によまれ人々に親しまれてきた雑木林(コナラ・クヌギ林など)は、
薪や炭に利用するため下刈り、落ち葉かき・伐採などつねに人間の手が加えられました。
しかし、放置すると目の前に見られるような樹齢約100年の大きなコナラになります。
林の下にはコナラの若木や芽生えが見当たりません。
光不足のため芽生えが育つことができないのです。
このコナラ林もやがてはシイ・カシなどの常緑樹へと移り変わっていく運命にあります。」
そして、この暑い植物園を後に、ビールを飲みに急ぎました。
ビアステーションへ来るのは初めてです。豪華な街になっていました。
むかし、恵比寿駅からこの辺まで、動かなくなった食堂車が並んでいて、その中でビールを味わったように記憶していますが、様変わりです。
いまは動く歩道になっていて、強引にビアステーションへ案内してくれています。
ただ、びっくりしたのは、恵比寿駅ホームから狭い陸橋を渡って、あるデパートに通った覚えがありますが、
その陸橋は昔のまま残っていました。
そこにはダンスホールがありました。
美女たちが華やかにアーク状に並んで我々を迎えてくれていましたが・・・。