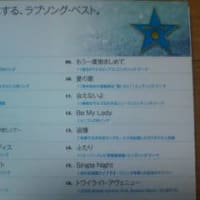「読売新聞・ケアノート」
『垣添忠生さん』
「自宅で妻の最期みとる希望かなえられて幸せ」
「妻は私の勤務先の病院に入院していたので、時間を見つけては病室を訪ねていました
国立がんセンター名誉総長の垣添忠生さん(68)は、2007年末に妻・昭子さんをがんで亡くしました。
「つらい経験だったが、最期に本人の希望通り自宅で過ごさせてやれたことは良かったと思う」と振り返ります。
☆率直に事実伝える
06年春、妻の右肺中心部に、4ミリ×5ミリぐらいの影が見つかりました。その数年前にも妻は肺の腺がんと甲状腺がんを患っていましたが、今度のがんは「小細胞がん」といい、腺がんよりも発育が早く転移しやすいがんでした。
抗がん剤と放射線による治療をしましたが、07年10月、脳、肺、肝臓、副腎への転移が判明。私は奈落の底に突き落とされました。
昭子さんは垣添さんより12歳年上。周囲の大反対を押し切っての結婚だったという。病弱ながら、垣添さんの海外出張にも同行し、国内外の研究者と家族ぐるみで交流するなど、多忙な垣添さんの仕事を支えた。
子どもがいなかった二人は、休日には登山やカヌーを共に楽しみ、強い絆(きずな)で結ばれていた。
妻には事実を率直に伝えましたが、取り乱すこともなく、淡々としていました。
検査の時の様子から、結果が良くないことは薄々感じていたのでしょう。
すぐに入院し、抗がん剤の治療を続けましたが、効果よりも副作用がひどく、口内炎で水を飲むのもつらい様子でした。
この頃の妻はもう、自分の命をあきらめていたのかもしれません。一度だけ「こんなにつらい治療を受けているのは、あなたのためですよ」と言われ、絶句したことがありました。
そんな妻が唯一強く希望していたことは、「年末年始は自宅で過ごしたい」ということでした。
07年12月には、昭子さんは背中や脚がむくみ、起きあがれない状態になっていた。垣添さんは、妻の希望をかなえるため、在宅用の医療機器や医薬品、酸素などの手配を進めた。
当初は訪問看護師を頼む予定にしていましたが、家の中に知らない人がいたら落ち着かないだろうと、すべて私が世話をすることにしました。
看護師から、点滴の自動注入ポンプの取り扱い方法などの猛特訓を受けました。
12月28日、久しぶりに自宅に帰ると、妻はたいそう喜びました。
夕食は妻のリクエストで九州から取り寄せておいた、アラという白身魚の鍋。
抗がん剤の副作用で食べ物を口にするのがつらいはずなのに、おいしそうに食べてくれました。「連れて帰ってきて本当に良かった」と私もうれしかったですね。
が、夫婦として普通に会話を交わせたのは、この時が最後でした。翌日からどんどん容体が悪化し、30日には意識も遠のき、大みそかの夕方、静かに息を引き取りました。
最期の時を、妻の希望通り自宅で過ごさせてやれたことは、本当に幸せなことだったと思います。が、もちろん、これは非常に恵まれたケースであることは分かっています。
私が医師であり、妻の入院していた病院が私の勤務先でもあったことなどから、こうしたことが可能になりました。普通は最期を自宅でと願っても、実現するのはなかなか難しいことです。
家庭と医療機関、訪問看護ステーションが連携して、希望すれば誰もが自宅で医療を受けられる態勢を、早く整える必要があるでしょう。
昭子さんの生前の希望通り、葬儀はせず、その死を積極的に周囲に知らせることもしなかった。
火葬も済み、1月5日にがんセンターに出勤すると、机の上に仕事が山積みになっていました。昼間は仕事に没頭していれば、妻のことを考えなくて済むので良かった。
問題は夜と週末。妻はおしゃべりだったので、家ではいつも二人でいろいろな話をしていました。その話し相手がいないのがつらかった。寂しさを紛らわすため、大量に酒を飲み、満足な食事を取らなかったため、体重が激減しました。
☆今でも妻はそばに
ようやく少し上向きの気持ちが出てきたのは、3か月を過ぎた頃。こんな私の状態を、妻は決して喜んではいないだろう。それに、今後は一人で生きていかねばならない。そのためには健康が大切、と思うようになりました。
まず、朝食を自分で作って食べることから始めました。夜は週の半分は外食ですが、それ以外は自分で作って食べる。妻が病弱だったため、もともと一通りの家事が出来たのが幸いでした。
二人の趣味だった登山とカヌーも、一人で再開することにしました。
08年の夏、日光の奥白根山に登った時のことです。道を間違えてくたびれ果てて、ひと休みしていた時、1メートルも離れていない目の前にメボソムシクイという野鳥がとまり、のどの奥まで見えるほど大きな口を開けて「チュルチュルチュル」と鳴くんです。妻が「あなた、こんなところで何してるのよ」と励ましてくれているように感じました。
ほかの山でもナキウサギが私の袖に触れるほど近くをバーッと横切って行ったり、アサギマダラというチョウがいつまでもヒラヒラと近くを舞っていたり……ということがあり、いつも私のそばに妻がいてくれると感じます。(聞き手・森谷直子)
※
かきぞえ・ただお 国立がんセンター名誉総長。1941年、大阪府生まれ。67年に東大医学部卒業後、都立豊島病院泌尿器科などを経て、75年から同センターに勤務。2002年4月から07年3月まで同センター総長。同4月から名誉総長。著書に「妻を看取る日」(新潮社)など。
◎取材を終えて 妻の死を公表せず、国立がんセンター名誉総長として多くの公的な仕事をこなしながら、一人で苦しんでいたことを知り、驚いた。その後、自ら計画的に生活を立て直していった過程は力強い。体を鍛え直そうと、腕立て伏せを1日数回から始め、今では1日70回、腹筋350回、スクワット100回をこなすという。「筋力を鍛えていると、体だけでなく心も上向きになっていくのを感じました」という言葉が印象に残った。
(2010年2月14日 読売新聞)
---------------------
8/23の朝刊、1面「地球を読む」(2面に続く)で
「伴侶の死に悲嘆ケアを」という見出しの記事を書かれていました。
以下に記すのは、がんを患っていた妻を自宅で看取った私の極めて個人的な体験と、
それに根ざしたがんの在宅医療、そして残された者の心のケア、いわゆるグリーフ・ケアに関する考察である。…中略…
国のがん対策推進基本方針計画は12年、当初の5年間の成果を評価し、後半の5年に向けて見直しが加えられる。
その際、こうしたがんの在宅医療やグリーフ・ケアに関する視点も積極的に取り入れる必要があると強く思う。
---------------------
奥様を「がん」で亡くされた経験は、悲しいことですが、
国立がんセンター名誉総長として、医療従事者だけの視点でなく、
家族の視点からも「今後のがん治療のあり方」を提言していただけることは、
世の中にプラスになると思います。
『垣添忠生さん』
「自宅で妻の最期みとる希望かなえられて幸せ」
「妻は私の勤務先の病院に入院していたので、時間を見つけては病室を訪ねていました
国立がんセンター名誉総長の垣添忠生さん(68)は、2007年末に妻・昭子さんをがんで亡くしました。
「つらい経験だったが、最期に本人の希望通り自宅で過ごさせてやれたことは良かったと思う」と振り返ります。
☆率直に事実伝える
06年春、妻の右肺中心部に、4ミリ×5ミリぐらいの影が見つかりました。その数年前にも妻は肺の腺がんと甲状腺がんを患っていましたが、今度のがんは「小細胞がん」といい、腺がんよりも発育が早く転移しやすいがんでした。
抗がん剤と放射線による治療をしましたが、07年10月、脳、肺、肝臓、副腎への転移が判明。私は奈落の底に突き落とされました。
昭子さんは垣添さんより12歳年上。周囲の大反対を押し切っての結婚だったという。病弱ながら、垣添さんの海外出張にも同行し、国内外の研究者と家族ぐるみで交流するなど、多忙な垣添さんの仕事を支えた。
子どもがいなかった二人は、休日には登山やカヌーを共に楽しみ、強い絆(きずな)で結ばれていた。
妻には事実を率直に伝えましたが、取り乱すこともなく、淡々としていました。
検査の時の様子から、結果が良くないことは薄々感じていたのでしょう。
すぐに入院し、抗がん剤の治療を続けましたが、効果よりも副作用がひどく、口内炎で水を飲むのもつらい様子でした。
この頃の妻はもう、自分の命をあきらめていたのかもしれません。一度だけ「こんなにつらい治療を受けているのは、あなたのためですよ」と言われ、絶句したことがありました。
そんな妻が唯一強く希望していたことは、「年末年始は自宅で過ごしたい」ということでした。
07年12月には、昭子さんは背中や脚がむくみ、起きあがれない状態になっていた。垣添さんは、妻の希望をかなえるため、在宅用の医療機器や医薬品、酸素などの手配を進めた。
当初は訪問看護師を頼む予定にしていましたが、家の中に知らない人がいたら落ち着かないだろうと、すべて私が世話をすることにしました。
看護師から、点滴の自動注入ポンプの取り扱い方法などの猛特訓を受けました。
12月28日、久しぶりに自宅に帰ると、妻はたいそう喜びました。
夕食は妻のリクエストで九州から取り寄せておいた、アラという白身魚の鍋。
抗がん剤の副作用で食べ物を口にするのがつらいはずなのに、おいしそうに食べてくれました。「連れて帰ってきて本当に良かった」と私もうれしかったですね。
が、夫婦として普通に会話を交わせたのは、この時が最後でした。翌日からどんどん容体が悪化し、30日には意識も遠のき、大みそかの夕方、静かに息を引き取りました。
最期の時を、妻の希望通り自宅で過ごさせてやれたことは、本当に幸せなことだったと思います。が、もちろん、これは非常に恵まれたケースであることは分かっています。
私が医師であり、妻の入院していた病院が私の勤務先でもあったことなどから、こうしたことが可能になりました。普通は最期を自宅でと願っても、実現するのはなかなか難しいことです。
家庭と医療機関、訪問看護ステーションが連携して、希望すれば誰もが自宅で医療を受けられる態勢を、早く整える必要があるでしょう。
昭子さんの生前の希望通り、葬儀はせず、その死を積極的に周囲に知らせることもしなかった。
火葬も済み、1月5日にがんセンターに出勤すると、机の上に仕事が山積みになっていました。昼間は仕事に没頭していれば、妻のことを考えなくて済むので良かった。
問題は夜と週末。妻はおしゃべりだったので、家ではいつも二人でいろいろな話をしていました。その話し相手がいないのがつらかった。寂しさを紛らわすため、大量に酒を飲み、満足な食事を取らなかったため、体重が激減しました。
☆今でも妻はそばに
ようやく少し上向きの気持ちが出てきたのは、3か月を過ぎた頃。こんな私の状態を、妻は決して喜んではいないだろう。それに、今後は一人で生きていかねばならない。そのためには健康が大切、と思うようになりました。
まず、朝食を自分で作って食べることから始めました。夜は週の半分は外食ですが、それ以外は自分で作って食べる。妻が病弱だったため、もともと一通りの家事が出来たのが幸いでした。
二人の趣味だった登山とカヌーも、一人で再開することにしました。
08年の夏、日光の奥白根山に登った時のことです。道を間違えてくたびれ果てて、ひと休みしていた時、1メートルも離れていない目の前にメボソムシクイという野鳥がとまり、のどの奥まで見えるほど大きな口を開けて「チュルチュルチュル」と鳴くんです。妻が「あなた、こんなところで何してるのよ」と励ましてくれているように感じました。
ほかの山でもナキウサギが私の袖に触れるほど近くをバーッと横切って行ったり、アサギマダラというチョウがいつまでもヒラヒラと近くを舞っていたり……ということがあり、いつも私のそばに妻がいてくれると感じます。(聞き手・森谷直子)
※
かきぞえ・ただお 国立がんセンター名誉総長。1941年、大阪府生まれ。67年に東大医学部卒業後、都立豊島病院泌尿器科などを経て、75年から同センターに勤務。2002年4月から07年3月まで同センター総長。同4月から名誉総長。著書に「妻を看取る日」(新潮社)など。
◎取材を終えて 妻の死を公表せず、国立がんセンター名誉総長として多くの公的な仕事をこなしながら、一人で苦しんでいたことを知り、驚いた。その後、自ら計画的に生活を立て直していった過程は力強い。体を鍛え直そうと、腕立て伏せを1日数回から始め、今では1日70回、腹筋350回、スクワット100回をこなすという。「筋力を鍛えていると、体だけでなく心も上向きになっていくのを感じました」という言葉が印象に残った。
(2010年2月14日 読売新聞)
---------------------
8/23の朝刊、1面「地球を読む」(2面に続く)で
「伴侶の死に悲嘆ケアを」という見出しの記事を書かれていました。
以下に記すのは、がんを患っていた妻を自宅で看取った私の極めて個人的な体験と、
それに根ざしたがんの在宅医療、そして残された者の心のケア、いわゆるグリーフ・ケアに関する考察である。…中略…
国のがん対策推進基本方針計画は12年、当初の5年間の成果を評価し、後半の5年に向けて見直しが加えられる。
その際、こうしたがんの在宅医療やグリーフ・ケアに関する視点も積極的に取り入れる必要があると強く思う。
---------------------
奥様を「がん」で亡くされた経験は、悲しいことですが、
国立がんセンター名誉総長として、医療従事者だけの視点でなく、
家族の視点からも「今後のがん治療のあり方」を提言していただけることは、
世の中にプラスになると思います。