 先日読んだ吉松隆さんの著書「クラシック音楽は『ミステリー』である」には、たっっぷり楽しませていただいた。著者の名人芸のような筆の運びもさることながら、音楽にミステリーをかけた発想も文句なくおもしろい。さてさて、映画『カラヴァッジョ』と平行して読破した宮下規久朗氏の「カラヴァッジョ 聖性とヴィジョン」によれば、クラシック音楽どころか「美術はもっと『ミステリー』である」!私も吉松さんに習って、まずは16世紀イタリア美術界の巨匠、カラヴァッジョのプロファイリングを試みる。
先日読んだ吉松隆さんの著書「クラシック音楽は『ミステリー』である」には、たっっぷり楽しませていただいた。著者の名人芸のような筆の運びもさることながら、音楽にミステリーをかけた発想も文句なくおもしろい。さてさて、映画『カラヴァッジョ』と平行して読破した宮下規久朗氏の「カラヴァッジョ 聖性とヴィジョン」によれば、クラシック音楽どころか「美術はもっと『ミステリー』である」!私も吉松さんに習って、まずは16世紀イタリア美術界の巨匠、カラヴァッジョのプロファイリングを試みる。氏名:ミケランジェロ・メリージ・ダ・カラヴァッジオ(Michelangelo Merisi da Caravaggio)
生年月日:1571年9月29日ミラノもしくはカラヴァッジョ
父母:フェルモ・メリージとルチア・アラトーリの間に生まれ、弟と妹あり
性別:♂
血液型:社会の既成の枠からはずれがち、唯我独尊型で思い込んだら突っ走るところからおそらくB型と思われる
職業:画家
犯罪履歴:20歳の頃からすでに非行を重ね、なんらかの殺人などのトラブルに巻き込まれてローマに逃亡。サンタンジェロ城の監獄を別荘代わりにしばしば居住。1603年8月、バリオーネをその作品とともに中傷したかどで所謂「バリオーネ裁判」の被告人として訴えられる。公証人パスクアーロを斬りつけてジェノバに逃走するもシピオーネ・ボルゲーゼ枢機卿の仲裁で示談で解決。しかしながら、対立グループのひとり、売春婦の見張りをしていたラヌッチオ・トマッソーニと賭けテニスの得点で喧嘩をしてはずみで、というのも言い訳がましいが相手を殺害してしまう。死刑宣告がされて、これ以降各地を転々として再びローマの地をふむことがなかった。逃亡生活の途上で名誉ある騎士団に入会を果たすも、1608年8月18日夜半にジョヴァンニ・ピエトロ・デ・ポンテ他仲間の騎士5人とともにベッツァ伯ジョヴァンニ・ロドモンテ・ロエロを襲撃して重傷を負わせ、サンタンジェロ要塞に投獄される。その後、脱獄するが病に倒れトスカーナで37年のその短い生涯を閉じた。
結婚暦:なし、生涯独身。《洗礼者ヨハネ》や《果物籠を持つ少年》のあやしげな絵、天使のモチーフが多いことからも想像されるように同性愛の傾向がみられる。シチリアで生活をしていた時、造船場でひとりの少年を熱心に付回し、その少年の引率の教師に訊問されるや逆に教師に剣で斬りつけるという事件を起こす。但し、ローマ時代に一躍セレブの仲間入りをするとそれなりに女性にもてて、多少の女性遍歴もあるそうだ。
 ところで、カラヴァッジョという画家の名前を聞いて、その絵の一枚でも記憶のストックからひっぱりだせる人が何人いるだろうか。映画『カラヴァッジョ』のコピーには、「彼が存在しなければレンブラントもベラスケスも誕生しなかった!」と記されている。本書の著者の宮下氏になると”はじめに”の最初の一行では、「バロック美術の先駆者としてだけでなく、西洋美術史においてもっとも大きな革命を起こした天才」「その影響は、(中略)17世紀の巨匠のほとんどすべてから現代にまでおよんでいる」と高らかに宣言している。ちょっとそれは大げさでは?ご贔屓の相撲取りへの賞賛という身びいきもあるのでは?ためしに友人や勤務先の人に聞いてみたら、さすがに友人は名前を知っていたが絵は思い浮かばず、職場の人にいたると誰それ、何それレベル。しかし、本書を読めばカラヴァッジョが大げさでもなくまぎれもなく革新的な天才であることがひしひしとわかる。映画では残念ながら、大仰な音楽効果が邪魔をして画家の内省にせまることもなく、アレッシオ・ボーニの熱演も血と暴力に生かされこそすれ、その作品も破滅型で悲劇の人生の比喩の表象とした一面でしか描かれていなかったと思うのは私だけだろうか。
ところで、カラヴァッジョという画家の名前を聞いて、その絵の一枚でも記憶のストックからひっぱりだせる人が何人いるだろうか。映画『カラヴァッジョ』のコピーには、「彼が存在しなければレンブラントもベラスケスも誕生しなかった!」と記されている。本書の著者の宮下氏になると”はじめに”の最初の一行では、「バロック美術の先駆者としてだけでなく、西洋美術史においてもっとも大きな革命を起こした天才」「その影響は、(中略)17世紀の巨匠のほとんどすべてから現代にまでおよんでいる」と高らかに宣言している。ちょっとそれは大げさでは?ご贔屓の相撲取りへの賞賛という身びいきもあるのでは?ためしに友人や勤務先の人に聞いてみたら、さすがに友人は名前を知っていたが絵は思い浮かばず、職場の人にいたると誰それ、何それレベル。しかし、本書を読めばカラヴァッジョが大げさでもなくまぎれもなく革新的な天才であることがひしひしとわかる。映画では残念ながら、大仰な音楽効果が邪魔をして画家の内省にせまることもなく、アレッシオ・ボーニの熱演も血と暴力に生かされこそすれ、その作品も破滅型で悲劇の人生の比喩の表象とした一面でしか描かれていなかったと思うのは私だけだろうか。 宮下氏は、これまでの通説の伝記の巧妙な作為をさけ、カラヴァッジョに影響を与えた作品、また影響を受けた作品、レプリカを対比させて豊富な資料の中から、過去の美術評論家の鋭い本質をついた批評を紹介しながら、尚且つ研究者としてのオリジナリティを画家の才能への愛情をもって展開していく。カラヴァッジョと言えば真っ先に思い浮かぶのは、私の場合、サンクトペテルブルグのエルミタージュ美術館に展示されている《リュート弾き》である。4日間に渡り、エルミタージュ美術館ではそれこそ膨大な絵画を観てきたはずなのに、この繊細な光をまろやかに受けた優美な絵はまるで音楽が聴こえてくるような雰囲気で忘れられない一枚だった。その時の印象(ミステリー)こそが、カラヴァッジョにおける宮下氏の優れた研究者の視点で解明されていく。命のひかりと罪の暗黒の中で、後々に物議をかもした写実主義が開花していく。そしてサン・ルイジ・デイ・フランチェージ聖堂コンタレッリ礼拝堂のために描かれた《聖マタイの召命》《聖マタイの殉教》《聖マタイと天使》はカラヴァッジョの宗教絵画の中でも特に傑作であるが、この作品には実際に設置される空間を考慮して効果を計算して光の効果と構成をした特徴が表れている。そればかりか、カラヴァッジョは宗教における回心という内面のドラマを、明暗表現や写実的な描写で現実空間でおこっているようなイリュージョンを与えた。客観的なリアリズムを通して内面的なヴィジョンを表現したのがカラヴァッジョである。しばしばカラヴァッジョが、宗教画を卑俗な次元に引き摺り下ろしたという非難にさらされたのは、映画でも取り上げられた《ロレートの聖母》への中傷のとおりだが、巡礼者の汚い足に観衆は自らを投影し感嘆し、聖母子のイリュージョンを体験する。神を希求する者にとっては現実的な表現こそが、もっとも神秘的な宗教性を与えることに彼は気がついていたのだ。個人的には、この絵のいかにも汚れた足の裏は、同じくエルミタージュ美術館に展示されているレンブラントの《放蕩息子の帰還》につながるように思える。
宮下氏は、これまでの通説の伝記の巧妙な作為をさけ、カラヴァッジョに影響を与えた作品、また影響を受けた作品、レプリカを対比させて豊富な資料の中から、過去の美術評論家の鋭い本質をついた批評を紹介しながら、尚且つ研究者としてのオリジナリティを画家の才能への愛情をもって展開していく。カラヴァッジョと言えば真っ先に思い浮かぶのは、私の場合、サンクトペテルブルグのエルミタージュ美術館に展示されている《リュート弾き》である。4日間に渡り、エルミタージュ美術館ではそれこそ膨大な絵画を観てきたはずなのに、この繊細な光をまろやかに受けた優美な絵はまるで音楽が聴こえてくるような雰囲気で忘れられない一枚だった。その時の印象(ミステリー)こそが、カラヴァッジョにおける宮下氏の優れた研究者の視点で解明されていく。命のひかりと罪の暗黒の中で、後々に物議をかもした写実主義が開花していく。そしてサン・ルイジ・デイ・フランチェージ聖堂コンタレッリ礼拝堂のために描かれた《聖マタイの召命》《聖マタイの殉教》《聖マタイと天使》はカラヴァッジョの宗教絵画の中でも特に傑作であるが、この作品には実際に設置される空間を考慮して効果を計算して光の効果と構成をした特徴が表れている。そればかりか、カラヴァッジョは宗教における回心という内面のドラマを、明暗表現や写実的な描写で現実空間でおこっているようなイリュージョンを与えた。客観的なリアリズムを通して内面的なヴィジョンを表現したのがカラヴァッジョである。しばしばカラヴァッジョが、宗教画を卑俗な次元に引き摺り下ろしたという非難にさらされたのは、映画でも取り上げられた《ロレートの聖母》への中傷のとおりだが、巡礼者の汚い足に観衆は自らを投影し感嘆し、聖母子のイリュージョンを体験する。神を希求する者にとっては現実的な表現こそが、もっとも神秘的な宗教性を与えることに彼は気がついていたのだ。個人的には、この絵のいかにも汚れた足の裏は、同じくエルミタージュ美術館に展示されているレンブラントの《放蕩息子の帰還》につながるように思える。神に背を向けるような蛮行の数々を繰り返し罪の闇に心を落としながらも、彼の作品からは敬虔な宗教と深い精神、魂の浄化を感じられる。そんな矛盾に魅了されたカラヴァジョ研究は、近年益々盛んになっているそうだ。4800円の本書は、著者の集大成ともいうべく強力な一冊であるとともに、日本人によるカラヴァッジョ研究の一家に一冊の決定版と推薦したい。私のようにカラヴァッジョに対してしてさほど興味がなかった方も、その名前すら知らなかった方でも、本書を開けばいつのまにかこの謎に満ちたカラヴァッジョのファンに。そしてカラヴァッジョが残した軌跡は、やはりミステリーである。
■アーカイヴへ
・映画『カラヴァッジョ』
・~美の巨人たち~カラヴァッジョ「聖マタイの召命」











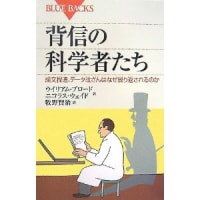

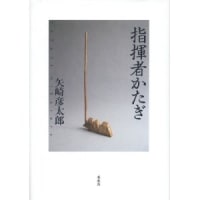
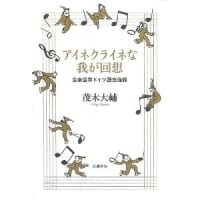
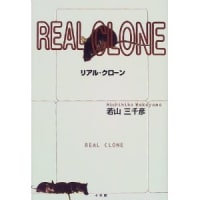
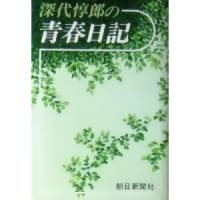
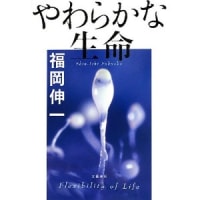
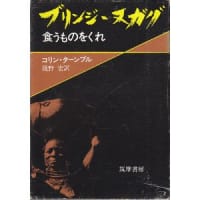
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます