-あなたはあなたの絵と同じ。
光の部分は限りなく美しく、
影の部分は罪深い
 16世紀イタリアを代表するバロック絵画最大の巨匠カラヴァッジョ。後のレンブラントやベラスケスに大きな影響を与え、数々の名画を後世に残したカラヴァッジョだが、彼ほどその作品と人物像がかけ離れている画家もまたいないだろう。今年は、彼が亡くなって400周年になる記念の年である。来月、謎に満ちた画家の生涯と傑作誕生の裏側にせまった映画『カラヴァッジョ』が公開される。カラヴァッジョの絵画の特徴と画家の内面の対比を巧みに表したこの言葉は、その映画の広告に使われていたものを拝借した。今夜の一枚は、「聖マタイの召命」。
16世紀イタリアを代表するバロック絵画最大の巨匠カラヴァッジョ。後のレンブラントやベラスケスに大きな影響を与え、数々の名画を後世に残したカラヴァッジョだが、彼ほどその作品と人物像がかけ離れている画家もまたいないだろう。今年は、彼が亡くなって400周年になる記念の年である。来月、謎に満ちた画家の生涯と傑作誕生の裏側にせまった映画『カラヴァッジョ』が公開される。カラヴァッジョの絵画の特徴と画家の内面の対比を巧みに表したこの言葉は、その映画の広告に使われていたものを拝借した。今夜の一枚は、「聖マタイの召命」。
場末の汚い酒場だろうか、ギャンブルと酒でくさい息を吐く男たちは、金勘定に余念がない。そこへ登場したのが、ふたりの男たち。突然の闖入者に、気色ばみ思わず身をのりだそうとする男、保身からだろうか逆に身をひく男、一心不乱にうつむいてお金を数える男。現れた男のうち、やせて金色の輪が頭上に見える男がイエス・キリストである。光の差す向こうに、キリストが指す男は誰なのか。後に聖マタイとなる罪深き収税吏レビを、キリストが自らの使徒にして召そうとする瞬間が描かかれた「聖マタイの召命」。これまでも多くの画家が描いてきたモチーフだが、カラヴァッジョは、芝居の舞台のような劇的空間をつくりあげ、既成の宗教画の概念を破った傑作でもある。
1571年、ミラノに生まれたカラヴァッジョ(本名はミケランジェロ・メリージ Michelangelo Merisi)は、シモーネ・ペテルツァーノの工房で修行を積んだ後、ローマに移る。一説によると、暴力事件を起こしてローマに逃れてきたという激情型で暴力的な性格が伝わる。今でいうホームレスのような貧しい暮らしをしながらも、絵筆をとれば天才性は秀でて、1595年頃にフランチェスコ・マリア・デル・モンテ枢機卿にその才能を見いだされて画家として成功していく。収入が入ると仲間を引き連れて呑み歩き、一銭もなくなるとまた絵筆をとるという繰り返し。喧嘩はお手の物、日常茶飯事で多くの敵をつくり、決闘で相手を殺してしまったために、ナポリ、やがてはシチリアへと流転していく。革新的な絵画は物議をよんだが、たとえば「トランプ詐欺師」のように舞台劇をみるかのような圧倒的な構成力は認められていった。
 カラヴァッジョの現実主義的な特徴をあらわした代表作として有名なのは、「病める少年バッコス 」であろう。不健康で、それでいて官能的ですらある不思議な絵。カラヴァッジョ自身を対象としたバッコスは、これまでのギリシャ神話の登場人物の酒神バッコスを美化せず、モデルを正確に写実的に描いている。そしてその写実的描写力で画家の類まれな才能を示した頂点とも言えるのが、「果物籠」。葡萄の瑞々しさと同時に虫に喰われた傷のある林檎、枯れて乾いた質感のある葉と伸びていく生命感のある枝、緻密に描かれた果物籠、テレビの画面だけでもその徹底したリアリズムによる溢れんばかりの才能が伝わってくる。小さな画面の中のその絵にすっかりひきこまれてしまった。
カラヴァッジョの現実主義的な特徴をあらわした代表作として有名なのは、「病める少年バッコス 」であろう。不健康で、それでいて官能的ですらある不思議な絵。カラヴァッジョ自身を対象としたバッコスは、これまでのギリシャ神話の登場人物の酒神バッコスを美化せず、モデルを正確に写実的に描いている。そしてその写実的描写力で画家の類まれな才能を示した頂点とも言えるのが、「果物籠」。葡萄の瑞々しさと同時に虫に喰われた傷のある林檎、枯れて乾いた質感のある葉と伸びていく生命感のある枝、緻密に描かれた果物籠、テレビの画面だけでもその徹底したリアリズムによる溢れんばかりの才能が伝わってくる。小さな画面の中のその絵にすっかりひきこまれてしまった。
さて、キリストに指をさされてうつむく男がこの劇の主人公である。ある時は時代の寵児に、ある時は反逆者、犯罪者の烙印をおされ、38歳でその短すぎる生涯を閉じるまで波乱万丈の生涯を送った謎のカラヴァッジョ。映画の公開がまたれる!
光の部分は限りなく美しく、
影の部分は罪深い
 16世紀イタリアを代表するバロック絵画最大の巨匠カラヴァッジョ。後のレンブラントやベラスケスに大きな影響を与え、数々の名画を後世に残したカラヴァッジョだが、彼ほどその作品と人物像がかけ離れている画家もまたいないだろう。今年は、彼が亡くなって400周年になる記念の年である。来月、謎に満ちた画家の生涯と傑作誕生の裏側にせまった映画『カラヴァッジョ』が公開される。カラヴァッジョの絵画の特徴と画家の内面の対比を巧みに表したこの言葉は、その映画の広告に使われていたものを拝借した。今夜の一枚は、「聖マタイの召命」。
16世紀イタリアを代表するバロック絵画最大の巨匠カラヴァッジョ。後のレンブラントやベラスケスに大きな影響を与え、数々の名画を後世に残したカラヴァッジョだが、彼ほどその作品と人物像がかけ離れている画家もまたいないだろう。今年は、彼が亡くなって400周年になる記念の年である。来月、謎に満ちた画家の生涯と傑作誕生の裏側にせまった映画『カラヴァッジョ』が公開される。カラヴァッジョの絵画の特徴と画家の内面の対比を巧みに表したこの言葉は、その映画の広告に使われていたものを拝借した。今夜の一枚は、「聖マタイの召命」。場末の汚い酒場だろうか、ギャンブルと酒でくさい息を吐く男たちは、金勘定に余念がない。そこへ登場したのが、ふたりの男たち。突然の闖入者に、気色ばみ思わず身をのりだそうとする男、保身からだろうか逆に身をひく男、一心不乱にうつむいてお金を数える男。現れた男のうち、やせて金色の輪が頭上に見える男がイエス・キリストである。光の差す向こうに、キリストが指す男は誰なのか。後に聖マタイとなる罪深き収税吏レビを、キリストが自らの使徒にして召そうとする瞬間が描かかれた「聖マタイの召命」。これまでも多くの画家が描いてきたモチーフだが、カラヴァッジョは、芝居の舞台のような劇的空間をつくりあげ、既成の宗教画の概念を破った傑作でもある。
1571年、ミラノに生まれたカラヴァッジョ(本名はミケランジェロ・メリージ Michelangelo Merisi)は、シモーネ・ペテルツァーノの工房で修行を積んだ後、ローマに移る。一説によると、暴力事件を起こしてローマに逃れてきたという激情型で暴力的な性格が伝わる。今でいうホームレスのような貧しい暮らしをしながらも、絵筆をとれば天才性は秀でて、1595年頃にフランチェスコ・マリア・デル・モンテ枢機卿にその才能を見いだされて画家として成功していく。収入が入ると仲間を引き連れて呑み歩き、一銭もなくなるとまた絵筆をとるという繰り返し。喧嘩はお手の物、日常茶飯事で多くの敵をつくり、決闘で相手を殺してしまったために、ナポリ、やがてはシチリアへと流転していく。革新的な絵画は物議をよんだが、たとえば「トランプ詐欺師」のように舞台劇をみるかのような圧倒的な構成力は認められていった。
 カラヴァッジョの現実主義的な特徴をあらわした代表作として有名なのは、「病める少年バッコス 」であろう。不健康で、それでいて官能的ですらある不思議な絵。カラヴァッジョ自身を対象としたバッコスは、これまでのギリシャ神話の登場人物の酒神バッコスを美化せず、モデルを正確に写実的に描いている。そしてその写実的描写力で画家の類まれな才能を示した頂点とも言えるのが、「果物籠」。葡萄の瑞々しさと同時に虫に喰われた傷のある林檎、枯れて乾いた質感のある葉と伸びていく生命感のある枝、緻密に描かれた果物籠、テレビの画面だけでもその徹底したリアリズムによる溢れんばかりの才能が伝わってくる。小さな画面の中のその絵にすっかりひきこまれてしまった。
カラヴァッジョの現実主義的な特徴をあらわした代表作として有名なのは、「病める少年バッコス 」であろう。不健康で、それでいて官能的ですらある不思議な絵。カラヴァッジョ自身を対象としたバッコスは、これまでのギリシャ神話の登場人物の酒神バッコスを美化せず、モデルを正確に写実的に描いている。そしてその写実的描写力で画家の類まれな才能を示した頂点とも言えるのが、「果物籠」。葡萄の瑞々しさと同時に虫に喰われた傷のある林檎、枯れて乾いた質感のある葉と伸びていく生命感のある枝、緻密に描かれた果物籠、テレビの画面だけでもその徹底したリアリズムによる溢れんばかりの才能が伝わってくる。小さな画面の中のその絵にすっかりひきこまれてしまった。さて、キリストに指をさされてうつむく男がこの劇の主人公である。ある時は時代の寵児に、ある時は反逆者、犯罪者の烙印をおされ、38歳でその短すぎる生涯を閉じるまで波乱万丈の生涯を送った謎のカラヴァッジョ。映画の公開がまたれる!











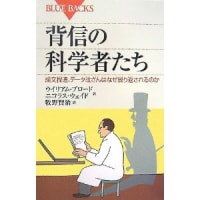

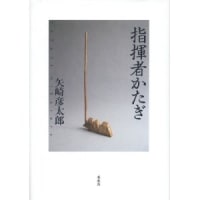
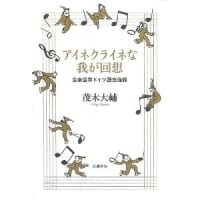
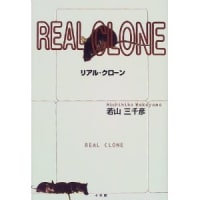
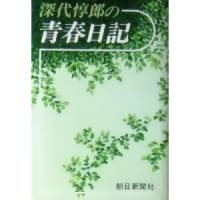
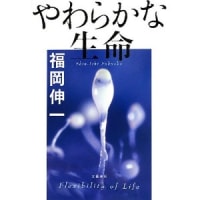
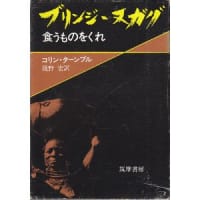
>極めて現実的、世俗的な描写に驚いたわけです
これは当時としては革新的だったと思いますね。
考えれば、優れた画家は常に革新的ですね。たとえ人々から批判され受け入れられなくても。