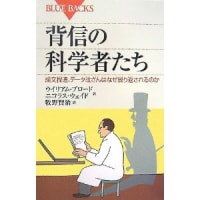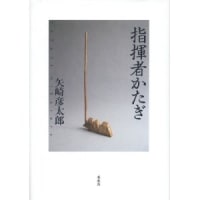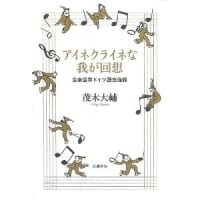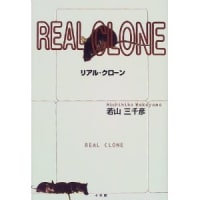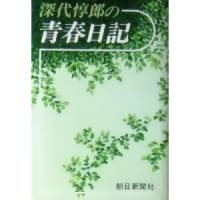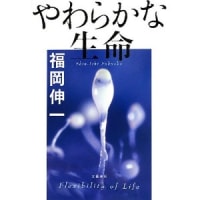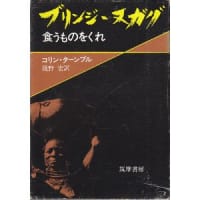花王と慶応大学の前野隆司教授(ロボット工学)の研究グループが、触った感触が肌とそっくりの人工皮膚を開発した。
ロボットに“移植”すると親しみやすさが増すかもしれない。14日に岡山大学で始まる日本ロボット学会で発表する。
人の皮膚は、軟らかい細胞を硬い角質層が覆っている。これをまねた人工皮膚は、弾力性を持つ厚さ約1センチのシリコンに、0・2ミリの硬めのウレタンを重ねて作った。ウレタンには六角形の溝を無数に刻んで凹凸を持たせた。
試作した人工皮膚を12人に触ってもらった結果、10人が「人の皮膚に似ている」と回答した。実際、器械で滑らかさを測定したところ、人の皮膚に近かった。
花王は、人工皮膚を化粧品開発などに役立てる計画。前野教授は、人間と触れ合う機会の多い家庭用ロボットなどに使うことを提案している。(2006年9月12日 読売新聞)
*************************************************************************************
この研究報告を読んで感じたことは、化粧品も扱う生活用品を製造している化学メーカーと大学の研究グループのハイブリッドな研究成果ということだ。
このようなコラボを異色の組合せと感じている自分が、もはや時代遅れなのだろう。産学協同の加速化する潮流は、今読書中の「全共闘とはなんだったのか」という政治の嵐から遠く隔たっている。
しかし、いったいロボットに人間に近い皮膚感覚を求めるのだろうか。”親しみやすさ”を感じるのだろうか。
ロボットには、産業用ロボットなどのように機能が充実しているが外見は”ただの機械”と、瀬名秀明氏の著書「デカルトの密室」の主人公、小学3年生の日本男児のような体躯と顔立ちの人工知能を搭載したケンイチのようなヒューマノイド型ロボットに大別される。。私は、終始一貫してヒューマノイド型ロボットには疑問をもっている。ヒトの姿・カタチはしているが、ロボットには命がない。最近のアンケートによると、半分以上の小・中学生が亡くなっても魂が存在し、生まれかわると信じているそうだ。近頃、ブームが再燃している「たまごっち」ではないが、リセットすればやりなおしがきくと本気で考えているのだろうか。私には、なんとも非科学的で幼稚に思えるのだが。外観においてロボットと人間の境界が曖昧になったら、命の軽視につながるのではないだろうか。
確かにアトム好きの私にとってケンイチのようなロボットが我家にやってきたら、生活にあかるさとはりがもたらせるだろうと想像するだけで愉快だ。だって「デカルトの密室」の中のケンイチは、完璧に近い素直で賢い理想的な小学生だったのだ。しかも永遠にこどもだ。だから逆に、ケンイチの生みの親であるロボット工学者・尾形祐輔と恋人の進化心理学者、一ノ瀬玲奈の間には、こどもがまだいないことも気になる。なにしろ彼らは、ケンイチを育てることに夢中である。
それにフランシーヌ・オハラのような美貌のロボットが発売され人間そっくりの皮膚でおおわれていたら、森永卓郎さんのような萌え系は、飛びつくだろう。間違いない。遠い存在の手の届かないヨンさまのような芸能人に恋をするのと、ロボットに擬似恋愛するというのも、似ているようで決定的に異なるのは、対象に命があるかないかだ。
つらつらと、そんなことを考える。あれからケンイチは、臭いをかぎわけることができるようになったのだろうか。チチの尾形氏は、香りをききわけられることは豊かな生活につながると開発をすすめていたのだったが。
■参考→人工皮膚の製品化
ロボットに“移植”すると親しみやすさが増すかもしれない。14日に岡山大学で始まる日本ロボット学会で発表する。
人の皮膚は、軟らかい細胞を硬い角質層が覆っている。これをまねた人工皮膚は、弾力性を持つ厚さ約1センチのシリコンに、0・2ミリの硬めのウレタンを重ねて作った。ウレタンには六角形の溝を無数に刻んで凹凸を持たせた。
試作した人工皮膚を12人に触ってもらった結果、10人が「人の皮膚に似ている」と回答した。実際、器械で滑らかさを測定したところ、人の皮膚に近かった。
花王は、人工皮膚を化粧品開発などに役立てる計画。前野教授は、人間と触れ合う機会の多い家庭用ロボットなどに使うことを提案している。(2006年9月12日 読売新聞)
*************************************************************************************
この研究報告を読んで感じたことは、化粧品も扱う生活用品を製造している化学メーカーと大学の研究グループのハイブリッドな研究成果ということだ。
このようなコラボを異色の組合せと感じている自分が、もはや時代遅れなのだろう。産学協同の加速化する潮流は、今読書中の「全共闘とはなんだったのか」という政治の嵐から遠く隔たっている。
しかし、いったいロボットに人間に近い皮膚感覚を求めるのだろうか。”親しみやすさ”を感じるのだろうか。
ロボットには、産業用ロボットなどのように機能が充実しているが外見は”ただの機械”と、瀬名秀明氏の著書「デカルトの密室」の主人公、小学3年生の日本男児のような体躯と顔立ちの人工知能を搭載したケンイチのようなヒューマノイド型ロボットに大別される。。私は、終始一貫してヒューマノイド型ロボットには疑問をもっている。ヒトの姿・カタチはしているが、ロボットには命がない。最近のアンケートによると、半分以上の小・中学生が亡くなっても魂が存在し、生まれかわると信じているそうだ。近頃、ブームが再燃している「たまごっち」ではないが、リセットすればやりなおしがきくと本気で考えているのだろうか。私には、なんとも非科学的で幼稚に思えるのだが。外観においてロボットと人間の境界が曖昧になったら、命の軽視につながるのではないだろうか。
確かにアトム好きの私にとってケンイチのようなロボットが我家にやってきたら、生活にあかるさとはりがもたらせるだろうと想像するだけで愉快だ。だって「デカルトの密室」の中のケンイチは、完璧に近い素直で賢い理想的な小学生だったのだ。しかも永遠にこどもだ。だから逆に、ケンイチの生みの親であるロボット工学者・尾形祐輔と恋人の進化心理学者、一ノ瀬玲奈の間には、こどもがまだいないことも気になる。なにしろ彼らは、ケンイチを育てることに夢中である。
それにフランシーヌ・オハラのような美貌のロボットが発売され人間そっくりの皮膚でおおわれていたら、森永卓郎さんのような萌え系は、飛びつくだろう。間違いない。遠い存在の手の届かないヨンさまのような芸能人に恋をするのと、ロボットに擬似恋愛するというのも、似ているようで決定的に異なるのは、対象に命があるかないかだ。
つらつらと、そんなことを考える。あれからケンイチは、臭いをかぎわけることができるようになったのだろうか。チチの尾形氏は、香りをききわけられることは豊かな生活につながると開発をすすめていたのだったが。
■参考→人工皮膚の製品化