これまで何度か「ひとりでできる!!触診練習法」シリーズをご紹介してきましたが、今回は、腰椎の可動性検査です。
腰椎については、ずいぶん前にも少しご紹介しましたが、屈曲・伸展をサラッとご紹介しただけでしたので、コツをもう少し付け加えて、さらに側屈・回旋も練習したいと思います。
「ひとりでできる!!触診練習法 その3」
耳にタコかもしれませんが、脊柱の機能障害を評価し治療するためには、その前提として、ひとつひとつの椎骨の可動性を調べる分節的な検査ができなければいけません。
今回は立位での練習ですが、それは座位での可動性検査はもちろん、

側臥位での屈曲・伸展検査

そして、側屈検査

回旋検査

さらには腰椎の関節モビライゼーションまでつながっていきます。

ですからしっかり練習しましょう。
まずは屈曲から。
立位で腰椎の棘突起の間にコンタクトします。

どの指でもお好みで構いません。写真では人差し指ですが、この場合、私は中指を使っています。

そのまま身体を前屈させて、棘突起間が開くような動きが確認できれば、その分節は屈曲ができているといことになります。

ちなみにC2~7の典型的頸椎の棘突起間にコンタクトしている場合は、椎間関節の形状から上位の棘突起は前上方にすべって棘間が開いていきます。
腰椎の場合は、地面に対して垂直な方向に関節面を持ち、棘突起も縦に並んでいるので、上下にパカッと開くような動きになります。
ところが体幹を前に倒したら、周囲の脊柱起立筋が遠心性収縮をして胸背筋膜が緊張するために、屈曲に伴う棘間部の開きがうまく感じ取れないことがあります。
そのような時はどうすればよいでしょう?
触診を行う上でもっとも大切なことは、「いかに感じ取るか」ということです。
そして、正確に感じ取るためには、自分や患者さんの体をどう操作するかということがポイントになります。
ですから今回の例で、どのように自分の体を操作すれば、腰椎の屈曲をよりスムーズに感じやすくなるか、みなさんで工夫なさってみてください。
合わせて、伸展の動きも感じ取ってみましょう。
私がオススメする方法は、次回ご紹介します。
 寺子屋DVD発売のご案内
寺子屋DVD発売のご案内
手技療法の寺子屋でご紹介しているような手技療法の基本が、医療情報研究所さんよりDVDとして発売されました。
私が大切にしていることを、出来る限りお伝えさせていただきました。
どうぞよろしくお願い致します。
医療情報研究所
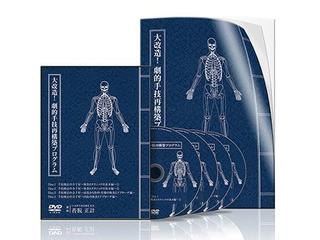
 ☆ブログの目次(PDF)を作りました 2014.01.03☆)
☆ブログの目次(PDF)を作りました 2014.01.03☆)
手技療法の寺子屋ブログを始めてから今月でまる6年になり、おかげさまで記事も300を越えました。
これだけの量になると、全体をみたり記事を探すのも手間がかかるかもしれません。
そこで、少しでもタイトルを調べやすくできるように、このお休みを使って目次を作ってみました。
手技療法を学ばれている方、興味を持たれている方にご活用いただき、お役に立てれば幸いです。
手技療法の寺子屋ブログ「目次」
腰椎については、ずいぶん前にも少しご紹介しましたが、屈曲・伸展をサラッとご紹介しただけでしたので、コツをもう少し付け加えて、さらに側屈・回旋も練習したいと思います。
「ひとりでできる!!触診練習法 その3」
耳にタコかもしれませんが、脊柱の機能障害を評価し治療するためには、その前提として、ひとつひとつの椎骨の可動性を調べる分節的な検査ができなければいけません。

今回は立位での練習ですが、それは座位での可動性検査はもちろん、

側臥位での屈曲・伸展検査

そして、側屈検査

回旋検査

さらには腰椎の関節モビライゼーションまでつながっていきます。

ですからしっかり練習しましょう。

まずは屈曲から。
立位で腰椎の棘突起の間にコンタクトします。

どの指でもお好みで構いません。写真では人差し指ですが、この場合、私は中指を使っています。

そのまま身体を前屈させて、棘突起間が開くような動きが確認できれば、その分節は屈曲ができているといことになります。

ちなみにC2~7の典型的頸椎の棘突起間にコンタクトしている場合は、椎間関節の形状から上位の棘突起は前上方にすべって棘間が開いていきます。
腰椎の場合は、地面に対して垂直な方向に関節面を持ち、棘突起も縦に並んでいるので、上下にパカッと開くような動きになります。
ところが体幹を前に倒したら、周囲の脊柱起立筋が遠心性収縮をして胸背筋膜が緊張するために、屈曲に伴う棘間部の開きがうまく感じ取れないことがあります。

そのような時はどうすればよいでしょう?
触診を行う上でもっとも大切なことは、「いかに感じ取るか」ということです。
そして、正確に感じ取るためには、自分や患者さんの体をどう操作するかということがポイントになります。

ですから今回の例で、どのように自分の体を操作すれば、腰椎の屈曲をよりスムーズに感じやすくなるか、みなさんで工夫なさってみてください。
合わせて、伸展の動きも感じ取ってみましょう。
私がオススメする方法は、次回ご紹介します。
 寺子屋DVD発売のご案内
寺子屋DVD発売のご案内
手技療法の寺子屋でご紹介しているような手技療法の基本が、医療情報研究所さんよりDVDとして発売されました。
私が大切にしていることを、出来る限りお伝えさせていただきました。
どうぞよろしくお願い致します。
医療情報研究所
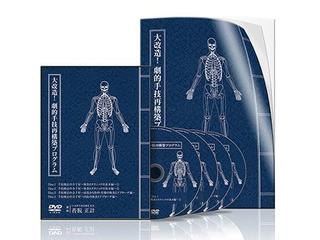
 ☆ブログの目次(PDF)を作りました 2014.01.03☆)
☆ブログの目次(PDF)を作りました 2014.01.03☆)
手技療法の寺子屋ブログを始めてから今月でまる6年になり、おかげさまで記事も300を越えました。
これだけの量になると、全体をみたり記事を探すのも手間がかかるかもしれません。
そこで、少しでもタイトルを調べやすくできるように、このお休みを使って目次を作ってみました。
手技療法を学ばれている方、興味を持たれている方にご活用いただき、お役に立てれば幸いです。
手技療法の寺子屋ブログ「目次」

















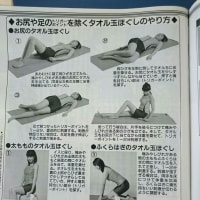


更新と同時に読んでくださっていて、感謝感謝です。
雪は、先週から、嫌になるくらい降り続いています。
夜、自宅に帰ったら20センチくらい積っているので雪かきをしたら、翌朝また同じくらい積っているので、出勤前に雪かきをするという具合です。
あまり続くとうんざりするのですが、より効率のよい体の動かし方を、あれこれ工夫しながらやっています。
これも修行ですね。
ブログもマイペースで続けていこうと思っていますので、どうぞよろしくお願いします。