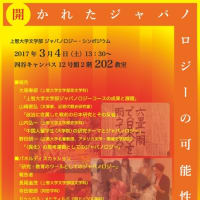8月末から9月初めにかけては、宗教史懇話会のサマーセミナー、上智古代史ゼミのOB研究会、得度の同窓会、ゼミの研修旅行など、イベントが盛り沢山であった。校務も、文化財レスキュー関連の説明会やら災害関連の会議やら幾つかあり、それなりに多忙かつ充実していた感がある。逆に原稿や研究は進捗しなかったが、学生の成長を感じられる機会が多かったので、それなりに教師冥利に尽きる日々だった。まあ、それらは追々紹介してゆくことにして、今回は印象が新鮮なうちに書き留めておきたい事柄を綴ってゆこう。なお、これはあくまでぼく自身の内面の記録であって、客観的な記事ではないことをお断りしておく。
 3日(土)ゼミ旅行の最終日、東北学院大学博物館での文化財レスキュー作業を終えたぼくは、希望の学生数名と、院生のO君の案内で東松島市野蒜地区に入った。四国に上陸した台風12号は紀伊半島周辺へ甚大な被害をもたらしつつあったが、東北地方への影響は断続的な降雨に止まり、ぼくらのゼミ旅行には大きな障害になりえなかった。学生を引率している立場上、関東・東北への直撃は勘弁してほしいと願い続け、雨天では実行できない被災文化財のクリーニングを、少しでも学生に体験させられたときには幸運に喜んだが、いざ関西での被害情況が具体的に報道され始めると、相変わらずの自分の身勝手さに暗澹たる思いがした。よって、仙石線と代行バスを乗り継ぎ、17:00頃に野蒜駅前に降り立ったときには、すでに気分はかなり落ち込み始めていた。そのうえでの、あの光景である。同地区の被害についてはいまさらいうまでもないが、真っ直ぐに伸びた海浜部に打ち寄せた津波は松の美林と家々をなぎ倒し、鳴瀬川からかなりの内陸部まで到達し一面の廃墟をもたらした。駅前に立ったぼくは、しかしその全体像すら思い描くことができず、半ば思考停止した状態で海浜部へ歩みを進めた。
3日(土)ゼミ旅行の最終日、東北学院大学博物館での文化財レスキュー作業を終えたぼくは、希望の学生数名と、院生のO君の案内で東松島市野蒜地区に入った。四国に上陸した台風12号は紀伊半島周辺へ甚大な被害をもたらしつつあったが、東北地方への影響は断続的な降雨に止まり、ぼくらのゼミ旅行には大きな障害になりえなかった。学生を引率している立場上、関東・東北への直撃は勘弁してほしいと願い続け、雨天では実行できない被災文化財のクリーニングを、少しでも学生に体験させられたときには幸運に喜んだが、いざ関西での被害情況が具体的に報道され始めると、相変わらずの自分の身勝手さに暗澹たる思いがした。よって、仙石線と代行バスを乗り継ぎ、17:00頃に野蒜駅前に降り立ったときには、すでに気分はかなり落ち込み始めていた。そのうえでの、あの光景である。同地区の被害についてはいまさらいうまでもないが、真っ直ぐに伸びた海浜部に打ち寄せた津波は松の美林と家々をなぎ倒し、鳴瀬川からかなりの内陸部まで到達し一面の廃墟をもたらした。駅前に立ったぼくは、しかしその全体像すら思い描くことができず、半ば思考停止した状態で海浜部へ歩みを進めた。
台風の影響を受けた風雨はもはや小康状態にみえたが、海からは激しい波浪のゆえと思われる轟音が、一瞬も弱まることなく鳴り響いていた。それは、大気全体の震動を視覚化させるような圧力を持っていたが、「あのとき」には、その数十倍、数百倍の海鳴りを伴い巨大な水壁が押し寄せてきたのだろう。台風のおかげか、ぼくの拙い想像力でも、その茫然とする光景の一端、何千分の一、何万分の一かは思い描くことができた。

 かつて賑やかな人の暮らしがあったところに、その僅かな痕跡だけが残る景観とは、これほどまでに静謐なものなのか。海鳴りさえも忘れる廃墟に立ちすくんでは進むうち、これまで穏やかだった天候が突如その相貌を変え、激しい風と横殴りの雨が打ち付けてきた。こういう書き方は好きではないが、まさにぼくらを拒むように襲い来る風雨に思わず背を向けると、目の前に黒々とした石碑が建っている。海岸の風景を称賛する歌碑でもあるのかと目を凝らすと、どういう皮肉か、それは東松島の「開拓記念碑」だった。被災地域の撮影にはずっと後ろめたさを覚えていたが(7月末に七ヶ浜町に入ったとき、欲求に勝てずに何枚かの写真を撮影したが、後悔して消去した)、このときには記念碑自身が何かを訴えているように感じ、暴風に震える身体を何とか支えながらその姿を捉えた。自然への勝利を誇らしげに体現すべく生まれてきた「彼」は、どのような思いで「あのとき」を受けとめ、いまこの廃墟に佇んでいるのだろうか。不思議なことに、撮影を終えてふと気付くと、雨も風も嘘のように止んでしまっていた(果たしてこの「物語」を、伝統的な形式に沿って受け取ってもよいものだろうか?)。
かつて賑やかな人の暮らしがあったところに、その僅かな痕跡だけが残る景観とは、これほどまでに静謐なものなのか。海鳴りさえも忘れる廃墟に立ちすくんでは進むうち、これまで穏やかだった天候が突如その相貌を変え、激しい風と横殴りの雨が打ち付けてきた。こういう書き方は好きではないが、まさにぼくらを拒むように襲い来る風雨に思わず背を向けると、目の前に黒々とした石碑が建っている。海岸の風景を称賛する歌碑でもあるのかと目を凝らすと、どういう皮肉か、それは東松島の「開拓記念碑」だった。被災地域の撮影にはずっと後ろめたさを覚えていたが(7月末に七ヶ浜町に入ったとき、欲求に勝てずに何枚かの写真を撮影したが、後悔して消去した)、このときには記念碑自身が何かを訴えているように感じ、暴風に震える身体を何とか支えながらその姿を捉えた。自然への勝利を誇らしげに体現すべく生まれてきた「彼」は、どのような思いで「あのとき」を受けとめ、いまこの廃墟に佇んでいるのだろうか。不思議なことに、撮影を終えてふと気付くと、雨も風も嘘のように止んでしまっていた(果たしてこの「物語」を、伝統的な形式に沿って受け取ってもよいものだろうか?)。
 防波堤から駅へ引き返す道では、少し冷静に考えをまとめてゆくことができた。それは結局、これまで何度も自分に問い続けてきたことの答えを、確認する作業に過ぎなかったのだが…。ひとつは「この景観を前にして、それでも自分は、人外の側に立とうという言説を紡ぎ続けることができるのか」、二つめは「自然の脅威を再認識した向こう側に巻き起こるヒト中心主義を、どのように相対化してゆくか、相対化してゆけるか」、三つめは「津波にさらされたのは人間だけではない。例えば多くなぎ倒された松林の松の生命については、一体誰が語ってゆけるのか」ということ。震災後、環境史や災害史の認知度は高まり、その必要性も「正義感を持って」主張されてきたように思う。しかしぼくには、かかる種類の歴史を叙述することの困難さが、一層高まったように感じられてならない。かつてぼくは、『環境と心性の文化史』の総論に、自然環境と文化との二項対立は恣意的に構築されてきたものであって、両者を両者たらしてめている本源的な関係態を見据えなければならないと書いた。両者の宿命的対立を説く論調もあるが、それは、自らが創りあげた幻に束縛されているにすぎない。いま、その言明を出発点として、もう一度慎重に歩みを進めてゆきたい。
防波堤から駅へ引き返す道では、少し冷静に考えをまとめてゆくことができた。それは結局、これまで何度も自分に問い続けてきたことの答えを、確認する作業に過ぎなかったのだが…。ひとつは「この景観を前にして、それでも自分は、人外の側に立とうという言説を紡ぎ続けることができるのか」、二つめは「自然の脅威を再認識した向こう側に巻き起こるヒト中心主義を、どのように相対化してゆくか、相対化してゆけるか」、三つめは「津波にさらされたのは人間だけではない。例えば多くなぎ倒された松林の松の生命については、一体誰が語ってゆけるのか」ということ。震災後、環境史や災害史の認知度は高まり、その必要性も「正義感を持って」主張されてきたように思う。しかしぼくには、かかる種類の歴史を叙述することの困難さが、一層高まったように感じられてならない。かつてぼくは、『環境と心性の文化史』の総論に、自然環境と文化との二項対立は恣意的に構築されてきたものであって、両者を両者たらしてめている本源的な関係態を見据えなければならないと書いた。両者の宿命的対立を説く論調もあるが、それは、自らが創りあげた幻に束縛されているにすぎない。いま、その言明を出発点として、もう一度慎重に歩みを進めてゆきたい。
なお、東北学院の加藤幸治さんは、すべてが押し流されてまったくの荒野と化した仙台平野の光景を、「厖大な情報量」と逆説的に表現している。しかし、あらゆる生活痕跡が消去されたそこには、事実、我々の認識・処理限界を超える示唆が内包されているのである。そのうえにまったく別の、新しい空間を建設しようとする復興プランは、人々の記憶さえも消し去ってしまう危険を持ち、ある意味で津波よりも恐ろしい。歴史に携わる者が立ち向かうべきなのは、そうした"リセット"の力かも知れない。
※ 野蒜海岸では、開拓記念碑と松の写真を数枚撮らせていただいた。建物の跡にはカメラを向けることができなかった。冒頭の航空写真はGoogleMapより。
 3日(土)ゼミ旅行の最終日、東北学院大学博物館での文化財レスキュー作業を終えたぼくは、希望の学生数名と、院生のO君の案内で東松島市野蒜地区に入った。四国に上陸した台風12号は紀伊半島周辺へ甚大な被害をもたらしつつあったが、東北地方への影響は断続的な降雨に止まり、ぼくらのゼミ旅行には大きな障害になりえなかった。学生を引率している立場上、関東・東北への直撃は勘弁してほしいと願い続け、雨天では実行できない被災文化財のクリーニングを、少しでも学生に体験させられたときには幸運に喜んだが、いざ関西での被害情況が具体的に報道され始めると、相変わらずの自分の身勝手さに暗澹たる思いがした。よって、仙石線と代行バスを乗り継ぎ、17:00頃に野蒜駅前に降り立ったときには、すでに気分はかなり落ち込み始めていた。そのうえでの、あの光景である。同地区の被害についてはいまさらいうまでもないが、真っ直ぐに伸びた海浜部に打ち寄せた津波は松の美林と家々をなぎ倒し、鳴瀬川からかなりの内陸部まで到達し一面の廃墟をもたらした。駅前に立ったぼくは、しかしその全体像すら思い描くことができず、半ば思考停止した状態で海浜部へ歩みを進めた。
3日(土)ゼミ旅行の最終日、東北学院大学博物館での文化財レスキュー作業を終えたぼくは、希望の学生数名と、院生のO君の案内で東松島市野蒜地区に入った。四国に上陸した台風12号は紀伊半島周辺へ甚大な被害をもたらしつつあったが、東北地方への影響は断続的な降雨に止まり、ぼくらのゼミ旅行には大きな障害になりえなかった。学生を引率している立場上、関東・東北への直撃は勘弁してほしいと願い続け、雨天では実行できない被災文化財のクリーニングを、少しでも学生に体験させられたときには幸運に喜んだが、いざ関西での被害情況が具体的に報道され始めると、相変わらずの自分の身勝手さに暗澹たる思いがした。よって、仙石線と代行バスを乗り継ぎ、17:00頃に野蒜駅前に降り立ったときには、すでに気分はかなり落ち込み始めていた。そのうえでの、あの光景である。同地区の被害についてはいまさらいうまでもないが、真っ直ぐに伸びた海浜部に打ち寄せた津波は松の美林と家々をなぎ倒し、鳴瀬川からかなりの内陸部まで到達し一面の廃墟をもたらした。駅前に立ったぼくは、しかしその全体像すら思い描くことができず、半ば思考停止した状態で海浜部へ歩みを進めた。台風の影響を受けた風雨はもはや小康状態にみえたが、海からは激しい波浪のゆえと思われる轟音が、一瞬も弱まることなく鳴り響いていた。それは、大気全体の震動を視覚化させるような圧力を持っていたが、「あのとき」には、その数十倍、数百倍の海鳴りを伴い巨大な水壁が押し寄せてきたのだろう。台風のおかげか、ぼくの拙い想像力でも、その茫然とする光景の一端、何千分の一、何万分の一かは思い描くことができた。

 かつて賑やかな人の暮らしがあったところに、その僅かな痕跡だけが残る景観とは、これほどまでに静謐なものなのか。海鳴りさえも忘れる廃墟に立ちすくんでは進むうち、これまで穏やかだった天候が突如その相貌を変え、激しい風と横殴りの雨が打ち付けてきた。こういう書き方は好きではないが、まさにぼくらを拒むように襲い来る風雨に思わず背を向けると、目の前に黒々とした石碑が建っている。海岸の風景を称賛する歌碑でもあるのかと目を凝らすと、どういう皮肉か、それは東松島の「開拓記念碑」だった。被災地域の撮影にはずっと後ろめたさを覚えていたが(7月末に七ヶ浜町に入ったとき、欲求に勝てずに何枚かの写真を撮影したが、後悔して消去した)、このときには記念碑自身が何かを訴えているように感じ、暴風に震える身体を何とか支えながらその姿を捉えた。自然への勝利を誇らしげに体現すべく生まれてきた「彼」は、どのような思いで「あのとき」を受けとめ、いまこの廃墟に佇んでいるのだろうか。不思議なことに、撮影を終えてふと気付くと、雨も風も嘘のように止んでしまっていた(果たしてこの「物語」を、伝統的な形式に沿って受け取ってもよいものだろうか?)。
かつて賑やかな人の暮らしがあったところに、その僅かな痕跡だけが残る景観とは、これほどまでに静謐なものなのか。海鳴りさえも忘れる廃墟に立ちすくんでは進むうち、これまで穏やかだった天候が突如その相貌を変え、激しい風と横殴りの雨が打ち付けてきた。こういう書き方は好きではないが、まさにぼくらを拒むように襲い来る風雨に思わず背を向けると、目の前に黒々とした石碑が建っている。海岸の風景を称賛する歌碑でもあるのかと目を凝らすと、どういう皮肉か、それは東松島の「開拓記念碑」だった。被災地域の撮影にはずっと後ろめたさを覚えていたが(7月末に七ヶ浜町に入ったとき、欲求に勝てずに何枚かの写真を撮影したが、後悔して消去した)、このときには記念碑自身が何かを訴えているように感じ、暴風に震える身体を何とか支えながらその姿を捉えた。自然への勝利を誇らしげに体現すべく生まれてきた「彼」は、どのような思いで「あのとき」を受けとめ、いまこの廃墟に佇んでいるのだろうか。不思議なことに、撮影を終えてふと気付くと、雨も風も嘘のように止んでしまっていた(果たしてこの「物語」を、伝統的な形式に沿って受け取ってもよいものだろうか?)。 防波堤から駅へ引き返す道では、少し冷静に考えをまとめてゆくことができた。それは結局、これまで何度も自分に問い続けてきたことの答えを、確認する作業に過ぎなかったのだが…。ひとつは「この景観を前にして、それでも自分は、人外の側に立とうという言説を紡ぎ続けることができるのか」、二つめは「自然の脅威を再認識した向こう側に巻き起こるヒト中心主義を、どのように相対化してゆくか、相対化してゆけるか」、三つめは「津波にさらされたのは人間だけではない。例えば多くなぎ倒された松林の松の生命については、一体誰が語ってゆけるのか」ということ。震災後、環境史や災害史の認知度は高まり、その必要性も「正義感を持って」主張されてきたように思う。しかしぼくには、かかる種類の歴史を叙述することの困難さが、一層高まったように感じられてならない。かつてぼくは、『環境と心性の文化史』の総論に、自然環境と文化との二項対立は恣意的に構築されてきたものであって、両者を両者たらしてめている本源的な関係態を見据えなければならないと書いた。両者の宿命的対立を説く論調もあるが、それは、自らが創りあげた幻に束縛されているにすぎない。いま、その言明を出発点として、もう一度慎重に歩みを進めてゆきたい。
防波堤から駅へ引き返す道では、少し冷静に考えをまとめてゆくことができた。それは結局、これまで何度も自分に問い続けてきたことの答えを、確認する作業に過ぎなかったのだが…。ひとつは「この景観を前にして、それでも自分は、人外の側に立とうという言説を紡ぎ続けることができるのか」、二つめは「自然の脅威を再認識した向こう側に巻き起こるヒト中心主義を、どのように相対化してゆくか、相対化してゆけるか」、三つめは「津波にさらされたのは人間だけではない。例えば多くなぎ倒された松林の松の生命については、一体誰が語ってゆけるのか」ということ。震災後、環境史や災害史の認知度は高まり、その必要性も「正義感を持って」主張されてきたように思う。しかしぼくには、かかる種類の歴史を叙述することの困難さが、一層高まったように感じられてならない。かつてぼくは、『環境と心性の文化史』の総論に、自然環境と文化との二項対立は恣意的に構築されてきたものであって、両者を両者たらしてめている本源的な関係態を見据えなければならないと書いた。両者の宿命的対立を説く論調もあるが、それは、自らが創りあげた幻に束縛されているにすぎない。いま、その言明を出発点として、もう一度慎重に歩みを進めてゆきたい。なお、東北学院の加藤幸治さんは、すべてが押し流されてまったくの荒野と化した仙台平野の光景を、「厖大な情報量」と逆説的に表現している。しかし、あらゆる生活痕跡が消去されたそこには、事実、我々の認識・処理限界を超える示唆が内包されているのである。そのうえにまったく別の、新しい空間を建設しようとする復興プランは、人々の記憶さえも消し去ってしまう危険を持ち、ある意味で津波よりも恐ろしい。歴史に携わる者が立ち向かうべきなのは、そうした"リセット"の力かも知れない。
※ 野蒜海岸では、開拓記念碑と松の写真を数枚撮らせていただいた。建物の跡にはカメラを向けることができなかった。冒頭の航空写真はGoogleMapより。