
伊予松山藩歴代藩主の家系を見る 14 松平勝善(第12代藩主)
第12代藩主となった定穀は、嘉永6年(1853)第12代将軍・徳川家定公にはばかり松平定穀は、勝善に、定成は、勝成と改名した。
なお第11代松平定通は子宝に恵まれず、薩摩藩主第9代島津斉宣(なりのぶ)の11男を養子とした(松平定穀・勝善)
松平定穀・勝善(以下勝善とする)の城郭復興計画が推進する。・・島津斉宣は、篤姫の祖父である。
弘化4年(1847)11月小川九十郎を普請奉行に命じ12月4日家老の服部玄蕃も参加して天守の位置を検討し、まず天守・小天守等々本壇の設計に着手、嘉永元年2月7日鍬入れ式を揚げ復興が始まった。
工事を着手してから6年嘉永5年(1852)12月20日天守を初め城郭全部が完成、落成式は安政元年(1854)2月8日に盛大に行われた。
実に天明4年の天守焼失から71年を経過し、また定通の復興計画から文化3年からすれば、35年の後の事であった。
松山藩としては大規模な工事でありこれらの経費の捻出は、藩の節約によるものと家臣の俸禄の減給でよるものであった。
落成式には先ず70歳以上の老人に酒を振舞い労をねぎらったとある。節約の感謝の表れであろう。
徒歩目付けの秋山久敬(坂の上の雲・主人公、秋山好古・秋山眞之)家も10石に減給されていた。
現在見る伊予松山城本壇の天守はこの時に再建されたもので、わが国の城郭のうち連立式建築の最も完備した形式と偉観を持つこととなった。
連立式城郭とは、天守が並立する二基以上の城櫓によって形成したものをいい、普通に中庭の備えがある。
松山城は天守を中心に多聞北隅櫓・南隅櫓・小天守・さらに東北に天神櫓・南東に二ノ門櫓を配している。
この様式を持つ城郭として全国に知られているものに、姫路・和歌山・の両城があり、なかでも松山城は安政元年の復興で、江戸時代の古城郭として最も新しく、かつ完全なものとして注目されている。
勝善は、松山城復興完成を終え、安政3年(1856)40歳で逝去、藩主は第13代松平勝成に継がれる。
従四位 左近衛権少将 隠岐守
画像は、松山城ニノ門東塀で、ニノ門とニノ門南櫓を結ぶ塀で枡形を通りニノ門の直前に迫った寄手を側射する防御塀。
建造時期は、嘉永期の再建で、第12代藩主松平勝善の建造である。
昭和10年5月13日国宝に指定されたが、昭和25年5月、文化財保護法の制定により重要文化財に指定された。
第12代藩主となった定穀は、嘉永6年(1853)第12代将軍・徳川家定公にはばかり松平定穀は、勝善に、定成は、勝成と改名した。
なお第11代松平定通は子宝に恵まれず、薩摩藩主第9代島津斉宣(なりのぶ)の11男を養子とした(松平定穀・勝善)
松平定穀・勝善(以下勝善とする)の城郭復興計画が推進する。・・島津斉宣は、篤姫の祖父である。
弘化4年(1847)11月小川九十郎を普請奉行に命じ12月4日家老の服部玄蕃も参加して天守の位置を検討し、まず天守・小天守等々本壇の設計に着手、嘉永元年2月7日鍬入れ式を揚げ復興が始まった。
工事を着手してから6年嘉永5年(1852)12月20日天守を初め城郭全部が完成、落成式は安政元年(1854)2月8日に盛大に行われた。
実に天明4年の天守焼失から71年を経過し、また定通の復興計画から文化3年からすれば、35年の後の事であった。
松山藩としては大規模な工事でありこれらの経費の捻出は、藩の節約によるものと家臣の俸禄の減給でよるものであった。
落成式には先ず70歳以上の老人に酒を振舞い労をねぎらったとある。節約の感謝の表れであろう。
徒歩目付けの秋山久敬(坂の上の雲・主人公、秋山好古・秋山眞之)家も10石に減給されていた。
現在見る伊予松山城本壇の天守はこの時に再建されたもので、わが国の城郭のうち連立式建築の最も完備した形式と偉観を持つこととなった。
連立式城郭とは、天守が並立する二基以上の城櫓によって形成したものをいい、普通に中庭の備えがある。
松山城は天守を中心に多聞北隅櫓・南隅櫓・小天守・さらに東北に天神櫓・南東に二ノ門櫓を配している。
この様式を持つ城郭として全国に知られているものに、姫路・和歌山・の両城があり、なかでも松山城は安政元年の復興で、江戸時代の古城郭として最も新しく、かつ完全なものとして注目されている。
勝善は、松山城復興完成を終え、安政3年(1856)40歳で逝去、藩主は第13代松平勝成に継がれる。
従四位 左近衛権少将 隠岐守
画像は、松山城ニノ門東塀で、ニノ門とニノ門南櫓を結ぶ塀で枡形を通りニノ門の直前に迫った寄手を側射する防御塀。
建造時期は、嘉永期の再建で、第12代藩主松平勝善の建造である。
昭和10年5月13日国宝に指定されたが、昭和25年5月、文化財保護法の制定により重要文化財に指定された。










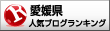

















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます