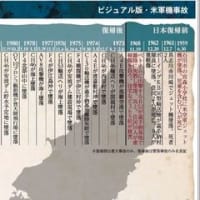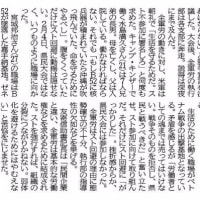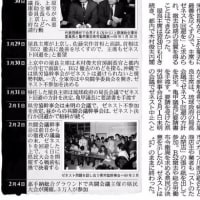宗教家が自分のDNA情報を記録したとする電子チップ入りの「ご神体」を1体100万円で販売し、所得隠しで摘発され
るなど、
宗教法人がその公益性から認められている優遇措置を悪用する例が後を絶ちません。
伝統仏教のお坊さんは「あんな胡散臭い連中と私たちは違う」と言うでしょう。
でも、お札や塔婆でお布施を頂くのとどう違うのでしょうか。
彼らに違いを証明することは難しいと僕は思います。
違いを突き詰めて考えることはしないからです。
生きづらいこの時代、助けを求めて「ご神体」などを購入した人々を責めることはできません。
本質的には「宗教的な付加価値」にいくら払うのかということなのですが、人々は「胡散臭い連中」も伝統仏教も「どっ
ちも
どっち」と思っている。
全国に8万近くあるお寺は、なぜ詐欺的な商法にひっかかった人々を救えなかったのでしょう。
伝統仏教は将来ある若者らの人生を誤らせたオウム真理教を「邪教」と切り捨てましたが、「生きるとは何か」などを厳しく
問うこともなく、人々の心の琴線に触れて宗教に向かわせる力を失っているのです。
お寺が公益性を持つ法人であり、正しく活動していることを証明する方法は結局、情報開示と説明責任に尽きます。
僕は様々なNPO(非営利組織)の活動にも携わっています。
NPOには情報開示や説明責任が義務づけられているのに、宗教法人は本当に甘いと感じます。
大半の寺院は収支報告書や事業報告書を重要視しておらず、その収入は外からはうかがい知れない「ブラックボックス」。
住職や職員の給料がどれくらいなのか、布教活動や寺院の整備にいくら使われているのかも判然としないのです。
神宮寺はこの20年以上、いずれも公開しています。
僕の月給は所得税などを払って手取り42万円。
職員の給与も公開しています。
公益を担う以上は当然なのです。
宗教法人の公益性は社会の様々な「苦」、人々の生老病死と向き合い、寄り添い、緩和しようとすることで認められる。
しかし、大半の寺院は世襲と家業化が進み、檀家制度というシステムに安住し、社会の苦とは向き合えていない。
葬儀でも通り一遍のお経をあげるだけで、納棺にすら立ち会わないお坊さんも多い。
寺の門も夜は締め切っているところが大半でしょう。
門を24時間開いていると「死にたい」とか「末期がんを宣告された」とか、世の様々な苦しみが飛び込んできます。
それを受け止め、ともに歩む寺になることが必要だと思うのです。
かつて寺院は地域の教育の場であり、お坊さんは地域の治水や土木工事にもかかわり、まさに地域社会の公益を担って
いたのです。
今はどうでしょうか。
神宮寺のある浅間温泉は観光客が減少しています。
廃業した温泉旅館を引き継ぎ、NPOを設立し、お年寄りのデイケアや訪問介護の拠点として運営しています。
食材も地元で仕入れ、お年寄りに温泉やおいしい食事を楽しんでもらい、地域活性化につながっています。
将来は通所型ホスピスも設置し、ここで生まれ育った人々が安心して生を全うできるようにしたい。
寺から飛び出し、世の中の苦と向き合う。
そこからしか寺院の公益性は回復できないと思うのです。
(聞き手・杉井昭仁)
高橋卓志
48年生まれ。76年に神宮寺副住職。
90年より住職。
チェルノブイリ原発事故の被災者救援などにも奔走。
近著に「寺よ、変われ」。
臨済宗神宮寺(長野県松本市)住職
*2009.10.4朝日新聞
よろしければ、下のマークをクリックして!

るなど、
宗教法人がその公益性から認められている優遇措置を悪用する例が後を絶ちません。
伝統仏教のお坊さんは「あんな胡散臭い連中と私たちは違う」と言うでしょう。
でも、お札や塔婆でお布施を頂くのとどう違うのでしょうか。
彼らに違いを証明することは難しいと僕は思います。
違いを突き詰めて考えることはしないからです。
生きづらいこの時代、助けを求めて「ご神体」などを購入した人々を責めることはできません。
本質的には「宗教的な付加価値」にいくら払うのかということなのですが、人々は「胡散臭い連中」も伝統仏教も「どっ
ちも
どっち」と思っている。
全国に8万近くあるお寺は、なぜ詐欺的な商法にひっかかった人々を救えなかったのでしょう。
伝統仏教は将来ある若者らの人生を誤らせたオウム真理教を「邪教」と切り捨てましたが、「生きるとは何か」などを厳しく
問うこともなく、人々の心の琴線に触れて宗教に向かわせる力を失っているのです。
お寺が公益性を持つ法人であり、正しく活動していることを証明する方法は結局、情報開示と説明責任に尽きます。
僕は様々なNPO(非営利組織)の活動にも携わっています。
NPOには情報開示や説明責任が義務づけられているのに、宗教法人は本当に甘いと感じます。
大半の寺院は収支報告書や事業報告書を重要視しておらず、その収入は外からはうかがい知れない「ブラックボックス」。
住職や職員の給料がどれくらいなのか、布教活動や寺院の整備にいくら使われているのかも判然としないのです。
神宮寺はこの20年以上、いずれも公開しています。
僕の月給は所得税などを払って手取り42万円。
職員の給与も公開しています。
公益を担う以上は当然なのです。
宗教法人の公益性は社会の様々な「苦」、人々の生老病死と向き合い、寄り添い、緩和しようとすることで認められる。
しかし、大半の寺院は世襲と家業化が進み、檀家制度というシステムに安住し、社会の苦とは向き合えていない。
葬儀でも通り一遍のお経をあげるだけで、納棺にすら立ち会わないお坊さんも多い。
寺の門も夜は締め切っているところが大半でしょう。
門を24時間開いていると「死にたい」とか「末期がんを宣告された」とか、世の様々な苦しみが飛び込んできます。
それを受け止め、ともに歩む寺になることが必要だと思うのです。
かつて寺院は地域の教育の場であり、お坊さんは地域の治水や土木工事にもかかわり、まさに地域社会の公益を担って
いたのです。
今はどうでしょうか。
神宮寺のある浅間温泉は観光客が減少しています。
廃業した温泉旅館を引き継ぎ、NPOを設立し、お年寄りのデイケアや訪問介護の拠点として運営しています。
食材も地元で仕入れ、お年寄りに温泉やおいしい食事を楽しんでもらい、地域活性化につながっています。
将来は通所型ホスピスも設置し、ここで生まれ育った人々が安心して生を全うできるようにしたい。
寺から飛び出し、世の中の苦と向き合う。
そこからしか寺院の公益性は回復できないと思うのです。
(聞き手・杉井昭仁)
高橋卓志
48年生まれ。76年に神宮寺副住職。
90年より住職。
チェルノブイリ原発事故の被災者救援などにも奔走。
近著に「寺よ、変われ」。
臨済宗神宮寺(長野県松本市)住職
*2009.10.4朝日新聞
よろしければ、下のマークをクリックして!