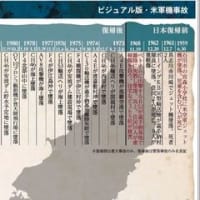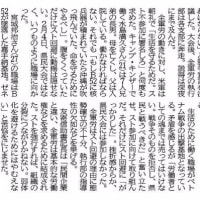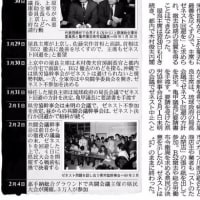アーミテージ・ナイ レポート2012年8月「CSIS(戦略・国際研究センター)報告書」(1) から続く
<中国の再興>
過去30年以上にわたる中国の経済的重要さや軍事的腕力、政治的影響力の流星のような
勃興は、世界最大の人口を持つ国を劇的に刷新してきただけでなく、東アジアの冷戦後
の地政学的な風景を決定的に形作ってもきた。強力な米日同盟は、中国の再興を圧迫す
るのではなく、その中で中国が繁栄してきた安定的で予見可能な安全保障上の環境をも
たらすことに役立つことで、それ[中国]に貢献してきた。この同盟は、中国の成功に
利害関係を持ってきた。しかしながら、中国が新たに見出した力をどのように使うつも
りか――現存の国際的規範を再強化するのか、北京の国益に沿ってそれらを見直すのか
、あるいは、その両方か――ということに関する透明性の欠如とあいまいさは、懸念が
増大する分野である。
特に不安な一つの分野は、中国の拡大しうる核心的利益である。公式の3地域――新疆
ウイグル自治区[Xinjiang]、チベット、台湾――に加えて、南シナ海と尖閣諸島が、
現れつつある利害地域として言及されてきた。後者は非公式だし宣言はされていないが
、人民解放軍(PLA)の海軍の南シナ海と東シナ海でのプレゼンスの増大は、われわ
れを別の推論に導いている。主権という共有のテーマが、尖閣諸島と南シナ海における
北京の意図についての疑問をさらに生じさせている。一つだけは確実である――中国の
不明確な核心的利益の主張は、この地域における中国の外交的信頼性をさらに低減させ
ている。
中国に対する同盟の戦略は、関与と障壁を設けることとのブレンドであり、中国が急速
に成長しつつある包括的な国力の使い方にどのような選択をするかについての不確実性
に相応している。しかし、中国の増大する軍事力と政治的自己主張に対する同盟による
障壁の最大の側面――地理的視点での同盟の活動の漸進的な拡大、ミサイル防衛技術で
の共同作業、[兵器、情報などでの]共通運用性とシーレーン交通路の維持に関連する
任務への注意の向上、東南アジア諸国連合(ASEAN)のような地域機構を強化する
努力、航海の自由に新たに焦点を当てること、および2011年12月に打ち出された米・日
・インドの3国対話――は、中国が高い経済成長の道を進み、防衛支出と能力を同様に
増大させ続けるだろうという想定に基づいてきた。
この想定は、もはや断言できない。中国は、1979年の{ケ小平による「改革開放」の打ち
上げから40年の時期[fourth decade]に入っているので、成長が遅くなっているとい
う多くの指標がある。輸出主導から国内消費を加速する経済に移行する中国の能力につ
いては、疑問が存在する。中国の指導者たちは今後数年間、少なくとも6つの悪魔と格
闘しなければならないだろう。すなわち、エネルギーの逼迫、悲惨な環境悪化、威圧的
な人口統計的現実、国民間および地域間の所得格差の拡大、新疆とチベットの御しがた
い少数民族、および根深い公務員の腐敗である。
経済的成功は、このリストに「中間所得の落とし穴」に対抗するという不確実性を付け
加える。そこでは増大しつつある中間所得層という軍団が、中国の政治構造に、期待の
高まりに対応するための格別の圧力をかけている。これらの課題のどれ一つも、中国の
経済成長の道を脱線させ、社会的安定を脅かしうるだろう。中国共産党は、これらの気
の滅入るような難問を自覚しており、その指導者たちが2012年に、防衛予算にほぼ匹敵
する1200億ドル[約9兆6000億円/1ドル=80円として]以上に国内治安の予算を増額
したのも、それが一つの理由である。人民解放軍は、台湾が正当な独立に向かって進む
のを抑止することを含む、外的脅威に対処するための財源の獲得に集中している。しか
し中国共産党は、同様に国内の脅威にも心配している。
ひどくつまづいている中国は、必ずしもより小さくはないが、まったく異なる課題を[
米日]同盟に提起しうるだろう。われわれはみな、平和で繁栄した中国から得るものが
多い。代わりに、深刻な国内的亀裂に直面している中国の指導者たちは、民族主義に逃
げ込むことができるだろうし、団結を再び捏造するために、たぶん、現実に、または想
像上の外的脅威を作り出しうるだろう。秩序を維持するために、指導部はさらに苛酷な
手段に向かうこともできる。現存する人権侵害をいっそう悪化させ、外国のパートナー
たちを遠ざけ、40年前にニクソンが扉を開けて以来、西側の中国への関与を動かしてき
た政治的合意を危険にさらす、などである。
代わりに、将来の中国の主席は、温家宝首相が求めたような新たな一連の政治改革を採
用して、中国の国内政治と対外的姿勢に異なる結果をもたらすかもしれない。確実なの
は、ただ一つである。すなわち、同盟は中国の変化しつつある軌道と、広い範囲にわた
る将来の可能性に適用できる能力と政策を発展させなければならない。高度経済成長と
変化しない政治的権威は、中国の新しい指導者たちが期待している将来ではない。した
がってわれわれは、彼らの判断を知らされるべきある。
<人権と米日同盟 : 行動計画を発展させる>
2012年4月30日、米日同盟の将来についての共同声明は、その関係を強化させる共通の
価値についての明確な言及を含んでいる。すなわち、「日本と米国は、民主主義、法の
支配、開かれた社会、人権、人間の安全保障、および自由で開かれた市場への誓約を共
有する。これらの価値は、この時代のグローバルな諸課題に対処する共同の努力にわれ
われを導く」と。この共同声明はそのあとで、これらの共通の価値を実行に移すことを
約束している。「われわれは、法の支配と人権の保護を推進するために共に努力するこ
とを約束し、平和維持、紛争後の安定化、開発援助、組織犯罪と麻薬取引、および感染
症に対する協調を強める」と。
人権に関する、より具体的な行動計画の策定は称賛に値する目的であり、その機会とす
べき多くの目標がある。ビルマ(ミャンマー)の民主的改革を進めることは、優先順位
の高いものであるべきである。米国と日本は、民間部門の投資や外国の援助、国際金融
機関からの融資でもたらされる経済的テコを、良好な統治や法の支配、人権の国際的規
範の厳守を前進させるために利用すべきである。企業の社会的責任に最高の基準を設け
、ビルマのすべての利害関係者たち――少数民族や政治的反対派を含む――がビルマの
経済的将来について意見を訊かれ、関与することを確保することにより、ワシントンと
東京は、国を野蛮な軍事独裁から真に代表制民主主義に変えるために動いているビルマ
の人びとを元気づけることができる。同様の協調による努力は、もし国際人権法を推進
し、市民社会を守る誠実な約束に沿って行われるなら、カンボジアとベトナムにおいて
配当金を支払うことができるだろう。貧弱な人権の記録を持つこの両国は、米国が最近
、安全保障協力を格上げしたし、日本は重要な経済的、政治的な利害関係を持っている
。
日本にはより密接なことだが、北朝鮮は難問を提示している。ピョンヤンによる人権の
悪用は、十分に記録されており言語道断で、米日両国はそれについて見解を明らかにし
てきた。しかし米国は伝統的に、北朝鮮における人権問題を、非核化という「メイン・
イベント」から気をそらすものと見てきた。そして日本は、何年も前に北朝鮮に拉致さ
れた日本市民の運命に大きな焦点を当ててきた。われわれは、すべての拉致被害者につ
いて十分な説明を受けとるための日本の努力への支持を再確認し、日本と米国が、人権
や北朝鮮のその他の課題に効果的に関与するためのより広範な戦略の文脈の中で、この
課題について緊密に協力することを勧告する。
この同盟にとっての解決は、韓国とともに、朝鮮半島の人道的課題という全体像に対処
しつつ、関心の視野を拡大することにあろう。すなわち、拉致や強制収容所、政治的自
由と宗教的自由への深刻な規制だけではなく、食糧安全保障、災害救助、公衆衛生、教
育、文化交流もそうである。この半島の非核化に関する6者協議が事実上、停止させら
れており、人道に焦点を当てた計画は、ソウルその他の関心を有する国との緊密な調整
により、ピョンヤンの新しい指導部が北朝鮮の将来を描くような戦略的環境を再形成す
る機会を、この同盟に提供できるだろう。
新たな安全保障戦略に向けて
<地域的安全保障への関与>
原子力やODA、人権のような実際的な課題への関与に加えて、東京はこの地域の民主
的パートナー諸国、特にインド、オーストラリア、フィリピン、台湾とともに、地域的
フォーラム、すなわちASEAN、ASEAN地域フォーラム(ARF)、アジア太平
洋経済協力機構(APEC)への関与を継続することを十分に助けられるだろう。日本
は、共通の価値を超えて、また共通の利益と目標に向けて、地域のパートナー諸国との
結びつきの基礎を強化してきた。日本は、平和的で合法的な海洋環境を推進し、海路に
よる貿易が妨害されないよう確保し、全体的な経済と安全保障の良好な状態を推進する
ために、地域のパートナー諸国との協働を継続すべきである。
安全保障環境はめざましく変化してきたが、われわれのそれぞれの戦略の構成要素もそ
うである。「役割・任務・能力」(RMC)の見直し[review]が最近完了し、日本の
防衛戦略は主に北と南に拡大した。1980年代のレビューは地理的な視野を拡大し、東ア
ジアにおける同盟の能力を高めた。1990年代のレビューは、日本の防衛協力の空間のた
めの機能を明確にした。今日、関心領域はさらに南へ、そして大きく西へ――遠く中東
まで――拡大している。われわれは、われわれの戦略を十分に再定義し、われわれの実
行方法と手段を調整すべきである。新たなレビューは、われわれの軍事的、政治的、経
済的な国力の包括的な組み合わせとともに、より広い地理的視野を含むべきである。
<防衛戦略 : 同盟の共通運用性に向けて>
日本は、[軍事]能力の増強と2国間および多国間の方法で、防衛と軍事的外交をより
十分に行うことができる。新たな役割と任務のレビューは、地域的な不測の事態におい
て、日本の防衛と米国と共同の防衛とを含む、日本が責任を持つ分野を拡大すべきであ
る。最も緊急な課題は、日本自身の近隣地域にある。東シナ海の大部分と、事実上、南
シナ海全体に対する中国の積極的な自己主張、および繰り返される日本周航を含む、人
民解放軍その他の海上機関の運用テンポの劇的な増大は、「第1列島線」(日本―台湾
―フィリピン)または北京が「近海」と考えている海域全体に、より大きな戦略的影響
力を主張するという北京の意図を示している。これらの類の接近阻止/拒否地域(A2
AD)[anti-access / area denial]の挑戦に対応するため、米国は、空海戦闘や合
同作戦接近コンセプト(JOAC)のような新たな作戦コンセプトの上に作業を始めて
きた。日本は、「動的防衛」のような同様のコンセプトで作業を始めてきた。米海軍と
日本の海上自衛隊は、歴史的に2国間の共通運用性[interoperability]を進めてきた
が、新しい環境は、米国と日本の間での相互的な、より大きなめざましい合同と共同運
用性の相互提供を要求している。この課題は、2国間の「役割・任務・能力」対話の核
心であるべきで、米国防総省と国務省における上級指導部により、日本の防衛省と外務
省と一緒に、完全に統合され推進されなければならない。予算に制限がある時期におい
て、「役割・任務・能力」は、断片的に、あるいは下級官僚によって対処されることは
できない。
同盟の防衛協力が潜在的に増大している追加的な分野は、ペルシア湾における機雷除去
と、南シナ海の合同監視である。ペルシア湾は、重要なグローバルな貿易とエネルギー
中継の軸である。ホルムズ海峡を封鎖するというイランの意図が最初に言葉で示される
か、その兆候が現れたら、日本は、この国際的な不法行為に対抗するため、この地域に
掃海艇を単独で派遣すべきである。南シナ海の平和と安定は、日本にとって特別に重要
な海域であることにより、なおも同盟のもう一つの重要な関心事である。死活的に重要
なエネルギー資源を含む、日本への供給の88%が南シナ海を経由しているので、安定と
航海の自由の継続を確保するために米国と協働して監視を増やすことは、日本の利益で
ある。
「日本の防衛」と地域的安全保障との差異は小さい。ホルムズ海峡の封鎖あるいは南シ
ナ海での不測の事態は、日本の安全保障と安定に深刻な影響を与えるだろう。昔、押し
売りされた矛と盾の例え話は、現在の安全保障のダイナミクスを単純化しすぎており、
日本が自国の防衛に備えるには攻撃的責務を必要とするという事実をまげて解釈するも
のである。しかし同盟諸国は、日本の領域をはるかに越えて広がる、強健で共有された
、共同運用性のある「情報・監視・偵察」(ISR)の能力と作戦を必要としている。
その一部として、在日米軍は、日本の防衛という特定の役割を与えられてきた。作戦能
力の目標と、事実上の在日米軍-自衛隊の合同タスクフォースの能力を念頭に置き、米
国は在日米軍に、より大きな責任と任務の意味を与えるべきである。
ワシントンと東京で立ちはだかっている予算削減と緊縮財政の真っ只中にあって、資源
の賢明な使用は能力を維持するのに不可欠である。より賢明な資源の使用の重要な表れ
が、共通運用性である。共通運用は、米国の装備の購入の婉曲的表現ではない。その核
心は、それが一緒に働くための基本的な能力であることである。米空軍と日本の航空自
衛隊は進展をさせつつあるが、米陸軍と海兵隊の陸上自衛隊との協力は、力点の違いが
あって限られてきた。日本が平和維持や災害救助の作戦を行ってきたのに対し、米国は
、中東で地上戦を戦うことに努力を集中させてきた。
共通運用を強化する一つの方法は、2国間の防衛演習の質を改善することである。米空
軍と海軍航空部隊は自衛隊と一緒に、民間空港を毎年巡回して訓練を行うべきである。
新たな訓練地域は、潜在的な不測の事態という、より広い視野を想定し、両軍により多
く体験させ、沖縄の人びとに負担共有の意味を与えることができよう。第2に、自衛隊
と米軍は危機に合同で対応する能力を改善するために、トモダチ作戦から学んだ教訓を
テストすべきである。第3に、陸上自衛隊は、注目すべき平和維持活動(PKO)と災
害救助活動を継続しつつも、水陸両面作戦の能力を強化すべきである。陸上自衛隊の態
勢を、陸上を基本にしたものから敏捷で展開可能な部隊に向け直すことは、同盟国にと
って将来の兵力構成をより良く準備することになろう。第4に、米国と日本は、オース
トラリアのダーウィンの新たな共有施設とともに、グアムと北マリアナ諸島連邦の新し
い訓練場を十分に使用すべきである。合同の海洋遠征能力は、日本、韓国、オーストラ
リア、カナダ、ニュージーランドにとって核心的な焦点である。米軍、特に海兵隊との
訓練は、より広範な共通運用性を強化するだろう。最後に、東京は、2国間と国家の安
全保障秘密および機密情報の保護のため、防衛省の法的能力を強化すべきである。[日
本の]現在の法体制は、機密性において同じ米国の基準を満たしていない。政策と厳し
い防衛訓練の組み合わせは、日本の発生期の「特殊作戦部隊」の能力を加速し、共通運
用性を改善するだろう。
<技術協力と共同研究開発>
共通運用の第2の側面は、ハードウェアである。米国と日本双方の経済的現実と防衛予
算の増大が起こりそうにないことから、防衛産業のより緊密な協働が必要である。日本
の「武器輸出3原則」の見直しは、武器輸出と技術協力についての政策的窓口を拡大し
てきた。合同の協働は、両国政府にとってコストを削減し、産業的関係(欧州と米国の
防衛企業間の数十年間のパートナーシップと同類の)を強化するだろうが、この同盟は
依然として、この分野でどう前進するかを決めなければならない。
米国は、[日本の]政策変更の音頭を取り、日本の防衛産業に技術を輸出するよう奨励
すべきである。アメリカ人が、日本の防衛輸出を米国の安全保障あるいは産業基盤に脅
威を及ぼすと危惧すべきだった時期は過去のものである。マイクロ・レベルでは、米国
はエレクトロニック、ナノテク、合成物、その他の高価値のコンポーネントを輸入すべ
きである(日本は自由に輸出すべきである)。この分野での同盟的貿易は、米国の防衛
企業に、日本がすでに独占的に製造し、あるいはライセンス生産をしている、精巧な2
次的または主要な源泉技術へのアクセスの機会を与えるだろう。日本からの輸入はまた
、米国と日本の防衛生産品のコストを引き下げ、品質を改善する可能性を持っている。
マイクロ・レベルでは、規制緩和は、将来の精巧な兵器やその他の安全保障システムの
共同開発の機会を容易にする。ミサイル防衛は、この点で優れたモデルとなってきた。
この計画は、同盟は協力によって非常に複雑な防衛システムを共同開発、共同生産、共
同作業をすることができることを示している。当面の同盟の兵器計画は、相互の関心と
作戦上の要請による特定のプロジェクトを考慮すべきである。しかしながら、この同盟
はまた、共同開発に向けて長期的な作戦上の要請を明確にすべきである。可能な兵器協
力の分野は、次世代戦闘機、戦闘艦、レーダー、戦略的空輸、通信および包括的なIS
R[情報・監視・偵察]能力でありうるだろう。加えて、米国は東京と他の同盟国の間
での武器輸出と技術協力を奨励すべきである。たとえば、オーストラリアはディーゼル
潜水艦と、もしかすると戦闘攻撃機の技術協力について日本と議論している。米国は、
このような対話を奨励し、この勢いをつけるべきである。
米国と日本は、地球上で最も大きな、最も能力のある研究開発の2カ国である。われわ
れは同盟国として、コストと複雑さが急速に高まっている部門でこれらの能力を結合さ
せ、効果を達成すべきである。兵器協力のための同盟の枠組みは、よりよい組織を必要
としよう。過去においては、協力は「科学・技術フォーラム」(S&TF)に追いやら
れてきた。この機関は、政策中心の「安全保障協議委員会」とは別個に運営されている
。この二つの機関のいっそうの統合は、兵器における同盟の効率と効果を達成するだろ
う。この努力にとっての基本は、米国の「対外軍事販売」(FMS)プロセスの改革で
あるだろう。それはもはや、現在の予算、軍、技術の現実を反映していない。
<サイバー安全保障>
サイバー安全保障は、米国と日本の役割と基準をさらに明確にすることを要求している
、生成中の戦略的分野である。すべての防衛作戦、協力、合同の戦闘は、情報を確実な
ものにする手段の信頼性と能力に厳しく依存している。近年、サイバー攻撃やサイバー
・ハッキングが、特に政府機関や防衛産業の企業に対して行われるケースの増加は、機
微なデータの安全保障を脅かし、機密情報がテロリストや反政府勢力の手に渡るリスク
をくりかえしてきた。情報の安全確保で共通の安全対策と基準がないため、米日の通信
回路は外部の侵入に対してますますもろくなっている。米国は国家安全保障局(NSA
)に並んでサイバー・コマンドを運営しているが、日本は同様なものを持っていない。
この不釣り合いを解消するため、米国と日本は調査と共通の情報安全保障基準の実施の
ための「合同サイバー安全保障センター」を設立すべきである。そのようなイニシアテ
ィヴは、日本のもろいサイバー安全保障のインフラを強固にしようし、日本の国防を支
えることになろう。サイバーへの関与と協議がないなら、安全保障の課題への同盟諸国
のいっそうの関与は制約に直面するだろう。
<抑止の傘>
同盟による防衛において信頼向上を必要とするもう一つのカギは、抑止の傘[核の傘]
である。日本は、核のない世界を見たいという願望と、もし米国が、その核戦力を中国
と同量まで減らすなら、米国の抑止の傘の信頼性が弱まり、日本がその結果に苦しむこ
とになるという懸念との間で引き裂かれている。抑止の傘は、核兵器の数の均衡とか日
本の領海内への核兵器の配置に依拠していると考えるのは間違いである。抑止の傘は、
能力と信頼性の組み合わせに依拠している。冷戦の間、米国はベルリンを防衛できたが
、それは、そうするというわれわれの約束が、高い賭け金、つまりNATO同盟によっ
て信頼できるものにされたからであり、また、米国の犠牲者とソビエトの攻撃の分離を
不可能にする米国軍のプレゼンスがあったからである。米国と日本は、米国の抑止の傘
の戦略と能力における相互信頼を助長するため、現在の抑止の傘の対話を再活性化させ
るべきである。日本への米国の抑止の傘の最良の保証は、やはり米軍のプレゼンスであ
り、それは日本の気前のいい受入国支援[host nation support]によって強化されて
いる。
<普天間>
日本における米軍のプレゼンスは、同盟の一体性の分野から遠いものであった。この同
盟は過去10年間、沖縄の米軍の配置という細部に過大に高度の注意を費やしてきた。そ
の結果は、普天間の海兵隊航空基地という第3順位[優先度の低い]の課題が時間と政
治的資本を奪うことになってきたが、[それがなければ]その資本は、これから10年間
の最善の兵力編成のための計画立案により良く投資されてきただろう。過去の配置から
生じた遺産問題がどんなものであったにせよ、われわれは、よりしっかりと将来に焦点
を当てるなら、それらがより容易に溶解できることが分かると思われる。
<集団的自衛の禁止>
3・11の三重の危機[大地震、大津波、原発の過酷事故]とトモダチ作戦は、米国と日
本の軍隊の展開について興味深い皮肉をもたらした。3・11は外敵に対して防衛すると
いう事態ではなかったが、自衛隊と米軍は、集団的自衛の禁止規定に注意することなく
行動した。米国の軍艦は危機に対応して、北海道にいる陸上自衛隊を日本の東北地方に
運んだ。両国の軍隊は、仙台の重要な飛行場が使用できるように行動し、そこでは軍と
市民組織が災害対策と救援に従事した。これらの活動は、東北アジア[東北地方の誤記
?]の復旧の条件をつくり出した。トモダチ作戦の期間中の憲法9条のあいまいな解釈
に加えて、日本と米国は他のいくつかの国と協力して、アデン湾で海賊行為と戦ってい
る。日本は、インド洋における重要な海賊取締りに参加できるよう、法的課題を解釈し
直してきた。しかしながら皮肉なことは、われわれの軍隊が日本を集団的に防衛するこ
とを法的に阻まれていることである。
日本の集団的自衛の禁止における一つの変化は、その皮肉に十分に対処することになる
だろう。政策の転換は、司令部の統一や、より軍事的に攻撃的な日本、あるいは日本の
平和憲法の変更を求めるべきではない。集団的自衛の禁止は、この同盟にとって障害物
である。3・11は、われわれの両軍が、必要な場合にはその能力を最大化できることを
示した。われわれの軍隊が平和時、緊張、危機、そして戦争という安全保障の全領域で
完全に協力して対応することを許すのは、それぞれの政府当局であるだろう。
<平和維持活動>
2012年は、国連平和維持活動への日本の参加の20周年に当たる。自衛隊は南スーダンで
、若い政府が国家の機能を拡大するのを助けるために基本的なインフラを建設している
。自衛隊はジブチでは、アデン湾で海賊取締りの任務のパトロールをするために駐留し
ている。自衛隊はハイチでは、災害後の復興を進め、感染症の拡大を封じ込めることに
参加している。PKOの役割と責任は根気のいるもので、非常にしばしば、過酷な環境
と生活条件を伴っている。PKOへの日本の参加を通じて、自衛隊はその国際的関与と
、対テロ作戦や核の非拡散、人道的援助、災害救助への準備態勢を拡げてきた。さらに
完全な参加のために、われわれは、日本が、必要な場合には武力をもって他国の平和維
持要員だけでなく市民をも防護するために、日本の国際的な平和維持軍に与える法的許
容範囲を拡大すべきであると勧告する。自衛隊についての認識は変化しつつあり、彼ら
は日本の外交政策の最も実行性のある手段の一つと見られている。
結論
日本についての現在の論文・講演は、「危機」と「不決断」に関する言い回しで責めた
てられている。これらの言葉は国の衰退を示唆しうるが、われわれは、それがすでに先
行した結論だとは信じない。日本が危機的な状況にあるというのは、われわれの意見で
ある。日本は、戦略的に重要なときには、自己満足とリーダーシップの間で決断する力
を持っている。アジア太平洋地域全体でダイナミックな変化が起こっているが、おそら
く日本は、この地域の運命を導くのに役立つための同じ機会を持つことは決してないだ
ろう。日本はリーダーシップの選択において、一つに結び付いた国としての地位と、同
盟における対等なパートナーとしての必要な役割を確保することができる。
この漂流の時期において、トモダチ作戦はしばらくの間、米日同盟を手に入れた。それ
はこの同盟に、過去3年間の特異な政治的不一致に続いて同盟が緊急に必要とした意味
と価値を与えた。しかし、それは直面する課題を通じて同盟を運用するには十分ではな
いだろう。急速に進展する戦略的見通しと、途方もない予算の難題は、米国と日本の側
に、より賢明でより適応性のある関与を要求している。この報告書に含まれている勧告
は、米国と日本がそれに関して前進できる分野に光を当てるための試みである。同様に
重要なのは、両国の側での実行である。そこで、最後の勧告として、われわれは米国と
日本の双方に、その[同盟の]改善に単独で専念する政策責任者を任命することによっ
て、米日同盟に対する誓約を立証するよう求める。この同盟は、この注意を払われるこ
とに値するし、それを必要としている。
勧告
<日本への勧告>
●原子力発電の慎重な再開は、日本にとって正しく責任ある前進である。原子炉を再起
動させることは、2酸
化炭素の排出を2020年までに25%削減するという東京の野心的な案を可能にする唯一の
方法である。再起動はまた、高いエネルギー価格が円高とあいまって、日本からエネル
ギー依存型の重要な産業を[海外に]追い出さないことを確実にするのに役立つ賢明な
ものである。フクシマからの実地の教訓に学びつつ、東京は安全な原子炉の設計と健全
な規制の実施を推進するリーダーシップを引き受けるべきである。
●東京は、海賊行為と戦い、ペルシア湾の海運を防護し、シーレーンを確保し、イラン
の核計画でもたらされ
ているような地域の平和への脅威に立ち向かう多国間の努力への積極的な関与を続ける
べきである。
●TPP交渉への参加に加えて、日本は、この報告書で説明されているCEESAのよ
うな、より野心的で包括的な交渉を検討すべきである。
●この同盟が潜在能力を十分に実現させるには、日本は、韓国との関係を複雑にし続け
ている歴史問題に向き合うべきである。東京は、長期的な戦略的展望において2国間の
結びつきを検証し、根拠のない政治的声明を出すことを避けるべきである。3カ国の防
衛協力を強化するため、東京とソウルは、延期されたGSOMIAとACSAの防衛協
定を締結し、3国間の軍事的関与を継続すべきである。
●東京は、民主主義的なパートナー諸国、特にインド、オーストラリア、フィリピン、
台湾とともに、地域的フォーラムへの関与を続けるべきである。
●役割と任務の新たな見直しにおいて、日本は、日本の防衛および地域的な不測の事態
において米国とともに行う防衛を含む責任分野を拡大すべきである。この同盟は、日本
の領域をかなり超える、より強健で、共有され、共通運用可能な「情報・監視・偵察」
の能力と作戦を要求している。米軍と自衛隊が、平和時、緊張、危機および戦争という
安全保障の全局面において十分に協力して対応することを許すのは、日本側の責任当局
であろう。
●ホルムズ海峡を封鎖するというイランの意図が言葉で示され、またはその兆候が出た
際は、日本は単独でこの地域に掃海艇を派遣すべきである。日本はまた、航海の自由を
確保するため、米国と協働して南シナ海の監視を増やすべきである。
●東京は、2国間および国家の安全保障上の秘密を防護するため、防衛省の法的権限を
強化すべきである。
●PKOへのより十分な参加を可能にするため、日本は、必要な場合には武力をもって
市民や他の国際的平和維持要員を防護することを含めるため、平和維持要員の許容範囲
を拡大すべきである。
<米日同盟への勧告>
●フクシマからの実地の教訓に学びつつ、東京とワシントンは、原子力の研究開発の協
力を再活性化させ、安全な原子炉の設計と健全な規制の実施をグローバルに推進すべき
である。
●安全保障関係の一部として、米国と日本は、天然ガスの同盟であるべきである。日本
と米国は、メタン・ハイドレートの研究開発における協働を強化し、代替エネルギー技
術の開発に参加すべきである。
●ワシントンと東京、ソウルは、歴史問題に関するトラック2の対話を拡大し、これら
機微な事柄をどのように扱うかについての合意を追求し、対話から生まれた政治的指導
者や政府の指導者たちの行動のための提案や勧告を採り上げるべきである。この作業は
、これらの困難な課題における相互協力についての「最良の行動」規範と原則について
の合意を追求すべきである。
●同盟は、中国の再興に対応する能力と政策を発展させなければならない。同盟は、平
和的で繁栄する中国から得るものは多いが、高度経済成長の持続と政治的安定は確実で
はない。同盟の政策と能力は、中国の核心的利益のありうる拡大、変化しつつある軌道
および広範な将来の可能性に適用できるものであるべきである。
●人権に関する具体的な行動計画の策定は、称賛に値する目標である。特に、ビルマ(
ミャンマー)、カンボジア、ベトナムでは、同盟国の関与が国際人道法と市民社会を助
長できる。北朝鮮に関しては、この同盟は韓国とともに、人道問題のすべてにわたって
対応すべきである。それには、非核化と拉致問題に加えて、食糧安全保障、災害救助、
公衆衛生が含まれる。
●米国と日本は、「役割・任務・能力」(RMC)対話により、空海戦闘と動的防衛の
ようなコンセプトを一致させるよう調整すべきである。それは現在まで、上級レベルの
注意は不十分にしか払われてこなかった。役割と任務の新たな見直しは、同盟国の軍事
的、政治的、経済的な国力の総合的な組み合わせとともに、より広い地理的視野を含む
べきである。
●米陸軍・海兵隊の陸上自衛隊との協力は、共通運用に向けて前進し、水陸両用の、敏
捷で、展開可能な兵力の態勢に向かうべきである。
●米国と日本は、民間飛行場を巡回使用し、トモダチ作戦から学んだ教訓をテストし、
水陸両用の能力を強化することで、2国間の防衛演習の質を高めるべきである。米国と
日本は、2国間および他のパートナー国とともに、グアム、北マリアナ諸島連邦、オー
ストラリアでの訓練の機会を十分利用すべきである。
●米国と日本は、将来の兵器の共同開発の機会を増やすべきである。当面の兵器計画は
、相互の関心と作戦上の要請による特定のプロジェクトを考慮すべきである。この同盟
はまた、[兵器の]共同生産のための長期的な作戦上の要請を明確にすべきである。
●米国と日本は、米国が重要な同盟国に差し伸べている抑止の傘の信頼性と能力におけ
る対等な信頼を確保するため、抑止の傘についての対話(おそらく韓国と協力して)を
再活性化すべきである。
●米国と日本は、共通の情報保証基準の研究と実施のための「合同サイバー・センター
」を設けるべきである。
<米国への勧告>
●米国は、資源ナショナリズムに訴えるべきではなく、民間のLNG輸出計画を禁じる
べきでもない。危機の際は、米国はその同盟国に定常的で安定したLNGの流れを提供
すべきである。議会は、日本を他の潜在的な天然ガス消費国と平等な地位に置き、自動
的なエネルギー認可を与えるために、FTAの要件を削除する取り除く法律改正をすべ
きである。
●TPP交渉における主導的役割を持つ米国は、交渉プロセスと協定草案に、より多く
の光[影響]を及ぼすべきである。TPPへの日本の参加は、米国の戦略的目標として
見直されるべきである。
●米国は、日本と韓国の間の機微な歴史問題に判断を差しはさむべきではない。しかし
ながら米国は、緊張を和らげ、両国の核心的な国家安全保障への注意に再び焦点を当て
るため、十分な外交努力をすべきである。
●在日米軍は、日本防衛のための特別の責任を負っている。米国は、在日米軍に対し、
より大きな責任と任務の意味を与える必要がある。
●米国は、「武器輸出3原則」の緩和を前進させ、日本の防衛産業が米国だけでなく、
オーストラリアのような他の同盟国にも[防衛]技術を輸出するよう奨励すべきである
。米国は、古臭く障害となるFMSの手続きを見直さなければならない。
●米国は、共同の研究開発と技術協力をさらに推進するため、「科学・技術フォーラム
」を政策中心の「安全保障協議委員会」の組織とより適切に統合し、活性化させるべき
である。
●米国は、大統領により任命される者を選択し、その物に米日同盟の強化の責任を負わ
せるべきである。日本は、同様の任命を考慮することを希望しうる。
筆者について
●リチャード・L・アーミテージ;
アーミテージ・インターナショナルの代表で、CSISの理事。2001年から2005年まで
、米国の国務副長官を務めた。その経歴の中で、世界的な広がりをもつビジネスや公共
政策に取り組み、ひんぱんに社会的発言や執筆を行ってきた。1992年から93年まで、ア
ーミテージ氏は(大使の資格で)、旧ソ連から新たに独立した諸国に対する米国の援助
を指揮した。1989年から92年まで、フィリピン軍事基地協定についての大統領特別交渉
人として、また中東の水問題の特別調停者として、核心的な外交的役割を果たした。ジ
ョージ・H・W・ブッシュ大統領は、1991年の湾岸戦争の間、彼をヨルダンのフセイン
国王への特使として派遣した。ペンタゴンでは1983年から89年まで、国際安全保障問題
担当の国防次官補を務めた。アーミテージ氏は、1967年に米国海軍大学を卒業、米海軍
の海軍少尉に任命された。彼はベトナムの銃軸線[前線]に派遣された駆逐艦に乗務し
、その後ベトナムで3期の軍務を全うした。彼は多数の米軍勲章を授与され、タイ、韓
国、バーレーン、パキスタンの各政府からも勲章を与えられた。アーミテージ氏は2010
年に、名誉ある[最高位の]オーストラリア勲章を授与され、2005年には聖ミカエルお
よび聖ジョージ勲章の騎士長となった。アーミテージ氏は現在、コノコ・フィリップス
、マンテック・インターナショナル社、おうおびトランスキュ・グループ社の役員を務
めている。彼はまた、アメリカン外交アカデミーの会員でもある。彼はごく最近、国務
省優秀業績賞を授与され、国防総省の優秀公務員メダルを4回、国防長官の傑出公務員
メダル、大統領市民メダル、国務省優秀名誉賞を受けてきた。
●ジョセフ・S・ナイ;
ハーバード大学のケネディ政府学部の名誉学部長であり、CSISの理事。1964年にハ
ーバードの教授陣に加わり、国際問題センターの所長、国際問題ディロン教授、教養・
科学の学部長補を務めてきた。1977年から79年に、ナイ博士は米国の国務長官の下で安
全保障援助・科学・技術担当の副長官を務め、国家安全保障会議[NSA]の核兵器非
拡散に関するグループの長を務めた。1993年と94年には、大統領のための情報評価を調
整する国家情報会議[NIC]の議長であった。1994年と95年には、国際安全保障問題
担当の国防次官補を務めた。この3つの機関のすべてで、彼は優秀業績賞を受けた。ナ
イ博士は、アメリカン教養科学アカデミーとアメリカン外交アカデミーのフェローであ
り、3極委員会の執行委員会メンバーである。ナイ博士はまた、アスペン戦略グループ
の所長、東西安全保障研究所の所長、国際戦略研究所の所長、国連軍縮問題諮問委員会
での米国代表、および国際経済研究所の諮問委員を務めた。彼は1958年に、プリンスト
ン大学から最優秀の成績で学士号を受けた。彼はオックスフォード大学でローズ奨学金
を得て大学院で仕事をし、ハーバード大学から政治科学博士号を得た。ナイ博士はまた
、ジュネーブ、オタワ、ロンドンで短期間の教鞭をとり、ヨーロッパ、東アフリカ、中
央アメリカで長期滞在をしてきた。彼は多数の書籍の著者であり、それには『権力の将
来』(The Future of Power、公共問題、2011年)、『指導すべき権力』(The Power t
o Lead、オックスフォード大学出版、2008年)、『ソフト・パワー:世界政治における
成功の方法』(Soft Power:The Means to Success in World Politics、公共問題、20
04年)が含まれる。
http://csis.org/files/publication/120810_Armitage_USJapanAlliance_Web.pdf
よろしければ、下のマークをクリックして!

よろしければ、もう一回!

<中国の再興>
過去30年以上にわたる中国の経済的重要さや軍事的腕力、政治的影響力の流星のような
勃興は、世界最大の人口を持つ国を劇的に刷新してきただけでなく、東アジアの冷戦後
の地政学的な風景を決定的に形作ってもきた。強力な米日同盟は、中国の再興を圧迫す
るのではなく、その中で中国が繁栄してきた安定的で予見可能な安全保障上の環境をも
たらすことに役立つことで、それ[中国]に貢献してきた。この同盟は、中国の成功に
利害関係を持ってきた。しかしながら、中国が新たに見出した力をどのように使うつも
りか――現存の国際的規範を再強化するのか、北京の国益に沿ってそれらを見直すのか
、あるいは、その両方か――ということに関する透明性の欠如とあいまいさは、懸念が
増大する分野である。
特に不安な一つの分野は、中国の拡大しうる核心的利益である。公式の3地域――新疆
ウイグル自治区[Xinjiang]、チベット、台湾――に加えて、南シナ海と尖閣諸島が、
現れつつある利害地域として言及されてきた。後者は非公式だし宣言はされていないが
、人民解放軍(PLA)の海軍の南シナ海と東シナ海でのプレゼンスの増大は、われわ
れを別の推論に導いている。主権という共有のテーマが、尖閣諸島と南シナ海における
北京の意図についての疑問をさらに生じさせている。一つだけは確実である――中国の
不明確な核心的利益の主張は、この地域における中国の外交的信頼性をさらに低減させ
ている。
中国に対する同盟の戦略は、関与と障壁を設けることとのブレンドであり、中国が急速
に成長しつつある包括的な国力の使い方にどのような選択をするかについての不確実性
に相応している。しかし、中国の増大する軍事力と政治的自己主張に対する同盟による
障壁の最大の側面――地理的視点での同盟の活動の漸進的な拡大、ミサイル防衛技術で
の共同作業、[兵器、情報などでの]共通運用性とシーレーン交通路の維持に関連する
任務への注意の向上、東南アジア諸国連合(ASEAN)のような地域機構を強化する
努力、航海の自由に新たに焦点を当てること、および2011年12月に打ち出された米・日
・インドの3国対話――は、中国が高い経済成長の道を進み、防衛支出と能力を同様に
増大させ続けるだろうという想定に基づいてきた。
この想定は、もはや断言できない。中国は、1979年の{ケ小平による「改革開放」の打ち
上げから40年の時期[fourth decade]に入っているので、成長が遅くなっているとい
う多くの指標がある。輸出主導から国内消費を加速する経済に移行する中国の能力につ
いては、疑問が存在する。中国の指導者たちは今後数年間、少なくとも6つの悪魔と格
闘しなければならないだろう。すなわち、エネルギーの逼迫、悲惨な環境悪化、威圧的
な人口統計的現実、国民間および地域間の所得格差の拡大、新疆とチベットの御しがた
い少数民族、および根深い公務員の腐敗である。
経済的成功は、このリストに「中間所得の落とし穴」に対抗するという不確実性を付け
加える。そこでは増大しつつある中間所得層という軍団が、中国の政治構造に、期待の
高まりに対応するための格別の圧力をかけている。これらの課題のどれ一つも、中国の
経済成長の道を脱線させ、社会的安定を脅かしうるだろう。中国共産党は、これらの気
の滅入るような難問を自覚しており、その指導者たちが2012年に、防衛予算にほぼ匹敵
する1200億ドル[約9兆6000億円/1ドル=80円として]以上に国内治安の予算を増額
したのも、それが一つの理由である。人民解放軍は、台湾が正当な独立に向かって進む
のを抑止することを含む、外的脅威に対処するための財源の獲得に集中している。しか
し中国共産党は、同様に国内の脅威にも心配している。
ひどくつまづいている中国は、必ずしもより小さくはないが、まったく異なる課題を[
米日]同盟に提起しうるだろう。われわれはみな、平和で繁栄した中国から得るものが
多い。代わりに、深刻な国内的亀裂に直面している中国の指導者たちは、民族主義に逃
げ込むことができるだろうし、団結を再び捏造するために、たぶん、現実に、または想
像上の外的脅威を作り出しうるだろう。秩序を維持するために、指導部はさらに苛酷な
手段に向かうこともできる。現存する人権侵害をいっそう悪化させ、外国のパートナー
たちを遠ざけ、40年前にニクソンが扉を開けて以来、西側の中国への関与を動かしてき
た政治的合意を危険にさらす、などである。
代わりに、将来の中国の主席は、温家宝首相が求めたような新たな一連の政治改革を採
用して、中国の国内政治と対外的姿勢に異なる結果をもたらすかもしれない。確実なの
は、ただ一つである。すなわち、同盟は中国の変化しつつある軌道と、広い範囲にわた
る将来の可能性に適用できる能力と政策を発展させなければならない。高度経済成長と
変化しない政治的権威は、中国の新しい指導者たちが期待している将来ではない。した
がってわれわれは、彼らの判断を知らされるべきある。
<人権と米日同盟 : 行動計画を発展させる>
2012年4月30日、米日同盟の将来についての共同声明は、その関係を強化させる共通の
価値についての明確な言及を含んでいる。すなわち、「日本と米国は、民主主義、法の
支配、開かれた社会、人権、人間の安全保障、および自由で開かれた市場への誓約を共
有する。これらの価値は、この時代のグローバルな諸課題に対処する共同の努力にわれ
われを導く」と。この共同声明はそのあとで、これらの共通の価値を実行に移すことを
約束している。「われわれは、法の支配と人権の保護を推進するために共に努力するこ
とを約束し、平和維持、紛争後の安定化、開発援助、組織犯罪と麻薬取引、および感染
症に対する協調を強める」と。
人権に関する、より具体的な行動計画の策定は称賛に値する目的であり、その機会とす
べき多くの目標がある。ビルマ(ミャンマー)の民主的改革を進めることは、優先順位
の高いものであるべきである。米国と日本は、民間部門の投資や外国の援助、国際金融
機関からの融資でもたらされる経済的テコを、良好な統治や法の支配、人権の国際的規
範の厳守を前進させるために利用すべきである。企業の社会的責任に最高の基準を設け
、ビルマのすべての利害関係者たち――少数民族や政治的反対派を含む――がビルマの
経済的将来について意見を訊かれ、関与することを確保することにより、ワシントンと
東京は、国を野蛮な軍事独裁から真に代表制民主主義に変えるために動いているビルマ
の人びとを元気づけることができる。同様の協調による努力は、もし国際人権法を推進
し、市民社会を守る誠実な約束に沿って行われるなら、カンボジアとベトナムにおいて
配当金を支払うことができるだろう。貧弱な人権の記録を持つこの両国は、米国が最近
、安全保障協力を格上げしたし、日本は重要な経済的、政治的な利害関係を持っている
。
日本にはより密接なことだが、北朝鮮は難問を提示している。ピョンヤンによる人権の
悪用は、十分に記録されており言語道断で、米日両国はそれについて見解を明らかにし
てきた。しかし米国は伝統的に、北朝鮮における人権問題を、非核化という「メイン・
イベント」から気をそらすものと見てきた。そして日本は、何年も前に北朝鮮に拉致さ
れた日本市民の運命に大きな焦点を当ててきた。われわれは、すべての拉致被害者につ
いて十分な説明を受けとるための日本の努力への支持を再確認し、日本と米国が、人権
や北朝鮮のその他の課題に効果的に関与するためのより広範な戦略の文脈の中で、この
課題について緊密に協力することを勧告する。
この同盟にとっての解決は、韓国とともに、朝鮮半島の人道的課題という全体像に対処
しつつ、関心の視野を拡大することにあろう。すなわち、拉致や強制収容所、政治的自
由と宗教的自由への深刻な規制だけではなく、食糧安全保障、災害救助、公衆衛生、教
育、文化交流もそうである。この半島の非核化に関する6者協議が事実上、停止させら
れており、人道に焦点を当てた計画は、ソウルその他の関心を有する国との緊密な調整
により、ピョンヤンの新しい指導部が北朝鮮の将来を描くような戦略的環境を再形成す
る機会を、この同盟に提供できるだろう。
新たな安全保障戦略に向けて
<地域的安全保障への関与>
原子力やODA、人権のような実際的な課題への関与に加えて、東京はこの地域の民主
的パートナー諸国、特にインド、オーストラリア、フィリピン、台湾とともに、地域的
フォーラム、すなわちASEAN、ASEAN地域フォーラム(ARF)、アジア太平
洋経済協力機構(APEC)への関与を継続することを十分に助けられるだろう。日本
は、共通の価値を超えて、また共通の利益と目標に向けて、地域のパートナー諸国との
結びつきの基礎を強化してきた。日本は、平和的で合法的な海洋環境を推進し、海路に
よる貿易が妨害されないよう確保し、全体的な経済と安全保障の良好な状態を推進する
ために、地域のパートナー諸国との協働を継続すべきである。
安全保障環境はめざましく変化してきたが、われわれのそれぞれの戦略の構成要素もそ
うである。「役割・任務・能力」(RMC)の見直し[review]が最近完了し、日本の
防衛戦略は主に北と南に拡大した。1980年代のレビューは地理的な視野を拡大し、東ア
ジアにおける同盟の能力を高めた。1990年代のレビューは、日本の防衛協力の空間のた
めの機能を明確にした。今日、関心領域はさらに南へ、そして大きく西へ――遠く中東
まで――拡大している。われわれは、われわれの戦略を十分に再定義し、われわれの実
行方法と手段を調整すべきである。新たなレビューは、われわれの軍事的、政治的、経
済的な国力の包括的な組み合わせとともに、より広い地理的視野を含むべきである。
<防衛戦略 : 同盟の共通運用性に向けて>
日本は、[軍事]能力の増強と2国間および多国間の方法で、防衛と軍事的外交をより
十分に行うことができる。新たな役割と任務のレビューは、地域的な不測の事態におい
て、日本の防衛と米国と共同の防衛とを含む、日本が責任を持つ分野を拡大すべきであ
る。最も緊急な課題は、日本自身の近隣地域にある。東シナ海の大部分と、事実上、南
シナ海全体に対する中国の積極的な自己主張、および繰り返される日本周航を含む、人
民解放軍その他の海上機関の運用テンポの劇的な増大は、「第1列島線」(日本―台湾
―フィリピン)または北京が「近海」と考えている海域全体に、より大きな戦略的影響
力を主張するという北京の意図を示している。これらの類の接近阻止/拒否地域(A2
AD)[anti-access / area denial]の挑戦に対応するため、米国は、空海戦闘や合
同作戦接近コンセプト(JOAC)のような新たな作戦コンセプトの上に作業を始めて
きた。日本は、「動的防衛」のような同様のコンセプトで作業を始めてきた。米海軍と
日本の海上自衛隊は、歴史的に2国間の共通運用性[interoperability]を進めてきた
が、新しい環境は、米国と日本の間での相互的な、より大きなめざましい合同と共同運
用性の相互提供を要求している。この課題は、2国間の「役割・任務・能力」対話の核
心であるべきで、米国防総省と国務省における上級指導部により、日本の防衛省と外務
省と一緒に、完全に統合され推進されなければならない。予算に制限がある時期におい
て、「役割・任務・能力」は、断片的に、あるいは下級官僚によって対処されることは
できない。
同盟の防衛協力が潜在的に増大している追加的な分野は、ペルシア湾における機雷除去
と、南シナ海の合同監視である。ペルシア湾は、重要なグローバルな貿易とエネルギー
中継の軸である。ホルムズ海峡を封鎖するというイランの意図が最初に言葉で示される
か、その兆候が現れたら、日本は、この国際的な不法行為に対抗するため、この地域に
掃海艇を単独で派遣すべきである。南シナ海の平和と安定は、日本にとって特別に重要
な海域であることにより、なおも同盟のもう一つの重要な関心事である。死活的に重要
なエネルギー資源を含む、日本への供給の88%が南シナ海を経由しているので、安定と
航海の自由の継続を確保するために米国と協働して監視を増やすことは、日本の利益で
ある。
「日本の防衛」と地域的安全保障との差異は小さい。ホルムズ海峡の封鎖あるいは南シ
ナ海での不測の事態は、日本の安全保障と安定に深刻な影響を与えるだろう。昔、押し
売りされた矛と盾の例え話は、現在の安全保障のダイナミクスを単純化しすぎており、
日本が自国の防衛に備えるには攻撃的責務を必要とするという事実をまげて解釈するも
のである。しかし同盟諸国は、日本の領域をはるかに越えて広がる、強健で共有された
、共同運用性のある「情報・監視・偵察」(ISR)の能力と作戦を必要としている。
その一部として、在日米軍は、日本の防衛という特定の役割を与えられてきた。作戦能
力の目標と、事実上の在日米軍-自衛隊の合同タスクフォースの能力を念頭に置き、米
国は在日米軍に、より大きな責任と任務の意味を与えるべきである。
ワシントンと東京で立ちはだかっている予算削減と緊縮財政の真っ只中にあって、資源
の賢明な使用は能力を維持するのに不可欠である。より賢明な資源の使用の重要な表れ
が、共通運用性である。共通運用は、米国の装備の購入の婉曲的表現ではない。その核
心は、それが一緒に働くための基本的な能力であることである。米空軍と日本の航空自
衛隊は進展をさせつつあるが、米陸軍と海兵隊の陸上自衛隊との協力は、力点の違いが
あって限られてきた。日本が平和維持や災害救助の作戦を行ってきたのに対し、米国は
、中東で地上戦を戦うことに努力を集中させてきた。
共通運用を強化する一つの方法は、2国間の防衛演習の質を改善することである。米空
軍と海軍航空部隊は自衛隊と一緒に、民間空港を毎年巡回して訓練を行うべきである。
新たな訓練地域は、潜在的な不測の事態という、より広い視野を想定し、両軍により多
く体験させ、沖縄の人びとに負担共有の意味を与えることができよう。第2に、自衛隊
と米軍は危機に合同で対応する能力を改善するために、トモダチ作戦から学んだ教訓を
テストすべきである。第3に、陸上自衛隊は、注目すべき平和維持活動(PKO)と災
害救助活動を継続しつつも、水陸両面作戦の能力を強化すべきである。陸上自衛隊の態
勢を、陸上を基本にしたものから敏捷で展開可能な部隊に向け直すことは、同盟国にと
って将来の兵力構成をより良く準備することになろう。第4に、米国と日本は、オース
トラリアのダーウィンの新たな共有施設とともに、グアムと北マリアナ諸島連邦の新し
い訓練場を十分に使用すべきである。合同の海洋遠征能力は、日本、韓国、オーストラ
リア、カナダ、ニュージーランドにとって核心的な焦点である。米軍、特に海兵隊との
訓練は、より広範な共通運用性を強化するだろう。最後に、東京は、2国間と国家の安
全保障秘密および機密情報の保護のため、防衛省の法的能力を強化すべきである。[日
本の]現在の法体制は、機密性において同じ米国の基準を満たしていない。政策と厳し
い防衛訓練の組み合わせは、日本の発生期の「特殊作戦部隊」の能力を加速し、共通運
用性を改善するだろう。
<技術協力と共同研究開発>
共通運用の第2の側面は、ハードウェアである。米国と日本双方の経済的現実と防衛予
算の増大が起こりそうにないことから、防衛産業のより緊密な協働が必要である。日本
の「武器輸出3原則」の見直しは、武器輸出と技術協力についての政策的窓口を拡大し
てきた。合同の協働は、両国政府にとってコストを削減し、産業的関係(欧州と米国の
防衛企業間の数十年間のパートナーシップと同類の)を強化するだろうが、この同盟は
依然として、この分野でどう前進するかを決めなければならない。
米国は、[日本の]政策変更の音頭を取り、日本の防衛産業に技術を輸出するよう奨励
すべきである。アメリカ人が、日本の防衛輸出を米国の安全保障あるいは産業基盤に脅
威を及ぼすと危惧すべきだった時期は過去のものである。マイクロ・レベルでは、米国
はエレクトロニック、ナノテク、合成物、その他の高価値のコンポーネントを輸入すべ
きである(日本は自由に輸出すべきである)。この分野での同盟的貿易は、米国の防衛
企業に、日本がすでに独占的に製造し、あるいはライセンス生産をしている、精巧な2
次的または主要な源泉技術へのアクセスの機会を与えるだろう。日本からの輸入はまた
、米国と日本の防衛生産品のコストを引き下げ、品質を改善する可能性を持っている。
マイクロ・レベルでは、規制緩和は、将来の精巧な兵器やその他の安全保障システムの
共同開発の機会を容易にする。ミサイル防衛は、この点で優れたモデルとなってきた。
この計画は、同盟は協力によって非常に複雑な防衛システムを共同開発、共同生産、共
同作業をすることができることを示している。当面の同盟の兵器計画は、相互の関心と
作戦上の要請による特定のプロジェクトを考慮すべきである。しかしながら、この同盟
はまた、共同開発に向けて長期的な作戦上の要請を明確にすべきである。可能な兵器協
力の分野は、次世代戦闘機、戦闘艦、レーダー、戦略的空輸、通信および包括的なIS
R[情報・監視・偵察]能力でありうるだろう。加えて、米国は東京と他の同盟国の間
での武器輸出と技術協力を奨励すべきである。たとえば、オーストラリアはディーゼル
潜水艦と、もしかすると戦闘攻撃機の技術協力について日本と議論している。米国は、
このような対話を奨励し、この勢いをつけるべきである。
米国と日本は、地球上で最も大きな、最も能力のある研究開発の2カ国である。われわ
れは同盟国として、コストと複雑さが急速に高まっている部門でこれらの能力を結合さ
せ、効果を達成すべきである。兵器協力のための同盟の枠組みは、よりよい組織を必要
としよう。過去においては、協力は「科学・技術フォーラム」(S&TF)に追いやら
れてきた。この機関は、政策中心の「安全保障協議委員会」とは別個に運営されている
。この二つの機関のいっそうの統合は、兵器における同盟の効率と効果を達成するだろ
う。この努力にとっての基本は、米国の「対外軍事販売」(FMS)プロセスの改革で
あるだろう。それはもはや、現在の予算、軍、技術の現実を反映していない。
<サイバー安全保障>
サイバー安全保障は、米国と日本の役割と基準をさらに明確にすることを要求している
、生成中の戦略的分野である。すべての防衛作戦、協力、合同の戦闘は、情報を確実な
ものにする手段の信頼性と能力に厳しく依存している。近年、サイバー攻撃やサイバー
・ハッキングが、特に政府機関や防衛産業の企業に対して行われるケースの増加は、機
微なデータの安全保障を脅かし、機密情報がテロリストや反政府勢力の手に渡るリスク
をくりかえしてきた。情報の安全確保で共通の安全対策と基準がないため、米日の通信
回路は外部の侵入に対してますますもろくなっている。米国は国家安全保障局(NSA
)に並んでサイバー・コマンドを運営しているが、日本は同様なものを持っていない。
この不釣り合いを解消するため、米国と日本は調査と共通の情報安全保障基準の実施の
ための「合同サイバー安全保障センター」を設立すべきである。そのようなイニシアテ
ィヴは、日本のもろいサイバー安全保障のインフラを強固にしようし、日本の国防を支
えることになろう。サイバーへの関与と協議がないなら、安全保障の課題への同盟諸国
のいっそうの関与は制約に直面するだろう。
<抑止の傘>
同盟による防衛において信頼向上を必要とするもう一つのカギは、抑止の傘[核の傘]
である。日本は、核のない世界を見たいという願望と、もし米国が、その核戦力を中国
と同量まで減らすなら、米国の抑止の傘の信頼性が弱まり、日本がその結果に苦しむこ
とになるという懸念との間で引き裂かれている。抑止の傘は、核兵器の数の均衡とか日
本の領海内への核兵器の配置に依拠していると考えるのは間違いである。抑止の傘は、
能力と信頼性の組み合わせに依拠している。冷戦の間、米国はベルリンを防衛できたが
、それは、そうするというわれわれの約束が、高い賭け金、つまりNATO同盟によっ
て信頼できるものにされたからであり、また、米国の犠牲者とソビエトの攻撃の分離を
不可能にする米国軍のプレゼンスがあったからである。米国と日本は、米国の抑止の傘
の戦略と能力における相互信頼を助長するため、現在の抑止の傘の対話を再活性化させ
るべきである。日本への米国の抑止の傘の最良の保証は、やはり米軍のプレゼンスであ
り、それは日本の気前のいい受入国支援[host nation support]によって強化されて
いる。
<普天間>
日本における米軍のプレゼンスは、同盟の一体性の分野から遠いものであった。この同
盟は過去10年間、沖縄の米軍の配置という細部に過大に高度の注意を費やしてきた。そ
の結果は、普天間の海兵隊航空基地という第3順位[優先度の低い]の課題が時間と政
治的資本を奪うことになってきたが、[それがなければ]その資本は、これから10年間
の最善の兵力編成のための計画立案により良く投資されてきただろう。過去の配置から
生じた遺産問題がどんなものであったにせよ、われわれは、よりしっかりと将来に焦点
を当てるなら、それらがより容易に溶解できることが分かると思われる。
<集団的自衛の禁止>
3・11の三重の危機[大地震、大津波、原発の過酷事故]とトモダチ作戦は、米国と日
本の軍隊の展開について興味深い皮肉をもたらした。3・11は外敵に対して防衛すると
いう事態ではなかったが、自衛隊と米軍は、集団的自衛の禁止規定に注意することなく
行動した。米国の軍艦は危機に対応して、北海道にいる陸上自衛隊を日本の東北地方に
運んだ。両国の軍隊は、仙台の重要な飛行場が使用できるように行動し、そこでは軍と
市民組織が災害対策と救援に従事した。これらの活動は、東北アジア[東北地方の誤記
?]の復旧の条件をつくり出した。トモダチ作戦の期間中の憲法9条のあいまいな解釈
に加えて、日本と米国は他のいくつかの国と協力して、アデン湾で海賊行為と戦ってい
る。日本は、インド洋における重要な海賊取締りに参加できるよう、法的課題を解釈し
直してきた。しかしながら皮肉なことは、われわれの軍隊が日本を集団的に防衛するこ
とを法的に阻まれていることである。
日本の集団的自衛の禁止における一つの変化は、その皮肉に十分に対処することになる
だろう。政策の転換は、司令部の統一や、より軍事的に攻撃的な日本、あるいは日本の
平和憲法の変更を求めるべきではない。集団的自衛の禁止は、この同盟にとって障害物
である。3・11は、われわれの両軍が、必要な場合にはその能力を最大化できることを
示した。われわれの軍隊が平和時、緊張、危機、そして戦争という安全保障の全領域で
完全に協力して対応することを許すのは、それぞれの政府当局であるだろう。
<平和維持活動>
2012年は、国連平和維持活動への日本の参加の20周年に当たる。自衛隊は南スーダンで
、若い政府が国家の機能を拡大するのを助けるために基本的なインフラを建設している
。自衛隊はジブチでは、アデン湾で海賊取締りの任務のパトロールをするために駐留し
ている。自衛隊はハイチでは、災害後の復興を進め、感染症の拡大を封じ込めることに
参加している。PKOの役割と責任は根気のいるもので、非常にしばしば、過酷な環境
と生活条件を伴っている。PKOへの日本の参加を通じて、自衛隊はその国際的関与と
、対テロ作戦や核の非拡散、人道的援助、災害救助への準備態勢を拡げてきた。さらに
完全な参加のために、われわれは、日本が、必要な場合には武力をもって他国の平和維
持要員だけでなく市民をも防護するために、日本の国際的な平和維持軍に与える法的許
容範囲を拡大すべきであると勧告する。自衛隊についての認識は変化しつつあり、彼ら
は日本の外交政策の最も実行性のある手段の一つと見られている。
結論
日本についての現在の論文・講演は、「危機」と「不決断」に関する言い回しで責めた
てられている。これらの言葉は国の衰退を示唆しうるが、われわれは、それがすでに先
行した結論だとは信じない。日本が危機的な状況にあるというのは、われわれの意見で
ある。日本は、戦略的に重要なときには、自己満足とリーダーシップの間で決断する力
を持っている。アジア太平洋地域全体でダイナミックな変化が起こっているが、おそら
く日本は、この地域の運命を導くのに役立つための同じ機会を持つことは決してないだ
ろう。日本はリーダーシップの選択において、一つに結び付いた国としての地位と、同
盟における対等なパートナーとしての必要な役割を確保することができる。
この漂流の時期において、トモダチ作戦はしばらくの間、米日同盟を手に入れた。それ
はこの同盟に、過去3年間の特異な政治的不一致に続いて同盟が緊急に必要とした意味
と価値を与えた。しかし、それは直面する課題を通じて同盟を運用するには十分ではな
いだろう。急速に進展する戦略的見通しと、途方もない予算の難題は、米国と日本の側
に、より賢明でより適応性のある関与を要求している。この報告書に含まれている勧告
は、米国と日本がそれに関して前進できる分野に光を当てるための試みである。同様に
重要なのは、両国の側での実行である。そこで、最後の勧告として、われわれは米国と
日本の双方に、その[同盟の]改善に単独で専念する政策責任者を任命することによっ
て、米日同盟に対する誓約を立証するよう求める。この同盟は、この注意を払われるこ
とに値するし、それを必要としている。
勧告
<日本への勧告>
●原子力発電の慎重な再開は、日本にとって正しく責任ある前進である。原子炉を再起
動させることは、2酸
化炭素の排出を2020年までに25%削減するという東京の野心的な案を可能にする唯一の
方法である。再起動はまた、高いエネルギー価格が円高とあいまって、日本からエネル
ギー依存型の重要な産業を[海外に]追い出さないことを確実にするのに役立つ賢明な
ものである。フクシマからの実地の教訓に学びつつ、東京は安全な原子炉の設計と健全
な規制の実施を推進するリーダーシップを引き受けるべきである。
●東京は、海賊行為と戦い、ペルシア湾の海運を防護し、シーレーンを確保し、イラン
の核計画でもたらされ
ているような地域の平和への脅威に立ち向かう多国間の努力への積極的な関与を続ける
べきである。
●TPP交渉への参加に加えて、日本は、この報告書で説明されているCEESAのよ
うな、より野心的で包括的な交渉を検討すべきである。
●この同盟が潜在能力を十分に実現させるには、日本は、韓国との関係を複雑にし続け
ている歴史問題に向き合うべきである。東京は、長期的な戦略的展望において2国間の
結びつきを検証し、根拠のない政治的声明を出すことを避けるべきである。3カ国の防
衛協力を強化するため、東京とソウルは、延期されたGSOMIAとACSAの防衛協
定を締結し、3国間の軍事的関与を継続すべきである。
●東京は、民主主義的なパートナー諸国、特にインド、オーストラリア、フィリピン、
台湾とともに、地域的フォーラムへの関与を続けるべきである。
●役割と任務の新たな見直しにおいて、日本は、日本の防衛および地域的な不測の事態
において米国とともに行う防衛を含む責任分野を拡大すべきである。この同盟は、日本
の領域をかなり超える、より強健で、共有され、共通運用可能な「情報・監視・偵察」
の能力と作戦を要求している。米軍と自衛隊が、平和時、緊張、危機および戦争という
安全保障の全局面において十分に協力して対応することを許すのは、日本側の責任当局
であろう。
●ホルムズ海峡を封鎖するというイランの意図が言葉で示され、またはその兆候が出た
際は、日本は単独でこの地域に掃海艇を派遣すべきである。日本はまた、航海の自由を
確保するため、米国と協働して南シナ海の監視を増やすべきである。
●東京は、2国間および国家の安全保障上の秘密を防護するため、防衛省の法的権限を
強化すべきである。
●PKOへのより十分な参加を可能にするため、日本は、必要な場合には武力をもって
市民や他の国際的平和維持要員を防護することを含めるため、平和維持要員の許容範囲
を拡大すべきである。
<米日同盟への勧告>
●フクシマからの実地の教訓に学びつつ、東京とワシントンは、原子力の研究開発の協
力を再活性化させ、安全な原子炉の設計と健全な規制の実施をグローバルに推進すべき
である。
●安全保障関係の一部として、米国と日本は、天然ガスの同盟であるべきである。日本
と米国は、メタン・ハイドレートの研究開発における協働を強化し、代替エネルギー技
術の開発に参加すべきである。
●ワシントンと東京、ソウルは、歴史問題に関するトラック2の対話を拡大し、これら
機微な事柄をどのように扱うかについての合意を追求し、対話から生まれた政治的指導
者や政府の指導者たちの行動のための提案や勧告を採り上げるべきである。この作業は
、これらの困難な課題における相互協力についての「最良の行動」規範と原則について
の合意を追求すべきである。
●同盟は、中国の再興に対応する能力と政策を発展させなければならない。同盟は、平
和的で繁栄する中国から得るものは多いが、高度経済成長の持続と政治的安定は確実で
はない。同盟の政策と能力は、中国の核心的利益のありうる拡大、変化しつつある軌道
および広範な将来の可能性に適用できるものであるべきである。
●人権に関する具体的な行動計画の策定は、称賛に値する目標である。特に、ビルマ(
ミャンマー)、カンボジア、ベトナムでは、同盟国の関与が国際人道法と市民社会を助
長できる。北朝鮮に関しては、この同盟は韓国とともに、人道問題のすべてにわたって
対応すべきである。それには、非核化と拉致問題に加えて、食糧安全保障、災害救助、
公衆衛生が含まれる。
●米国と日本は、「役割・任務・能力」(RMC)対話により、空海戦闘と動的防衛の
ようなコンセプトを一致させるよう調整すべきである。それは現在まで、上級レベルの
注意は不十分にしか払われてこなかった。役割と任務の新たな見直しは、同盟国の軍事
的、政治的、経済的な国力の総合的な組み合わせとともに、より広い地理的視野を含む
べきである。
●米陸軍・海兵隊の陸上自衛隊との協力は、共通運用に向けて前進し、水陸両用の、敏
捷で、展開可能な兵力の態勢に向かうべきである。
●米国と日本は、民間飛行場を巡回使用し、トモダチ作戦から学んだ教訓をテストし、
水陸両用の能力を強化することで、2国間の防衛演習の質を高めるべきである。米国と
日本は、2国間および他のパートナー国とともに、グアム、北マリアナ諸島連邦、オー
ストラリアでの訓練の機会を十分利用すべきである。
●米国と日本は、将来の兵器の共同開発の機会を増やすべきである。当面の兵器計画は
、相互の関心と作戦上の要請による特定のプロジェクトを考慮すべきである。この同盟
はまた、[兵器の]共同生産のための長期的な作戦上の要請を明確にすべきである。
●米国と日本は、米国が重要な同盟国に差し伸べている抑止の傘の信頼性と能力におけ
る対等な信頼を確保するため、抑止の傘についての対話(おそらく韓国と協力して)を
再活性化すべきである。
●米国と日本は、共通の情報保証基準の研究と実施のための「合同サイバー・センター
」を設けるべきである。
<米国への勧告>
●米国は、資源ナショナリズムに訴えるべきではなく、民間のLNG輸出計画を禁じる
べきでもない。危機の際は、米国はその同盟国に定常的で安定したLNGの流れを提供
すべきである。議会は、日本を他の潜在的な天然ガス消費国と平等な地位に置き、自動
的なエネルギー認可を与えるために、FTAの要件を削除する取り除く法律改正をすべ
きである。
●TPP交渉における主導的役割を持つ米国は、交渉プロセスと協定草案に、より多く
の光[影響]を及ぼすべきである。TPPへの日本の参加は、米国の戦略的目標として
見直されるべきである。
●米国は、日本と韓国の間の機微な歴史問題に判断を差しはさむべきではない。しかし
ながら米国は、緊張を和らげ、両国の核心的な国家安全保障への注意に再び焦点を当て
るため、十分な外交努力をすべきである。
●在日米軍は、日本防衛のための特別の責任を負っている。米国は、在日米軍に対し、
より大きな責任と任務の意味を与える必要がある。
●米国は、「武器輸出3原則」の緩和を前進させ、日本の防衛産業が米国だけでなく、
オーストラリアのような他の同盟国にも[防衛]技術を輸出するよう奨励すべきである
。米国は、古臭く障害となるFMSの手続きを見直さなければならない。
●米国は、共同の研究開発と技術協力をさらに推進するため、「科学・技術フォーラム
」を政策中心の「安全保障協議委員会」の組織とより適切に統合し、活性化させるべき
である。
●米国は、大統領により任命される者を選択し、その物に米日同盟の強化の責任を負わ
せるべきである。日本は、同様の任命を考慮することを希望しうる。
筆者について
●リチャード・L・アーミテージ;
アーミテージ・インターナショナルの代表で、CSISの理事。2001年から2005年まで
、米国の国務副長官を務めた。その経歴の中で、世界的な広がりをもつビジネスや公共
政策に取り組み、ひんぱんに社会的発言や執筆を行ってきた。1992年から93年まで、ア
ーミテージ氏は(大使の資格で)、旧ソ連から新たに独立した諸国に対する米国の援助
を指揮した。1989年から92年まで、フィリピン軍事基地協定についての大統領特別交渉
人として、また中東の水問題の特別調停者として、核心的な外交的役割を果たした。ジ
ョージ・H・W・ブッシュ大統領は、1991年の湾岸戦争の間、彼をヨルダンのフセイン
国王への特使として派遣した。ペンタゴンでは1983年から89年まで、国際安全保障問題
担当の国防次官補を務めた。アーミテージ氏は、1967年に米国海軍大学を卒業、米海軍
の海軍少尉に任命された。彼はベトナムの銃軸線[前線]に派遣された駆逐艦に乗務し
、その後ベトナムで3期の軍務を全うした。彼は多数の米軍勲章を授与され、タイ、韓
国、バーレーン、パキスタンの各政府からも勲章を与えられた。アーミテージ氏は2010
年に、名誉ある[最高位の]オーストラリア勲章を授与され、2005年には聖ミカエルお
よび聖ジョージ勲章の騎士長となった。アーミテージ氏は現在、コノコ・フィリップス
、マンテック・インターナショナル社、おうおびトランスキュ・グループ社の役員を務
めている。彼はまた、アメリカン外交アカデミーの会員でもある。彼はごく最近、国務
省優秀業績賞を授与され、国防総省の優秀公務員メダルを4回、国防長官の傑出公務員
メダル、大統領市民メダル、国務省優秀名誉賞を受けてきた。
●ジョセフ・S・ナイ;
ハーバード大学のケネディ政府学部の名誉学部長であり、CSISの理事。1964年にハ
ーバードの教授陣に加わり、国際問題センターの所長、国際問題ディロン教授、教養・
科学の学部長補を務めてきた。1977年から79年に、ナイ博士は米国の国務長官の下で安
全保障援助・科学・技術担当の副長官を務め、国家安全保障会議[NSA]の核兵器非
拡散に関するグループの長を務めた。1993年と94年には、大統領のための情報評価を調
整する国家情報会議[NIC]の議長であった。1994年と95年には、国際安全保障問題
担当の国防次官補を務めた。この3つの機関のすべてで、彼は優秀業績賞を受けた。ナ
イ博士は、アメリカン教養科学アカデミーとアメリカン外交アカデミーのフェローであ
り、3極委員会の執行委員会メンバーである。ナイ博士はまた、アスペン戦略グループ
の所長、東西安全保障研究所の所長、国際戦略研究所の所長、国連軍縮問題諮問委員会
での米国代表、および国際経済研究所の諮問委員を務めた。彼は1958年に、プリンスト
ン大学から最優秀の成績で学士号を受けた。彼はオックスフォード大学でローズ奨学金
を得て大学院で仕事をし、ハーバード大学から政治科学博士号を得た。ナイ博士はまた
、ジュネーブ、オタワ、ロンドンで短期間の教鞭をとり、ヨーロッパ、東アフリカ、中
央アメリカで長期滞在をしてきた。彼は多数の書籍の著者であり、それには『権力の将
来』(The Future of Power、公共問題、2011年)、『指導すべき権力』(The Power t
o Lead、オックスフォード大学出版、2008年)、『ソフト・パワー:世界政治における
成功の方法』(Soft Power:The Means to Success in World Politics、公共問題、20
04年)が含まれる。
http://csis.org/files/publication/120810_Armitage_USJapanAlliance_Web.pdf
よろしければ、下のマークをクリックして!
よろしければ、もう一回!