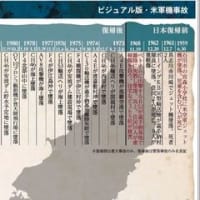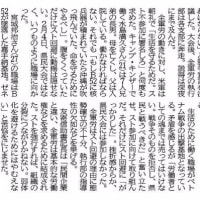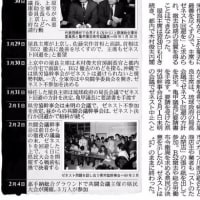グッドマン: 街頭の活動家と対比して、各国代表団、気候サミットに出席す
る人々についてはどうでしょう。10年前、シアトルの闘いでは興味深いことが
起こって、それも事態を変えたわけですが、内部から「われわれの話を聞いて
もらっていない」と言う陣営が出てきました。たとえば途上国、アフリカ諸国
ですね。そうした国々は今回はどうですか。そうした国々のコペンハーゲン気
候サミットでの役割は?
クライン: そうですね、もう少し見てみる必要があります。お話ししたよう
に、最も有望な解決策を交渉テーブルに乗せているのはボリビアやエクアドル
といった南アメリカ諸国の政府です。
でも、コペンハーゲンサミット前に交渉を進展させる最後の重要な場だったバ
ルセロナでは、アフリカ諸国の一団が大挙して議場を退席しました。これは要
するにサミット内部での市民的不服従の形で、先進国からの排出削減の約束が
極めて低調なことに抗議したものです。興味深いのは、アフリカ諸国の退席の
理由が、配分される資金の不足でも気候変動対策援助の不足でもないことです。
アフリカ諸国は単に援助を求めているのではなく、私たち金持ち国側が自分の
生活スタイルを変えることを求めています。彼らこそその影響に直面している
からです。彼らが気候変動の最前線に置かれているのです。
コペンハーゲンでもまたこのようなシーンを目にするかもしれないと思ってい
ます。でも、実はね、バルセロナでの議場退席でアフリカ諸国の交渉担当者は
かなり大きな政治的影響を被ったんです。本国政府によって解任された担当者
もいました。本国政府が米政府やEUから裏で圧力をかけられたからです。「交
渉担当者に勝手なことをさせるな」と。ですから、バルセロナでそういうこと
が起きたのは少し心配です。コペンハーゲンではそのときのような大胆さがア
フリカ諸国の担当者に見られなくなるかもしれない。とはいえもちろん公式に
は、交渉に満足がいかなければ退席すると彼らは言っています。
グッドマン: 『ブランドなんかいらない』の10周年記念版を新しく出され
ますね。副題は「ブランド支配をうつ」。シアトルで起きたこと、またこのブラ
ンド戦略問題全体の話をお願いします。
クライン: そうですね、出版社から新しい序文を書いて新版を出す気がある
かと聞かれたとき「ある」と言った理由は、今にふさわしいと思ったからです。
シアトルだけでなく、企業権力に反対する運動が世界中で爆発していた1999
年や2000年の政治運動から学ぶべきことがある気がします。この運動の、な
んというか、始まりをメキシコのサパティスタに見る人はたくさんいますが、
IMF(国際通貨基金)サミットやジェノバのG8サミットがあるたびに、活動
家たちが街頭に結集してこの経済モデルを問い直しました。
メディアからは「反グローバル化運動」と呼ばれましたが、私たちは、グロー
バル化に反対しているのではなく、企業支配に反対していることをいつもきわ
めて明確にしてきました。私たちが問うていたのは資本主義、WTOやIMFと
いった機関が推し進めていた、この野放しの「未開の西部」資本主義でした。
おもしろいことは、1999年のシアトルを振り返ってみてほしいのですが、私た
ちが企業支配をめぐるこうした議論を展開していたのは、景気の絶頂期、好景
気に沸く街ででした。シアトルは当時、シリコンバレーと並んでドットコムブ
ームの中心だった。ですから、その経済モデルを本当に進んで擁護する人たち
はたくさんいました。
そして10年経ち、政治的に本当に意味のある時期を迎えています。それで『ブ
ランドなんかいらない』をもう一度出して再構成したかったんです。私たちが
展開していた議論は……私たちは本当に過激派扱いされていましたから。『ニュ
ーヨークタイムズ』紙でトーマス・フリードマンに「地球が丸いという事実を
認めようとしない石頭」と呼ばれたのを忘れません。フリードマンが世界はフ
ラット化していると世に告げる本を書くよりも前でした。
私たちは「石頭」と呼ばれ、過激派と呼ばれました。でも今、企業と政府の間
にまったくの癒着、融合が存在し続けてきたという見方は政治的に完全に主流
になっています。乗っ取りに他ならない、という見方です。私たちが10年前
にこの経済モデルの失敗について展開していた議論は、今では主流です。
でも10年前に私たちもその一部だった広範な運動は、街頭から姿を消してし
まっています。たぶん大部分は米国の「オバマ効果」と関係があると思います。
米国ではみながまだ、最後にはオバマが救ってくれることを期待する、待ちの
姿勢にあります。
コペンハーゲンが特に米国の若い世代にとって転換点になりうるかもしれない、
と私が思う理由の一つは、ここにあります。たくさんの若者がオバマの選挙の
ために本当に懸命に働きました。若者たちを動かした大きな要因は、環境に対
する懸念、気候変動に対する懸念で、彼らは本当にオバマを、これまでとは違
う選択肢とみていました。
ある時点で何が政治的に実現可能かを議論することができる問題というのはた
くさんあります。でも気候変動となると、多くの若者がそう感じていると思い
ますが、本当に交渉の余地はない。ビル・マッキベン[350.orgを主宰する環境
ジャーナリスト]が明言してきたことですが、科学を相手に交渉はできません。
ハリー・リード[民主党上院多数派院内総務]の予定表のようにはいかないので
す。
オバマの選挙で働いた若者とコペンハーゲンへの準備過程から見えてくること
のひとつは、若者たちが単に民主党の先兵であることをやめて問題の原点にも
どりつつあるということです。今月、NGOの350.orgが組織した行動で刺激的
だったことのひとつはそれだと思います。失礼、先月でした。350[ppm]という
科学的な目標の数字に狙いを絞った運動で、ジョン・ケリーが書いたことに焦
点を絞るのとは正反対です。ジョン・ケリーは何週間か前に記事を書いて、自
分の法案が上院を通過するよう若者たちに動員を呼びかけました。でも問題は、
ケリーが上院を通そうとしていた法案は、現在の環境危機に対応できるもので
はないということです。若者たちは問題にもどりつつあり、10年前シアトルの
私たちのように、どれか一つの政党やその要求ではなく、問題そのものに焦点
をあてています。
グッドマン: 『ブランドなんかいらない』10周年記念版の序文のはじめに書
かれているある種のブランド化について、ブランド戦略がどう変わってきたか
についてお願いします。具体的に。
クライン: そうですね、ブランド戦略は反対意見を吸収することに長けてい
るんです。「ブランドなんかいらな」くした企業の例をいくつか挙げました。た
とえばウォッカのアブソリュートは、ラベルもロゴも瓶から取りました。スタ
ーバックスはなんとシアトルで、ブランド名のまったくない店を開きました。
ブランドに姿を消させようとしているわけです。企業ブランド戦略はこんなふ
うに変わってきています。
でも焦点を当てようと決めたのは、企業――企業戦略の最新機軸やテクニック
――ではなく、むしろ政治家が、というか政府が、超一流ブランドを作り上げ
売り込むために、90年代に企業によって磨きをかけられたテクニックをいかに
吸収してきたかということです。今ではこうしたテクニックは、政党、という
より政治家によって自分を売り込むために使われています。
残念ながらオバマはこれに当てはまるのではないかと思います。オバマは、私
が『ブランドなんかいらない』で取り上げた企業の多くと似た超一流ブランド
です。『ブランドなんかいらない』で取り上げた、ナイキやアップル――スター
バックスも――など、こうしたすべての企業と同じ問題の多くが彼にもありま
す。こうしたすべての、1990年代のライフスタイルブランドは、公民権運動、
女性運動といった変化をもたらす政治運動のモチーフの多くを吸収しました。
これが1990年代のブランド戦略の特徴でした。
このひとつは……私が『ブランドなんかいらない』で書いたことの大部分は、
こうした政治的運動がマーケティングの世界に取り込まれたことです。ウィ
ル・アイ・アムが作った「イエス・ウィ・キャン」のミュージックビデオを初
めて見たとき、私が最初に思ったことは「うわ、政治家がとうとうナイキに負
けない広告を作った。今より理想主義的だった時代の色褪せた記憶につけこみ、
でも本当は大したことを何も言わないものを」。私たちは自分が聞きたいと思っ
ているメッセージを聞いている気がしていますが、本当によく分析してみると、
そこには約束はなく、あるのは実は感情です。
そしてある意味では、それで米国の進歩派運動の停滞が説明できると思います。
米国で私たちはオバマが何らかの立場に立っていると考える。いろいろな問題
について私たちの感情がかき立てられたからです。でも本当はオバマに守らせ
るべきことはあまりない。実は選挙キャンペーンの間にオバマが言ったことを
見ると、どの超一流ブランドでもそうであるように、どの優れたマーケティン
グでもそうであるように、約束をたくさんしすぎないようにしています。守れ
なくならないように。
アフガニスタンは絶好例です。オバマが選挙公約をやぶっていると主張するの
は難しい。選挙キャンペーンの間に言っていたことをやっているだけですから。
たとえ、平和運動のモチーフ、イメージを利用して、自分は和平派の候補者だ
と私たちに思わせたとしても。労働問題でも同じことです。「イエス・ウィ・キ
ャン」、[スペイン語で]「スィ・セ・プエデ」。これは農場労働者のイメージ、
農場労働者のスローガンですよね。オバマのあの有名なポスター、あれだって
チェ・ゲバラのポスターのように見えますが、でも真の社会運動ではありませ
ん。変化をもたらす要求をしたことは一度もないのですから。
そしてそれこそが社会運動がするべきことです。基本にもどること。コペンハ
ーゲンではそれを目にするはずです。
グッドマン: ナオミ・クラインでした。お話ありがとうございました。『ショ
ックドクトリン』の著者で、最新作は『ブランドなんかいらない』の新版です。
---------------------------------------------------------------------------
原文(放映画像と書き起こし): "Naomi Klein on Climate Debt: Why Rich Countries
Should Pay Reparations To Poor Countries For The Climate Crisis"
Monday, November 23, 2009 by Democracy Now!
URI: http://www.democracynow.org/2009/11/23/naomi_klein_on_climate_debt_why
---------------------------------------------------------------------------
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
TUP速報
配信担当 古藤加奈
電子メール: TUP-Bulletin-owner@yahoogroups.jp
TUP速報の申し込みは:
http://groups.yahoo.co.jp/group/TUP-Bulletin/
ナオミ・クライン:「環境債務」気候変動について先進国が途上国に補償をするべき理由(1)
よろしければ、下のマークをクリックして!

る人々についてはどうでしょう。10年前、シアトルの闘いでは興味深いことが
起こって、それも事態を変えたわけですが、内部から「われわれの話を聞いて
もらっていない」と言う陣営が出てきました。たとえば途上国、アフリカ諸国
ですね。そうした国々は今回はどうですか。そうした国々のコペンハーゲン気
候サミットでの役割は?
クライン: そうですね、もう少し見てみる必要があります。お話ししたよう
に、最も有望な解決策を交渉テーブルに乗せているのはボリビアやエクアドル
といった南アメリカ諸国の政府です。
でも、コペンハーゲンサミット前に交渉を進展させる最後の重要な場だったバ
ルセロナでは、アフリカ諸国の一団が大挙して議場を退席しました。これは要
するにサミット内部での市民的不服従の形で、先進国からの排出削減の約束が
極めて低調なことに抗議したものです。興味深いのは、アフリカ諸国の退席の
理由が、配分される資金の不足でも気候変動対策援助の不足でもないことです。
アフリカ諸国は単に援助を求めているのではなく、私たち金持ち国側が自分の
生活スタイルを変えることを求めています。彼らこそその影響に直面している
からです。彼らが気候変動の最前線に置かれているのです。
コペンハーゲンでもまたこのようなシーンを目にするかもしれないと思ってい
ます。でも、実はね、バルセロナでの議場退席でアフリカ諸国の交渉担当者は
かなり大きな政治的影響を被ったんです。本国政府によって解任された担当者
もいました。本国政府が米政府やEUから裏で圧力をかけられたからです。「交
渉担当者に勝手なことをさせるな」と。ですから、バルセロナでそういうこと
が起きたのは少し心配です。コペンハーゲンではそのときのような大胆さがア
フリカ諸国の担当者に見られなくなるかもしれない。とはいえもちろん公式に
は、交渉に満足がいかなければ退席すると彼らは言っています。
グッドマン: 『ブランドなんかいらない』の10周年記念版を新しく出され
ますね。副題は「ブランド支配をうつ」。シアトルで起きたこと、またこのブラ
ンド戦略問題全体の話をお願いします。
クライン: そうですね、出版社から新しい序文を書いて新版を出す気がある
かと聞かれたとき「ある」と言った理由は、今にふさわしいと思ったからです。
シアトルだけでなく、企業権力に反対する運動が世界中で爆発していた1999
年や2000年の政治運動から学ぶべきことがある気がします。この運動の、な
んというか、始まりをメキシコのサパティスタに見る人はたくさんいますが、
IMF(国際通貨基金)サミットやジェノバのG8サミットがあるたびに、活動
家たちが街頭に結集してこの経済モデルを問い直しました。
メディアからは「反グローバル化運動」と呼ばれましたが、私たちは、グロー
バル化に反対しているのではなく、企業支配に反対していることをいつもきわ
めて明確にしてきました。私たちが問うていたのは資本主義、WTOやIMFと
いった機関が推し進めていた、この野放しの「未開の西部」資本主義でした。
おもしろいことは、1999年のシアトルを振り返ってみてほしいのですが、私た
ちが企業支配をめぐるこうした議論を展開していたのは、景気の絶頂期、好景
気に沸く街ででした。シアトルは当時、シリコンバレーと並んでドットコムブ
ームの中心だった。ですから、その経済モデルを本当に進んで擁護する人たち
はたくさんいました。
そして10年経ち、政治的に本当に意味のある時期を迎えています。それで『ブ
ランドなんかいらない』をもう一度出して再構成したかったんです。私たちが
展開していた議論は……私たちは本当に過激派扱いされていましたから。『ニュ
ーヨークタイムズ』紙でトーマス・フリードマンに「地球が丸いという事実を
認めようとしない石頭」と呼ばれたのを忘れません。フリードマンが世界はフ
ラット化していると世に告げる本を書くよりも前でした。
私たちは「石頭」と呼ばれ、過激派と呼ばれました。でも今、企業と政府の間
にまったくの癒着、融合が存在し続けてきたという見方は政治的に完全に主流
になっています。乗っ取りに他ならない、という見方です。私たちが10年前
にこの経済モデルの失敗について展開していた議論は、今では主流です。
でも10年前に私たちもその一部だった広範な運動は、街頭から姿を消してし
まっています。たぶん大部分は米国の「オバマ効果」と関係があると思います。
米国ではみながまだ、最後にはオバマが救ってくれることを期待する、待ちの
姿勢にあります。
コペンハーゲンが特に米国の若い世代にとって転換点になりうるかもしれない、
と私が思う理由の一つは、ここにあります。たくさんの若者がオバマの選挙の
ために本当に懸命に働きました。若者たちを動かした大きな要因は、環境に対
する懸念、気候変動に対する懸念で、彼らは本当にオバマを、これまでとは違
う選択肢とみていました。
ある時点で何が政治的に実現可能かを議論することができる問題というのはた
くさんあります。でも気候変動となると、多くの若者がそう感じていると思い
ますが、本当に交渉の余地はない。ビル・マッキベン[350.orgを主宰する環境
ジャーナリスト]が明言してきたことですが、科学を相手に交渉はできません。
ハリー・リード[民主党上院多数派院内総務]の予定表のようにはいかないので
す。
オバマの選挙で働いた若者とコペンハーゲンへの準備過程から見えてくること
のひとつは、若者たちが単に民主党の先兵であることをやめて問題の原点にも
どりつつあるということです。今月、NGOの350.orgが組織した行動で刺激的
だったことのひとつはそれだと思います。失礼、先月でした。350[ppm]という
科学的な目標の数字に狙いを絞った運動で、ジョン・ケリーが書いたことに焦
点を絞るのとは正反対です。ジョン・ケリーは何週間か前に記事を書いて、自
分の法案が上院を通過するよう若者たちに動員を呼びかけました。でも問題は、
ケリーが上院を通そうとしていた法案は、現在の環境危機に対応できるもので
はないということです。若者たちは問題にもどりつつあり、10年前シアトルの
私たちのように、どれか一つの政党やその要求ではなく、問題そのものに焦点
をあてています。
グッドマン: 『ブランドなんかいらない』10周年記念版の序文のはじめに書
かれているある種のブランド化について、ブランド戦略がどう変わってきたか
についてお願いします。具体的に。
クライン: そうですね、ブランド戦略は反対意見を吸収することに長けてい
るんです。「ブランドなんかいらな」くした企業の例をいくつか挙げました。た
とえばウォッカのアブソリュートは、ラベルもロゴも瓶から取りました。スタ
ーバックスはなんとシアトルで、ブランド名のまったくない店を開きました。
ブランドに姿を消させようとしているわけです。企業ブランド戦略はこんなふ
うに変わってきています。
でも焦点を当てようと決めたのは、企業――企業戦略の最新機軸やテクニック
――ではなく、むしろ政治家が、というか政府が、超一流ブランドを作り上げ
売り込むために、90年代に企業によって磨きをかけられたテクニックをいかに
吸収してきたかということです。今ではこうしたテクニックは、政党、という
より政治家によって自分を売り込むために使われています。
残念ながらオバマはこれに当てはまるのではないかと思います。オバマは、私
が『ブランドなんかいらない』で取り上げた企業の多くと似た超一流ブランド
です。『ブランドなんかいらない』で取り上げた、ナイキやアップル――スター
バックスも――など、こうしたすべての企業と同じ問題の多くが彼にもありま
す。こうしたすべての、1990年代のライフスタイルブランドは、公民権運動、
女性運動といった変化をもたらす政治運動のモチーフの多くを吸収しました。
これが1990年代のブランド戦略の特徴でした。
このひとつは……私が『ブランドなんかいらない』で書いたことの大部分は、
こうした政治的運動がマーケティングの世界に取り込まれたことです。ウィ
ル・アイ・アムが作った「イエス・ウィ・キャン」のミュージックビデオを初
めて見たとき、私が最初に思ったことは「うわ、政治家がとうとうナイキに負
けない広告を作った。今より理想主義的だった時代の色褪せた記憶につけこみ、
でも本当は大したことを何も言わないものを」。私たちは自分が聞きたいと思っ
ているメッセージを聞いている気がしていますが、本当によく分析してみると、
そこには約束はなく、あるのは実は感情です。
そしてある意味では、それで米国の進歩派運動の停滞が説明できると思います。
米国で私たちはオバマが何らかの立場に立っていると考える。いろいろな問題
について私たちの感情がかき立てられたからです。でも本当はオバマに守らせ
るべきことはあまりない。実は選挙キャンペーンの間にオバマが言ったことを
見ると、どの超一流ブランドでもそうであるように、どの優れたマーケティン
グでもそうであるように、約束をたくさんしすぎないようにしています。守れ
なくならないように。
アフガニスタンは絶好例です。オバマが選挙公約をやぶっていると主張するの
は難しい。選挙キャンペーンの間に言っていたことをやっているだけですから。
たとえ、平和運動のモチーフ、イメージを利用して、自分は和平派の候補者だ
と私たちに思わせたとしても。労働問題でも同じことです。「イエス・ウィ・キ
ャン」、[スペイン語で]「スィ・セ・プエデ」。これは農場労働者のイメージ、
農場労働者のスローガンですよね。オバマのあの有名なポスター、あれだって
チェ・ゲバラのポスターのように見えますが、でも真の社会運動ではありませ
ん。変化をもたらす要求をしたことは一度もないのですから。
そしてそれこそが社会運動がするべきことです。基本にもどること。コペンハ
ーゲンではそれを目にするはずです。
グッドマン: ナオミ・クラインでした。お話ありがとうございました。『ショ
ックドクトリン』の著者で、最新作は『ブランドなんかいらない』の新版です。
---------------------------------------------------------------------------
原文(放映画像と書き起こし): "Naomi Klein on Climate Debt: Why Rich Countries
Should Pay Reparations To Poor Countries For The Climate Crisis"
Monday, November 23, 2009 by Democracy Now!
URI: http://www.democracynow.org/2009/11/23/naomi_klein_on_climate_debt_why
---------------------------------------------------------------------------
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
TUP速報
配信担当 古藤加奈
電子メール: TUP-Bulletin-owner@yahoogroups.jp
TUP速報の申し込みは:
http://groups.yahoo.co.jp/group/TUP-Bulletin/
ナオミ・クライン:「環境債務」気候変動について先進国が途上国に補償をするべき理由(1)
よろしければ、下のマークをクリックして!