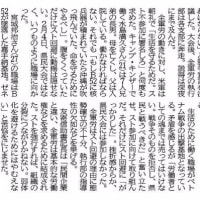12月1日の夕方、とあるテレビ局のディレクターから電話が入った。その局のワイドショーの担当ディレクターだと名乗り、広島安芸区での少女殺害事件の取材を進めているという。関心はもっぱら、その前日に容疑者として逮捕された日系ペルー人の周辺事情にあるようだった。
あふれかえる「事実」が、犯罪への想像力を奪う事件報道
『派兵チェック』第159号(2005年12月15日発行)掲載
太田昌国
「なぜ5万5千人ものペルー人が日本へ出稼ぎに来ているのでしょう?」「南米の国では、ペルーが一番早く日本と国交を結んだらしいのですが、そのことと関係があるのでしょうか?」「ペルーでは、平均月収が2万円程度だというのは本当ですか?」
どんなジャーナリストにも、不得手の分野はあるだろうし、何を聞かれても構わないというくらいの心構えはあるが、20歳代だろう、若い声のそのディレクターは、本当に信じられないといった調子の声で、いくつかの質問を畳み掛けるかのように連発した。
それらの質問には簡潔に答えた。明日の放映に間に合わせたいので、これからでも取材に来たいという。
用事があって、今夜は無理だというと、翌朝早朝に事務所に来たいという。コメンテーターの「人選」にだけは慎重なテレビ局にしては、ずいぶんと無警戒なことだなと思う一方、そのワイドショーは見たことはないが、今はなき『噂の真相』誌によく出ていた「噂」記事を思い起こし、当該のキャスターも主要なコメンテーターもろくな者ではないことくらいは覚えていて、警戒心がわく。
録画撮り映像を編集されるのはいやだ、一分間程度の時間しかないならそれでもいいから、一続きで話すこと全体を放映してほしいという条件を出した。ディレクターは納得し、翌朝取材を受けることにした。
早口ではない私が、努力して一分間に話すことのできる文字数は400字である。その夜、私は次のような趣旨のことを語る準備をした。
「貧しい国から産業先進国へ労働力が移動するのは世界的必然。とりわけラテンアメリカ諸国は、世界に先駆けて1970年代から80年代にかけて新自由主義政策の洗礼を浴びた。
世界経済を支配する米国や国際金融機関の指導の下で、社会的公正さに配慮することのない、市場経済一辺倒の政策が採られた。貧困のうちに放置された民衆は農村から都市へ、都市から先進国へ労働の場を求めて流浪した。
ちょうど、日本では、労働力不足に悩む雇用主から外国人労働力の雇用を認めるよう働きかけがあった。純血・血統主義の日本政府は、1990年、日系3世までの外国人を単純労働力として雇用することを認めた。
内外の条件が見合って外国から多数の人びとが殺到し、私たちといっしょに暮している。大事なことは、よく言われることとは違って、外国人が犯す凶悪犯罪は、人口対比から見ると、日本人が犯す犯罪に比して決して増えていないことを知ること。
外国人であることを理由に、それらの人びとを疎んじる社会にならないことだ」。
言い足りないことは、もちろん、たくさんある。日本がたどりつつある新自由主義的「構造改革」路線の行き着く先を、ラテンアメリカ諸国が悲劇的に示してきたことは、内橋克人・佐野誠編『ラテン・アメリカは警告する――「構造改革」日本の未来』(新評論、2005年)のように具体的に示すと、わかりやすい。外国人犯罪を問題にする場合に、世界最悪の「凶器(大量破壊兵器、と言ってもいい)準備集合罪」部隊である米軍の、5万1000人に及ぶ在日駐留兵士の犯罪に言及されることが少ないのはおかしい――こうして、問題はさまざまな方向に深めることができる。そのきっかけをつくることができればいいのだ。
私がコメントのおさらいをしていたその夜、容疑者は「自供」したらしい。「悪魔が自分のなかに入り、身体を動かした」。
気がつくと、少女は死んでおり、「少女について祈り続け、1日朝になって悪魔が抜けた」と語ったらしい。当該のディレクターが所属するテレビ局も、一夜明けてみると方針を変えたらしく、自供によって外国人労働者問題を扱う時間がなくなった、またの機会にしたいと言ってきた。
テレビ局の「人選」としては当然だろうと妙に「納得」したが、準備したコメントが日の目をみなかったのは残念だった。
容疑者が「悪魔」云々の「自供」を本当にしたとすれば、事件それ自体が悲惨であることは自明のこととして、犯罪をなすに至る人間の心理の問題としては、考えるべきことやその言葉から想像力が飛翔しうる世界は確実にあるように思える。
それは、まるで、コロンビアの作家、ガルシア=マルケスが、作家になる以前にジャーナリストとして、いわゆる「事件記者」時代に書いていたフィクションと見紛うばかりの新聞記事の世界を彷彿させる(ガルシア=マルケス著『幸福な無名時代』筑摩書房、同『ジャーナリズム作品集』現代企画室、いずれも1991年)。
だが、容疑者のこの「自供」をきっかけに、日本における事件報道は、いつもの道をたどった。
特派員はペルー現地に飛び、容疑者の生地にまで行って、家族・親族・幼なじみ・友人・役場・警察などの取材に明け暮れている。
容疑者のかつての「性犯罪歴」がだれ彼の口を通して語られる。事件報道は、ひたすら、猟奇的な側面において、受け手の人びとの興味を引きつけようとしているかに思える。
あふれかえる「事実」が、犯罪に対する想像力を私たちから奪いとり、問題の本質から私たちを遠ざけようとしている。事件が悲劇的なものであることは言うをまたないが、ニη
あふれかえる「事実」が、犯罪への想像力を奪う事件報道
『派兵チェック』第159号(2005年12月15日発行)掲載
太田昌国
「なぜ5万5千人ものペルー人が日本へ出稼ぎに来ているのでしょう?」「南米の国では、ペルーが一番早く日本と国交を結んだらしいのですが、そのことと関係があるのでしょうか?」「ペルーでは、平均月収が2万円程度だというのは本当ですか?」
どんなジャーナリストにも、不得手の分野はあるだろうし、何を聞かれても構わないというくらいの心構えはあるが、20歳代だろう、若い声のそのディレクターは、本当に信じられないといった調子の声で、いくつかの質問を畳み掛けるかのように連発した。
それらの質問には簡潔に答えた。明日の放映に間に合わせたいので、これからでも取材に来たいという。
用事があって、今夜は無理だというと、翌朝早朝に事務所に来たいという。コメンテーターの「人選」にだけは慎重なテレビ局にしては、ずいぶんと無警戒なことだなと思う一方、そのワイドショーは見たことはないが、今はなき『噂の真相』誌によく出ていた「噂」記事を思い起こし、当該のキャスターも主要なコメンテーターもろくな者ではないことくらいは覚えていて、警戒心がわく。
録画撮り映像を編集されるのはいやだ、一分間程度の時間しかないならそれでもいいから、一続きで話すこと全体を放映してほしいという条件を出した。ディレクターは納得し、翌朝取材を受けることにした。
早口ではない私が、努力して一分間に話すことのできる文字数は400字である。その夜、私は次のような趣旨のことを語る準備をした。
「貧しい国から産業先進国へ労働力が移動するのは世界的必然。とりわけラテンアメリカ諸国は、世界に先駆けて1970年代から80年代にかけて新自由主義政策の洗礼を浴びた。
世界経済を支配する米国や国際金融機関の指導の下で、社会的公正さに配慮することのない、市場経済一辺倒の政策が採られた。貧困のうちに放置された民衆は農村から都市へ、都市から先進国へ労働の場を求めて流浪した。
ちょうど、日本では、労働力不足に悩む雇用主から外国人労働力の雇用を認めるよう働きかけがあった。純血・血統主義の日本政府は、1990年、日系3世までの外国人を単純労働力として雇用することを認めた。
内外の条件が見合って外国から多数の人びとが殺到し、私たちといっしょに暮している。大事なことは、よく言われることとは違って、外国人が犯す凶悪犯罪は、人口対比から見ると、日本人が犯す犯罪に比して決して増えていないことを知ること。
外国人であることを理由に、それらの人びとを疎んじる社会にならないことだ」。
言い足りないことは、もちろん、たくさんある。日本がたどりつつある新自由主義的「構造改革」路線の行き着く先を、ラテンアメリカ諸国が悲劇的に示してきたことは、内橋克人・佐野誠編『ラテン・アメリカは警告する――「構造改革」日本の未来』(新評論、2005年)のように具体的に示すと、わかりやすい。外国人犯罪を問題にする場合に、世界最悪の「凶器(大量破壊兵器、と言ってもいい)準備集合罪」部隊である米軍の、5万1000人に及ぶ在日駐留兵士の犯罪に言及されることが少ないのはおかしい――こうして、問題はさまざまな方向に深めることができる。そのきっかけをつくることができればいいのだ。
私がコメントのおさらいをしていたその夜、容疑者は「自供」したらしい。「悪魔が自分のなかに入り、身体を動かした」。
気がつくと、少女は死んでおり、「少女について祈り続け、1日朝になって悪魔が抜けた」と語ったらしい。当該のディレクターが所属するテレビ局も、一夜明けてみると方針を変えたらしく、自供によって外国人労働者問題を扱う時間がなくなった、またの機会にしたいと言ってきた。
テレビ局の「人選」としては当然だろうと妙に「納得」したが、準備したコメントが日の目をみなかったのは残念だった。
容疑者が「悪魔」云々の「自供」を本当にしたとすれば、事件それ自体が悲惨であることは自明のこととして、犯罪をなすに至る人間の心理の問題としては、考えるべきことやその言葉から想像力が飛翔しうる世界は確実にあるように思える。
それは、まるで、コロンビアの作家、ガルシア=マルケスが、作家になる以前にジャーナリストとして、いわゆる「事件記者」時代に書いていたフィクションと見紛うばかりの新聞記事の世界を彷彿させる(ガルシア=マルケス著『幸福な無名時代』筑摩書房、同『ジャーナリズム作品集』現代企画室、いずれも1991年)。
だが、容疑者のこの「自供」をきっかけに、日本における事件報道は、いつもの道をたどった。
特派員はペルー現地に飛び、容疑者の生地にまで行って、家族・親族・幼なじみ・友人・役場・警察などの取材に明け暮れている。
容疑者のかつての「性犯罪歴」がだれ彼の口を通して語られる。事件報道は、ひたすら、猟奇的な側面において、受け手の人びとの興味を引きつけようとしているかに思える。
あふれかえる「事実」が、犯罪に対する想像力を私たちから奪いとり、問題の本質から私たちを遠ざけようとしている。事件が悲劇的なものであることは言うをまたないが、ニη