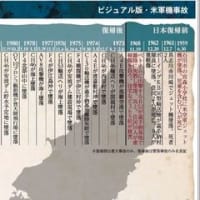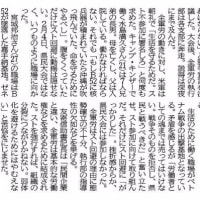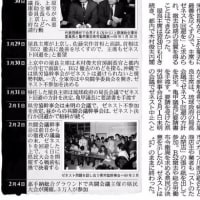小沢一郎信者のブロガー諸氏へ。とりわけ 元リベラルだった信者の皆さん
小沢側近というだけで 森ゆうこ(文科副大臣)を絶賛していた あなたがたも共犯なのだよ。
--------------------
つくる会系育鵬社教科書の採択検討求める 文科省、沖縄に通知/朝日新聞
沖縄県八重山地区(石垣市、与那国町、竹富町)の中学校の公民教科書採択問題で、文部科学省は15日、県教委に通知を出し、3市町で同じ教科書を採択するよう指導することを求めた。事実上、8月に地区協議会が選定した育鵬社版を中心に検討するよう求めたものだ。来春使用する教科書の報告期限である16日までの報告を求めている。
教科書選びをめぐって地区内の市町が対立する混乱は、文科省が指導に乗り出す異例の事態に発展した。
八重山地区では、3市町の教育長や教育委員各1人ら8人でつくる協議会が8月23日、「新しい歴史教科書をつくる会」の元会長らが執筆した育鵬社版を選んだが、竹富町教委は選定の方法に問題があるとして育鵬社版を不採択とした。
今月8日には、協議会メンバー以外も含む3市町の教育委員全13人が集まり再協議。育鵬社版の採択撤回と東京書籍版の採択を多数決で決めた。すると今度は石垣、与那国の両教育長が反発。混迷が続いていた。
通知は「地区協議会の規約に従ってまとめられた結果に基づいて採択を」と指示している。文科省教科書課は「特定の教科書の採択を求めたものではない」と説明するが、森ゆうこ文科副大臣は15日の記者会見で「現時点で正式に決定された答申は(育鵬社版を採択した)一つだ。それに基づいて採択するように努力していただきたい」と述べた。
■教科書制度の矛盾が表面化
今回の混乱は、教科書制度がもともと抱えていた矛盾が表面化したものだ。
教科書の無償配布や採択方法を定めた教科書無償措置法(1963年施行)は、採択地区内の市区町村は同じ教科書を使うと定めている。文部科学省はその趣旨を(1)小規模自治体の事務作業の効率化(2)情報集約や配布に関する国、教科書会社の負担軽減(3)近隣市町村に転校しても同じ教科書を使える、と説明する。つまりは効率化の観点だ。
一方、教育委員会制度などについて定めた地方教育行政法は、教科書採択を市町村教委の権限と定める。「採択は各市町村教委が行うが、地区内で同一の教科書を採択するよう条件付けられている」というのが文科省教科書課の見解。協議会と各教委の判断が分かれる事態は「想定していなかった」と繰り返す。
だが、採択地区協議会と市町村教委の間で採択が揺れたケースは過去にもあった。2001年に栃木県の下都賀地区教科書採択協議会が、「新しい歴史教科書をつくる会」主導による扶桑社版中学歴史教科書の採択方針をいったん決めたが、参加する全10市町の反発を受けて撤回。05年には茨城県大洗町教委が独自に扶桑社版の教科書を採択しようとしたが、「法律に抵触する可能性がある」として、地区協議会の決定に従うよう方針転換した。
この2例では結局いずれも地区内で教科書が一本化されたため、文科省は二つの法の矛盾点を放置してきた。だが今回は竹富町が別の教科書を採択する方針を変えておらず、このままだと地区全体として無償措置法に反する状態となる。文科省は15日、やっと今後の採択制度のあり方を検討することを明らかにした。
今後も一つの教科書にまとまらない場合、八重山地区は教科書無償配布の対象から外れるのか。担当者は「前例がないので法解釈を詰めないといけない。同じ教科書を採択してもらうようお願いするしかない」と言葉を濁した。(井上裕一)
■深まる亀裂、地元は困惑
「文科省から通知で求められたような指導は、これまでもやってきた。それで一本化できないから問題になっているのに」。沖縄県教委義務教育課の担当者は困惑した様子で話した。
沖縄県では、大城浩教育長が16日午後に記者会見する予定だが、育鵬社版の採択を求める石垣市・与那国町の教育長と、不採択とした竹富町教育委員会の亀裂は深く、一本化のめどは立たない。「教育委員13人が集まった8日の臨時総会で、育鵬社は不採択にすると決着したはず。納得いかない」と、竹富町教委の担当者は危機感を募らせる。
八重山地区の教育委員長3人は、育鵬社版の「不採択」に同意している。「石垣市と与那国町の教育長2人の異議は、市や町の意思とは言えない」と、育鵬社版の採択に反対してきた「子どもと教科書を考える八重山地区住民の会」の大浜敏夫事務局長は言う。「文科省は、これまで具体的な指導を何もしなかったくせに、今になって竹富町に圧力をかけるとは。あまりに傲慢(ごうまん)だ」
おきなわ教育支援ネットワークの中村英吉事務局長は、もし国や県が育鵬社版の採択を竹富町に強要すれば、「第2の教科書問題になる」と警告する。2007年9月、高校教科書での沖縄戦の集団自決の記述をめぐり、検定意見の撤回を求める超党派の県民大会があり、11万人が集まった。
「問題は『育鵬社ありき』で採択地区協議会を運営した石垣市教育長にある。そんなやり方にお墨付きを与えるなら、八重山地区だけの問題ではおさまらない。沖縄全体の問題だ」
なぜ、ここまで混乱したのか。教科書問題に詳しい高嶋伸欣琉球大名誉教授は「教科書調査員が推薦していない教科書が協議会で選ばれるなど採択手続きに問題があった。また、二つの法律で採択主体の位置づけが違い、矛盾している状態を、文科省が放置してきた責任もある」と話す。
石垣市と与那国町が教科書無償措置法の定める協議会を事実上の決定の場としているのに対し、竹富町は、地方教育行政法上の教科書の採択主体は教育委員会だとする文科省の長年の解釈を根拠にして対抗。抜き差しならない対立に陥った。
「協議会と教育委員会の採択が食い違った際のルールづくりを文科省が怠ってきたツケが回ってきた」(谷津憲郎、宮崎健二)
*2011.9.16朝刊
----------------------
八重山の教科書採択 文科省認めず/朝日新聞
沖縄県の八重山地区の教科書採択問題が混迷の度を増している。中学公民での「つくる会」系・育鵬社版の採択を多数決で撤回した石垣、与那国、竹富の3市町の臨時総会について、中川正春文部科学相は13日、「協議は整っていないと考えざるをえない」と発言。ボールを投げ返された地元・沖縄は困惑している。
東京の自民党本部では、教科書採択問題をテーマとして文部科学部会が開かれた。文科省の担当者や狩俣智・県義務教育課長、玉津博克・石垣市教育長らが出席。文科省の担当者は、撤回の決定について「石垣市と与那国町から教育長名で『協議は無効』との文書が届いている。両市町の合意がなく、協議が成立しているとは言えない」と説明。「これまでは県教委の自主性に任せていたが、今の状態を是正するためどんな指導や助言ができるか検討している」と述べた。
8日の臨時総会には、3市町の全教育委員13人が集まった。議長役をつとめた竹盛洋一・竹富町教育委員長は「協議が整っていないと言われても、あれ以外に解決策はない」と憤る。
総会には狩俣課長も立ち会い、「教育委員13人がそろっており、最も民主的な会合だ」「皆さんには一本化にむけて話し合う義務がある」と促していた。
だが石垣市の玉津教育長は「育鵬社の採択という結論を変えるつもりはない」とし、「多数決には従わない」とも発言。同調する与那国町の崎原用能教育長と途中で退席してしまった。
竹盛委員長は「一本化には多数決で決めるしかなかった。やれるだけのことはやったつもりだ」。
12日に文科省を訪れ、総会での決定に「お墨付き」を得ようと考えていた県も「ボールが戻ってきてしまった」と頭を抱える。
育鵬社版の採択に反対してきた八重山地区PTA連合会の平良守弘会長は「教科書の中身についてほとんど議論されてこなかった。文科省が8日の決定を無効とするなら、中身のよしあしを議論して教科書を決めてほしい」と話した。
http://mytown.asahi.com/okinawa/news.php?k_id=48000001109140001
----------------------------------
沖縄タイムス「八重山教科書:3教育委員長「協議有効」」
http://www.okinawatimes.co.jp/article/2011-09-16_23486/
沖縄タイムス「八重山教科書:文科省、教科書一本化指導」
http://www.okinawatimes.co.jp/article/2011-09-16_23485/
琉球新報「「つくる会」系の採択指導 文科省、県教委に通 知」
http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-181718-storytopic-238.html
琉球新報「全員協議は「有効」 八重山教科書問題」
http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-181734-storytopic-7.html
よろしければ、下のマークをクリックして!

よろしければ、もう一回!

小沢側近というだけで 森ゆうこ(文科副大臣)を絶賛していた あなたがたも共犯なのだよ。
--------------------
つくる会系育鵬社教科書の採択検討求める 文科省、沖縄に通知/朝日新聞
沖縄県八重山地区(石垣市、与那国町、竹富町)の中学校の公民教科書採択問題で、文部科学省は15日、県教委に通知を出し、3市町で同じ教科書を採択するよう指導することを求めた。事実上、8月に地区協議会が選定した育鵬社版を中心に検討するよう求めたものだ。来春使用する教科書の報告期限である16日までの報告を求めている。
教科書選びをめぐって地区内の市町が対立する混乱は、文科省が指導に乗り出す異例の事態に発展した。
八重山地区では、3市町の教育長や教育委員各1人ら8人でつくる協議会が8月23日、「新しい歴史教科書をつくる会」の元会長らが執筆した育鵬社版を選んだが、竹富町教委は選定の方法に問題があるとして育鵬社版を不採択とした。
今月8日には、協議会メンバー以外も含む3市町の教育委員全13人が集まり再協議。育鵬社版の採択撤回と東京書籍版の採択を多数決で決めた。すると今度は石垣、与那国の両教育長が反発。混迷が続いていた。
通知は「地区協議会の規約に従ってまとめられた結果に基づいて採択を」と指示している。文科省教科書課は「特定の教科書の採択を求めたものではない」と説明するが、森ゆうこ文科副大臣は15日の記者会見で「現時点で正式に決定された答申は(育鵬社版を採択した)一つだ。それに基づいて採択するように努力していただきたい」と述べた。
■教科書制度の矛盾が表面化
今回の混乱は、教科書制度がもともと抱えていた矛盾が表面化したものだ。
教科書の無償配布や採択方法を定めた教科書無償措置法(1963年施行)は、採択地区内の市区町村は同じ教科書を使うと定めている。文部科学省はその趣旨を(1)小規模自治体の事務作業の効率化(2)情報集約や配布に関する国、教科書会社の負担軽減(3)近隣市町村に転校しても同じ教科書を使える、と説明する。つまりは効率化の観点だ。
一方、教育委員会制度などについて定めた地方教育行政法は、教科書採択を市町村教委の権限と定める。「採択は各市町村教委が行うが、地区内で同一の教科書を採択するよう条件付けられている」というのが文科省教科書課の見解。協議会と各教委の判断が分かれる事態は「想定していなかった」と繰り返す。
だが、採択地区協議会と市町村教委の間で採択が揺れたケースは過去にもあった。2001年に栃木県の下都賀地区教科書採択協議会が、「新しい歴史教科書をつくる会」主導による扶桑社版中学歴史教科書の採択方針をいったん決めたが、参加する全10市町の反発を受けて撤回。05年には茨城県大洗町教委が独自に扶桑社版の教科書を採択しようとしたが、「法律に抵触する可能性がある」として、地区協議会の決定に従うよう方針転換した。
この2例では結局いずれも地区内で教科書が一本化されたため、文科省は二つの法の矛盾点を放置してきた。だが今回は竹富町が別の教科書を採択する方針を変えておらず、このままだと地区全体として無償措置法に反する状態となる。文科省は15日、やっと今後の採択制度のあり方を検討することを明らかにした。
今後も一つの教科書にまとまらない場合、八重山地区は教科書無償配布の対象から外れるのか。担当者は「前例がないので法解釈を詰めないといけない。同じ教科書を採択してもらうようお願いするしかない」と言葉を濁した。(井上裕一)
■深まる亀裂、地元は困惑
「文科省から通知で求められたような指導は、これまでもやってきた。それで一本化できないから問題になっているのに」。沖縄県教委義務教育課の担当者は困惑した様子で話した。
沖縄県では、大城浩教育長が16日午後に記者会見する予定だが、育鵬社版の採択を求める石垣市・与那国町の教育長と、不採択とした竹富町教育委員会の亀裂は深く、一本化のめどは立たない。「教育委員13人が集まった8日の臨時総会で、育鵬社は不採択にすると決着したはず。納得いかない」と、竹富町教委の担当者は危機感を募らせる。
八重山地区の教育委員長3人は、育鵬社版の「不採択」に同意している。「石垣市と与那国町の教育長2人の異議は、市や町の意思とは言えない」と、育鵬社版の採択に反対してきた「子どもと教科書を考える八重山地区住民の会」の大浜敏夫事務局長は言う。「文科省は、これまで具体的な指導を何もしなかったくせに、今になって竹富町に圧力をかけるとは。あまりに傲慢(ごうまん)だ」
おきなわ教育支援ネットワークの中村英吉事務局長は、もし国や県が育鵬社版の採択を竹富町に強要すれば、「第2の教科書問題になる」と警告する。2007年9月、高校教科書での沖縄戦の集団自決の記述をめぐり、検定意見の撤回を求める超党派の県民大会があり、11万人が集まった。
「問題は『育鵬社ありき』で採択地区協議会を運営した石垣市教育長にある。そんなやり方にお墨付きを与えるなら、八重山地区だけの問題ではおさまらない。沖縄全体の問題だ」
なぜ、ここまで混乱したのか。教科書問題に詳しい高嶋伸欣琉球大名誉教授は「教科書調査員が推薦していない教科書が協議会で選ばれるなど採択手続きに問題があった。また、二つの法律で採択主体の位置づけが違い、矛盾している状態を、文科省が放置してきた責任もある」と話す。
石垣市と与那国町が教科書無償措置法の定める協議会を事実上の決定の場としているのに対し、竹富町は、地方教育行政法上の教科書の採択主体は教育委員会だとする文科省の長年の解釈を根拠にして対抗。抜き差しならない対立に陥った。
「協議会と教育委員会の採択が食い違った際のルールづくりを文科省が怠ってきたツケが回ってきた」(谷津憲郎、宮崎健二)
*2011.9.16朝刊
----------------------
八重山の教科書採択 文科省認めず/朝日新聞
沖縄県の八重山地区の教科書採択問題が混迷の度を増している。中学公民での「つくる会」系・育鵬社版の採択を多数決で撤回した石垣、与那国、竹富の3市町の臨時総会について、中川正春文部科学相は13日、「協議は整っていないと考えざるをえない」と発言。ボールを投げ返された地元・沖縄は困惑している。
東京の自民党本部では、教科書採択問題をテーマとして文部科学部会が開かれた。文科省の担当者や狩俣智・県義務教育課長、玉津博克・石垣市教育長らが出席。文科省の担当者は、撤回の決定について「石垣市と与那国町から教育長名で『協議は無効』との文書が届いている。両市町の合意がなく、協議が成立しているとは言えない」と説明。「これまでは県教委の自主性に任せていたが、今の状態を是正するためどんな指導や助言ができるか検討している」と述べた。
8日の臨時総会には、3市町の全教育委員13人が集まった。議長役をつとめた竹盛洋一・竹富町教育委員長は「協議が整っていないと言われても、あれ以外に解決策はない」と憤る。
総会には狩俣課長も立ち会い、「教育委員13人がそろっており、最も民主的な会合だ」「皆さんには一本化にむけて話し合う義務がある」と促していた。
だが石垣市の玉津教育長は「育鵬社の採択という結論を変えるつもりはない」とし、「多数決には従わない」とも発言。同調する与那国町の崎原用能教育長と途中で退席してしまった。
竹盛委員長は「一本化には多数決で決めるしかなかった。やれるだけのことはやったつもりだ」。
12日に文科省を訪れ、総会での決定に「お墨付き」を得ようと考えていた県も「ボールが戻ってきてしまった」と頭を抱える。
育鵬社版の採択に反対してきた八重山地区PTA連合会の平良守弘会長は「教科書の中身についてほとんど議論されてこなかった。文科省が8日の決定を無効とするなら、中身のよしあしを議論して教科書を決めてほしい」と話した。
http://mytown.asahi.com/okinawa/news.php?k_id=48000001109140001
----------------------------------
沖縄タイムス「八重山教科書:3教育委員長「協議有効」」
http://www.okinawatimes.co.jp/article/2011-09-16_23486/
沖縄タイムス「八重山教科書:文科省、教科書一本化指導」
http://www.okinawatimes.co.jp/article/2011-09-16_23485/
琉球新報「「つくる会」系の採択指導 文科省、県教委に通 知」
http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-181718-storytopic-238.html
琉球新報「全員協議は「有効」 八重山教科書問題」
http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-181734-storytopic-7.html
よろしければ、下のマークをクリックして!
よろしければ、もう一回!