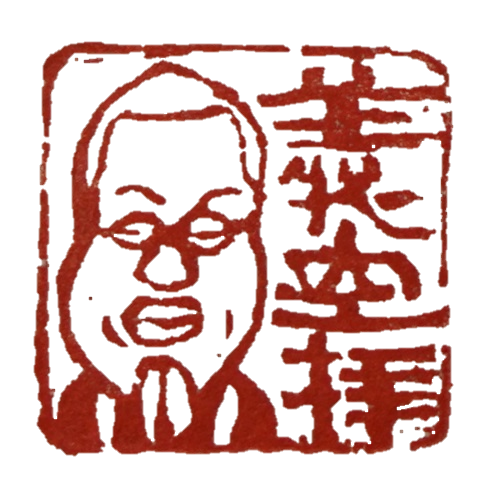5月は時候も爽やかなので檀務も何かと多用になっているけれど、合間には仏具を磨いたり寺務を進めたり元気に過ごしている。
さて、観賢さんの続きを。
お大師さまが高野山の廟窟に御入定されて身を留め、今なお衆生済度の慈悲行を行っておられることを一首の詩から察せられた醍醐天皇は深く感動し、御心を決められた。
その1週間後の延喜21年(921)10月27日、勅使少納言平惟助卿が高野山に登嶺して、お大師さまは「桧皮色の装束一式」と「弘法大師」の諡号を下賜された。その時に同席していた観賢さん、そして仁和寺の寛平法皇(宇多天皇)の感涙は計り知れない。嬉しかっただろうと想像される。
詔勅奉告の式が執行されたのち、時の真言長者・観賢さんは帝から賜った御衣をお大師さまに奉呈する為に弟子・淳祐(しゅんにゅう)と寛空と廟窟の扉を開いた。実にお大師さまの御入定から86年後の出来事だ。・淳祐…大本山・石山寺の第三代座主。

入定留身の御影(勝福寺蔵)
廟窟の内部は深い霧に包まれていたけれども、そこには帝が夢枕でご覧になられたお大師さまのお姿があった。ところが、弟子の淳祐にはその姿を拝することが出来なかったので、観賢さんは淳祐の手をとってお大師さまの御膝にそっと置かれたという。Gikoohはこの場面を想像する時、いつも身震いしそうになる。
その手には芳薫が移り生涯消えなかったという。その手で書写した聖経は「薫聖経」(国宝)と称され、代々の座主によって護り伝えられている。
観賢さん達は、お大師さまの長く伸びた御髪をお剃りして、御体を浄めて帝より賜った衣をお取り替えした。
『弘法大師物語』(朱鷺書房)には、この時の様子が以下のように書かれている。
大師の御廟より「われ昔、薩埵に遭い親しく悉く印明を伝う、無比の誓願を発して辺地異城に倍す、昼夜に万民を憐れんで普賢の悲願に住し、肉親に三昧を証して慈氏(弥勒)の下生を待つ」とのお声があったと伝えられている。
御廟でのお衣替えの行事が終り、観賢僧正と淳祐と寛空の二人のお供を連れて、玉川に架かる御廟橋まで歩を運ぶと、後から大師が三人を橋の上まで送ってくだされている御姿に気づいた。観賢僧正は恐懼して思わず「南無大師遍照金剛」の言葉をもって大師を礼拝された。大師はこれに答えられて、「われ汝の仏性を送るなり」と言われ、相互に合掌してお別れになったと伝えられている。
以来、大師を供養礼拝する真心の言葉として、「南無大師遍照金剛」は御宝号と呼ばれることとなり、御廟橋を渡り終えた所で、もう一度振り返って、大師と相互合掌して別れるという美しい習慣ができたのである。
真言宗では毎月21日のお大師さま御入定の御聖日を御影供といって、供養の法会を捧げることになっているけれども、3月21日の正当日は正御影供と称して特に大切にしている。
詔勅奉告の式の後、毎年3月21日には御衣替えの儀式が執行されるようになり、これが御影供の根源となっている。

久米寺


時代の移り変わりの中で、現在は境内が寂れていることに一抹の寂しさを感じるけれども、一方でGikoohが感銘を受けたのは、地元高松市立鶴雄小学校の田中義人校長先生をはじめ、学校の子ども達、そして有志の方々による「観賢さんを大切に思う気持ち」が強く感じられた。
そして「弘法大師」諡号奏請の背景には、観賢さんや寛平法皇(宇多天皇)の尽力によるところが大きく、所縁のある剃刀塚も国の宝として、後世に伝えられていくことを念じている。