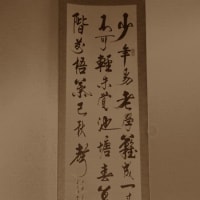今では、有機栽培野菜や無農薬米が市場に定着し、農薬を使わずに栽培した美味しい作物が産地直販で消費者へ届けられる。政府機関による農薬規制も以前より厳しくなり、2001年には果物王国山形県で起きた果樹に対する不法農薬問題がマスコミを大いに騒がせた。特に、家族を守るため食物の安全性に関心の深い主婦は、この15年で環境問題に敏感になった。
ここ数年、中共産の野菜、魚介が薬物汚染されていると指摘され、水際検閲でかなりの輸入が阻止されているが、我が国の食品流通システムはもっと輸入食品に敏感であるべきだ。それは、中共国内で頻発している公害問題にも警鐘を鳴らす事に繋がると思う。
日本では、高度成長期の最中に昭和34年(1959年)に水俣病(熊本)を始めとする産業公害が取り上げられ、昭和45年(1970年)前後には自動車排気ガスによる環境汚染及び騒音問題が話題となった。環境庁が総理府内に設置されたのもこの頃だ。しかし、神岡鉱山による富山県神通川下流域のカドミウム汚染米の指摘があっても、農薬問題全般への関心は更に時間が経たなければ深まらなかったのだ。
DDTやBHCあるいはドリン系農薬が我が国で使用禁止されたのは昭和46年(1971)、米国で禁止された内容に1年遅れて農水省は追従した。作家有吉佐和子女史が、それまでの作風と異なる形で朝日新聞に「複合汚染」を書き始めたのは、昭和49年(1974)10月である。彼女は当時43才で、作家として脂の乗り切った時であったし、時代の環境保全に対する流れを鋭く読んでいたと想像する。約8ヶ月の連載の後、これは単行本になった。
有吉さんは、農薬などの環境汚染について、「すでに専門家や先覚者が警告し、告発している事実を、私はより多くの人達に知って頂きたく思い、広報のお手伝いをした」と述べている。一般には目新しく映る学術用語の複合汚染を用い、大衆を引き付ける文学のテーマにしたわけだ。改めて「複合汚染」を読み返すと、それ自身が仲々立派な環境問題への警告書になっている。それは、化学分野に慣れていない有吉さんが300冊以上の関連書を読破し、一方で多くの専門家へのインタビューや現地取材を行って得た成果である。
この著作の中で、有吉さんはレイチェル・カーソン(Rachel Louise Carson、1907-1964)の「沈黙の春」(Silent Spring、1962年刊)を引用し、殺虫剤や除草剤の化学物質による環境汚染を広く紹介している。
「複合汚染」を読んだ当時の人達には、カーソンの「沈黙の春」の存在に大きな興味を持ったはずだ。カーソンの著作は、始め「生と死の妙薬」と言う些か変わった題名で、新潮社から青樹簗一氏による翻訳が出された(1964年)。これは、昭和49年(1974)に改題され、同じ訳者により「沈黙の春」の名で新潮文庫に採録されている。それでも、有吉さんの作品が公表された頃は、翻訳出版後既に10年を経過していたわけで、文庫版は別として日本語版「生と死の妙薬」の入手は当時仲々難しかった。
そうした状況の中で、「沈黙の春」が内包している大きな意味を有吉さんが始めて大衆に分りやすく紹介されたことになる。彼女は昭和59年(1984)に心不全のため54才で逝去されたが、もし生きておられたら、こだわりを持って生み出した作品「複合汚染」で指摘した内容が、今や国家・国民レベルで相当に意識され、人々の認識が変わっている状況を興味深く思われることだろう。
ところで、昭和62年(1987)にカーソンの生誕80周年を記念し、青樹簗一氏による翻訳が、新装版「沈黙の春」と改題されて新潮社から再版された。この著作は、原著出版後約40年を経過しているが、挿し絵や文献がきちんと示されている。上記のように新潮文庫に収められた著作も入手可能だから、どちらでも良い、是非若い人達に一読をお勧めする。
海洋生物学者で科学ジャーナリストであるカーソンが、月刊雑誌<ニューヨーカー>に一部を連載し、次いでその全体が記述された「沈黙の春」を出版した(当時55才)。彼女は、内務省米国魚類・野生生物局出版編集長を退職し、当時は生物と自然についての文筆活動に専念していた。すでに海洋生物分野の著作で、米国の中では名声を得ていたが、ガンに罹り病い重き身であった。執筆のため農薬被害の調査をしている段階でさえ、産業界などから様々な抵抗や妨害があったけれども、彼女は渾身の力を振り絞ってその出版をやり遂げたのである。
「沈黙の春」は、農薬(DDT,BHC、ドリン系などの有機塩素系殺虫剤、パラチオンなどのリン酸化合物)更には除草剤が環境や生物にどのように深刻な影響を与え、これらを汚染し、破壊するかの様相を科学的に検証し、それらの使用に際しては人々に情報公開されなければならない、と静かな筆致で著わした名著である。当然ながらこのタイプの本としては、世界で初めて登場したのであった。
カーソンの基本的な考えは、自然と人間の共生である。そして、内表紙にはカーソンが終生尊敬して止まなかったアルベルト・シュヴァイッツアーに献ぐと記されている。
出版された「沈黙の春」は、化学薬品会社や食品工業それに一部の政府機関から猛烈な攻撃を受けた。非科学的であると言う啓蒙雑誌からの非難も多かった。全米農薬化学工業連盟に至っては、米国全土に「沈黙の春」攻撃用のパンフレットをばらまいた。しかし、カーソンはそれらに負けなかったし、非難には誠実に討論で応じた。勿論、彼女を弁護する化学者も、学協会も多数現れた。カーソンへの投書数千通の内、彼女を支持するものは90%に達したと言う。「沈黙の春」は、発売以来たちまちの内に米国内で100万部を越えるベストセラーになり、また翻訳されて世界中の人々に読まれた。
このように騒がしかったその年の夏、J.F.ケネディ大統領は、科学諮問委員会に対し農薬問題の調査を命じた。翌年委員会としては、政府機関が一致してカーソンの指摘、すなわち農薬に関しては情報公開をすべきであるとの答申を行った。その後、議会では、リビコフ上院議員らにより環境汚染に関する公聴会も開かれ、世論の関心は益々高まって行ったのである。
出版後、2年経ってカーソンは惜しまれながらに逝去する(1964年)。ワシントン大聖堂で執り行われた告別式には、内務省長官自らや名士達が数多く参加した。そして、世界中から多数の弔電が届いたのである。ふと思うのは、カーソンはこの世に「沈黙の春」を残し、世界に環境保全の警鐘を鳴らすために生まれて来たのではと言うことだ。そこで、カーソン女史とはどんな人物であったのか、彼女の著作を幾つも翻訳している上遠恵子氏の紹介を参考に少し考えてみたい。
1907年、米国ピッツバーグ市(ペンシルバニア州)から北へ20kmほど離れたスプリングデールの農家に可愛い女の子が生まれた。父親の名は、ロバート・ワルデン・カーソン、母はマリアである。この末っ子である女の子は、レイチェルと名付けられた。日本は、少し前に日露戦争(1904-5年)を終えて明治40年を迎えた頃である。
貧しかったけれども西ペンシルヴァニアの豊かな緑に包まれて、幼いレイチェルはやさしい母親と共に川べりを歩き、虫や花の名前を教えてもらって自然に親しみつつ成長した。小さかった彼女も何時の間にか小学生となり、勉強は良く出来たが、身体が弱く学校を休みがちで、引っ込み思案なため友達は少ししかいなかった。
文学と古典音楽を好む母親は、レイチェルに沢山の本を読んであげたが、彼女は次第に自分で物語を書くようになった。10才の頃始めて書いた物語「雲の中の戦い」で、彼女はある子供雑誌の銀賞を貰う。それは、レイチェルの作家としての一生を決める程に大きな意味を持っていたと、若い時代を振返って彼女自身が述懐している。
1924年に、レイチェルはピッツバーグ市にあるキリスト教系のペンシルヴァニア女子大学(現在のチャタム・カレッジ)へ入学した。この時、彼女の父母は、土地を担保に借金をしながら学資を捻出しているし、レイチェル自身も女子学生が出来る範囲でありとあらゆるアルバイトをして、授業料と生活費を賄った。父母としては、優秀な我が子に当時最高の教育を受けさせたかったのであろう。
私は、1981-82年に1年間ピッツバーグ大学に客員教授として滞在した。この街は、レイチェルの生家近くを流れるアルゲニー川とモノンゲヘラ川が合流して、悠久の大河オハイオ川となる三角地点を中心とする大都市で、歴史的には独立戦争の激戦地であった。また、USスティール、ベツレヘム・スティールなどのある鉄鋼産業の町としても知られ、レイチェルが住んだ当時は多少不景気な中でも、企業活動は活発であった。
そこには、ピッツバーグ大学やカーネギー・メロン大学のような著名大学があるし、一方、米国民謡で知られたステファン C.フォスター生誕の地でもある。筆者は滞米当時、カーソン女史の逸話を知らなかったが、品の良いチャタム・カレッジの建物前を頻繁に通ったし、またエリー湖方面へのドライブで数回スプリングデールを通過した経験がある。
さて、レイチェルは女子大学で教養課程を終えた後、英文学を専攻するつもりであったが、必修科目で習った生物学に興味を覚え、悩んだ末、動物学を専攻することにした。この時、優れた教師メアリー・スコット・スキンカー教授の教えを受けながら、標本と顕微鏡を覗く毎日に明け暮れた。
1928年、21才になったレイチェルは大学を優等で卒業し、ジョンズ・ホプキンズ大学大学院(ボルチモア市)に進む。そこでは、専攻を発生遺伝学へ変え、男子学生と対等な努力を重ねた。アドバイザーはH.S.ジェニングス教授とレイモンド・ペール教授であった。
1929年の<大恐慌>の余波が続く中、父母は経済的に立ち行かなくなり、土地を処分してボルチモアへ移って来た。おまけに姉マリアンが離婚して二人の姪を連れ帰った。こうして家族が共に住むようになったが、家計は大変であった。
1930年代のこの頃は、英国もそうなのだが、米国も女子学生に対して全く暖かい配慮は無く、客観性を重んじる科学分野においてでさえ性的差別は著しかった。でも彼女は挫けなかった。レイチェルは、ペール教授の研究補助をして家計を助けた。少し期間は伸びたけれども、彼女は1932年に修士号を得た。
大学院時代の夏期研修でウッズホール海洋研究所(マサチューセッツ州ケープコッド)へ行った時、レイチェルは海及び海洋生物に深い関心を抱くようになる。これは、彼女に新しい境地を開かせる転機となった。冬には、メリーランド大学で、夏はジョンズ・ホプキンス大学で非常勤講師をしながら動物学を教え、地道に自分の研究を続けた。
やがて悲劇が彼女を見舞う。1935年に不動産業を営んでいた父が亡くなり、28才のレイチェルは経済的に一層追い詰められて行く。それで商務省漁業局のラジオ放送をパート・タイムで手伝うようになる。海に関連した脚本の企画・執筆である。翌年、姉マリアンが亡くなり、二人の中学生の姪を引き取って養わねばならなくなった。
もうレイチェルが定職を得なければカーソン一家はやって行けない。学問を続けることに未練があったけれども、彼女は公務員試験を受け、漁業局の生物学助手として正規職員となった(年俸2000ドル)。結局、経済的理由から彼女は学究生活を諦めなければならなかったのだ。
レイチェルは、放送脚本をまとめ、月刊誌<アトランティック>に「海の中」と題した記事を発表する(1940)。これが認められて、次いで1941年に単行本「潮風の下で」を発表したが、直ぐに真珠湾攻撃があり、太平洋戦争に突入したので殆ど売れなかった。
太平洋戦争中には一時期シカゴに移り、レイチェルは専門的立場から海産物食品、あるいはタンパク質源としての海洋生物に関する情報収集と広報活動を行っていた。終戦後暫くの間は、自然保護に関するシリーズを編集していたが、戦争中に集めた膨大な資料を用いて「我らをめぐる海」(The sea around us)を出版する(1951年)。この本は、大ベストセラーになり、数百万部33カ国語に翻訳されたと言う。
その後の著作「海辺」も良く売れたし、再版された「潮風の下で」もベストセラーになった。45才にして、ようやく彼女は海洋自然学者兼作家としての世間的立場を得たのである。もう、経済的に困るようなことは無くなり、思い出深い漁業局を退職して文筆活動に専念し、老母と共に落ち着いた家庭を持った。二人の姪もそれぞれに結婚していた。1953年、レイチェルはメイン州ウエストサウスポートの海岸近くに、念願の小さな別荘を作り、夏はそこで過ごすようになる。
結局、彼女自身は結婚することが無かった。仕事が忙しかったし、家族を養うために機会を失ったのかも知れぬ。しかし、別な側面から見ると、静謐な生活を好む彼女には結婚が煩わしいものに思えたのだろう。姪の一人マージョリーは、夫と死別して再びレイチェルと共に生活することになった。そのマージョリーが1957年に病死し、残された5才の男の子ロジャーを彼女は養子にした。50才の時である。
レイチェルはロジャーを可愛がり、彼と共に海岸の別荘で過したり野外生活を楽しんだ。慌ただしかった彼女の人生の中で、それは束の間の落ち着いた期間であったと考えられる。きっと彼女の脳裏には、自分が幼い時アルゲニー川の畔で母親が自然のありのままの姿を優しく教えてくれたことなどがあったはずだ。そのロジャーと過ごした想い出などを、彼女は著書「センス・オブ・ワンダー」(没後出版、1967)に残している。
1958年1月、友人のオルガ・オーエンス・ハギンス夫人が飛行機による大量の農薬散布の後、周辺の鳥が死んでしまったとの連絡を寄越した。それが契機となり、レイチェルは農薬の使用実態を調査し始めた。自然と人間の共生を重んじる彼女には、物言わぬ動植物が痛めつけられるのを黙って見ているわけに行かなかった。こうして様々な機関へ手紙を送り、データを集めたり化学者の見解を糺した。この当時から企業の妨害や圧力があった。この年の12月、苦労を共にした優しい母が88才で亡くなる。レイチェルの落胆は大きかったが、1年後には作業を再開する。
数多くの病気に襲われながら、友人達の協力を得て「沈黙の春」は1962年春に完成した。その後の討論や、講演などでレイチェルは益々体力を弱めたことであろう。彼女は、2年後に亡くなったが、どれほど世界から惜しまれたかは既に述べた。
レイチェルが逝去した後、1965年12月にレイチェル・カーソン協会(Rachel Carson Council)が親しかった友人達により結成された。その目的は、レイチェルの考え方を継承し、環境に関する情報収集、問題提起、意見交換であり、環境問題についての総合情報センターになることである。現在も、シャーリー・ブリッグス女史を中心に、活発な活動が続けられている。
参考:
レイチェル・カーソン、「沈黙の春」(青樹簗一訳)、新潮社(1987);新潮文庫版(1974)もある。これは、 Rachel Carson, "Silent Spring", Houghton Mifflin Company, Boston, 1962 の翻訳である。
上遠恵子、「レイチェル・カーソンーその生涯」、かもがわ出版(1993)
レイチェル・カーソン日本協会編、「『沈黙の春』を読む」、かもがわ出版(1992)
レイチェル・カーソン、「われらをめぐる海」(日下実男訳)、ハヤカワ文庫(1977)
ポール・ブルックス「レイチェル・カーソン」(上遠恵子訳)、新潮社(1992)
レイチェル・カーソン、「センス・オブ・ワンダー」(上遠恵子訳)、新潮社(1996)
ここ数年、中共産の野菜、魚介が薬物汚染されていると指摘され、水際検閲でかなりの輸入が阻止されているが、我が国の食品流通システムはもっと輸入食品に敏感であるべきだ。それは、中共国内で頻発している公害問題にも警鐘を鳴らす事に繋がると思う。
日本では、高度成長期の最中に昭和34年(1959年)に水俣病(熊本)を始めとする産業公害が取り上げられ、昭和45年(1970年)前後には自動車排気ガスによる環境汚染及び騒音問題が話題となった。環境庁が総理府内に設置されたのもこの頃だ。しかし、神岡鉱山による富山県神通川下流域のカドミウム汚染米の指摘があっても、農薬問題全般への関心は更に時間が経たなければ深まらなかったのだ。
DDTやBHCあるいはドリン系農薬が我が国で使用禁止されたのは昭和46年(1971)、米国で禁止された内容に1年遅れて農水省は追従した。作家有吉佐和子女史が、それまでの作風と異なる形で朝日新聞に「複合汚染」を書き始めたのは、昭和49年(1974)10月である。彼女は当時43才で、作家として脂の乗り切った時であったし、時代の環境保全に対する流れを鋭く読んでいたと想像する。約8ヶ月の連載の後、これは単行本になった。
有吉さんは、農薬などの環境汚染について、「すでに専門家や先覚者が警告し、告発している事実を、私はより多くの人達に知って頂きたく思い、広報のお手伝いをした」と述べている。一般には目新しく映る学術用語の複合汚染を用い、大衆を引き付ける文学のテーマにしたわけだ。改めて「複合汚染」を読み返すと、それ自身が仲々立派な環境問題への警告書になっている。それは、化学分野に慣れていない有吉さんが300冊以上の関連書を読破し、一方で多くの専門家へのインタビューや現地取材を行って得た成果である。
この著作の中で、有吉さんはレイチェル・カーソン(Rachel Louise Carson、1907-1964)の「沈黙の春」(Silent Spring、1962年刊)を引用し、殺虫剤や除草剤の化学物質による環境汚染を広く紹介している。
「複合汚染」を読んだ当時の人達には、カーソンの「沈黙の春」の存在に大きな興味を持ったはずだ。カーソンの著作は、始め「生と死の妙薬」と言う些か変わった題名で、新潮社から青樹簗一氏による翻訳が出された(1964年)。これは、昭和49年(1974)に改題され、同じ訳者により「沈黙の春」の名で新潮文庫に採録されている。それでも、有吉さんの作品が公表された頃は、翻訳出版後既に10年を経過していたわけで、文庫版は別として日本語版「生と死の妙薬」の入手は当時仲々難しかった。
そうした状況の中で、「沈黙の春」が内包している大きな意味を有吉さんが始めて大衆に分りやすく紹介されたことになる。彼女は昭和59年(1984)に心不全のため54才で逝去されたが、もし生きておられたら、こだわりを持って生み出した作品「複合汚染」で指摘した内容が、今や国家・国民レベルで相当に意識され、人々の認識が変わっている状況を興味深く思われることだろう。
ところで、昭和62年(1987)にカーソンの生誕80周年を記念し、青樹簗一氏による翻訳が、新装版「沈黙の春」と改題されて新潮社から再版された。この著作は、原著出版後約40年を経過しているが、挿し絵や文献がきちんと示されている。上記のように新潮文庫に収められた著作も入手可能だから、どちらでも良い、是非若い人達に一読をお勧めする。
海洋生物学者で科学ジャーナリストであるカーソンが、月刊雑誌<ニューヨーカー>に一部を連載し、次いでその全体が記述された「沈黙の春」を出版した(当時55才)。彼女は、内務省米国魚類・野生生物局出版編集長を退職し、当時は生物と自然についての文筆活動に専念していた。すでに海洋生物分野の著作で、米国の中では名声を得ていたが、ガンに罹り病い重き身であった。執筆のため農薬被害の調査をしている段階でさえ、産業界などから様々な抵抗や妨害があったけれども、彼女は渾身の力を振り絞ってその出版をやり遂げたのである。
「沈黙の春」は、農薬(DDT,BHC、ドリン系などの有機塩素系殺虫剤、パラチオンなどのリン酸化合物)更には除草剤が環境や生物にどのように深刻な影響を与え、これらを汚染し、破壊するかの様相を科学的に検証し、それらの使用に際しては人々に情報公開されなければならない、と静かな筆致で著わした名著である。当然ながらこのタイプの本としては、世界で初めて登場したのであった。
カーソンの基本的な考えは、自然と人間の共生である。そして、内表紙にはカーソンが終生尊敬して止まなかったアルベルト・シュヴァイッツアーに献ぐと記されている。
出版された「沈黙の春」は、化学薬品会社や食品工業それに一部の政府機関から猛烈な攻撃を受けた。非科学的であると言う啓蒙雑誌からの非難も多かった。全米農薬化学工業連盟に至っては、米国全土に「沈黙の春」攻撃用のパンフレットをばらまいた。しかし、カーソンはそれらに負けなかったし、非難には誠実に討論で応じた。勿論、彼女を弁護する化学者も、学協会も多数現れた。カーソンへの投書数千通の内、彼女を支持するものは90%に達したと言う。「沈黙の春」は、発売以来たちまちの内に米国内で100万部を越えるベストセラーになり、また翻訳されて世界中の人々に読まれた。
このように騒がしかったその年の夏、J.F.ケネディ大統領は、科学諮問委員会に対し農薬問題の調査を命じた。翌年委員会としては、政府機関が一致してカーソンの指摘、すなわち農薬に関しては情報公開をすべきであるとの答申を行った。その後、議会では、リビコフ上院議員らにより環境汚染に関する公聴会も開かれ、世論の関心は益々高まって行ったのである。
出版後、2年経ってカーソンは惜しまれながらに逝去する(1964年)。ワシントン大聖堂で執り行われた告別式には、内務省長官自らや名士達が数多く参加した。そして、世界中から多数の弔電が届いたのである。ふと思うのは、カーソンはこの世に「沈黙の春」を残し、世界に環境保全の警鐘を鳴らすために生まれて来たのではと言うことだ。そこで、カーソン女史とはどんな人物であったのか、彼女の著作を幾つも翻訳している上遠恵子氏の紹介を参考に少し考えてみたい。
1907年、米国ピッツバーグ市(ペンシルバニア州)から北へ20kmほど離れたスプリングデールの農家に可愛い女の子が生まれた。父親の名は、ロバート・ワルデン・カーソン、母はマリアである。この末っ子である女の子は、レイチェルと名付けられた。日本は、少し前に日露戦争(1904-5年)を終えて明治40年を迎えた頃である。
貧しかったけれども西ペンシルヴァニアの豊かな緑に包まれて、幼いレイチェルはやさしい母親と共に川べりを歩き、虫や花の名前を教えてもらって自然に親しみつつ成長した。小さかった彼女も何時の間にか小学生となり、勉強は良く出来たが、身体が弱く学校を休みがちで、引っ込み思案なため友達は少ししかいなかった。
文学と古典音楽を好む母親は、レイチェルに沢山の本を読んであげたが、彼女は次第に自分で物語を書くようになった。10才の頃始めて書いた物語「雲の中の戦い」で、彼女はある子供雑誌の銀賞を貰う。それは、レイチェルの作家としての一生を決める程に大きな意味を持っていたと、若い時代を振返って彼女自身が述懐している。
1924年に、レイチェルはピッツバーグ市にあるキリスト教系のペンシルヴァニア女子大学(現在のチャタム・カレッジ)へ入学した。この時、彼女の父母は、土地を担保に借金をしながら学資を捻出しているし、レイチェル自身も女子学生が出来る範囲でありとあらゆるアルバイトをして、授業料と生活費を賄った。父母としては、優秀な我が子に当時最高の教育を受けさせたかったのであろう。
私は、1981-82年に1年間ピッツバーグ大学に客員教授として滞在した。この街は、レイチェルの生家近くを流れるアルゲニー川とモノンゲヘラ川が合流して、悠久の大河オハイオ川となる三角地点を中心とする大都市で、歴史的には独立戦争の激戦地であった。また、USスティール、ベツレヘム・スティールなどのある鉄鋼産業の町としても知られ、レイチェルが住んだ当時は多少不景気な中でも、企業活動は活発であった。
そこには、ピッツバーグ大学やカーネギー・メロン大学のような著名大学があるし、一方、米国民謡で知られたステファン C.フォスター生誕の地でもある。筆者は滞米当時、カーソン女史の逸話を知らなかったが、品の良いチャタム・カレッジの建物前を頻繁に通ったし、またエリー湖方面へのドライブで数回スプリングデールを通過した経験がある。
さて、レイチェルは女子大学で教養課程を終えた後、英文学を専攻するつもりであったが、必修科目で習った生物学に興味を覚え、悩んだ末、動物学を専攻することにした。この時、優れた教師メアリー・スコット・スキンカー教授の教えを受けながら、標本と顕微鏡を覗く毎日に明け暮れた。
1928年、21才になったレイチェルは大学を優等で卒業し、ジョンズ・ホプキンズ大学大学院(ボルチモア市)に進む。そこでは、専攻を発生遺伝学へ変え、男子学生と対等な努力を重ねた。アドバイザーはH.S.ジェニングス教授とレイモンド・ペール教授であった。
1929年の<大恐慌>の余波が続く中、父母は経済的に立ち行かなくなり、土地を処分してボルチモアへ移って来た。おまけに姉マリアンが離婚して二人の姪を連れ帰った。こうして家族が共に住むようになったが、家計は大変であった。
1930年代のこの頃は、英国もそうなのだが、米国も女子学生に対して全く暖かい配慮は無く、客観性を重んじる科学分野においてでさえ性的差別は著しかった。でも彼女は挫けなかった。レイチェルは、ペール教授の研究補助をして家計を助けた。少し期間は伸びたけれども、彼女は1932年に修士号を得た。
大学院時代の夏期研修でウッズホール海洋研究所(マサチューセッツ州ケープコッド)へ行った時、レイチェルは海及び海洋生物に深い関心を抱くようになる。これは、彼女に新しい境地を開かせる転機となった。冬には、メリーランド大学で、夏はジョンズ・ホプキンス大学で非常勤講師をしながら動物学を教え、地道に自分の研究を続けた。
やがて悲劇が彼女を見舞う。1935年に不動産業を営んでいた父が亡くなり、28才のレイチェルは経済的に一層追い詰められて行く。それで商務省漁業局のラジオ放送をパート・タイムで手伝うようになる。海に関連した脚本の企画・執筆である。翌年、姉マリアンが亡くなり、二人の中学生の姪を引き取って養わねばならなくなった。
もうレイチェルが定職を得なければカーソン一家はやって行けない。学問を続けることに未練があったけれども、彼女は公務員試験を受け、漁業局の生物学助手として正規職員となった(年俸2000ドル)。結局、経済的理由から彼女は学究生活を諦めなければならなかったのだ。
レイチェルは、放送脚本をまとめ、月刊誌<アトランティック>に「海の中」と題した記事を発表する(1940)。これが認められて、次いで1941年に単行本「潮風の下で」を発表したが、直ぐに真珠湾攻撃があり、太平洋戦争に突入したので殆ど売れなかった。
太平洋戦争中には一時期シカゴに移り、レイチェルは専門的立場から海産物食品、あるいはタンパク質源としての海洋生物に関する情報収集と広報活動を行っていた。終戦後暫くの間は、自然保護に関するシリーズを編集していたが、戦争中に集めた膨大な資料を用いて「我らをめぐる海」(The sea around us)を出版する(1951年)。この本は、大ベストセラーになり、数百万部33カ国語に翻訳されたと言う。
その後の著作「海辺」も良く売れたし、再版された「潮風の下で」もベストセラーになった。45才にして、ようやく彼女は海洋自然学者兼作家としての世間的立場を得たのである。もう、経済的に困るようなことは無くなり、思い出深い漁業局を退職して文筆活動に専念し、老母と共に落ち着いた家庭を持った。二人の姪もそれぞれに結婚していた。1953年、レイチェルはメイン州ウエストサウスポートの海岸近くに、念願の小さな別荘を作り、夏はそこで過ごすようになる。
結局、彼女自身は結婚することが無かった。仕事が忙しかったし、家族を養うために機会を失ったのかも知れぬ。しかし、別な側面から見ると、静謐な生活を好む彼女には結婚が煩わしいものに思えたのだろう。姪の一人マージョリーは、夫と死別して再びレイチェルと共に生活することになった。そのマージョリーが1957年に病死し、残された5才の男の子ロジャーを彼女は養子にした。50才の時である。
レイチェルはロジャーを可愛がり、彼と共に海岸の別荘で過したり野外生活を楽しんだ。慌ただしかった彼女の人生の中で、それは束の間の落ち着いた期間であったと考えられる。きっと彼女の脳裏には、自分が幼い時アルゲニー川の畔で母親が自然のありのままの姿を優しく教えてくれたことなどがあったはずだ。そのロジャーと過ごした想い出などを、彼女は著書「センス・オブ・ワンダー」(没後出版、1967)に残している。
1958年1月、友人のオルガ・オーエンス・ハギンス夫人が飛行機による大量の農薬散布の後、周辺の鳥が死んでしまったとの連絡を寄越した。それが契機となり、レイチェルは農薬の使用実態を調査し始めた。自然と人間の共生を重んじる彼女には、物言わぬ動植物が痛めつけられるのを黙って見ているわけに行かなかった。こうして様々な機関へ手紙を送り、データを集めたり化学者の見解を糺した。この当時から企業の妨害や圧力があった。この年の12月、苦労を共にした優しい母が88才で亡くなる。レイチェルの落胆は大きかったが、1年後には作業を再開する。
数多くの病気に襲われながら、友人達の協力を得て「沈黙の春」は1962年春に完成した。その後の討論や、講演などでレイチェルは益々体力を弱めたことであろう。彼女は、2年後に亡くなったが、どれほど世界から惜しまれたかは既に述べた。
レイチェルが逝去した後、1965年12月にレイチェル・カーソン協会(Rachel Carson Council)が親しかった友人達により結成された。その目的は、レイチェルの考え方を継承し、環境に関する情報収集、問題提起、意見交換であり、環境問題についての総合情報センターになることである。現在も、シャーリー・ブリッグス女史を中心に、活発な活動が続けられている。
参考:
レイチェル・カーソン、「沈黙の春」(青樹簗一訳)、新潮社(1987);新潮文庫版(1974)もある。これは、 Rachel Carson, "Silent Spring", Houghton Mifflin Company, Boston, 1962 の翻訳である。
上遠恵子、「レイチェル・カーソンーその生涯」、かもがわ出版(1993)
レイチェル・カーソン日本協会編、「『沈黙の春』を読む」、かもがわ出版(1992)
レイチェル・カーソン、「われらをめぐる海」(日下実男訳)、ハヤカワ文庫(1977)
ポール・ブルックス「レイチェル・カーソン」(上遠恵子訳)、新潮社(1992)
レイチェル・カーソン、「センス・オブ・ワンダー」(上遠恵子訳)、新潮社(1996)