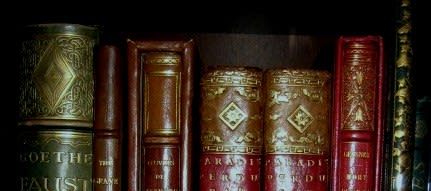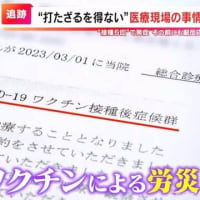傀儡子または、傀儡師 (くぐつ し、かいらい し)
当初は流浪の民や旅芸人のうち狩猟と芸能を生業とした集団
後代になると旅回りの芸人の一座を指した語。
傀儡師とも書く。また女性の場合は傀儡女(くぐつ め)ともいう。
平安時代(9世紀)にはすでに存在し、それ以前からも連綿と続いていたとされる。当初は、狩も行っていたが諸国を旅し、芸能によって生計を営む集団になっていき、一部は寺社普請の一環として、寺社に抱えられた「日本で初めての職業芸能人」といわれている。操り人形の人形劇を行い、女性は劇に合わせた詩を唄い、男性は奇術や剣舞や相撲や滑稽芸を行っていた。呪術の要素も持ち女性は禊や祓いとして、客と閨をともにしたともいわれる。
寺社に抱えられたことにより、一部は公家や武家に庇護され、猿楽に昇華し、操り人形は人形浄瑠璃となり、その他の芸は能楽(能、式三番、狂言)や歌舞伎となっていった。または、そのまま寺社の神事として剣舞や相撲などは、舞神楽として神職によって現在も伝承されている。
寺社に抱えられなかった多くも、寺社との繋がりは強くなっていき、祭りや市の隆盛もあり、旅芸人や渡り芸人としての地位を確立していった。寺社との繋がりや禊や祓いとしての客との褥から、その後の渡り巫女(歩巫女、梓巫女、市子)として変化していき、そのまま剣舞や辻相撲や滑稽芸を行うもの、大神楽や舞神楽を行う芸人やそれらを客寄せとした街商(香具師・矢師)など現在の古典芸能や幾つかの古式床しい生業として現在も引き継がれている。
その源流の形態を色濃く残すものとして、サンカ(山窩)との繋がりを示唆する研究者もいる。また、平安時代の文人、大江匡房の『傀儡子記』に日本民族とは異なる習俗であるとあり、インドからヨーロッパに渡ったジプシーと同源で、インドから中国・韓国経由で日本に来た浮浪漂泊の民族とする研究もある[1]。
(wikipedia)
2014 10 10 人形に、釘を打つ。 【わが郷】
2014 02 04 傀儡 (くぐつ) 師の陰謀 【わが郷】
2013 08 30 腹話術師の 口ぱく人形 【わが郷】