おいっすー!
最近どうよ調子は。
よろしくやってんの?
え?
俺?
漢字で言えば無ですけど何か?

さ、
冒頭からテンションを間違えてしまった今日この頃、
いかがお過ごしでしょうか。
こんばんは、
悠です。
え?
何かいいことあったんじゃないかって?
違いますよー、
やだなー。
逆ですよ逆。
やけくそです

ただまぁ考えたんですよ。
このままでは普及委員会は自然消滅してしまうなと。
外に出したネペンテスも、
日差しにやられて自然消滅しそうですけれども。
で、
ここは一つ、
有意義な情報を提供する植物ブログとして、
ネペンテス達が復活するまで食いつないでいこうじゃないかと、
まぁそういうわけです。
というわけで、
本日お送りするのはこちら!
俺たち肥料組
そう、
皆様にもっと肥料に関して関心を持っていただきたく、
観葉植物栽培歴ん十年の悠が、
リアルな経験で得た知識をお伝えしていくという趣旨のページです。
ここで、
植物初心者の方がおられましたら、
質問です。
ズバリ、
肥料と堆肥の違いは?
これ、
すぐ答えられますでしょうか?
どっちも肥料でしょと答えられた方がいましたら、
そう、
正解です。
どちらも肥料なんですね。
で、
悠が推奨するのは、
堆肥ではなく肥料だということです。
では堆肥とはなんぞやというこですが、
簡単に言えば、
有機肥料だということです。
つまり、
落ち葉とか牛糞とか、
まぁそういうものを、
発酵させてできたものと思っていただいて間違いないと思います。
腐葉土とか牛糞堆肥とかってやつですね。
有機栽培と言うと、
なんとなく聞こえもよく、
安全で、
植物もいきいきと育つイメージがありますが、
ただ残念なことに、
有機肥料は微生物に分解される過程が必要な肥料ですから、
すぐには役に立たないというわけですね。
しかも、
分解が強すぎたり早すぎたりすると、
土中の環境が急変してしまい、
植物体に大ダメージを与えるだけでなく、
最悪枯れさせる危険性だってあるわけです。
で、
鉢植えという環境下でそのようなコントロールは難しいので、
すでに栄養価の高い有機質だけを抽出して濃縮したもの、
つまり肥料なのですが、
これが一般的に向いているというわけです。
ここまで書くのに三日も要してしまいました。
もう夜になると仕事の疲れでぐったりです。
そんな生活を改善すべく、
新たに運動を、
っと、
話しがそれてまた寝てしまうのでまた今度。
飛び飛びで書いているので、
前後が合ってなかったらすみません。
話しを進めまして、
じゃあ実際のところ、
肥料にはどれくらい効力があるのか。
まぁ私は?
自分でやってみないと気がすまない性質ですから?
さっそくやってみましたよ。
数ヶ月前、
がじゅまるを剪定したとき、
切った枝から無作為に選び、
そこらの庭土を使って挿し木。
で、
その際にグループ分けをし、
1、肥料なし、
2、肥料適量、
3、肥料過多、
の三つに分けました。

えー、
すみません。
検証とか言いながら、
実験前の写真を一枚しか撮っていないという、
相変らずのおちゃめっぷりを発揮してしまいました。
写真に向かって左から肥料なし、
肥料過多、
そして右側の二つの鉢が肥料適量です。
肥料適量を二鉢にした理由は、
適量がわからなかったため、
大目と少な目にしてみました。
そして、
元々、
限界を超えた肥料を与えた場合、
どうなってしまうのかを調べるためだったので、
肥料過多の鉢にはどっさり山盛りで固形肥料を与えました。
適量グループの3倍以上は肥料が入っています。
写真が一枚しかないのであれですが、
全体的に、
大体みんな同じ大きさだということを、
なんとなくイメージしてください。
長さ、
葉の枚数、
枝の太さも、
均等とまではいきませんが、
だいたい同じ感じで挿し木を振り分けました。
挿し木なので根はまったくない状態、
土は肥料分が少ないと思われるそこらの庭土、
肥料は近くのホムセンで特価品で販売されていたもの、
温度や日照などの環境の変化を少しでも少なくするため、
同じ窓辺に置いて室内栽培。
さぁ、
たった数ヶ月ですが、
どういう結果になったのか。
冬前、
しかも挿し木なので、
生きてるだけでも御の字で、
葉っぱが数枚出てればいいかなってくらいの気持ちでしたが、
はたしてどうか。
まずは肥料なしから見てみましょう。
こちらです。

成長のばらつきを考慮して、
鉢に数本挿したのですが、
これは一本しか成功せず、
成長具合もまぁまぁと言ったところでしょうか。
挿し木した当初の写真と比べてみると、
葉っぱが5~6枚増えたかなという感じで、
まぁまぁという言葉以外、
特に感想を思いつかない状態です。
一番勢いがあるのが、
雑草という状態でした。
では次に、
肥料適量グループを見てみましょう。
ここがいわゆるベンチマークで、
これ以下であれば成長が遅く、
これ以上であれば成長が早いというわけですね。
では見てみましょう。
こちらです。

おー、
さすが適量グループ。
万遍なく育ってますね。
どうでしょう、
なんとなく、
肥料の重要性が伝わってくる感じはしないでしょうか。
葉も青々として元気よく、
挿した数本はほぼ全部挿し木成功しており、
肥料が生育を助けているのは明らかです。
成長のばらつきも特に感じられず、
非常に参考になる結果と言えるでしょう。
では最後に、
お楽しみの、
肥料をやりすぎるとどうなるのか。
どうなったと思います?
もったいぶらずに早く見せろって?
わかりましたよ。
ではいきますよ。
予めお伝えしておきますが、
あ、
枯れたわけじゃないですよ。
これからご覧頂く画像ですが、
比較のために、
写真向かって左、
ちょっと手前気味なのが適量グループ、
写真に向かって右、
奥側にあるのが肥料やりすぎチームです。
では見てみましょう。
ジャーン、
こちらです。

デデデデデケーーー!!!

うおぉぉぉ、
マジか

え、
うそ、
こんなに差がつくもんなの?
写真向かって左の、
肥料なしグループなんて、
もはやどこにあるかわからないじゃんこれ。
いや、
実際写ってないけど、
別に雑草と変わらない大きさだから、
もうこれでいいよ別に。
え、
マジで。
肥料なしだとこれでしょ。

なんかよくわからない雑草がよく育ってるわけでしょ。
で、
肥料ありと比べるとこれでしょ。

ほんと、
挿し木したときは、
みんなあの雑草くらいの大きさだったんだよマジで。
凄くないこれ。
いやでもで、
正直に言います。
やっぱ差がつくなってのは育ててすぐに気づきました。
だって土の乾き具合が尋常じゃないんだもん。
肥料どっさりグループなんか、
ピーク時、
夜に水をあげたのに、
朝起きたら土が乾ききってましたからね。
対して肥料なしグループは、
一週間くらい水をやらなくても特に問題ない感じでした。
やっべー、
眠気が限界です、
ではでは、
また今度。
最近どうよ調子は。
よろしくやってんの?
え?
俺?
漢字で言えば無ですけど何か?

さ、
冒頭からテンションを間違えてしまった今日この頃、
いかがお過ごしでしょうか。
こんばんは、
悠です。
え?
何かいいことあったんじゃないかって?
違いますよー、
やだなー。
逆ですよ逆。
やけくそです

ただまぁ考えたんですよ。
このままでは普及委員会は自然消滅してしまうなと。
外に出したネペンテスも、
日差しにやられて自然消滅しそうですけれども。
で、
ここは一つ、
有意義な情報を提供する植物ブログとして、
ネペンテス達が復活するまで食いつないでいこうじゃないかと、
まぁそういうわけです。
というわけで、
本日お送りするのはこちら!
俺たち肥料組
そう、
皆様にもっと肥料に関して関心を持っていただきたく、
観葉植物栽培歴ん十年の悠が、
リアルな経験で得た知識をお伝えしていくという趣旨のページです。
ここで、
植物初心者の方がおられましたら、
質問です。
ズバリ、
肥料と堆肥の違いは?
これ、
すぐ答えられますでしょうか?
どっちも肥料でしょと答えられた方がいましたら、
そう、
正解です。
どちらも肥料なんですね。
で、
悠が推奨するのは、
堆肥ではなく肥料だということです。
では堆肥とはなんぞやというこですが、
簡単に言えば、
有機肥料だということです。
つまり、
落ち葉とか牛糞とか、
まぁそういうものを、
発酵させてできたものと思っていただいて間違いないと思います。
腐葉土とか牛糞堆肥とかってやつですね。
有機栽培と言うと、
なんとなく聞こえもよく、
安全で、
植物もいきいきと育つイメージがありますが、
ただ残念なことに、
有機肥料は微生物に分解される過程が必要な肥料ですから、
すぐには役に立たないというわけですね。
しかも、
分解が強すぎたり早すぎたりすると、
土中の環境が急変してしまい、
植物体に大ダメージを与えるだけでなく、
最悪枯れさせる危険性だってあるわけです。
で、
鉢植えという環境下でそのようなコントロールは難しいので、
すでに栄養価の高い有機質だけを抽出して濃縮したもの、
つまり肥料なのですが、
これが一般的に向いているというわけです。
ここまで書くのに三日も要してしまいました。
もう夜になると仕事の疲れでぐったりです。
そんな生活を改善すべく、
新たに運動を、
っと、
話しがそれてまた寝てしまうのでまた今度。
飛び飛びで書いているので、
前後が合ってなかったらすみません。
話しを進めまして、
じゃあ実際のところ、
肥料にはどれくらい効力があるのか。
まぁ私は?
自分でやってみないと気がすまない性質ですから?
さっそくやってみましたよ。
数ヶ月前、
がじゅまるを剪定したとき、
切った枝から無作為に選び、
そこらの庭土を使って挿し木。
で、
その際にグループ分けをし、
1、肥料なし、
2、肥料適量、
3、肥料過多、
の三つに分けました。

えー、
すみません。
検証とか言いながら、
実験前の写真を一枚しか撮っていないという、
相変らずのおちゃめっぷりを発揮してしまいました。
写真に向かって左から肥料なし、
肥料過多、
そして右側の二つの鉢が肥料適量です。
肥料適量を二鉢にした理由は、
適量がわからなかったため、
大目と少な目にしてみました。
そして、
元々、
限界を超えた肥料を与えた場合、
どうなってしまうのかを調べるためだったので、
肥料過多の鉢にはどっさり山盛りで固形肥料を与えました。
適量グループの3倍以上は肥料が入っています。
写真が一枚しかないのであれですが、
全体的に、
大体みんな同じ大きさだということを、
なんとなくイメージしてください。
長さ、
葉の枚数、
枝の太さも、
均等とまではいきませんが、
だいたい同じ感じで挿し木を振り分けました。
挿し木なので根はまったくない状態、
土は肥料分が少ないと思われるそこらの庭土、
肥料は近くのホムセンで特価品で販売されていたもの、
温度や日照などの環境の変化を少しでも少なくするため、
同じ窓辺に置いて室内栽培。
さぁ、
たった数ヶ月ですが、
どういう結果になったのか。
冬前、
しかも挿し木なので、
生きてるだけでも御の字で、
葉っぱが数枚出てればいいかなってくらいの気持ちでしたが、
はたしてどうか。
まずは肥料なしから見てみましょう。
こちらです。

成長のばらつきを考慮して、
鉢に数本挿したのですが、
これは一本しか成功せず、
成長具合もまぁまぁと言ったところでしょうか。
挿し木した当初の写真と比べてみると、
葉っぱが5~6枚増えたかなという感じで、
まぁまぁという言葉以外、
特に感想を思いつかない状態です。
一番勢いがあるのが、
雑草という状態でした。
では次に、
肥料適量グループを見てみましょう。
ここがいわゆるベンチマークで、
これ以下であれば成長が遅く、
これ以上であれば成長が早いというわけですね。
では見てみましょう。
こちらです。

おー、
さすが適量グループ。
万遍なく育ってますね。
どうでしょう、
なんとなく、
肥料の重要性が伝わってくる感じはしないでしょうか。
葉も青々として元気よく、
挿した数本はほぼ全部挿し木成功しており、
肥料が生育を助けているのは明らかです。
成長のばらつきも特に感じられず、
非常に参考になる結果と言えるでしょう。
では最後に、
お楽しみの、
肥料をやりすぎるとどうなるのか。
どうなったと思います?
もったいぶらずに早く見せろって?
わかりましたよ。
ではいきますよ。
予めお伝えしておきますが、
あ、
枯れたわけじゃないですよ。
これからご覧頂く画像ですが、
比較のために、
写真向かって左、
ちょっと手前気味なのが適量グループ、
写真に向かって右、
奥側にあるのが肥料やりすぎチームです。
では見てみましょう。
ジャーン、
こちらです。

デデデデデケーーー!!!

うおぉぉぉ、
マジか

え、
うそ、
こんなに差がつくもんなの?
写真向かって左の、
肥料なしグループなんて、
もはやどこにあるかわからないじゃんこれ。
いや、
実際写ってないけど、
別に雑草と変わらない大きさだから、
もうこれでいいよ別に。
え、
マジで。
肥料なしだとこれでしょ。

なんかよくわからない雑草がよく育ってるわけでしょ。
で、
肥料ありと比べるとこれでしょ。

ほんと、
挿し木したときは、
みんなあの雑草くらいの大きさだったんだよマジで。
凄くないこれ。
いやでもで、
正直に言います。
やっぱ差がつくなってのは育ててすぐに気づきました。
だって土の乾き具合が尋常じゃないんだもん。
肥料どっさりグループなんか、
ピーク時、
夜に水をあげたのに、
朝起きたら土が乾ききってましたからね。
対して肥料なしグループは、
一週間くらい水をやらなくても特に問題ない感じでした。
やっべー、
眠気が限界です、
ではでは、
また今度。
















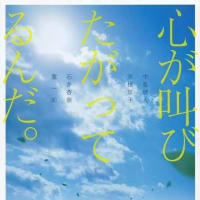






ネペンテスやってると「肥料?不要でしょ?」ってなり家庭菜園の野菜とかも同じような扱いになり重要性を忘れそうになります・・・
返信遅れてすみません。
色々あって抜け殻のようになってしまい、
家に帰ったらそのまま寝てしまう生活をしておりました(^^;)
わかりますよ、
ネペンテスやってると、
植物の育て方を忘れそうになるんですよね。
水のやりすぎなのかどうかとか、
長年培ってきた勘ですら失いそうになります(^ω^;)
毎年この季節は、
植物栽培も含め、
色々な意味で初心にかえる良い時期なので、
もっと精進していこうと思います。