これから真面目に生きることにしました。
そう決めて数時間後に、
不真面目なことをしてしまいましたが、
真面目に生きることにしました。
そんな今日この頃、
いかがお過ごしでしょうか。
こんばんは、
悠です。
えー、
今日はですね、
またしても私のてきとうなアドバイスにより、
被害者を出してしまう可能性が出てきましたので、
急きょ、
この記事を書くことにしました。
あと30分くらいで寝る時間なので、
バーっと書きますので、
今回の経緯や、
その他の説明は省略します。
すみません。
1 ミズゴケを使った室内栽培について
私がミズゴケの使用を止めた理由の一つが、
この室内栽培での不適です。
まず第一に、
管理が凄く難しいのです。
乾かしたらダメ、
湿らせすぎてもダメ。
ある程度、
ミズゴケが用土として落ち着いてくると、
毎日水をあげても、
数日おきにおげても、
特に問題はないのですが、
初期管理を失敗すると、
あっという間にどろどろになって、
用土としての役目を果たさなくなってしまいます。
失敗の要因は様々ですが、
これは知識よりも経験をつまないと、
どうやっても対処できません。
ユグドラシル肥料編で書く予定の、
【場の清め】を理解していると、
用土の悪化に対応しやすいのですが、
それを踏まえた上でも、
室内でのミズゴケの管理は難しいでしょう。
2 腰水とミズゴケ
これは本当に申し訳なかったのですが、
ミズゴケや腰水について、
詳しく扱っているサイトや本が少ないようで、
そのことを踏まえた上で説明するべきでした。
上記の続きになりますが、
ミズゴケの難しいところは、
ランクもあるということです。
一口にミズゴケと言っても、
質や産地によって値段が全然違います。
用土に関して言えば、
値段=品質がほぼ当てはまり、
超高ランクのミズゴケほど、
失敗は少なくなります。
何がその質を分けるのか。
これは、
ミズゴケをリサイクルしてみるとわかります。
状態が安定していたミズゴケを水洗いし、
乾燥させて再度使うと、
だいたいは購入当初の能力を発揮してくれます。
逆に、
一度腐敗してしまったミズゴケは、
同じように再利用しても、
ほぼほぼ失敗する傾向があります。
つまり、
現地でどのような状態のミズゴケを、
どのような処理をしてパッケージングしたのか、
それが値段だと見て間違いないでしょう。
無機質な土はあまり心配はないのですが、
有機系の用土は、
最初の状態がもろに影響してしまうんですね。
高ランクのミズゴケ以外はダメというわけではありませんが、
特に腰水栽培においては、
初期の出来がすべてのため、
成功率を上げるためには、
良いミズゴケを使うか、
出費をおさえるために、
砂利系の用土に切り替えるのが無難でしょう。
3 腰水管理について
ちょっともうマジで時間がないので、
色々と省きますが、
一口に腰水と言っても、
ある程度のルールはあります。
特に室内においては、
以下の注意事項を守った方が、
余計なトラブルが少なくなります。
水と空気の当たる面積を極力減らす
一週間くらいで吸いきれる水位にする
腰水がなくなるまで水を与えない
表土が湿っている時は下皿に水を足す
水の吸い上げが出来ていない場合は中止する
まずはこのルールをお守りください。
その上でミズゴケですが、
ミズゴケ自体にはスポンジの様な吸水力はあるのですが、
逆に水を手放すのが苦手なので、
雑菌が大繁殖しやすい室内では、
とにかく腰水と相性が悪いと言わざるおえません。
ぬめりは100%発生しますので、
それは大した問題ではありませんが、
そこから藻や雑菌が大繁殖してしまうため、
あっという間に手に負えない状態になります。
水をザブザブかけれる状態や、
自然に近い風を再現できる、
温室などの環境であれば、
良好な結果を出してくれるミズゴケも、
乾燥している上に無風に近く、
ちょろちょろとしか水を与えられない室内においては、
超ハードモードと言えるでしょう。
どうしてもミズゴケを使う場合は、
鹿沼土など、
水分を適度にコントロールしてくれる、
無機質な用土と組み合わせて使うのが無難です。
4 腐敗をコントロールする
ヤバイ、
マジでもう寝る時間です。
大急ぎで書きます。
まず腰水とはどういうものなのか、
そしてどのような管理が正解なのか、
どうしても理解が難しい方は、
底面給水方式である、
とだけイメージしておけば大丈夫です。
ちょっと違うんじゃないかと思われるでしょうが、
腰水の本質はそこにある、
と私は思っています。
私に言わせれば、
腰水は、
水切れや水のやり忘れを防止する、
便利なテクニックの一つではありません。
歴とした栽培法の一つです。
大地の下に染み渡っている大量の水分は、
なぜ腐敗しないのか。
言いたいことは沢山ありますが、
ここではまず、
この言葉だけ胸に刻み込んでください。
澱んだ水は腐敗する
逆に言えば、
水はちょっとでも動いていれば、
決して腐敗しないということです。
例えそれが、
植物が水を吸い上げる程度のスピードであっても、
です。
上から水をやると腐敗し、
下からやるとなぜ腐敗しないのか。
幾つか理由はありますが、
水の蒸散も、
水が動いてるのと同義、
とだけここではおぼえてください。
5 それでも抗ってみる
うひょー、
もうタイムオーバーです。
私の栽培場ですが、
基本、
全部が腰水です。
水耕ではなく、
腰水にしたのは、
理由がありますが、
もう時間がないので割愛です。
腐敗への抵抗ですが、
雑菌抑制のためアルミホイルをしく、
苔を活用する、
穴のない容器を使い空気を遮断する
ユグドラソイルをフルパワー化する
などがあります。
時間切れです。
ではでは、
また次回、
お会いしましょう。
そう決めて数時間後に、
不真面目なことをしてしまいましたが、
真面目に生きることにしました。
そんな今日この頃、
いかがお過ごしでしょうか。
こんばんは、
悠です。
えー、
今日はですね、
またしても私のてきとうなアドバイスにより、
被害者を出してしまう可能性が出てきましたので、
急きょ、
この記事を書くことにしました。
あと30分くらいで寝る時間なので、
バーっと書きますので、
今回の経緯や、
その他の説明は省略します。
すみません。
1 ミズゴケを使った室内栽培について
私がミズゴケの使用を止めた理由の一つが、
この室内栽培での不適です。
まず第一に、
管理が凄く難しいのです。
乾かしたらダメ、
湿らせすぎてもダメ。
ある程度、
ミズゴケが用土として落ち着いてくると、
毎日水をあげても、
数日おきにおげても、
特に問題はないのですが、
初期管理を失敗すると、
あっという間にどろどろになって、
用土としての役目を果たさなくなってしまいます。
失敗の要因は様々ですが、
これは知識よりも経験をつまないと、
どうやっても対処できません。
ユグドラシル肥料編で書く予定の、
【場の清め】を理解していると、
用土の悪化に対応しやすいのですが、
それを踏まえた上でも、
室内でのミズゴケの管理は難しいでしょう。
2 腰水とミズゴケ
これは本当に申し訳なかったのですが、
ミズゴケや腰水について、
詳しく扱っているサイトや本が少ないようで、
そのことを踏まえた上で説明するべきでした。
上記の続きになりますが、
ミズゴケの難しいところは、
ランクもあるということです。
一口にミズゴケと言っても、
質や産地によって値段が全然違います。
用土に関して言えば、
値段=品質がほぼ当てはまり、
超高ランクのミズゴケほど、
失敗は少なくなります。
何がその質を分けるのか。
これは、
ミズゴケをリサイクルしてみるとわかります。
状態が安定していたミズゴケを水洗いし、
乾燥させて再度使うと、
だいたいは購入当初の能力を発揮してくれます。
逆に、
一度腐敗してしまったミズゴケは、
同じように再利用しても、
ほぼほぼ失敗する傾向があります。
つまり、
現地でどのような状態のミズゴケを、
どのような処理をしてパッケージングしたのか、
それが値段だと見て間違いないでしょう。
無機質な土はあまり心配はないのですが、
有機系の用土は、
最初の状態がもろに影響してしまうんですね。
高ランクのミズゴケ以外はダメというわけではありませんが、
特に腰水栽培においては、
初期の出来がすべてのため、
成功率を上げるためには、
良いミズゴケを使うか、
出費をおさえるために、
砂利系の用土に切り替えるのが無難でしょう。
3 腰水管理について
ちょっともうマジで時間がないので、
色々と省きますが、
一口に腰水と言っても、
ある程度のルールはあります。
特に室内においては、
以下の注意事項を守った方が、
余計なトラブルが少なくなります。
水と空気の当たる面積を極力減らす
一週間くらいで吸いきれる水位にする
腰水がなくなるまで水を与えない
表土が湿っている時は下皿に水を足す
水の吸い上げが出来ていない場合は中止する
まずはこのルールをお守りください。
その上でミズゴケですが、
ミズゴケ自体にはスポンジの様な吸水力はあるのですが、
逆に水を手放すのが苦手なので、
雑菌が大繁殖しやすい室内では、
とにかく腰水と相性が悪いと言わざるおえません。
ぬめりは100%発生しますので、
それは大した問題ではありませんが、
そこから藻や雑菌が大繁殖してしまうため、
あっという間に手に負えない状態になります。
水をザブザブかけれる状態や、
自然に近い風を再現できる、
温室などの環境であれば、
良好な結果を出してくれるミズゴケも、
乾燥している上に無風に近く、
ちょろちょろとしか水を与えられない室内においては、
超ハードモードと言えるでしょう。
どうしてもミズゴケを使う場合は、
鹿沼土など、
水分を適度にコントロールしてくれる、
無機質な用土と組み合わせて使うのが無難です。
4 腐敗をコントロールする
ヤバイ、
マジでもう寝る時間です。
大急ぎで書きます。
まず腰水とはどういうものなのか、
そしてどのような管理が正解なのか、
どうしても理解が難しい方は、
底面給水方式である、
とだけイメージしておけば大丈夫です。
ちょっと違うんじゃないかと思われるでしょうが、
腰水の本質はそこにある、
と私は思っています。
私に言わせれば、
腰水は、
水切れや水のやり忘れを防止する、
便利なテクニックの一つではありません。
歴とした栽培法の一つです。
大地の下に染み渡っている大量の水分は、
なぜ腐敗しないのか。
言いたいことは沢山ありますが、
ここではまず、
この言葉だけ胸に刻み込んでください。
澱んだ水は腐敗する
逆に言えば、
水はちょっとでも動いていれば、
決して腐敗しないということです。
例えそれが、
植物が水を吸い上げる程度のスピードであっても、
です。
上から水をやると腐敗し、
下からやるとなぜ腐敗しないのか。
幾つか理由はありますが、
水の蒸散も、
水が動いてるのと同義、
とだけここではおぼえてください。
5 それでも抗ってみる
うひょー、
もうタイムオーバーです。
私の栽培場ですが、
基本、
全部が腰水です。
水耕ではなく、
腰水にしたのは、
理由がありますが、
もう時間がないので割愛です。
腐敗への抵抗ですが、
雑菌抑制のためアルミホイルをしく、
苔を活用する、
穴のない容器を使い空気を遮断する
ユグドラソイルをフルパワー化する
などがあります。
時間切れです。
ではでは、
また次回、
お会いしましょう。
















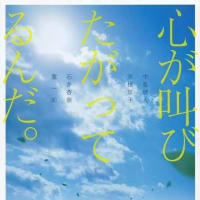






本当に申し訳ありません。
お忙しい中 わざわざ回答して頂き
ありがとうござます‼︎
腰水の件ですが
私は全部違う事をしておりましたね(´∀`;)
・腰水の水が 思いっきり空気に触れていた
・1週間で吸い切れるはずもない水量
・上からも水をやって 流しきってから
また新しく腰水に浸からせていた
そりゃ臭くなってくるはずですね(´;◞౪◟;)
ここで ふと思ったのですが
悠先生が仰っている腰水栽培法が
ハイドロカルチャーと
よく似た原理な気がしまして
ちょうど使っていないハイドロ鉢があるので
それに ユグドラソイルを入れて
再度 挑戦してみようかと思ったのですが…
また失敗しちゃいますかね(^_^;)
ミズゴケの方は本体は元気です。
葉も一枚も枯れたり変色はありません。
ただ ほんの少しだけ 匂ってきてます。
こちらの母体も ユグドラソイルにしてあげた方が良さそうですね。
あと 臭くなってしまったユグドラソイルは
洗って 天日干しすれば
再利用できますでしょうか?
せっかく頂いた大切な用土なので(●´ω`●)
ユグドラソイルのフルパワー化のお話も
楽しみにしております。
最近 一気に寒くなってきたので
どうか ご自愛くださいませ(*⁰▿⁰*)
ありがとうございます、
体調に気を付けつつ、
これからも頑張ります(´▽`*)
さっそくブログにお邪魔させて頂きました(^ω^)
読みやすく丁寧なブログで、
今後が楽しみですね~、
と正直に書くと、
続かないフラグになるので、
まぁいいんじゃないでしょうかという、
偉そうな感想にしておきます笑
ブログにもコメントさせて頂きましたが、
ハイドロカルチャーは水と栽培なので、
ハイドロボールの代わりにユグドラソイルを投入しただけであると考えれば、
ハイドロカルチャー=ユグドラシルという図式で正解です(*'▽')
腰水栽培については私も研究中なので、
全部が逆とは一概には言えないかもしれません。
事実、
野外では蛙さんのやり方で問題なく育ちます。
むしろそのやり方の方が、
断然調子が良くなりますね。
あ、
ボウフラがわきまくるので、
むしろそちらの対策に追われるかもしれませんが(;'∀')
ユグドラソイルの再利用は、
どれくらいダメージを受けたかにもよりますが、
正直、
難しいと思います(;´∀`)
藻や雑菌が一度大発生すると、
用土に定着してしまうので、
よほど入念に消毒などをしないと、
同じことの繰り返しになる可能性が大です。
雑菌とやわらかく表現していますが、
要は腐敗菌や病原菌のことなので、
そう考えますと、
廃棄してしまうか、
リサイクルするにしても、
他の抵抗力の強い、
まったく別の植物に使った方が安全です。
用土はまた配合しますので、
ご入用でしたらまたご連絡ください('ω')ノ
用土の再利用については、
フルパワー化とちょっとだけ関係していますので、
時間が出来たら書きますので、
良かったらご参考ください(^^)
日記も家計簿もダイエットも
本気の三日坊主の私なので
そうですねw
学校で何か課題があった時に書く
作文程度で考えます( ´,_ゝ`)
腰水栽培は 屋外深いですねぇ。
いや
植物全部が奥深いのですね。
春から秋にかけて
屋外栽培が良いのは充分に分かってるのですが
部屋の中をジャングルにしたくて
ついつい
屋内栽培が出来る環境を考えてしまいます。
避けて通れないのが虫問題ですね。
日本の夏は どこでもそうかもしれませんが
我が家も漏れなく蚊が多く
ボウフラとか想像したら気が遠くなりますw
先日、多肉植物を
知人の方から頂きました。
もちろん屋外栽培されていまして
植物を頂けたのは嬉しかったんですが
確実に虫がいるだろうなぁと思い
アレコレとチェックしました所
やはり シッカリと。。。
とりあえず今はベランダに置いてます。
虫対策の為に 植え替えをしてから
室内に入れようと思います。
ネペンテスの栽培で
このハイドロ式ユグドラシルが成功して
上手く生長してくれれば
虫や腐敗に悩む事なく
室内での栽培が続けてられるかなぁと
一縷の望みにかけております(^^;)
ユグドラソイルの再利用は難しいのですか…
私のズサンな栽培で
せっかく頂いたユグドラソイルを
半分以上 駄目にしてしまいました。
誠に申し訳ありません。
今の所 洗って天日干しをしていましたが
それでも夏の暑さではないので
滅菌はされなさそうですね。
用土のフルパワー化の記事を
楽しみにしていますね(^-^)
用土は 頂いた時の4分の1ほど残ってます。
親元のミズゴケの方を植え替える時に
ハイドロボールと平野して使えば
なんとか足りるかなぁと…
ちょっと少ないでしょうかねぇ(^_^;)
また経過報告をさせて頂きます。
悠先生の貴重なお時間を割いてしまって
本当にすいませんでした(>人<;)
何か説明しようと思っていたのですが、
まったく思い出せず、
全然頭が回らないので、
話しがあっちゃこっちゃに飛ぶと思いますが、
徐々に書いていきますので(;・∀・)
眠気に勝てず、
まともに返事もできない日が続いており、
申し訳ないです(;^ω^)
今も8割寝ちゃってる状態なので(;'∀')
ユグドラソイルというか、
用土は全般的に、
変色やにおいがなければ、
再利用は可能です。
ただ、
やはり、
菌は残ると思いますので。
使っても問題はないと思いますが、
推奨はできないということで笑
すみません、
もう首も曲がったような状態なので、
今日はもう寝ることにします(*‘ω‘ *)
まとめみたいな形になるかもしれませんが、
書きますので、
よろしくお願いします(^^)/