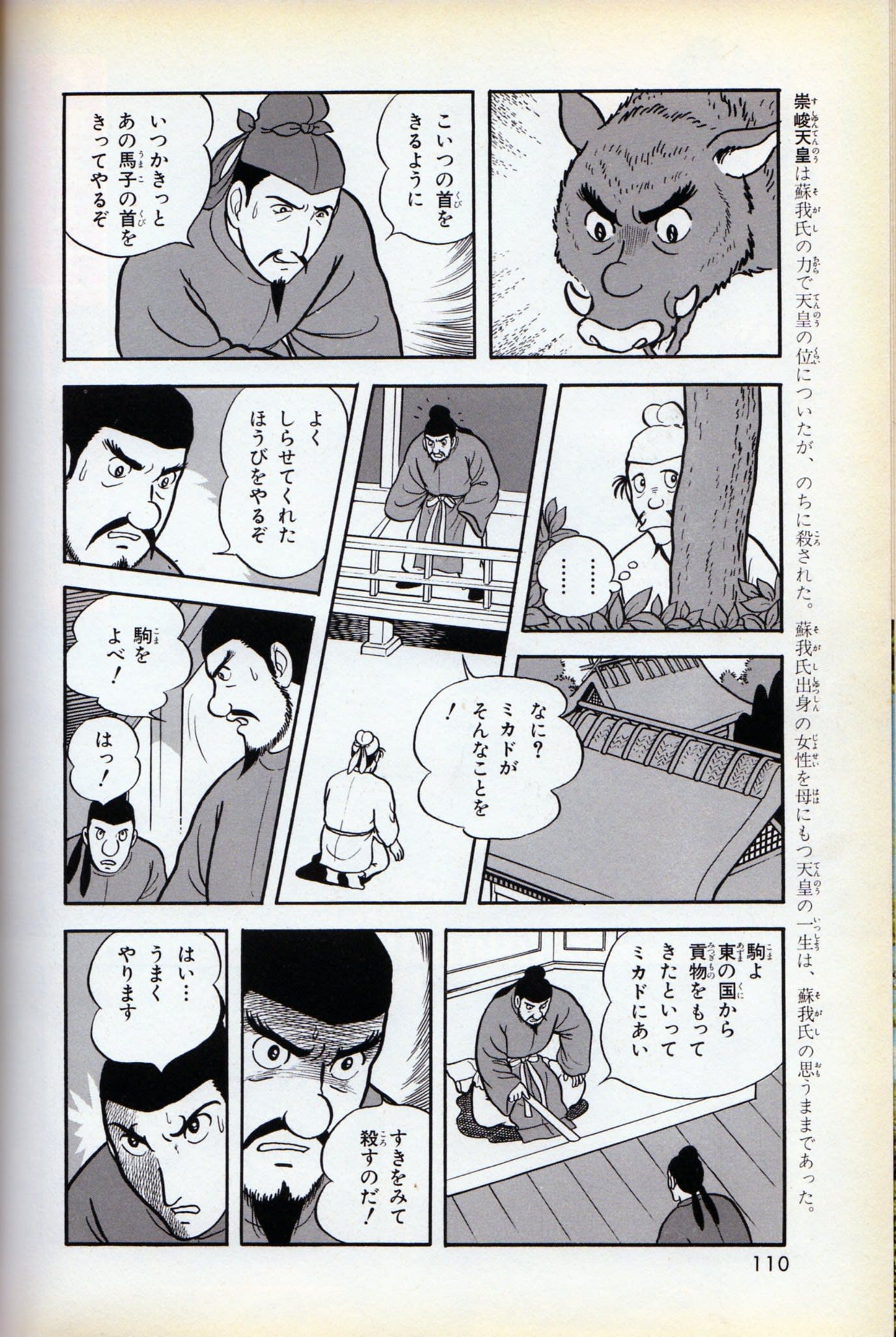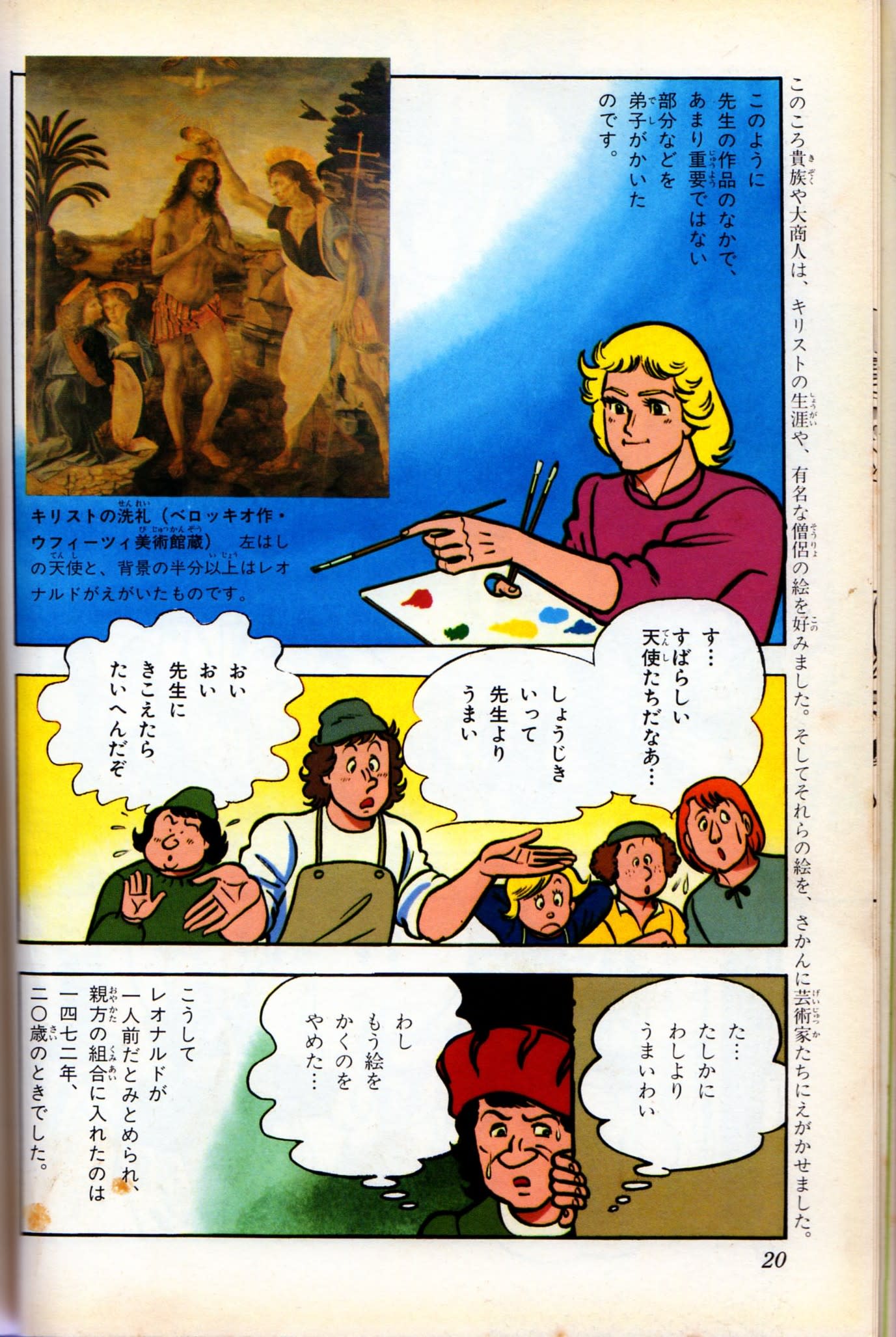一般に、我々が思うところの対立構造はおそらくこんな感じであろうと思われる。
例えば、
引っ込み思案な人←→図々しい人
寡黙←→多弁
慎重←→大胆
国語の勉強ってワケじゃないが・・・・人の特徴を自分なりに捉えようとするとき、普通はこういう風なタイプ分けを行うのではないだろうか。「あいつは口数が少ないよな~」「アイツはおとなし過ぎる。もうちょっと積極的になった方がいいよな」といった感じに。
これらの人間的性格は、バランスが難しく、どの要素もあればあるだけ良いというものでもなく、度を過ぎれば変人扱いされ、もっと悪ければ変態・狂人レベルに嫌悪されるものとなる。
こうした性質の理想的バランスとは何か?そして、そんなものはそもそもあるのか?といった疑問に対し、アリストテレスはこう回答する。
恥知らずと内気の中間に慎みが存在し、これが理想的であるといった具合に、中間点が人間にとって最も望ましいと彼は考えた。
臆病と無謀の中間は勇気であり、これが理想。
敵意と追従の中間は親愛であり、これが理想。
横柄と媚びの中間は威厳であり、これが理想。
臆病すぎても駄目。かといって、何にでも立ち向かっていくような無謀さだけしかないのも駄目。ふたつの性質をよく理解し、心得た者がその中間に近い位置、つまり勇気ある者といえる。・・こう彼は述べる。
極端すぎず、中間であれ、という例にこんなのがある。
野暮な人は、冗談を全く受け付けないか、あるいはやっと受け付けるかであるが、おどけ者は、どんな冗談でも無造作に、かつ喜んで受け入れる。
しかし本当は、そのどちらであってもならず、冗談のうちのあるものは受け入れ、他のものは受け入れないようにすべきであり、しかもそのことを理に即してなすべきである。そしてこのようにする人が、機知に富んだ人なのである。
冗談はむしろ、中の状態にある人(おどけ者でもなく、頑固者でもないという人)に喜ばれるものでなければならない。と、いうのも、その中の状態にある人は、正しく判別してくれるのだから。
<いかがわしい意訳>
堅物も駄目だが、下品で低次元なネタでゲラゲラ笑う無教養な人間もまた駄目だ。冗談やギャグにも色んな程度がある。笑うに値するものには反応を示し、くだらな過ぎるものは斬って捨てる、こういう判断を的確に行える者は教養人だ。
そういった意味でも、ある冗談が下品か上品かを判断してもらう対象は、品のなさ過ぎる人でもなく、堅物でもない、その丁度中間に位置する人に判断してもらうのが良い。他の連中は、正しく判別できっこないぜ。
また金の使い方に関する話はこんな感じだ。
かくて、大きな支出をなすにあたって、事柄にふさわしい金額を選ぶことができる者、つまり、そのような大きな支出をなす場合にも、そういった「中」の状態を目指すことの出来る人が、豪勢なのである。
これに対して、過大で、度外れな支出をなす傾向の者には、名前がついていないのであるが、しかし、一部の人たちが「趣味の悪い人」とか「見栄っ張り」とか呼んでいる人たちが、これに近い人間である。
また理の命ずる通りにもてなす人が、豪勢な人なのである。何故なら、「ふさわしいこと」とは、事柄に相応していることだからであり、つまり、不相応なことはどれも、ふさわしくないからである。
<いかがわしい意訳>
一般的に、豪勢な人というと、気前よく金を使う人のように思われがちだが、それは間違っている。常識や適正値を超えた水準で身分不相応な出費をしている者は、俺から言わせれば、まともな判断力のないただの肥えた豚だ。全然理性的な行動をとってねぇじゃね~か!馬鹿と豪勢を履き違えるな。身の丈に合った、つつましくお金を使う者こそが豪勢な人というのだ!
アリストテレスは臆病者と無謀な者の中間に勇気ある者がいる、と述べておきながら、性質としては臆病者と無謀な者の方がよく似ているし、近いと語っている。
これは図で表すと奇妙に思えるかもしれないが、逆にいうとこの構図にとらわれている事が、思考の硬直化ともいえる。柔軟に考えるキッカケになりそうな話しだ。
臆病者←勇者→無謀な者
中間に勇者が来るので、臆病者と無謀な者同士が最も対極的に見える。でも性質的には
勇者←→臆病者&無謀な者
と見るのが正しいだろうと彼は言う。その説明箇所を引用してみよう。
ところで、中の両極端との対立のほうが、両極端相互の対立よりもいっそう大きいのである。というのは、中は両極端のいずれとも一緒に生じることはないが、両極端は互いに一緒に生ずるからである。つまり時には、同じ人が「無謀な臆病者」であったり、ある事柄では放漫であるが、他の事柄ではケチであったり、要するに、悪しき面ではその行動に一様性がないからである。
<いかがわしい意訳>
臆病者と無謀な者というのは、両極端の存在とみなされがちだが、勇者と比べると、むしろ彼ら同士のほうが同族的で仲が良い。そして、臆病と無謀は同一人物に同時に備わることが珍しくない。
何故、全く逆とも思える性質が同居するのか?話は簡単だ。臆病も無謀も悪い性質だ。悪い性質は悪い性質同士、結託する。だから、浪費家な面と非常にケチな面を同時に持っている人も存在する。欠点や悪い面というのは一面的というよりは、多面的であるという事を肝に銘じてほしい。悪い行動は、様々な形で表面化する。
全面的に支持するかどうかはともかく、なかなか面白い着眼点だと思う。
※引用先
『世界の名著 アリストテレス』 中央公論社より