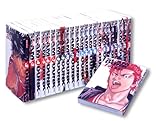■リアリストとビジョナリスト
「 Mr.Children DOME TOUR 2009 SUPERMARKET FANTASY」でも紹介した
Mr.Childrenの『365日』が流れるNTT東日本のCMに興味深い親子のやり取りがあります。
野球少年の子供は、大のイチローファンなのですが、
その子供がお父さんにふとした疑問を投げ、それに応えるシーンです。
イチロー並の才能を持ち、実際に輝かしい成績を残す選手は息子 「僕、イチローみたいになれるかな・・・」
父 「なろうと思ってなれるもんじゃないよ。でもな、なろうと思わなきゃ何にもなれないよ」[ NTT東日本のCM ]
それこそ数十年に一人の逸材であることは間違いありません。
つまり、普通に考えればこの息子は「イチローになれるはずない」でしょうし、
結果だけ見ればこの予想はほぼ100%当たるでしょう。
という現実的な期待値を合理的に見積もってシミュレーションする人を「リアリスト」と呼び
ビジョンを持ってその実現のために努力する人を「ビジョナリスト」と呼ぶとします。
どちらが良いとか悪いとかの問題ではありませんが、
一つだけ間違いなく言えるのは、リアリストでは世の中は変えられないということでしょう。
ではビジョナリストの方がいいのか?
こういった二元論の問題にした時点で真相には近づけないでしょう。
ビジョナリストの中でも実際に事を成す人を見れば
少なからず必ずリアリスト的な要素も持ち合わせているはずです。
なぜならビジョンを実現するためには現在地点とゴールを設定し、
そこに至るまでの道なりを「現実的に」試算していく必要があるからです。
しかし普通のリアリストと圧倒的に違うのがこの「現実的に」という部分です。
見ているスケールが違いすぎるため、両者の「現実」には大きな開きがあります。
だからリアリストには見えていない現実が「ビジョナリスト」には見えているはずです。
将棋や囲碁をやった事がある人ならわかるかもしれませんが、
素人は1手2手先しか想像できませんが、プロは10手以上先を考えています。
だから次の1手が悪手に見えたり目先の損になっていたとしても、
その効果は巡り巡って驚くべき形で絶妙手に成り代わる事があります。
これも見ているスケールが違うために生じる「現実」の違いと言えそうです。
ここでいう「現実」は、狭い意味だと「前提」とも置き換えられるかもしれません。
■現実を見よう
リアリストの考える「現実」は頭の中で想像したシミュレーション
に過ぎないことが多々あります。
結局、「現実」を定義するのは自分で、自分が定義した「現実」を狭めてしまえば
その外に飛躍することは絶対に出来ません。
その方が「楽」だし「堅実」だし「失敗」は少ないでしょうが。
リアリストはビジョナリストの無謀さ・無知さ・見当外れさを理をもって説得します。
数字と完璧な論理でその無謀さを証明しようとしますが、
それは現実ではなく、「想像の世界」です。
10年前、20年前に今の生活が想像できたでしょうか。
全て「想定通り」だったでしょうか。
その影では
「ビジョンを持ち、淡々と目の前の現実(課題)と向き合い、事を成してきた」
ビジョナリストによって支えられているのではないでしょうか。
■私の過去
最後に、個人的な話になり恐縮ですが私がこんな話をしたのには訳があります。
私も昔はリアリストだったんですが、少し路線転換をしようとしているからです。
小学生の頃の私は、全ての行動に理由をつけ、
行動の裏には将来のパターンをいくつも想定した上で
最も確実性(リターン)の高い行動を選択しようと努めていました。
しかし、皆さんの想像通り、その目論見は失敗に終わります。
事前に何十通りもシミュレーションしたところで、
現実は悲しいかな、全く違う経過を辿るばかりだったのです。
もちろんシミュレーションを事前にしたことによるメリットは大きいですし、
何のシミュレーションもない無策で現実に望むのはそれこそ無謀です。
しかしシミュレーションを行うには前提条件が必要ですが、
目的やビジョンのなかった当時の私はその前提条件を
狭い視野でしか設定する事が出来ませんでした。
この時、悩んだ末に出た答えは、
「探してたもんはこんなにもシンプルなもんだったんだ」
という結論でした。
過程は複雑怪奇で小説よりも奇ですが、行き着く先はシンプルな答えです。
- SLAM DUNK 8 (ジャンプ・コミックス)/井上 雄彦
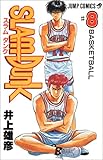
- ¥410
- Amazon.co.jp