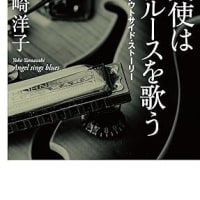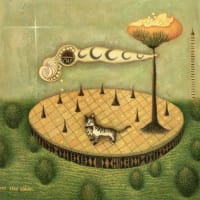何度かベランダの山椒を見に行った。
そこにいるアゲハの幼虫達を。
先月、青虫からサナギになった子たちは
四頭とも無事に羽化して空へ飛び立って行った。
いま山椒の木にいるのは、まだ青虫になる前の子たち。
黒に白い帯という体色の小さな子たちだ。
最初に気づいた時は10頭もいた。
山椒が足りるかと心配したけど、嬉しかった。
うちの山椒は蝶のためのものだから。
なのにいつの間にか四頭に減った。
鳥についばまれたのだと思う。
生き抜くのはなかなか難しいことなのだ。
その四頭を、毎日、楽しみに眺めていた。
この段階ではまだあまり食べない。
でも脱皮して青虫になればもりもち食べる。
鉢の周りには小さな丸い糞がたくさん落ちる。
掃除しなければならないけど、ちっともいやじゃない。
元気なしるしだから。
で、ゆうべの話に戻る。
あまりに風雨が激しいので、山椒の鉢を
家の中に入れた。
その時、三頭しかいないことに気づいた。
さっき見たときは四頭だったのに。
暗いベランダで雨に打たれながら必死に捜した。
なにしろ黒っぽい色だし、まだ一センチくらいの大きさなのだ。
びしょ濡れになりながらもようやく見つけた。
鉢から30センチくらいも離れたベランダの床に
その子が転がっていたのだ。
割り箸の先でそっとつまんで葉の上に置いた。
でも雨に打たれまくって体が弱っているらしく
すぐにぽとりと落ちてしまう。
紙皿に山椒の葉を敷き、その子を葉の上に置いた。
だけどとうとう息絶えてしまった。
鉢の土に埋葬した。
今朝、起きて、すぐ幼虫たちの様子を見た。
いない!
三頭のうち一頭だけは二センチに成長していたのだが
その子だけを残し、あとの二頭がいない。
そんな馬鹿なと、さほど大きくもない山椒の木を、
さらに鉢の土、周囲の床もくまなく見た。
ここはベランダではない。
うちの居間なのだ。
見つからないわけはないのにいない。
二頭の幼虫は消えてしまった。
幼虫が食草から離れるのはサナギになるときだけ。
でもこの子たちはまだその段階ではないので、
みずから木を降りて移動することはない。
なのに消えるって、どこにも見当たらないって、
いったいどういうこと?!
思い出すのは23歳で体験した初めての海外旅行。
当時のパートナーと一緒に、有金はたいてニューギニアへ行った。
まだオーストラリア統治領で、オーストラリアドルはⅠドル400円だった。
山の中の村にハワイの博物館が研究者用に建てた家がある。
そこを借りて一か月半滞在した。
パートナーは毎日、昆虫採集。
私は暑さにやられ、家の中でぐったり。
ある日、彼が体長20センチくらいもあるトビナナフシを採ってきた。
ニューギニアのトビナナフシ
https://search.yahoo.co.jp/image/search?ei=UTF-8&p=%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%AE%E3%83%8B%E3%82%A2+%E3%83%8A%E3%83%8A%E3%83%95%E3%82%B7&fr=mcafeess1#mode%3Ddetail%26index%3D2%26st%3D0
それをガラス瓶に入れて殺処分し、ビニール袋に移した。
一夜明けると、ビニール袋は空っぽになっていた。
口はしっかり縛られている。袋が破れてもいない。
中身が入っていた時そのままの場所に、そのままの
膨らみ方で置かれている。
さんざん考えた末、アリだと気が付いた。
体長5ミリにも満たない小さなアリが袋を食い破り
自分が通れるだけの穴を開ける。
そこから、気が遠くなるほどたくさんのアリが
一匹ずつ入っていき、大きなナナフシを一噛みずつ
外へ持って出る。一晩かけて彼らはその大仕事をやった。
ナナフシのかけらすら残さず。
アリの一穴という言葉は「ちょっとしたことで天下が崩壊する」
というような意味らしいが、まさにその一穴は、痕跡も残さず
このようなことをやってのけることができるのだ。
とはいえ、こんな嵐の夜に大量のアリが侵入したとは思えない。
ベランダのサッシはもちろん閉めて、鍵も掛かっていた。
昨年ここへ移ってきてから、ゴキブリもネズミもまだ見ていない。
けどこれは、なにか生き物の仕業だとかしか思えない。
なぜかといえば、倍ほどの大きさだったもう一頭は、無事に残っている。
彼、もしくは彼らは、仕事にあたって選別したのだ。
我が家にはなにかがいる。
それが心配で山椒の鉢をまたベランダに戻した。
雨風の影響をあまり受けないよう、周りを別の鉢で囲った。
それでも十分おきくらいにベランダに出て、残った一頭の
無事を確かめずにはいられない。
お願いだから、あんただけは無事に脱皮して青虫になって!