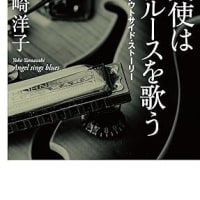まちづくりプロデューサーの福井功さんから
「赤い靴」のストラップをいただいた。
茨城県北茨木市にある野口雨情記念館と
雨情の生家へ行ってらしたという。

野口雨情作詞の童謡「赤い靴」は、
岩崎きみという静岡生まれの少女が、
モデルだという説がある。
彼女の親は開拓農民として北海道に渡るが
貧しさで食うや食わず。
それを見たアメリカ人宣教師が、幼いきみを
養女として引き取った。
歌の中では横浜から船に乗っているが、
じつは宣教師と一緒に東京へ行った後、
きみは病気になり、そのまま孤児院で亡くなったという。
だから、静岡、青森、東京、神奈川に
赤い靴の女の子像があり、その数八体!
雨情が彼女をモデルにしたという証拠はない。
が、時代背景を思えば、こうした境遇の少女が
いたとしても不思議ではないだろう。
野口雨情は1921(大正10)年に、
「赤い靴」と「青い眼の人形」を発表している。
どちらも作曲は本居長世。舞台は横浜。
後者には「日本の港」としか詠われていないが
横浜をイメージして書かれたことは間違いないだろう。
童謡だというのに、なんとも哀切なメロディーである。
詞にも、これからどうなるのだろうという、
恐怖にも似た不安が漂っている。
この歌が世に出た頃、日本はまだ貧しかった。
食べていくために家財を売り払い、一家揃って
海外へ出稼ぎ移住をする人が多くなった。
おもに農場での重労働で、決して楽なものではない。
気候、食べ物、風俗習慣も違う。
体を壊して亡くなった人も少なくはなかっただろう。
横浜には、港に近い関内地区を中心に、
移民宿と呼ばれる旅館があった。
現在の関内にはその痕跡すら残っていないが、
最盛期には20軒を超えたという。
地方から出てきた人々は、ここに泊まり、船を待つ。
その間、宿は、海外情報、先に行った人達の消息などを
できる限り提供するほか、パスポートの取得、荷物の運搬、
必要な物品の手配と、なんでも代行した。
海外どころか、生まれたところから出るのが初めて、
という人がほとんどだった時代だから、
こうした移民宿が必須だった。
日本人移民達は、概して真面目でよく働いた。
その勤勉さが現地の人々の危機感をあおった。
やがて、「自分達の仕事を奪う者」として、
アメリカやカナダで排斥の対象になってしまう。
太平洋戦争時には、苦労して築き上げた財産を
すべて没収された。
それでも彼らは、世界のあちこちに、
日本人ならではの功績を残している。
オバマ大統領は今日の退任演説で、
「移民がアメリカを強くした」と言った。
故国を離れ、他国で必死に居場所を
築いてきた人達は、その言葉を嬉しく
受け止めたことだろう。
(次期大統領は真逆の考えらしいが……)
日本は経済大国になり、もう他国へ出稼ぎに
行って最低賃金で働かなくてもよくなった。
でも、移民として他国へ渡らざるをえない人々は
世界中に溢れている。
戦禍から逃れてさまようシリア難民は
もっと切実だろう。
童謡「赤い靴」が世に出てから二年後、
東京・横浜は関東大震災で壊滅状態になった。
時代はほどなく、大正から昭和に移ったが、
戦争が始まり、大空襲、原爆投下、敗戦と
暗い世の中が続いた。
そこからよく立ち直ったものだと、
歴史を振り返るたびに驚く。
記念館の「赤い靴」は、金色のリボンがついた
華やかなもの。
いまの日本にはこれが似合うのかもしれない。
でも、雨情が詠んだ「不安な赤い靴」が
消えてしまったわけではない。
足音をしのばせ、そうっと近づいてきつつ
あるようで、私はなんだか怖い。
「赤い靴」のストラップをいただいた。
茨城県北茨木市にある野口雨情記念館と
雨情の生家へ行ってらしたという。

野口雨情作詞の童謡「赤い靴」は、
岩崎きみという静岡生まれの少女が、
モデルだという説がある。
彼女の親は開拓農民として北海道に渡るが
貧しさで食うや食わず。
それを見たアメリカ人宣教師が、幼いきみを
養女として引き取った。
歌の中では横浜から船に乗っているが、
じつは宣教師と一緒に東京へ行った後、
きみは病気になり、そのまま孤児院で亡くなったという。
だから、静岡、青森、東京、神奈川に
赤い靴の女の子像があり、その数八体!
雨情が彼女をモデルにしたという証拠はない。
が、時代背景を思えば、こうした境遇の少女が
いたとしても不思議ではないだろう。
野口雨情は1921(大正10)年に、
「赤い靴」と「青い眼の人形」を発表している。
どちらも作曲は本居長世。舞台は横浜。
後者には「日本の港」としか詠われていないが
横浜をイメージして書かれたことは間違いないだろう。
童謡だというのに、なんとも哀切なメロディーである。
詞にも、これからどうなるのだろうという、
恐怖にも似た不安が漂っている。
この歌が世に出た頃、日本はまだ貧しかった。
食べていくために家財を売り払い、一家揃って
海外へ出稼ぎ移住をする人が多くなった。
おもに農場での重労働で、決して楽なものではない。
気候、食べ物、風俗習慣も違う。
体を壊して亡くなった人も少なくはなかっただろう。
横浜には、港に近い関内地区を中心に、
移民宿と呼ばれる旅館があった。
現在の関内にはその痕跡すら残っていないが、
最盛期には20軒を超えたという。
地方から出てきた人々は、ここに泊まり、船を待つ。
その間、宿は、海外情報、先に行った人達の消息などを
できる限り提供するほか、パスポートの取得、荷物の運搬、
必要な物品の手配と、なんでも代行した。
海外どころか、生まれたところから出るのが初めて、
という人がほとんどだった時代だから、
こうした移民宿が必須だった。
日本人移民達は、概して真面目でよく働いた。
その勤勉さが現地の人々の危機感をあおった。
やがて、「自分達の仕事を奪う者」として、
アメリカやカナダで排斥の対象になってしまう。
太平洋戦争時には、苦労して築き上げた財産を
すべて没収された。
それでも彼らは、世界のあちこちに、
日本人ならではの功績を残している。
オバマ大統領は今日の退任演説で、
「移民がアメリカを強くした」と言った。
故国を離れ、他国で必死に居場所を
築いてきた人達は、その言葉を嬉しく
受け止めたことだろう。
(次期大統領は真逆の考えらしいが……)
日本は経済大国になり、もう他国へ出稼ぎに
行って最低賃金で働かなくてもよくなった。
でも、移民として他国へ渡らざるをえない人々は
世界中に溢れている。
戦禍から逃れてさまようシリア難民は
もっと切実だろう。
童謡「赤い靴」が世に出てから二年後、
東京・横浜は関東大震災で壊滅状態になった。
時代はほどなく、大正から昭和に移ったが、
戦争が始まり、大空襲、原爆投下、敗戦と
暗い世の中が続いた。
そこからよく立ち直ったものだと、
歴史を振り返るたびに驚く。
記念館の「赤い靴」は、金色のリボンがついた
華やかなもの。
いまの日本にはこれが似合うのかもしれない。
でも、雨情が詠んだ「不安な赤い靴」が
消えてしまったわけではない。
足音をしのばせ、そうっと近づいてきつつ
あるようで、私はなんだか怖い。