
さて 後半編をまとめてみました。
<ムラサキ> ムラサキ科 ムラサキ(紫草) 別名:ムラサキネ(紫根)、ネムラサキ(根紫)



〔名前の由来〕
根が紫色である事から、ムラサキと名付けられた。
以前は山地や草原に自生していましたが、現在は絶滅が心配されています。ムラサキの根は紫根と呼ばれ、江戸時代には江戸紫色の原料として利用されていたと言う。
台上に極まれにしか見れなくなりました。
そして今年最後のエビネもみてきました。これで今年はお終いにします。


<タカネエビネ> 高嶺海老根 ラン科


<エビネ> エビネ 淡緑色でなんとも上品で 私個人的には (アオエビネ)と呼んでいます。
来年も逢えますように そ~~とその場を立ち去りました。
<ハシナガヤマサギソウ>

<ツレサギソウ> 連鷺草。ラン科
白い花を多数つける・かなり密生して咲く。



豪華で丁度見ごろの勢いでした。
<クララ>
クララ(眩草、苦参)マメ科の多年草。

名前は アニメの一場面を思い出しますが・・・・
和名の由来は、根を噛むとクラクラするほど苦いことから、眩草(くららぐさ)と呼ばれ、これが転じてクララと呼ばれるようになったといわれる。
そして最後にまた登場しました。
<白花オカウツボ> これも豪華な花。

前回も登場しましたが別場所で見れた。
数本が肩寄せ合って見事なものでした。
私もこれだけ一緒に咲いたのを確認したのは初めてです。
台上も梅雨入りとなりました。
山野草がまた 一層 生き生きとする季節です。
さあ 梅雨の間これからどんな お花さんが登場するのでしょうか。
楽しみです。
<ムラサキ> ムラサキ科 ムラサキ(紫草) 別名:ムラサキネ(紫根)、ネムラサキ(根紫)



〔名前の由来〕
根が紫色である事から、ムラサキと名付けられた。
以前は山地や草原に自生していましたが、現在は絶滅が心配されています。ムラサキの根は紫根と呼ばれ、江戸時代には江戸紫色の原料として利用されていたと言う。
台上に極まれにしか見れなくなりました。
そして今年最後のエビネもみてきました。これで今年はお終いにします。


<タカネエビネ> 高嶺海老根 ラン科


<エビネ> エビネ 淡緑色でなんとも上品で 私個人的には (アオエビネ)と呼んでいます。
来年も逢えますように そ~~とその場を立ち去りました。
<ハシナガヤマサギソウ>

<ツレサギソウ> 連鷺草。ラン科
白い花を多数つける・かなり密生して咲く。



豪華で丁度見ごろの勢いでした。
<クララ>
クララ(眩草、苦参)マメ科の多年草。

名前は アニメの一場面を思い出しますが・・・・
和名の由来は、根を噛むとクラクラするほど苦いことから、眩草(くららぐさ)と呼ばれ、これが転じてクララと呼ばれるようになったといわれる。
そして最後にまた登場しました。
<白花オカウツボ> これも豪華な花。

前回も登場しましたが別場所で見れた。
数本が肩寄せ合って見事なものでした。
私もこれだけ一緒に咲いたのを確認したのは初めてです。
台上も梅雨入りとなりました。
山野草がまた 一層 生き生きとする季節です。
さあ 梅雨の間これからどんな お花さんが登場するのでしょうか。
楽しみです。
















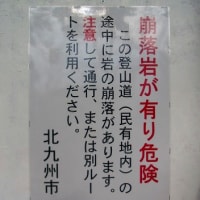



台上のお花を楽しませてもらってます。
サギソウにも種類があるんですね。
クララは初めて見ました。
前回のフナバラソウは本で見たことが
あります。 本によると、分布は日本全国とありましたから、宮崎にもあるのかな。
キョロキョロしてみます。
>サギソウにも種類~~
そうなんですね、台上にいくつかの サギソウの
仲間があありますね。
トンボソウなどもいくつかあってよく見ないと
混乱します。
お盆の頃には 純白の サギソウが見られます。
クララや フナバラソウはきっとそちらの
山系でも見れるかと思います。
お花のイメージを大切に歩いていれば
見れるかもしれませんね。