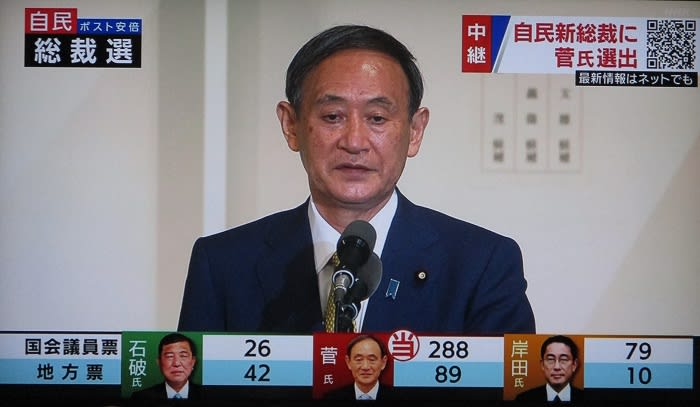5年に一度の酷勢、否、国勢調査票がやって来た。
回答義務がある。
面倒だな。

やってきました!見逃してはくれません
調査票は文字が小さい。
虫眼鏡の応援が要りそうだ。
背を丸めて書き入れている姿は哀れな図だ。
高齢者社会だから、それに応じた配慮が必要ではないか。
ちょっとした配慮が感じられれば書く気も起こる。
それとも壮年者扱いを喜ぶべきか?
国はインターネットでの回答を希望している。
目標50パーセント!らしい。
文字のこともあるので、よし!インターネトでやってみるか。
(未だサイトにログインしていないので読みやすさは不明だが、駄目で元々)
回答義務がある。
面倒だな。

やってきました!見逃してはくれません
調査票は文字が小さい。
虫眼鏡の応援が要りそうだ。
背を丸めて書き入れている姿は哀れな図だ。
高齢者社会だから、それに応じた配慮が必要ではないか。
ちょっとした配慮が感じられれば書く気も起こる。
それとも壮年者扱いを喜ぶべきか?
国はインターネットでの回答を希望している。
目標50パーセント!らしい。
文字のこともあるので、よし!インターネトでやってみるか。
(未だサイトにログインしていないので読みやすさは不明だが、駄目で元々)