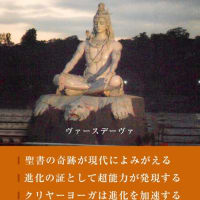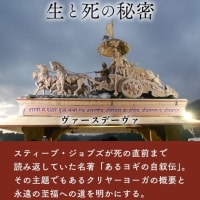本稿も実は、本ブログPartI 第17章ヨーガ・スートラの第1話、「ヨーガとその歴史」と内容的には重なる部分もあるが、引き続き中村元氏(以下、著者)の『ヨーガとサーンキャの思想』(以下、同書)から、関連部分を引用のうえ解説を試みたい。
先ずは、以前第6章⑧で紹介した「臨終正念」とも関連する記述である。
◇◇◇
ウパニシャッドのうちには、人が心のうちになにごとかを念じていると、死後にはそのとおりのものとして生まれるという思想がある。顕著な一例として、
『人はじつに意向からなる。人がこの世に於いていかなる意向をもったとしても、この世を去ったのちに、かれはその通りに意向がかなう。[それゆえに、]人は意向を[次のように、正しい方向に]定めるべきである』
とシャーンディリヤが教えたことは有名である。[この見解は、仏教の若干の人々にも継承され、特に浄土教では「臨終正念」ということを重んずるにいたった。]・・・
ウパニシャッドの哲人たちがヨーガの修行を行っていたことは、たしかな事実である。<ヨーガ>は述語としては「心のはたらきを止滅すること」すなわち、外界からの影響にもとづく心の作用を抑制することなのである。積極的にいうならば、「唯一なる原理を念じ続けること」であり、その<唯一なる原理>とはアートマンと解すべきであろう。・・・
◇◇◇
さらに、修行であるから当然のことではあるが、「ヨーガは突然実現されるものではない」と言う。
◇◇◇
・・・そのためには、なすべきこととなすべからざることとをはっきりと区別して認識し、理解力をもち、感官を制御しなければならない。
『それらのかたちは、視野のうちには存在しない。なんぴとも、かれを眼によって見ることはできない。[しかし]かれは心によって、叡智によって、思考作用によって、理解される。これを知る人々は不死となる。
五つの認識器官が意とともに[外に向かっての活動から]静止するとき、統覚機能もまた動きはたらかないときに、それを人々は最高の状態と呼ぶ。
感官をしっかりとたもって堅固に住することがヨーガである、とかれらは考える。そのときかれらは、心の乱れない者となる。ヨーガとはじつに起源であり、また帰入である。』
◇◇◇
以上の中で、「かれは心によって、叡智によって、思考作用によって、理解される」との記述の目的語は「かれ」であり、それがアートマンであり、「心」などによって理解されるとなると、内容的に筆者としては納得しかねるが、ウパニシャッドの記述としてそのまま引用した。いずれ章を改めて、その理由を説明することになろう。
次は以前引用した「馬車」の譬喩であるが、非常に的確で判り易いと思うので、かなり長くなるが再度著者の訳で引用する(内容的にはこの部分がPartI第17章①と重複、但しPartIは佐保田鶴治の『ヨーガ・スートラ』から引用している)。
◇◇◇
このウパニシャッドの具象的、比喩的説明を見ると、ヨーガすなわち「結びつけること」という場合には、「馬を手綱で車につなぐ」という連想をもって説かれている。
『アートマンは車に乗る者であり、身体は実に車であると知れ。統覚機能(buddhi 理解力)は御者であり、そして意(こころ)はまさに手綱であると知れ。
人々は、もろもろの感官をもろもろの馬と呼び、感官の対象を馬に関して馬場と呼ぶ。アートマンと感官と意(こころ)とが結合したときに、賢者はこれ(それが結合したもの)を享受者(経験の主体)と呼ぶ。』
経験の主体は身体をもっているアートマンであり、純粋のアートマンそのものとは異なったものである。そうしてもろもろの感官は、馬のように跳びはねるものであるから、しっかりと手綱をしめなければならないと考えていた。・・・中略・・・
「意馬心猿」という句がある。われわれの心は馬のようにあちこちに奔放に跳躍するから、我々は注意して馬を手綱で制するように全身をもって努力しなければならない。
『しかるに理解力なく、意を専注することなく、つねに不浄なる者は、その境地(=解脱)に達することなく、輪廻(迷いの生存)におもむく。
されど理解力あり、注意深く、つねに清らかとなる者は、その境地に達し、もはやその境地から堕して再び[迷いの世界に]生まれることはない。』
ヨーガを修する修行者は、御者が手綱をもって悍馬を御するような気持でいなければならない。
『しかるに理解力という御者を有し、意(こころ)という手綱をもつ人は、旅路の終局に到達する。それは、ヴィシュヌの最高の地位である。』
ここに見られるように、『カータカ・ウパニシャッド』では、
(1) ヨーガとは、悍馬にたとえられる自分の心を、軛をつけ、手綱をもって制御すると考えられていた。
(2) ヴィシュヌ神は最高神であるから、その最高神のもとに到達することが究極の理想と考えられていた。この思想はやがて古典ヨーガにおいて主宰神への専念を説くことにつながるのである。
(3) ここではヨーガの修行がヴィシュヌ神信仰と結びついているのであり、ヒンドゥー教にむかっての一歩を踏み出している。
◇◇◇
以上から、ヨーガはウパニシャッドの時代からあり、「解脱」という最高の境地に向かって、心の統御を通じて修行することであったことが判る。またそれは、最高神であるヴィシュヌに到達することと同義とされ、後にヨーガで説かれる「主宰神祈念」に受け継がれると共に、ヒンドゥー教的な色彩を帯びる端緒ともなったということが判る。但し・・・
◇◇◇
ただし古いもろもろのウパニシャッドの説くヨーガは、主宰神に対する献身、専念(イシュヴァラ・プラニダーナ)を説いていない。それは、ヨーガ学派によると、「一切の行為の果報を最高の師(主宰神)にささげること」であるが、それを明示していない。だから人の心を動かすほどの力をもっていなかった。ヨーガの伝統がインド人の心をとらえるためには、のちのヨーガ学派の確立をまたなければならなかった。
ヨーガの実践を説くことは、後期の古ウパニシャッドの著しい特徴のひとつである。前期の古ウパニシャッドにおいてもすでにこの傾向が認められるが、後期の古ウパニシャッドになると、明らかに解脱はヨーガの修行によって得られるということを強調している。そうしてその際には、ブラフマンを念じ、そうしていっそう適切な手段としては、ブラフマンの象徴としての聖音「オーム」を念じるのである。
◇◇◇
次に、道徳(倫理観)と修行双方の重要性を説いた部分を同書から紹介しておきたい。
◇◇◇
さらに『カータカ・ウパニシャッド』第二編においては、アートマンという隠れた原理が、救わるべき人を選ぶと説いているが、しかしアートマンは恣意的に恩寵を授けるのではない。アートマンに選ばれるためには実践的な準備を必要とする。倫理的にも身を修め、調えていなければならない。
『[ヤマは続けた、]「悪い行いを止めない者、静かにしていない者、心の統一されていない者、また心の静まっていない者も、正しい知慧によってこのアートマンを体得することはできないであろう」と。』
全体としてのヨーガの修行が必要であるということは、このウパニシャッドの中では繰り返し教えられている。そうしてヨーガに基づいて恩寵が得られるのである。
◇◇◇
こうしてヨーガの実践に関する規定も整っていく。
◇◇◇
さらに『マイトリ・ウパニシャッド』においては、ヨーガの実践に関する規定も整い、ヨーガの六つの部門、すなわち呼吸の調整(プラーナヤーマ)、感官の抑制(プラティアハーラ)、禅定(ディヤーナ)、思いつづけること(ダーラナ)、思慮(ターラカ)、三昧(サマーディ)をあげている。ここにあげられている六つの部門のうちから「思慮」を取り去って、それに坐法(アーサナ)と制戒(ヤマ)と内制(ニヤマ)を加えると、『ヨーガ・スートラ』に説く八つの部門となる。
◇◇◇
この後、「坐法と制戒と内制とは『ヨーガ・スートラ』においても決してヨーガの修行の中心的意義あるものとして詳説されることはされることはなかった」としてその理由を説明している。
◇◇◇
・・・だから実質的には、『ヨーガ・スートラ』の説くヨーガがすでにこのウパニシャッドにおいては成立していたと考えることができる。すなわちこれらの事項は、いちいち詳論しないでも、いっただけですぐその内容が判ったのである。
◇◇◇
第6章⑫「俗世の超越とヨーガ」において、著者がこのマイトリ・ウパニシャッドに坐法と制戒と内制が含まれていないことに関して「ヨーガ行者の生活規制や修行の外的条件はてんでかまわなかったのである」と記述していることに筆者は違和感を覚え、「こうした基本的な倫理や修行の内容をいい加減にして、その他のヨーガ技法だけを習得すれば良いといったことではなく、恐らくは特にバラモンの修行者にとっては当然の『前提』として敢えて触れなかったと考えた方は筋が通っていると思う」と述べたが、上記の引用部分を読み、著者も基本的に筆者と同じ意見だということが判明した。「だから実質的には、『ヨーガ・スートラ』の説くヨーガがすでにこのウパニシャッドにおいては成立していたと考えることができる」。
PS(1): 尚、このブログは書き込みが出来ないよう設定してあります。若し質問などがあれば、wyatt999@nifty.comに直接メールしてください。
PS(2):『ヴォイス・オブ・ババジ』の日本語訳がアマゾンから発売されました(キンドル版のみ)。『或るヨギの自叙伝』の続編ともいえる内容であり、ババジの教えなど詳しく書かれていますので、興味の有る方は是非読んでみて下さい。価格は¥800です。
先ずは、以前第6章⑧で紹介した「臨終正念」とも関連する記述である。
◇◇◇
ウパニシャッドのうちには、人が心のうちになにごとかを念じていると、死後にはそのとおりのものとして生まれるという思想がある。顕著な一例として、
『人はじつに意向からなる。人がこの世に於いていかなる意向をもったとしても、この世を去ったのちに、かれはその通りに意向がかなう。[それゆえに、]人は意向を[次のように、正しい方向に]定めるべきである』
とシャーンディリヤが教えたことは有名である。[この見解は、仏教の若干の人々にも継承され、特に浄土教では「臨終正念」ということを重んずるにいたった。]・・・
ウパニシャッドの哲人たちがヨーガの修行を行っていたことは、たしかな事実である。<ヨーガ>は述語としては「心のはたらきを止滅すること」すなわち、外界からの影響にもとづく心の作用を抑制することなのである。積極的にいうならば、「唯一なる原理を念じ続けること」であり、その<唯一なる原理>とはアートマンと解すべきであろう。・・・
◇◇◇
さらに、修行であるから当然のことではあるが、「ヨーガは突然実現されるものではない」と言う。
◇◇◇
・・・そのためには、なすべきこととなすべからざることとをはっきりと区別して認識し、理解力をもち、感官を制御しなければならない。
『それらのかたちは、視野のうちには存在しない。なんぴとも、かれを眼によって見ることはできない。[しかし]かれは心によって、叡智によって、思考作用によって、理解される。これを知る人々は不死となる。
五つの認識器官が意とともに[外に向かっての活動から]静止するとき、統覚機能もまた動きはたらかないときに、それを人々は最高の状態と呼ぶ。
感官をしっかりとたもって堅固に住することがヨーガである、とかれらは考える。そのときかれらは、心の乱れない者となる。ヨーガとはじつに起源であり、また帰入である。』
◇◇◇
以上の中で、「かれは心によって、叡智によって、思考作用によって、理解される」との記述の目的語は「かれ」であり、それがアートマンであり、「心」などによって理解されるとなると、内容的に筆者としては納得しかねるが、ウパニシャッドの記述としてそのまま引用した。いずれ章を改めて、その理由を説明することになろう。
次は以前引用した「馬車」の譬喩であるが、非常に的確で判り易いと思うので、かなり長くなるが再度著者の訳で引用する(内容的にはこの部分がPartI第17章①と重複、但しPartIは佐保田鶴治の『ヨーガ・スートラ』から引用している)。
◇◇◇
このウパニシャッドの具象的、比喩的説明を見ると、ヨーガすなわち「結びつけること」という場合には、「馬を手綱で車につなぐ」という連想をもって説かれている。
『アートマンは車に乗る者であり、身体は実に車であると知れ。統覚機能(buddhi 理解力)は御者であり、そして意(こころ)はまさに手綱であると知れ。
人々は、もろもろの感官をもろもろの馬と呼び、感官の対象を馬に関して馬場と呼ぶ。アートマンと感官と意(こころ)とが結合したときに、賢者はこれ(それが結合したもの)を享受者(経験の主体)と呼ぶ。』
経験の主体は身体をもっているアートマンであり、純粋のアートマンそのものとは異なったものである。そうしてもろもろの感官は、馬のように跳びはねるものであるから、しっかりと手綱をしめなければならないと考えていた。・・・中略・・・
「意馬心猿」という句がある。われわれの心は馬のようにあちこちに奔放に跳躍するから、我々は注意して馬を手綱で制するように全身をもって努力しなければならない。
『しかるに理解力なく、意を専注することなく、つねに不浄なる者は、その境地(=解脱)に達することなく、輪廻(迷いの生存)におもむく。
されど理解力あり、注意深く、つねに清らかとなる者は、その境地に達し、もはやその境地から堕して再び[迷いの世界に]生まれることはない。』
ヨーガを修する修行者は、御者が手綱をもって悍馬を御するような気持でいなければならない。
『しかるに理解力という御者を有し、意(こころ)という手綱をもつ人は、旅路の終局に到達する。それは、ヴィシュヌの最高の地位である。』
ここに見られるように、『カータカ・ウパニシャッド』では、
(1) ヨーガとは、悍馬にたとえられる自分の心を、軛をつけ、手綱をもって制御すると考えられていた。
(2) ヴィシュヌ神は最高神であるから、その最高神のもとに到達することが究極の理想と考えられていた。この思想はやがて古典ヨーガにおいて主宰神への専念を説くことにつながるのである。
(3) ここではヨーガの修行がヴィシュヌ神信仰と結びついているのであり、ヒンドゥー教にむかっての一歩を踏み出している。
◇◇◇
以上から、ヨーガはウパニシャッドの時代からあり、「解脱」という最高の境地に向かって、心の統御を通じて修行することであったことが判る。またそれは、最高神であるヴィシュヌに到達することと同義とされ、後にヨーガで説かれる「主宰神祈念」に受け継がれると共に、ヒンドゥー教的な色彩を帯びる端緒ともなったということが判る。但し・・・
◇◇◇
ただし古いもろもろのウパニシャッドの説くヨーガは、主宰神に対する献身、専念(イシュヴァラ・プラニダーナ)を説いていない。それは、ヨーガ学派によると、「一切の行為の果報を最高の師(主宰神)にささげること」であるが、それを明示していない。だから人の心を動かすほどの力をもっていなかった。ヨーガの伝統がインド人の心をとらえるためには、のちのヨーガ学派の確立をまたなければならなかった。
ヨーガの実践を説くことは、後期の古ウパニシャッドの著しい特徴のひとつである。前期の古ウパニシャッドにおいてもすでにこの傾向が認められるが、後期の古ウパニシャッドになると、明らかに解脱はヨーガの修行によって得られるということを強調している。そうしてその際には、ブラフマンを念じ、そうしていっそう適切な手段としては、ブラフマンの象徴としての聖音「オーム」を念じるのである。
◇◇◇
次に、道徳(倫理観)と修行双方の重要性を説いた部分を同書から紹介しておきたい。
◇◇◇
さらに『カータカ・ウパニシャッド』第二編においては、アートマンという隠れた原理が、救わるべき人を選ぶと説いているが、しかしアートマンは恣意的に恩寵を授けるのではない。アートマンに選ばれるためには実践的な準備を必要とする。倫理的にも身を修め、調えていなければならない。
『[ヤマは続けた、]「悪い行いを止めない者、静かにしていない者、心の統一されていない者、また心の静まっていない者も、正しい知慧によってこのアートマンを体得することはできないであろう」と。』
全体としてのヨーガの修行が必要であるということは、このウパニシャッドの中では繰り返し教えられている。そうしてヨーガに基づいて恩寵が得られるのである。
◇◇◇
こうしてヨーガの実践に関する規定も整っていく。
◇◇◇
さらに『マイトリ・ウパニシャッド』においては、ヨーガの実践に関する規定も整い、ヨーガの六つの部門、すなわち呼吸の調整(プラーナヤーマ)、感官の抑制(プラティアハーラ)、禅定(ディヤーナ)、思いつづけること(ダーラナ)、思慮(ターラカ)、三昧(サマーディ)をあげている。ここにあげられている六つの部門のうちから「思慮」を取り去って、それに坐法(アーサナ)と制戒(ヤマ)と内制(ニヤマ)を加えると、『ヨーガ・スートラ』に説く八つの部門となる。
◇◇◇
この後、「坐法と制戒と内制とは『ヨーガ・スートラ』においても決してヨーガの修行の中心的意義あるものとして詳説されることはされることはなかった」としてその理由を説明している。
◇◇◇
・・・だから実質的には、『ヨーガ・スートラ』の説くヨーガがすでにこのウパニシャッドにおいては成立していたと考えることができる。すなわちこれらの事項は、いちいち詳論しないでも、いっただけですぐその内容が判ったのである。
◇◇◇
第6章⑫「俗世の超越とヨーガ」において、著者がこのマイトリ・ウパニシャッドに坐法と制戒と内制が含まれていないことに関して「ヨーガ行者の生活規制や修行の外的条件はてんでかまわなかったのである」と記述していることに筆者は違和感を覚え、「こうした基本的な倫理や修行の内容をいい加減にして、その他のヨーガ技法だけを習得すれば良いといったことではなく、恐らくは特にバラモンの修行者にとっては当然の『前提』として敢えて触れなかったと考えた方は筋が通っていると思う」と述べたが、上記の引用部分を読み、著者も基本的に筆者と同じ意見だということが判明した。「だから実質的には、『ヨーガ・スートラ』の説くヨーガがすでにこのウパニシャッドにおいては成立していたと考えることができる」。
PS(1): 尚、このブログは書き込みが出来ないよう設定してあります。若し質問などがあれば、wyatt999@nifty.comに直接メールしてください。
PS(2):『ヴォイス・オブ・ババジ』の日本語訳がアマゾンから発売されました(キンドル版のみ)。『或るヨギの自叙伝』の続編ともいえる内容であり、ババジの教えなど詳しく書かれていますので、興味の有る方は是非読んでみて下さい。価格は¥800です。