*以下、ブルーの文字は本文からの引用です。
第二章 始祖登場――ソシュールと『一般言語学講義』(p59~77)
まず聖書からの引用。
「神である主が、土からあらゆる野の獣と、あらゆる空の鳥をかたちづくられたとき、それにどんな名を彼(注:アダム byおれ)がつけるかを見るために、人のところに連れて来られた。人が、生き物につける名は、みな、それがその名となった。こうして、人は、すべての家畜、空の鳥、野のあらゆる獣に名をつけた。」(『創世記』二、19~20)(p61)
牧歌的な聖書の言語観を、ソシュールは「名称目録的言語観」=カタログ的言語観(by内田)と名づけた。
ギリシャ以来の伝統的なものらしい。
この伝統的な言語観から、知れるものが二つあるという。
1.ものの名前は人間が勝手につけた。(p62)
例:犬(日本語)とdog(英語)、chien(フランス語)、Hund(ドイツ語)
客から「そこ右、あそこ左」と指示されて、どっちだったけ? なんて迷っているようじゃタクドラはできない。
「必要なのは愛よね」といわれて、どんな意味だったか考え込んでいる男から、女は間違いなく去っていく。
「もう会わないでおきましょうよ、わたしたち」という言葉だけは、何ひとつ理解したくないけどね。
ある言語圏にばかり暮らしているためか、ものの名前や言葉の意味は必然的に、厳格に決まっているんだと、おれたちはどこかで思いこんでいる。そんな思いこみや固定観念にとらわれるくらい言語に慣れ親しまないと、日常生活は困難だし、ときには危険だ。
ところが、関東から関西に転居したり、不幸にもアメリカなんかに放り込まれちゃったりしたら、たちどころに言語障害に陥って途方にくれる。あの店は七面鳥の尻尾でも売っているんだろうかと、「cocktail」と書かれた看板を眺めているようじゃ、帰国するまで酒にも女にも縁はない。そして成田空港の汚れなじんだ空気に「おかえりなさい」をしてもらって、やっと身にしみて述懐するのだ。ヘンチクリンな言葉を勝手気ままに使い回しやがって、外国じゃちっとも楽めなかったと……。
こうして言語の身勝手さに気がついたおれたちは、しかし、もうひとつの錯覚にとらわれている。
2.「名づけられる前からすでにものはあった」という前提への盲信。(p62)
これは、ものすごく過激な指摘だ。
おれたちが、日常的に盲目でいるはずの前提条件を指摘するのは、なんだって過激な様相を帯びる。
命名される前の「名前を持たないもの」は実在しない、とソシュールは考えたんだ。(p62)
こうなると、さまざまな反論、というか嫌悪感がわき起こってくるだろう。
亀は万年生きるんだ。それに比べりゃ、言葉なんてコナイダできたばっかじゃねーの?
ソウソウ。
名前を呼んだら実在するっつーの? おーい、羽音ちゃーん! …現れてくんないじゃん!
イヤイヤ。
何も知らないのに、ちゃんと口座から金は引き落とされる。これって矛盾だろがっ!?
マアマア。
しかしだ、ソシュールの仕事は1910年前後のことだったといわれている。アインシュタインの『特殊相対性理論』が発表されたのは1905年だ。質量と光がエネルギーという点で一緒だなんて、だれが考えられる? 太ったやつのほうがエネルギッシュで、オリンピック村じゃ象みたいな足ばっかりが歩いているってのかい? こんなふうにして二十世紀は、おれたちの「常識」を、「常識」の前提を、乗り越える形ではじまっちゃったんだよ。
っと、煙に巻いておくけど。
ソシュールの引用。
「フランス語の『羊』(mouton)(注:ムートン byおれ)は英語の『羊』(sheep)と語義はだいたい同じである。しかしこの語の持っている意味の幅は違う。理由の一つは、調理して食卓に供された羊肉のことを英語では『羊肉』(mutton)と言ってsheepとは言わないからである。sheepとmoutonは意味の幅が違う。それはsheepにはmuttonという第二の項が隣接しているが、moutonにはそれがない、ということに由来する。」(p62~63)
*下線、おれ。
「第二の項」とは、近接する類義語のことだろう。
ここで、辞書でも思い出してみようか。
仏日辞書:mouton……1.羊 2.羊肉
英日辞書:sheep……羊(羊肉は表さない) 類義語はmutton(羊肉)
なんて感じで。
こう書くと、moutonもsheepも、羊と羊肉という二つの意味をきちんと区別しているように見える。だけど、そう思うのは、おれたちが日本語圏につよく束縛されているからだ。moutonは羊と羊肉を区別しない。しないから、する日本人向けの辞書には詳細にわたって説明が要る。これが事実だ。
なので、意味の幅としては
mouton(仏)≠ sheep(英), mouton(仏)⊃ sheep(英)
であるし、羊肉を表す類義語としてsheepにはmuttonが用意されるのに、moutonのほうには必要がない。…etc。
sheepのほうが、sharpな言葉だといえなくもない。というおれは、とってもshapely(かっこいい)。いや単なるshape-up(日雇い労働者)だった。ごめんよぉ。
著者の内田さんは、このほかにも英語のdevilfishとseveralを例にとっている。
devilfish…悪魔の魚。エイとタコのことで、日本語にはない。
several…なんとなく日本語の5か6ぐらいと思われているが、2や10以上のときもある。
ソシュールの引用、続き。
「もし語というものがあらかじめ与えられた概念を表象するものであるならば、ある国語に存在する単語は、別の国語のうちに、それとまったく意味を同じくする対応物を見出すはずである。しかし現実はそうではない。(略)あらゆる場合において、私たちが見いだすのは、概念はあらかじめ与えられているのではなく、語の持つ意味の厚みは言語システムごとに違うという事実である。」(p63)
*下線、おれ。
おれたちの前で、概念(意味)は名前づけられるのを待っている、ってんじゃない。おれたちが、いわば勝手に「現実」の名前を呼んだことで、その「現実」のなかに、ありもしなかった意味、概念が、生成されてきたというんだ。じゃなかったら、言語圏の違いによる言葉の意味の違いは説明できないじゃないか。
「ありもしなかった意味、概念」といったのは、多少いい過ぎかもしれない。人はそれぞれ必要な生活を営んできたので、「現実」とのかかわり方も多種多様だったろう。そんなかかわり方から、言葉の異なる意味や概念が生まれ、維持されてきた、と想像するのは容易い。
しかし、たとえそうだったとしても、おれたち自身が、おもに生存という特殊な拘束を受けてきて、いわばこっちの身勝手な都合で、いまだに特殊な角度からしか「現実」を見られていないってことじゃないのか?
どっちにしてもだ。ある言語圏の人間が、自分たちの言葉を通してみえる「現実」を、唯一のものと思い込んだり、そうはみえない人をバカ、気違い、危険物扱いするのは、どうかしているということだ。
ここでニーチェのいう大衆社会、畜群、大衆社会をおおう不安という強制力、排他性、を思い出すのは見当違いだろうか? 彼のいう「超人」への方向性は、大衆社会からの脱出ではなく、おれたちの言語を成立させている前提条件への考察と反省から生まれてくるのではないか、というふうに。
また、ある共通言語圏において、その言葉では表せない個人、または個人的な経験はありえるはずだ。言語圏に特有の都合=エゴが、個々の構成員がもっている都合=エゴにぴったり一致するとは考えられない。多かれ少なかれ、長靴に足をあわせるようにして、おれたちは生きてきたんじゃないかということだ。この場合、本人でさえ排斥したいと願う自分の意識が、フロイトの無意識を構成するとは考えられないだろうか?
さらに、こうした限りある現実認識にもとづく行為が、いつも成功つづきでハッピ-なものだとは考えられない。おれたちは絶えず勘違いして行動し、そして失敗することを運命づけられている(笑)。失敗は、現実と自分との齟齬をいやおうなく見せつけ、おれたちは自分をふくむ世界(人間のネットワーク)の検討を迫られる。のではないか?(マルクスとヘーゲル)
それぞれの言語圏に発生しえる思い込みは、異なる民族や言語圏のあいだに起こる不幸だけに当てはまる事情ではないはずだ。おれたち個人と個人のあいだにも生じえる、ほとんど不可避的な不幸の原因だとはいえないか?
だったら、おれたちはどうする? 少なくとも、ボクチャンこんな感じ、アタシあんな感じ、ココロとココロで感じあおうよ、だけで生きていこうとする姿勢が、せいぜい十九世紀の、前々世紀のものだ、ぐらいは理解できなくっちゃな。
「こんな感じ、あんな感じ」や「ココロとココロで」なんてものは、自分たちが使う言葉を通してしか見えない「現実」そのものだ。ごく限られた田舎でしか使われない方言への無批判な服従が、この世界を考えていくのに役立つツールであるわけはない。失敗するということだ。だって、いまはもう二十一世紀なんだぜ。
「それだけを取ってみると、思考内容というのは、星雲のようなものだ。そこには何一つ輪郭のたしかなものはない。あらかじめ定立された観念はない。言語の出現以前には、判然としたものは何一つないのだ。」(『一般言語学講義』)(p67)
*下線、おれ。
つまり、
言語活動とは「すでに分節されたもの」に名を与えるのではなく、満天の星を星座に分かつように、非定型的で星雲状の世界に(注:「を」の誤植だろう。byおれ)切り分ける作業そのものなのです。ある観念があらかじめ存在し、それに名前がつくのではなく、名前がつくことで、ある観念が私たちの思考の中に存在するようになるのです。(p67)
*下線、おれ。
おれたちは、言葉の呪詛のなかで生きてきた(笑)。ごくごく狭い範囲と角度に限定された方言に、身もココロも無批判にささげ服従してきた。ご利益に富むありがたい方言に習熟し、そこをとおして見えた「現実」を揺るがせない真理や真実とみなし、他者に対してもその世界観を強権的に押しつけてきた。
クサくて滑稽な片田舎の自己中心性をとおして、人間は紳士面、淑女面しながら生きてきたのだ。
二十世紀初頭からはじまった言語観は、人間のこうした偏狭な姿への反省と批判である。 《続》
第二章 始祖登場――ソシュールと『一般言語学講義』(p59~77)
まず聖書からの引用。
「神である主が、土からあらゆる野の獣と、あらゆる空の鳥をかたちづくられたとき、それにどんな名を彼(注:アダム byおれ)がつけるかを見るために、人のところに連れて来られた。人が、生き物につける名は、みな、それがその名となった。こうして、人は、すべての家畜、空の鳥、野のあらゆる獣に名をつけた。」(『創世記』二、19~20)(p61)
牧歌的な聖書の言語観を、ソシュールは「名称目録的言語観」=カタログ的言語観(by内田)と名づけた。
ギリシャ以来の伝統的なものらしい。
この伝統的な言語観から、知れるものが二つあるという。
1.ものの名前は人間が勝手につけた。(p62)
例:犬(日本語)とdog(英語)、chien(フランス語)、Hund(ドイツ語)
客から「そこ右、あそこ左」と指示されて、どっちだったけ? なんて迷っているようじゃタクドラはできない。
「必要なのは愛よね」といわれて、どんな意味だったか考え込んでいる男から、女は間違いなく去っていく。
「もう会わないでおきましょうよ、わたしたち」という言葉だけは、何ひとつ理解したくないけどね。
ある言語圏にばかり暮らしているためか、ものの名前や言葉の意味は必然的に、厳格に決まっているんだと、おれたちはどこかで思いこんでいる。そんな思いこみや固定観念にとらわれるくらい言語に慣れ親しまないと、日常生活は困難だし、ときには危険だ。
ところが、関東から関西に転居したり、不幸にもアメリカなんかに放り込まれちゃったりしたら、たちどころに言語障害に陥って途方にくれる。あの店は七面鳥の尻尾でも売っているんだろうかと、「cocktail」と書かれた看板を眺めているようじゃ、帰国するまで酒にも女にも縁はない。そして成田空港の汚れなじんだ空気に「おかえりなさい」をしてもらって、やっと身にしみて述懐するのだ。ヘンチクリンな言葉を勝手気ままに使い回しやがって、外国じゃちっとも楽めなかったと……。
こうして言語の身勝手さに気がついたおれたちは、しかし、もうひとつの錯覚にとらわれている。
2.「名づけられる前からすでにものはあった」という前提への盲信。(p62)
これは、ものすごく過激な指摘だ。
おれたちが、日常的に盲目でいるはずの前提条件を指摘するのは、なんだって過激な様相を帯びる。
命名される前の「名前を持たないもの」は実在しない、とソシュールは考えたんだ。(p62)
こうなると、さまざまな反論、というか嫌悪感がわき起こってくるだろう。
亀は万年生きるんだ。それに比べりゃ、言葉なんてコナイダできたばっかじゃねーの?
ソウソウ。
名前を呼んだら実在するっつーの? おーい、羽音ちゃーん! …現れてくんないじゃん!
イヤイヤ。
何も知らないのに、ちゃんと口座から金は引き落とされる。これって矛盾だろがっ!?
マアマア。
しかしだ、ソシュールの仕事は1910年前後のことだったといわれている。アインシュタインの『特殊相対性理論』が発表されたのは1905年だ。質量と光がエネルギーという点で一緒だなんて、だれが考えられる? 太ったやつのほうがエネルギッシュで、オリンピック村じゃ象みたいな足ばっかりが歩いているってのかい? こんなふうにして二十世紀は、おれたちの「常識」を、「常識」の前提を、乗り越える形ではじまっちゃったんだよ。
っと、煙に巻いておくけど。
ソシュールの引用。
「フランス語の『羊』(mouton)(注:ムートン byおれ)は英語の『羊』(sheep)と語義はだいたい同じである。しかしこの語の持っている意味の幅は違う。理由の一つは、調理して食卓に供された羊肉のことを英語では『羊肉』(mutton)と言ってsheepとは言わないからである。sheepとmoutonは意味の幅が違う。それはsheepにはmuttonという第二の項が隣接しているが、moutonにはそれがない、ということに由来する。」(p62~63)
*下線、おれ。
「第二の項」とは、近接する類義語のことだろう。
ここで、辞書でも思い出してみようか。
仏日辞書:mouton……1.羊 2.羊肉
英日辞書:sheep……羊(羊肉は表さない) 類義語はmutton(羊肉)
なんて感じで。
こう書くと、moutonもsheepも、羊と羊肉という二つの意味をきちんと区別しているように見える。だけど、そう思うのは、おれたちが日本語圏につよく束縛されているからだ。moutonは羊と羊肉を区別しない。しないから、する日本人向けの辞書には詳細にわたって説明が要る。これが事実だ。
なので、意味の幅としては
mouton(仏)≠ sheep(英), mouton(仏)⊃ sheep(英)
であるし、羊肉を表す類義語としてsheepにはmuttonが用意されるのに、moutonのほうには必要がない。…etc。
sheepのほうが、sharpな言葉だといえなくもない。というおれは、とってもshapely(かっこいい)。いや単なるshape-up(日雇い労働者)だった。ごめんよぉ。
著者の内田さんは、このほかにも英語のdevilfishとseveralを例にとっている。
devilfish…悪魔の魚。エイとタコのことで、日本語にはない。
several…なんとなく日本語の5か6ぐらいと思われているが、2や10以上のときもある。
ソシュールの引用、続き。
「もし語というものがあらかじめ与えられた概念を表象するものであるならば、ある国語に存在する単語は、別の国語のうちに、それとまったく意味を同じくする対応物を見出すはずである。しかし現実はそうではない。(略)あらゆる場合において、私たちが見いだすのは、概念はあらかじめ与えられているのではなく、語の持つ意味の厚みは言語システムごとに違うという事実である。」(p63)
*下線、おれ。
おれたちの前で、概念(意味)は名前づけられるのを待っている、ってんじゃない。おれたちが、いわば勝手に「現実」の名前を呼んだことで、その「現実」のなかに、ありもしなかった意味、概念が、生成されてきたというんだ。じゃなかったら、言語圏の違いによる言葉の意味の違いは説明できないじゃないか。
「ありもしなかった意味、概念」といったのは、多少いい過ぎかもしれない。人はそれぞれ必要な生活を営んできたので、「現実」とのかかわり方も多種多様だったろう。そんなかかわり方から、言葉の異なる意味や概念が生まれ、維持されてきた、と想像するのは容易い。
しかし、たとえそうだったとしても、おれたち自身が、おもに生存という特殊な拘束を受けてきて、いわばこっちの身勝手な都合で、いまだに特殊な角度からしか「現実」を見られていないってことじゃないのか?
どっちにしてもだ。ある言語圏の人間が、自分たちの言葉を通してみえる「現実」を、唯一のものと思い込んだり、そうはみえない人をバカ、気違い、危険物扱いするのは、どうかしているということだ。
ここでニーチェのいう大衆社会、畜群、大衆社会をおおう不安という強制力、排他性、を思い出すのは見当違いだろうか? 彼のいう「超人」への方向性は、大衆社会からの脱出ではなく、おれたちの言語を成立させている前提条件への考察と反省から生まれてくるのではないか、というふうに。
また、ある共通言語圏において、その言葉では表せない個人、または個人的な経験はありえるはずだ。言語圏に特有の都合=エゴが、個々の構成員がもっている都合=エゴにぴったり一致するとは考えられない。多かれ少なかれ、長靴に足をあわせるようにして、おれたちは生きてきたんじゃないかということだ。この場合、本人でさえ排斥したいと願う自分の意識が、フロイトの無意識を構成するとは考えられないだろうか?
さらに、こうした限りある現実認識にもとづく行為が、いつも成功つづきでハッピ-なものだとは考えられない。おれたちは絶えず勘違いして行動し、そして失敗することを運命づけられている(笑)。失敗は、現実と自分との齟齬をいやおうなく見せつけ、おれたちは自分をふくむ世界(人間のネットワーク)の検討を迫られる。のではないか?(マルクスとヘーゲル)
それぞれの言語圏に発生しえる思い込みは、異なる民族や言語圏のあいだに起こる不幸だけに当てはまる事情ではないはずだ。おれたち個人と個人のあいだにも生じえる、ほとんど不可避的な不幸の原因だとはいえないか?
だったら、おれたちはどうする? 少なくとも、ボクチャンこんな感じ、アタシあんな感じ、ココロとココロで感じあおうよ、だけで生きていこうとする姿勢が、せいぜい十九世紀の、前々世紀のものだ、ぐらいは理解できなくっちゃな。
「こんな感じ、あんな感じ」や「ココロとココロで」なんてものは、自分たちが使う言葉を通してしか見えない「現実」そのものだ。ごく限られた田舎でしか使われない方言への無批判な服従が、この世界を考えていくのに役立つツールであるわけはない。失敗するということだ。だって、いまはもう二十一世紀なんだぜ。
「それだけを取ってみると、思考内容というのは、星雲のようなものだ。そこには何一つ輪郭のたしかなものはない。あらかじめ定立された観念はない。言語の出現以前には、判然としたものは何一つないのだ。」(『一般言語学講義』)(p67)
*下線、おれ。
つまり、
言語活動とは「すでに分節されたもの」に名を与えるのではなく、満天の星を星座に分かつように、非定型的で星雲状の世界に(注:「を」の誤植だろう。byおれ)切り分ける作業そのものなのです。ある観念があらかじめ存在し、それに名前がつくのではなく、名前がつくことで、ある観念が私たちの思考の中に存在するようになるのです。(p67)
*下線、おれ。
おれたちは、言葉の呪詛のなかで生きてきた(笑)。ごくごく狭い範囲と角度に限定された方言に、身もココロも無批判にささげ服従してきた。ご利益に富むありがたい方言に習熟し、そこをとおして見えた「現実」を揺るがせない真理や真実とみなし、他者に対してもその世界観を強権的に押しつけてきた。
クサくて滑稽な片田舎の自己中心性をとおして、人間は紳士面、淑女面しながら生きてきたのだ。
二十世紀初頭からはじまった言語観は、人間のこうした偏狭な姿への反省と批判である。 《続》










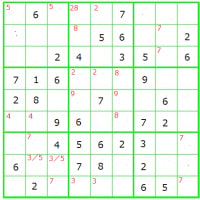
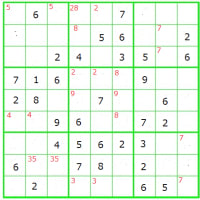
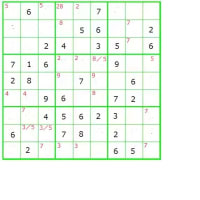
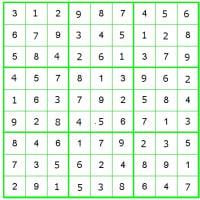
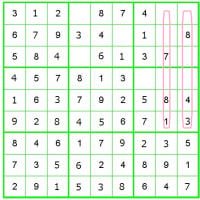
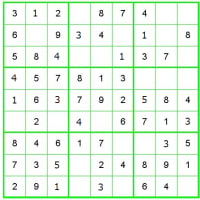
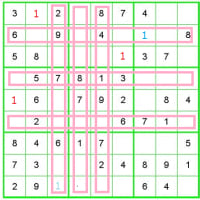
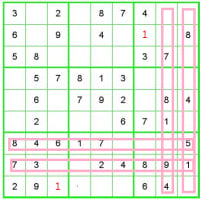
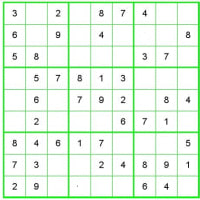

――勘違いマン
少し長くなるかも知れないが、こういう話題はなかなか短くも締めくくれないだろうな。
最も短くするのはキミの腕前となるのだが、苦労はしてみたらいいだろう。
ある部族の言語に於いては数量的概念が我々と違うものもある。少ない、とか、多い、とかという表現がどの辺りの数から始まるのかっていう概念なんだがね。ソレでシステムが機能する。印欧語圏内には無い概念も総体として含めてみるのがたぶん今日的になっているのだろう。
空間性を示す記号としての言語は言うまでも無く歴史という時間性やその中で存在をしている個人の時間性の中でも変容してゆくものだ。
とにかくソシュールは「言葉」というものを考える上では重要だ。
聖書もはじめのころはギリシャ語で書かれたものが普及しやすかったようだ。従来の哲学的概念もギリシャ語(ギリシャ哲学)から発展していることから、ある意味では旧来の概念に縛られることになった。現象学と云う20世紀の新しい概念もその言語観からある意味では出ることはなかった。つまり、構造主義の発展はそれを乗り越えることから始まると言っても過言ではないだろう。
しかしこのような壮大な「お題」をやろうとするアナタに脱帽ですよ。ふふふ。
・・・・勘違いジジィ
そうだったんですか。なにも知らなかったもんで…。
泳ごうと飛び込んでみると、そこは広くて深いけど、マァがんばれよ。っていわれたようなもんですなあ(怖)。
>最も短くするのはキミの腕前
本書の各項は、とっても短いんですよ。
ミジカイミジカイミジカイ…(汗)。
>とにかくソシュールは「言葉」というものを考える上では重要だ。
そうですね。しかしソシュールは、脱出するには高すぎる壁、ってな感じがしてきましたよ。
どーなるんでしょうね、この読書会は!?
ハハハハッ!(嘘笑)
*本年もよろしくお願いいたします。
でもおれは、ソシュールも何とか乗り越えなくちゃと思っているんですよ。
もう、むちゃくちゃ。死んできます(獏)。
Please help me.
はるく、というものです。
同じ本を読んでいたようですが、私の記事よりはるかに詳しく本格的ですね。
TBさせていただきました。
よろしくお願いします。