こんにちは、みなさまのガスショップ(株)和光商会の土門です。
今回の「お客様の生活に役立つ情報」は「意外にも外国生まれだった馴染み深いことわざ」です。
ソニー生命の生活まめ知識からの引用です。
=====
実は外来語だった意外な言葉というのが日本語にはたくさんありますね。
たとえば、雨具の「カッパ」の由来はポルトガル語(capa)、屋根の「カワラ」の由来はサンスクリット語(kapara)、「タバコ」はスペイン語(tabaco)、「天ぷら」はポルトガル語(tempero)、といった具合です。
これらはご存知の皆さまも大勢いらっしゃるかもしれませんね。
外国語由来の日本語は何も単語だけではないようです。
たとえば「鉄は熱いうちに打て」ということわざはそのひとつです。
このことわざからは、つい江戸時代あたりの日本の鍛冶屋さんたちが火の前で「トンテンカン、トンテンカン」と鉄を打つ光景を思い浮かべてしまいそうですが、由来は“Strike while the iron is hot.”でイギリス発祥です。
鉄を打つ光景は洋の東西を問わないかもしれませんね。
調べてみると、ほかにもいくつか外国語由来の「てっきり日本オリジナル?」と思ってしまいそうなことわざがいくつか見つかりました。
誰もが知る有名な「時は金なり」は“Time is money.”の和訳で、日本語と英語にたまたま同じことわざがあったというわけではないそうです。
「一石二鳥」も、四字熟語なのでつい日本か中国あたりの故事が由来なのかと思いきや、イギリスのことわざ“Kill two birds with one stone.”、“To kill two birds with one stone.”からきています。
こうなるともう反対に、うまい具合に四字熟語を作ったものだなぁと感心させられてしまいそうですね。
さらに「終わりよければすべてよし」は、イギリスはシェイクスピアの戯曲“All’s Well That Ends Well”が由来とのこと。
この戯曲は解釈が難しいなどの理由から、シェイクスピアの作品のなかでも『ハムレット』や『ロミオとジュリエット』などに比べてあまり有名ではないようです。
このことわざの由来が知られていないのはそういうことも影響しているのかもしれませんね。
ここまで読むと、もう「隣の芝生は青い」などは「芝生」という言葉からヨーロッパかな?とつい思ってしまいますが、正にその通りです。
古代ローマの詩の一節“The grass is always greener on the other side of the fence.”が由来だそうです。
いつの時代も、隣家の畑はいつもよく育っているように見え、よその家は裕福そうに見えるものなのかもしれません。
最後に、ことわざの由来を調べるなかでついでに見つけた意外な外来語を2つご紹介して締めくくりたいと思います。
ひとつ目は「ハツ」です。
この「ハツ」は、牛・豚・鶏の心臓のことですが、その語源は何と英語の「heart」で、その複数形「hearts(ハーツ)」がなまって「ハツ」と呼ばれるようになったのだそうです。
もうひとつは「政界のドン」「財界のドン」といった具合に親分とか権力者、実力者などの意味合いで使われる「ドン」です。
これはスペイン語やイタリア語に由来し、貴人や高位の聖職者の名前の前につける尊称の「Don」に由来します。
(女性の場合は「ドナ(ポルトガル語)」「ドーニャ(スペイン語)」となります)
ただし、2018年に放映され話題を呼んだNHK大河ドラマ「西郷どん(せごどん)」の「どん」はこの「Don」ではなく「殿」が変化したものだそうです。
すこし古い話題で恐縮ですがご参考までに。
ほかにも面白そうな表現や言葉がありましたらまたご紹介したいと思います。
=====
外来語がたくさんあるのは良く知られていますが、外国由来のことわざまであるとは知りませんでした。
しかもあまりに馴染みのあることわざばかりで驚きました。
さらにその中にはシェークスピアのマイナーな戯曲の一節や古代ローマの詩の一節まであるとは思いませんでいた。
いつからどうやって私たち庶民に使われるようになったのか、興味がわきました。
**********************************************
<< 七十二候 >>
旧暦は心と体で72もの季節を感じる楽しみに満ちています
〇小雪(次候) 新暦:およそ11月27日~12月1日ごろ
朔風葉を払う(さくふうはをはらう)
冷たい北風が、木々の葉を払い落とすころ。
朔風の朔とは北という意味で、木枯らしのことです。
(参考文献:日本の七十二候を楽しむ ~旧暦のある暮らし~
文・白井明大、絵・有賀一広、発行・東邦出版)
**********************************************










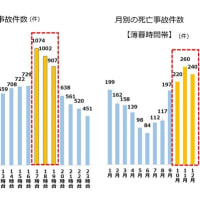



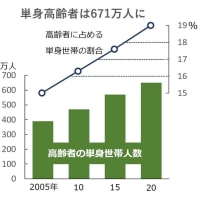



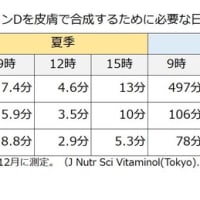
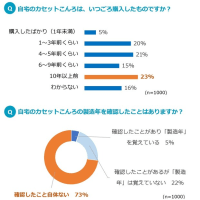
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます