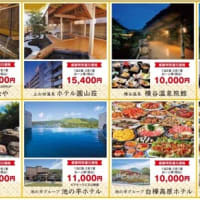東信州中山道連絡協議会主催のウォーキングツアーの準備のため、9/27(木)、10/15(月)。10/18(木)の3回のトレーニングについての総まとめ。
コース
百沢石仏→→牧布施道標一里塚→瓜生坂石碑「百万遍供養塔」→林中の昔道(石仏)→長坂の石仏群→大応院(当山派真言宗修験寺)→長坂橋→枡形→ばん龍窟→井出野屋→地蔵→神明宮→本陣(歴史民俗資料館)→生活道(裏道)→脇本陣→大和屋→たて看板→大伴神社→金井原より
百沢の男女の双体道祖神。モデルはその服装からも高貴な方と思われる。
左側の女性と思われる人から、右の人はお酒を注いでもらっている。
高遠の石工が彫った本格的なもの。
このあたりから、南側の国道越しに布施川、その上段に八幡用水、さらに上に旧五郎兵衛用水が見える。
中山道でも、見逃せないポイント。「左布施谷、右中仙道」の道標。中山道の「山」→「仙」と刻まれている。
道標から趣のある道を直登する。
国道わきの案内板。ちょっと見にくいが上が南になる。
瓜生坂石碑の場所。百万遍念仏塔、石仏がある。ここの左の平坦地は茶屋があったとされる。右の道は望月城に向かっている。
石仏、石碑が並ぶ長坂石碑群の上部。望月の街が手前と対比しまぶしく輝く。
左の建物が、旧真言宗当山派の修験寺の宝物を伝承している民家・滋田家。
江戸時代は、南斜面上の山に修験寺があったとのことである。
鹿曲川に架かる長坂橋上より、中之橋を望む。中之橋が戌の満水前の中山道。
反対側が、弁天様、ばん龍窟、去来の句碑、江戸末期に勧誘された豊川稲荷社などが望める。
橋は望月橋。「駒曳の木曽や出るらん三日の月(芭蕉)」の石碑は正しくは、弟子の去来の句であるらしい。
長坂橋隣接の民家。出桁づくりを再現し、雰囲気を残しながら改築されている。
自作の望月宿絵図。
望月宿は、江戸から約46里(約180km)25番目の宿場。八幡宿から約32町(約3.5km)、茂田井間の宿まで約28町(約3km)。宿の長さ:本町5町5間(約554m)、新町1町2間(約113m)合計6町7間(約667m)
道幅:5間(9m)、中央に用水路が流れていた。
井出野屋。
角川映画、金田一耕助シリーズ(主演:石坂浩二)「犬神家一族」のロケにて那須ホテルとして使用された。建物は、大正14年に建てられ現在も旅館として営業しています。
望月歴史民俗資料館。
本陣問屋の大森家跡。本陣に兼ねて、名主、問屋を明治の宿駅制度廃止まで務めた。現在の歴史民俗資料館の場所まで含めた大きな敷地であった。建物は建坪180坪で門構え、玄関付きであった。7代目久左衛門は軽井沢~和田宿の11宿、9代目は軽井沢~本山宿の15宿の取締役を務めた。望月歴史民俗資料館の約2/3と大森医院の部分に建坪180坪の建屋があった。
脇本陣鷹野家。
八幡宿出身と伝えられる。間口10間、建坪約200坪、門構え、玄関なしで馬屋は左側。
旅籠大和屋の真山家。(国重文)問屋と旅籠を兼ねていた。明和3年(1765)大火により焼失、翌年、再建された建築を現在まで残しており、間口6間、出(だし)桁造(けたづく)り、切り妻造り、板葺き(現、瓦葺き)の建物は国重要文化財に指定されている。
問屋の取次以外に、建物の縁側部分では、お菓子や旅の道具なども販売していた。
また、建物の左側2間は、奥まで続く納屋になっており、馬がつながれていた。その二階には奉公人が寝泊まりしていた。
大伴神社の急階段。佐久郡式内社三座(英多、長倉、大伴)の一つ。伝説として、大伴武日連(むらじ)が乗って来た馬を種馬として駒の改良繁殖をはかリ、この地は、多数の馬を産する地となったと言われている。鳥居前「大伴神社.」は比田井天来書。
御岳大権現は、代々旧記「望月六郎次郎信雅殿御相続の砌(みぎり)、甲州よりお引越し、樋ノ口の社にては、氏子の参詣薄を嘆き、1710(宝永7)大伴神社境内に移した。」と記されている。
境内では他に、「神明宮」は支所の下から1595(永禄2)移された。「八幡神社」の灯篭もあるが、本尊は小諸藩主が祈願し子宝に恵まれたと言われ、小諸に移転されたままである。
金井原(望月宿の上の地区)。望月の町全体が見下ろせる場所です。
最新の画像[もっと見る]