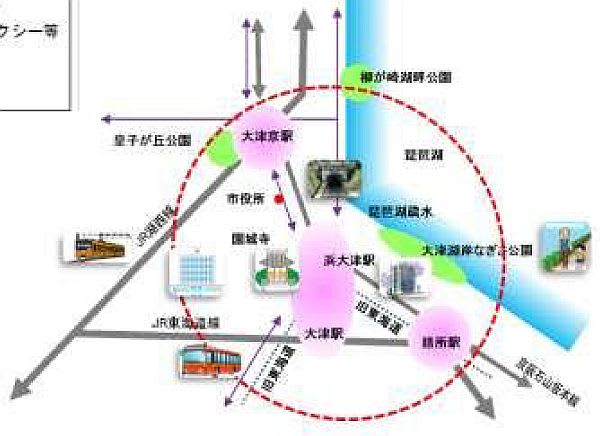融神社の入り口 県道47号線横にある
車を止められそうな場所は、この入り口付近と参道脇道の社殿左側に数台分ある
ひとつ前の記事で書いたBIWA-TEKUのスタンプラリー「紫式部ゆかりの地を巡るコース」のラリーポイントである、伊香立(大津市伊香立、いかだちと読む)の融(とおる)神社に行ってきました。
とおる・・・というと、私には漫才の酒井くにお・とおる※の「とおるちゃん!」というのが先ず浮かんでしまうのですが、ここには嵯峨天皇(786-842)の第12皇子でこの伊香立に荘園のあった源融(みなもとの とおる)が祀られており、光源氏のモデルの一人ということでNHK「光る君へ」の番組最後で紫式部ゆかりの地としても紹介されていました。
BIWA-TEKUなので歩いていくのが本来ということは重々承知しているのですが、このラリーポイントは自宅からだと往復14km、他の一番近いラリーポイントの浮御堂からでも往復13kmと貧脚?の私には遠すぎ、多少の後ろめたさを感じながらも車で訪問。せめてもの誠意?ということで、社殿すぐ横では無く県道47号線(伊香立浜大津線)脇の空き地に車を止め、300m程の参道を徒歩で往復してきました。

鬱蒼とした木々に囲まれた参道 石の鳥居の奥には木製の鳥居が見える

向かって右側に源融、左側に大原全子(ぜんし・またこ:融の母)が祀られているようだ
TVで紹介されたので他にも訪問者が居て駐車スペースがあるか多少心配したのですが、それは全くの杞憂、我々だけの静かな参拝となりました。
※兄弟漫才、酒井くにお・とおるの兄、くにおさんは2022年にお亡くなりになり、今はもう「とおるちゃん!」を聞くことはできません。