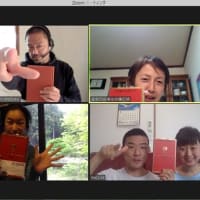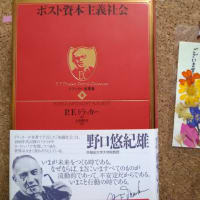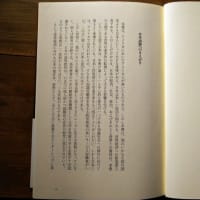今回、京都にある楽天堂の千晶さんより、「らくてん通信」になばなの事を書いてみるようにとご提案を頂きまして、改めてこれまでの9年を振り返ってみました。
千晶さんと言えば、私にとっては10年以上も前に雑誌で紹介された記事を読んでから、いつかお会いしたいと思っていた方でして、昨年その想いが叶ったのでした。
そのときの顛末は、コチラをご覧ください。
なばなを始めてから折々に思ったことなど、取り止めもなく書いてしまいました。
これから何かを始められる方の参考になるかどうか分かりませんが、ご覧いただければ幸いです。
*******************************************
なばなを始めたのは、2010年の2月です。
その頃、和裁の先生に教えに来て頂いていたのですが、その先生が糖尿病をお持ちで、お稽古後のお茶の時間に手作りおやつを作ったところ気に入られて、近くの喫茶店に置いてもらえるようになりました。それがきっかけで、当時、空き家になっていた今の場所でなばなを開店しました。その頃の様子です。
当時は裏六甲の自然豊かなところに住んでいて、近くには蛍がたくさん住む綺麗な川が流れていてました。
そこで野草を摘んで漬物や天ぷらにした り、薬草茶を作ったり。
味噌や漬物を自分で仕込み始めたのも、この頃からです。
↓セリ、クレソン、コゴミ、イタドリ、ツクシ、ノビルなど。この川で母に教わって、見分けられるようになりました。
なばなを始めた翌2011年に東日本大震災が起きました。
それからしばらくして、尼崎からも近い舞洲という地域で、東日本で出た瓦礫を焼却することになり、この辺りに住んで いる人の間でも不安が広がったことがありました。
その時に流れた噂では、放射能を含んだ瓦礫が焼却されると、風向きによってはこの辺りも住めなくなるといったもので、私もとても不安になったのを覚えています。
(↓当時、あちらこちらでシェアされていた画像です)
そこで、瓦礫焼却によって本当に問題が起きるのか調べてみることにしました。
焼却処分が始まる2カ月前から、行政が発表している地元の拠点(尼崎合同庁舎前)と、なばなの玄関前の2か所で空間線量の計測を始めたのです。
その時のデータを基準にして、焼却が始まってから1年ほど、毎朝定点観測を続けてみた結果、空間線量に目立った変化は無く、問題は起きなかったということが分かりました。
当時は毎朝シェアしていたので、記憶されている方もいらっしゃると思います。
こんな事もあって、ネットでの情報からは少し距離を置いて、できるだけ自分で確かめるというのが基本姿勢になりました。
元々、大阪の正食協会に通っていたこともあって、なばなのメニューは、初期の頃はマクロビオティックをベースにしていましたが、その後、八百屋さんや農家さんたちとの出会いがあり、だんだんと、良い食事というのは、自分の台所だけで完結するのではなくて、もっと全体のことを考えて、関わる人や環境にとって無理や負担がないのが良いんじゃないかと思うようになり、伝統的な食生活や地域での循環などに関心が向くようになりました。
また、なばなを始めた当初から、健康的な食事が、お金と情報を持ってる人だけのものだったらつまらないという思いもありました。
太陽や空気や水と同じように、きれいな食べものが、誰にとっても簡単に手に入るのが本来の自然だという思いです。
現在、なばなで提供しているのは、完全菜食料理ですが、お客さまはいろんな方がいらっしゃいます。
ヴィーガンの方はもちろん、健康を気遣われる方、オーガニックな食事に関心がある方、食物アレルギーをお持ちの方、犬好きな方(白い保護犬が居ます)。
いろんな嗜好の方がいらっしゃいますが、たとえば普段は肉食中心の方にも満足して頂けるように、メニューを工夫しています。
アレルギーがある方もそうでない方も、肉食の方も菜食の方も、一緒に楽しんで頂きたいと思っています。
ひとつ嬉しかった例は、なばなのお客様で近くの事業所の産業医をされている方がいらっしゃるのですが、その先生に勧められて、週に一度なばなに通われていた40代半ばの男性が、1年後の定期健診で全ての値が大きく改善したとのご連絡を頂いた事です。
一週間にたった一度の食事が、体調に大きく影響するとは考えにくいのですが、その方のお話によると、意識が変わるのだとか。
なばなのメニューは、菜食ですが食べ応えがあります。
週に一度でも、野菜とご飯を中心にした食事をしっかり摂ることで、すっきりする感じを味わって頂けたのかも知れません。
そして、日常の選択が少しずつ変わっていったのかも。
これは、私にとっては予想外の嬉しいお知らせでした。
オーガニックの食材と天然醸造の調味料を使いますが、とくに健康を目指しているのではなくて、それが美味しいから。
気持ちよく作られたものを美味しく食べて、それで身体の調子も良くなるのだったら、とても良い!と改めて見直した次第です。
それと最近おもしろいと思ったのは、もう何年も前にHappycowという海外のベジタリアン向け情報サイトでなばなを紹介して頂いたのですが、最近になってから時々、海外からのお客さまが来られるようになったことです。
事前にネットで情報検索して、googlemapで目的地に辿りつくのが当たり前になると、どんな場所にいても、結構いろんな事ができてしまうのかも知れません。
(なばなは駅から離れた住宅街の中で、かなり分かりにくい所にあります)
先日来られたオーストラリア人カップルのお客さまには、うちの玄関先で作っている醤油を説明したり、使ってる食材を見て頂いたりしたところ 、とても楽しんでくださって、素敵なレビューを投稿してくださいました。ローカルで庶民的な生活感が楽しかったとの事でした。
ただ、やはり辺鄙な立地ですので、人が来られるときと来られないときの差が大きいという悩みもあります。
食材を無駄にしないためにも出来るだけご予約をお願いしているのですが、やはり直接来られる方もいらっしゃって、そんな時にわざわざ来て頂いたのにお断りするのも忍びなくて、この点に迷いがあります。
いずれにしても、こちらの姿勢をはっきりさせる必要があると感じています。
これまで、食事の提供とは別に、映画の上映やお話会なども、その時々で大切と思うことを主催してきました。
とくに印象に残っているのは、「カンタ!ティモール」という映画です。
そこで描かれていたのは、土に近づくことや、周囲と手を繋ぐことの大切さ。
その機会を失うと、人間らしい感覚も薄れてしまうのかも知れません。
そして、都会での個人主義の危うさを思いました。
人との距離が大きくなって、繋がりが感じにくくなったりだとか。
都会で一人暮らしをしていた頃の自分を思い出しました。
それから、猪名川と武庫川流域の仲間と一緒に、尼崎の地区会館で「エディブルシティ」という映画の上映もしました。
(流域について補足しますが、尼崎は東に猪名川、西に武庫川が流れていて、そのどちらの川を辿っても、上流に住む仲間と繋がっているというイメージで、流域を一つのまとまりと考えています)
「エディブルシティ」は、都市部に住んでいても、自分たちの手を使って食べることに関わっていこうというお話なのですが、上映会の当日には 、身近で見つかる食べられる草を寄せ植えにして持ち込んだり、食べられる野草で作ったふりかけを添えたおにぎりを食べて頂いたり、そのお皿 もビワの葉で、お土産にして入浴剤にして頂いたり。楽しかったなあ!
そのときに参加されていた方が、空いている場所を畑にと申し出てくださって、2018年の4月より、なばなから歩いて20分ほどの住宅地の中に、尼崎はたけ部が発足しました。


2年前、能勢で育てた青大豆を譲ってもらって以来、尼崎で種を継いでいるのですが、その3世代目が、尼崎の畑でたくさん収穫できました。
流域の流れの中から、しょうゆ部もできました!
また、2015年の6月からは、「まあるい食卓」という名前で、月に一度、地域食堂を開いています。
↓子どもさんたちと一緒にコロッケを作ったこともありました。みんな、一生懸命で盛り上がりましたね!
2015年の4月に、近くに住んでいた友人が学校関連の職に就き、尼崎の子どもの状況について聞く機会がありました。
その頃からよく話題に上がっていた子どもの貧困問題が、この地域でも深刻化しているというお話でした。
すぐ近くにそんな子たちが居るはずなのに、まったく見えていないことにショックを受け、どうやったら繋がりを持てるのだろうと考え、まずは 場を開くべく、子ども食堂としてスタートしました。
スタート当初は、しんどい状況にある子どもさんに来てほしいという気持ちが強かったのですが、たくさんの方に関わって頂くうちに、誰にでも来てもらうのが自然と思えるようになり、「子ども食堂」から「地域食堂」へと名乗り方を変え、同時にどなたにでも来てくださいとお伝えするようになりました。
参加費は、大人が300円で中学生以下は無料です。
この活動も続けているうちに、サポートする側とされる側、運営側と参加側、そんな境目は本当は要らないような気がしてきています。
その時に動けるひとが自然に動いて、お互いの関係がお互いさまであることが、いちばん心地よい気がします。
こうして振り返っているうちに、「まあるい食卓」を始める前に周囲の人たちにいろんな事を相談していた時に、地元の自然農農家の友人から「日佐美さんのやりたかった事が、やっと形になるね」と言われたことを思い出しました。
たしかに、なばなを始めた当初から「健康的な食事が、お金と情報を持ってる人だけのものだったらつまらない」と周囲の人にも話していて、町と田舎の交流の会を作ったり、模索していたことを思い出しました。
結局、私が今まで意識せずともやってきていて、そしてこれからも続けていきたいのは、全体にとって健康的な食事や生活が、誰にとっても手に入りやすくなるようにしたいという事でした。
このコンセプトを言葉にすると、「オーガニックを日常に。地に足のついた、当たり前のオーガニ ック」という感じです。
直接的な食事の提供というだけでなく、食材や生産者さんのご紹介や、調理のワークショップなども増やしていきたいですし、特に調理に苦手意識を持ってる方に成功体験を味わって頂きたいです。
あと1年で10年という節目を迎えるのですが、その先も無理なく続けていける働き方を作っていきたいと思います。
文章を書くのも好きなので、これからは文字での発信にも力を入れて行きたいと思っています。
今回、これまでを振り返るにあたって、自分のブログやSNSでの写真や文章がとても助けになりました。
もし、まだ具体的ではないけど、これから何かを始めようと思う方がいらっしゃったら、ぜひ、ブログなどに記録しておくことをお勧めします。
ある程度の時間が経ってから振り返ると、自分の独自性のようなものが見えてきて、それが宝物のような気がします。