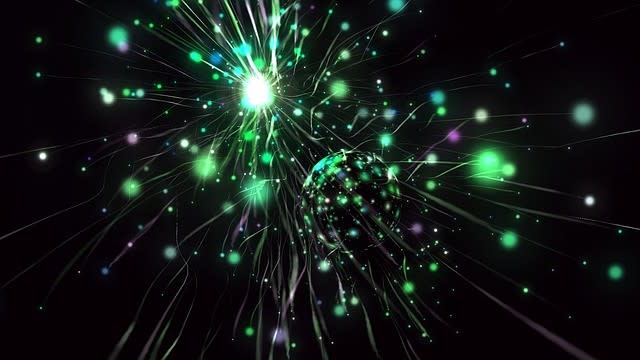今回は、解説はあまりに長くなると、実践の部分とわかりにくくなるので、まずは、最初に心身統一合氣道の籐平光一氏の「心身統一の四大原則」、「心身統一の正しい姿勢」の作り方と、「氣の呼吸法」のみをご紹介する
その前に、「心身統一合氣道」と、「籐平光一氏」について解説する
心身統一合氣道とは?
氣と生活 籐平光一著 IK MANAGEMENT株式会社
巻末解説より敬意を持って引用させていただく
心身統一合氣道は、1974年、合鎮道十段の藤平光一宗主によって創始されました。
「心が身体を動かす」という原理に基づき、相手の心を尊重し導く武道です。心身統一合氣道の原理原則は何事行う上でも土台であり、スポーツ・芸術・経営・教育など様々な分野で学ばれています。
2013年3月現在、アメリカ・ヨーロッパ・ロシア・オセアニア・アジアの世界24カ国で、言葉・文化・宗教を超えて、約5万人の方が心身統一合氣道を学んでいます。
籐平光一氏について
以下のHPの中で、中村天風氏との出会いについて語られている箇所を引用する
「心が身体に大きな影響を及ぼす」という 中村天風師の一言で、 合氣道の本質に氣づく。
戦争が終わり、再び禅とみそぎの呼吸法、合氣道の修行に打ち込むが、ある時、知人の紹介で中村天風師に出会う。 その教えに心を打たれ天風会に入門。 中村天風師の講演で聞いた「心が身体に大きな影響を及ぼす」という一言をきっかけに、心身統一こそ合氣道の根本であることに氣づく。
合氣道とは、相手の氣に合わせるのではなく、「天地の氣に合する道」でなければならない。 だが、天地自然の氣に合するには、まず天地から与えられた心と身体を統一していなければならない。 この心身統一を土台にして、初めて真の合氣道となるのである。この氣づきにより自身の合氣道は劇的に変化し、合氣道を指導する際の根幹となった。
プロフィールにはこうある
19歳から合氣道開祖・植芝盛平師に師事。戦後、中村天風師に師事。
先生 藤平光一 | 心身統一合氣道会 | 心身統一合氣道会 | 合氣道, 合気道
氣の呼吸法 著者 籐平光一 株式会社幻冬舎
より敬意を持って引用させていただく
p75 3行
私は誰でも心身統一をできる方法として、「心身統一の四大原則」をまとめました。
この四大原則は天地自然と一体になるための具体的な方法であり、四大原則そのものが目標ではありません。
心身統一の四大原則
ー、臍下せいかの一点に心をしずめ統一する
二、全身の力を完全に抜く
三、身体の総すべての部分の重みを、その最下部におく
四、氣を出す
これらはちょうど、山の頂に至る、異なる四つの登り道に似ています。どの道を登っても山頂に至ることは間違いありません。したがって、四大原則はどれか一つを行えば、他の三つを満たしているのです。一度に二つ、三つ行う必要はありません。
p62 11行
まず、写真のように膝立ちをします。多くの人が胸を張って力を入れる習慣があるので、肩を完全に上下させます。このとき、肩を回してはいけません。必ず上下をさせてください。そうすると、胸を張った状態では肩を上下させにいことがわかります。
一方で、猫背の状態でも肩を上下させにくいことがわかります。肩を最も上下させやすい場所が肩のもともとの位置、すなわち肩の自然の位置と言えます。
次に、ふわっと腰を下ろします。腰を下ろしたとき、下半身を床に押しつけないように氣をつけてください。また足の指は左の第一指 (親指)と右の第一指が軽く重なっています。ちなみに、左右どちらが上でもかまいません。
念のために肩を再度数回上下させましょう。手は太ももの上に、押しつけずに軽く置きます。このときに氣のテストを行うと、「動くまい」としなくても、自然に安定していることがわかります。この状態が心身統一した静坐の姿勢です。
p63図より

p99図より

p98 1行
実践 氣の呼吸法
まずは坐った状態での姿勢をチェックしましょう。このとき、自分以外にもう一人、氣のテストを行う人がいるとよいでしょう。
なぜ氣のテストが必要かというと、自分では余計な力が入っていることに氣づきにくいからです。とはいえ、一人暮らしの人もいらっしやるでしょう。
その場合は、自分の姿勢にどこか違和感がないか、常に確認してください。
①心身統一した姿勢を確認する
正しい姿勢になるためには、まず肩を上下して、一番楽に肩を上下しやすい位置を探しましょう。そこが肩の自然な位置で、上体に余分な力が入っていない状態です。このとき、肩を回すのではなく、肩を大きく上下させることがポイントです。
上下したあと、手を太ももの上に軽く置きます。
そして、氣のテストを行って、正しい姿勢かどうかチェツクしましょう。
氣持ちがよく安定した姿勢になっていますか。身体に余分な力は入っていませんか。身体のどこかに張ったような違和感はありませんか。ふわっとしていて、しかも安定している状態でしょうか。
正しい姿勢ができれば、氣の呼吸法は半分以上できたといっても過言ではありません。
②静かに吐く
次に息の吐き方を説明しましょう。
これを「呼氣こき」といいます。体内の二酸化炭素を吐き出すことです。
初めての方は、胸や肺を意識して息を吐くために、七、八秒ですぐに息がなくなってしまいます。身体に力が入ってしまうからです。
バスから降りるとき、車掌は必ず「出口の方から順にお降りください」と言います。乗るときには「奥の方からおつめください」と言います。
呼吸も同じことです。息を吐くときには、出口である頭部の息から始まって、胸・腰・脚・足先と順番に息が出ていくイメージを持つと楽にできます。
ただ、あまりこれにとらわれる必要はありません。呼吸が胸や肺だけで行うものではないということを理解し、楽に吐けるようになれば、あとはもう氣にしなくていいでしょう。
「あいうえお」の「あ」の口の形で口を開き、息を正面に向かってまつすぐ吐きます。
このとき、「ハア〜」と息を吐く音がわずかにしますが、意識して吐く音を大きく立てる必要はありません。また、やってみるとわかりますが、音を全く出さずに吐くことはできません。自然に息を吐くことが大切です。
ここでのポイントは、何秒吐こうとか、うまく吐こうとか考えないことです。意識して吐くことで余分な力が身体に入ってしまうためです。
いわゆる「深呼吸」などの影響で、「吐く」「吸う」という行為を何か特別なものと考えてしまう人がいます。呼吸法となると、つい力強く吐いて、力強く吸うもののように思い込んでいるようです。
ゆえに「吐こう」と思った瞬間に力が入ってしまいます。
通常の呼吸をするように、静かに吐くことを心がけてください。
また、虚脱状態で息を吐くと、「ため息」になってしまい、息が漏れてしまうので氣をつけてください。
最初に確認した心身統一の姿勢で行うことが大切です。何度かくり返してみると、十五秒から二十秒程度ならば誰でも楽に息を吐けるようになります。
まずは、息を吸うことよりも、楽に息を吐けることを目指しましょう。氣は出せば新しい氣が入ってくるように、息も出すことによって新しい空氣が自然に入ってきます。
③吐くに任せる
楽に息を吐けるようになつたら次の段階に進みましょう。
吐く息は次第に少なくなりますが、ここで多くの方が息を意識して止めてしまいます。
これは間違いです。私たちは生きている間は常に息をしています。意識して息を止めると、どうしても身体に余分な力が入ります。
力が入ってしまうと、毛細血管が圧迫され、血流が阻害されてしまうのです。
吐く息をそのままに任せておくと、次第に少なくなって無限小に静まっていきます。その間、ロは閉じずに開けたままにしておきます。吐く息が十分に静まってきたら上体をわずかに前へかがめ、残りのかすかな息を無理なく静かに吐きます。吐く息を意識して止めずかに、吐く息が自然に静まっていくことが大切です。
そうすると、「ー、二、三」と数えるくらいの間まが自然とあきます。上体をわずかに前傾したまま口を閉じて、今度は鼻先から息を吸い始めます。そこまでできたら次の段階です。

④吸うに任せる
次に吸い方を稽古けいこしましょう。
これを「吸氣きゆうき」といいます。天地自然の精氣を体内に吸収することです。
上体を前傾したままで、鼻先で花の香りをかぐように、静かに鼻から息を吸い始めます。このときも、何秒吸おうとか、うまく吸おうなどとする必要はありません。
中には、一氣に吸い込んでしまって苦しいという方がいますが、そういった場合、最初のうちは、吸った息が足先から入って、脚、腰、胸、頭と徐々に満たされるイメージを持つと楽に吸うことができます。意識が下がることで、胸や肺に力が入って滞ることを防ぐためです。
バスに乗るとき、より多くの乗客が乗るためには乗車口より入り、奥の坐席からつめて坐る必要があるのと同じです。乗車口で立ち止まっていると、それ以上乗客はバスに乗ることができません。
特に、息を吸うときに胸を膨らませて上体に力を入れる人が多いので注意してください。胸や肺を意識して吸ってしまうと、二、三秒で吸い終わり、苦しくなってしまいます。
静かに吸って、吸う息をそのままに任せておくと、吸う息は、吐く息と同様に無限小に静まってしきます。充分に静まってきたら上体は元の位置に戻ります。このとき、後頭部まで、さらに空氣が「スー」と吸い込まれるのを感じます。
そのときも「ー、二、三」と数えるくらいの間まがあります。吸う息が十分に静まったら口を開けて吐き始めます。
初心者は、呼氣より、吸氣の方を難しく感じるようです。
吸氣のとき、どうしても力が身体に滞りやすいからです。呼氣を何度も稽古し、リラックスして吐くことを身体で覚えると、吸氣も楽にできるようになります。
肺に吸い込んだ酸素のうち、脳で使われるのはなんとその二〇 %です。
氣の呼吸法では、まるで後頭部に空氣が流れこむように、足先から頭部に至るまで氣を充満させます。そのため行えば行うほど、脳が活性化します。十五分もやっていると、視力も回復してきます。物忘れも防げるでしょう。
⑤出づるに任せ、入るに任す
それでは、いよいよ吐く息、吸う息をくり返します。氣の呼吸法を学ばれる方はこの「出づるに任せ、入るに任す」ということの意味をしっかり理解してください。
楽に吐いて、楽に吸うことができても、吐く息と吸う息をくり返す段階になると、「任せる」ということを忘れてしまうようです。心身統一した姿勢で息を吐けば、吸う息は自然に入ってきます。これが「任せる」ということです。
多くの方が陥りやすいミスは、吐く息から吸う息に変わるときに、もしくは吸う息から吐く息に変わるときに、意識して息を止めてしまうことです。
自分で呼吸をコントロールしようとすると、身体に、余分な力が入ってしまいます。身体に力が入ると呼吸は苦しくなって長続きしません。
吐く息を意識してコントロールし、止めてしまうと、息は入ってこなくなります。「吐くよりも吸うほうが難しい」という方が多い原因の一つです。
氣は止めたり、引つ込めたりするものではありません。氣の呼吸法は天地自然の氣と五体の氣が交流することです。氣は出すことで入ってきます。
苦しいときは、やり方に何かしら間違いがあるから苦しいので、そのまま我慢して続けてはいけません。心身統一した姿勢に立ち返って、もう一度初めからやり直しましょう。
さらに、ほんとうに「吐くに任せて」吐いているか「吸うに任せて」吸っているか、氣のテストを通して確認してみてください。意識して吐いたり吸ったりしていると、身体に余分な力が入るので、氣のテストを行うと姿勢が不安定になっているのがわかります。
通常の呼吸と同様に、呼吸していることすら忘れてしまうようであれば、言うことはありません。そのときに氣のテストをすると、磐石の姿勢になっているのがわかります。
呼吸法を実践するときは常に「出づるに任せ、入るに任す」ということを忘れずに呼吸することを心がけてください。
私たちは、自分の身体に力が入っているとき、力が入っていることを自覚しにくいものです。しかし、その都度氣のテストを行うことによって、自分の身体にいかに余分な力が入っているか氣づくことができます。
次第に、氣のテストを行わなくても、自分で身体のどこに力が入っているかわかるようになってきます。「私は力を抜いているのにうまくできない」という場合は、正しいリラックスができていないか、力を抜いているつもりになっていることがほとんどです。だからこそ、氣のテストを大切にしていただきたいと思います。
そもそも、「心が身体を動かす」のですから、心はリラックスしているのに身体にだけ力が入ることはありません。
氣の呼吸法を行って力が入るときは、心で必ず何か不自然なことをしているのです。意識してコントロールしょうするのは、不自然な心の使い方の一例です。
どういった心の状態が身体に力を与えているか考えることも大切です。
真剣勝負の世界では、「無息の呼吸」というものがあります。
無息の呼吸と言っても、息をしないことではありません。
昔の武士が立ち合うとき、呼吸が相手に読まれてしまうと動きが読まれてしまいました。そこで、心を静めることによって、あたかも呼吸をしていないかのような静かな呼吸を身につけることが不可欠でした。それが、無息の呼吸です。「氣の呼吸法」もこれに近いと言えるでしょう。
私は吐くだけなら、五十秒でも六十秒でも吐いていられます。
ただ、間違えてはいけないことは、呼吸を長くすることが大事なのではないということです。苦しいのを我慢して長い呼吸をしても、健康によくありません。
全身をリラックスすれば、呼吸は自然に深くなり長くなることをよく理解してください。肺活量を大きくすることが目的ではなく、リラックスの訓練だと思って行ってください。
「長生き」とは「長息」ということなのです。
一生のうち、精神的にも、健康維持のうえでも、大きな差ができるのは当然でしょう。
⑥まずは一日十五分から始めてみる
そこまでできたら、あとは毎日の実践あるのみです。まずは一日十五分から始めてみましよう。なぜ十五分かといいますと、十五分ぐらい行うことで、体内から七割ぐらいの二酸化炭素が除去され、全身に酸素が充満するからなのです。このとき、ご自分の手をご覧ください。いつもより、いきいきとした肌色に変わっているはずです。
そして、少なくとも二週間は続けてください。氣の呼吸法で深い呼吸が身についてくると日常の呼吸も深まる実感が得られることでしょう。
通常、人間は一分間に十五回から二十回くらい呼吸しています。それが四回から五回くらいの深い呼吸に変わつてきます。
椅子に坐った姿勢以外でも、静坐の状態、立った状態、寝た状態でも氣の呼吸法を行うことができます。その際にも心身統一した姿勢かどうかを必ず確認してください。
ただし、食事の直後日入浴中は血液の循環が変化するので行わないように注意してください。それ以外であれば、いつ、どこで、何回行っても構いません。
氣の呼吸法は、今日やったから明日めざましい効果が出るというものではありません。毎日続けていれば、いつの間にか自分が健康になっている。それが氣の呼吸法です。
氣の呼吸法は、一日に何回やれとか、何回以上やるなとかいった制約も取り決めもありません。坐禅を組んで瞑想めいそうして、などということもしません。いつでも、どこでもできます。皆さんも、日々の暮らしの中で実践してみてください。
朝夕の通勤時、買い物の行き帰りなど歩きながらの呼吸法、テレビを観ているときなどの時間を有効に使っていろいろ実践してください。
自分の氣持ちの持ち方で、いくらでも氣の呼吸法をする時間は作ることができます。
志を立てて何事かを行うには、強い意志を必要とします。いくら貴重なことを習っても、これを続けなければ身につきません。意志の弱い人は、こうすればよいとわかっていても、続けることができないでいます。
私が臍下せいかの一点を教えプラスの氣を教えるとそれを実行し成果をあげている人は多くいらっしやいます。一方で、二、三日やるともう止めてしまう人も少なくありません。
正しいことは今行って今すぐにできるものですが、それが自分の身につくには飽きずに継続することが不可欠です。
何事を始めるにも、必ずプラスの氣を起こし、強い意志をもって完遂してください。
引用終わり
投稿の予定では、順を追った解説を予定していたが、体調のよろしくない方々のために、順番をとばして、実践法をいきなりご紹介した
なので、まずは、実践法を、のちに詳しい解説を今後してゆく
実体験から、この氣の呼吸法は身体の強い体勢をつくるのに非常に役立つと実感する、また鎮魂行と同時並行で実践すると一層効果的に思う
いろいろ正しい姿勢の作り方を著書より引用したが、とは言うものの
正しい姿勢をつくるが難しそう
座って氣の呼吸をする時間が無い
睡眠時間すら短いのに、これ以上何かやる時間は無い
体のどこかがこっていて座っているだけで緊張する
などの方には、私の体験から、いっそ、「仰向けで大の字になってやる」のも良いかもというもの、究極、どんな姿勢も心身統一を目指すというのが最終目標であるなら、どんな姿勢で氣の呼吸を行っても良いことになる、それなら、時間が無い、体のどこかが痛い、などの理由で座れない方は
昼寝の前に、仰向けで氣の呼吸をやって、そのまま寝てしまってもいい
就寝前に、仰向けで氣の呼吸をやって、そのまま寝てしまってもいい
のではないだろうか、そして、私が仰向けでやってみて感じたことは
はじめ、マニュアル通りやってみて、呼吸をしている最中に、呼吸をしている時、からだのどこかの部分、呼吸時のどこかの時などで、非常に気持ちよくなる時、気持ちよくなる箇所、が発生する
その発生した「気持ちよさ」の感じを大切にし、壊さないように維持して、引き続き「気持ちよさ」を感じ続ける
やがて、「気持ちよさ」を感じている、からだのどこかの部分、呼吸時のどこかの時が、徐々に自然と範囲が拡大してゆき、そして、「気持ちよさ」が全身にまでなった時、呼吸は無理な力が一切かかっていない深い呼吸になっている
難しく考えず、「そもそも、無理は長くは続かない」と考えて、呼吸も自然に任せれば、無理のないように変化してゆく、あせらず「気持ちよさ」に任せてしまうのも一つの手に思う
合氣道は、読んで字の如く、自然の氣と合わせる道、カタカムナのマノスベの道、カムナガラの道
人体は、沢山の命の集積とも言える一つの宇宙、その宇宙が自然のバランスで成り立っている、しかし、人間は、自分こそが人体の所有者であり、自分がすべてにおいて人体をどう使うか決定権があると思い込んで生きている
そのような自意識の都合だけで心も身体も、魂までも、引っ張って、振り回してきた、「どうしても、やらなくちゃ」、「疲れていても、やらなくちゃ」、「寝ないで、やらなくちゃ」、「体調が悪くても、やらなくちゃ」など、あたかもそれが正当な理由かのように、だが、人体を機能させているのは自然の力に従う命たち
一度でも、自分の身体に、身体を構成する一つ一つの命に、問いかけたことがあるだろうか?
本当は、どのように空気を吸い込んでほしいのか?その時、肺は、お腹は、背骨は、吸い込む速度は、間隔は・・・
もしも、そんな身体すべての声に耳を傾け、それらを第一にした呼吸が体験できれば、今までの呼吸は何と不自然、不完全であったかがわかってくる
それと同時に、心身統一の氣の呼吸をすれば、今までの身体は、完全に活用されていなかったことがわかる、そして、完全に活用された身体にみなぎるエネルギーの大きさに圧倒されるだろう
次回に続く