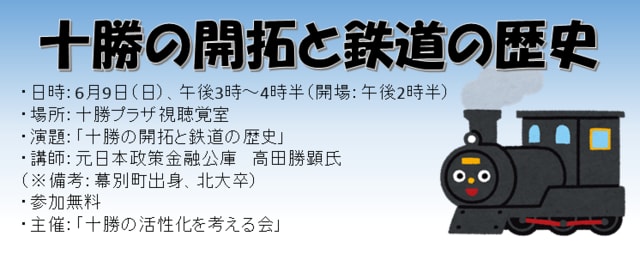アッツ島玉砕との報伝えられる
校長先生涙ながらに

アッツ島の戦いは、1943年(昭和18年)5月12日にアメリカ軍のアッツ島上陸によって開始された日本軍とアメリカ軍との戦闘である。山崎保代陸軍大佐の指揮する日本軍のアッツ島守備隊は5月29日に玉砕した。当時のアッツ島の様子を伝える貴重な史料である辰口信夫曹長の日記もこの日が最後となっている。最後の突撃の直前、山崎部隊長はほとんどの書類を焼却したため、当時の様子を偲ばせる数少ない資料である。
“夜二〇時本部前に集合あり。野戦病院隊も参加す。最後の突撃を行ふこととなり、入院患者全員は自決せしめらる。僅かに三十三年の命にして、私は将に死せんとす。但し何等の遺憾なし。天皇陛下万歳。
聖旨を承りて、精神の平常なるは我が喜びとすることなり。十八時総ての患者に手榴弾一個宛渡して、注意を与へる。私の愛し、そしてまた最後まで私を愛して呉れた妻耐子よ、さようなら。どうかまた会ふ日まで幸福に暮して下さい。ミサコ様、やっと四才になったばかりだが、すくすくと育って呉れ。ムツコ様、貴女は今年二月生れたばかりで父の顔も知らないで気の毒です。
〇〇お大事に。〇〇ちゃん、〇〇ちゃん、〇〇ちゃん、〇〇ちゃん、さようなら。”
『ウィキペディア(Wikipedia)』
北の海には凄惨な歴史が残されています。
丸山さんは酒に酔って、何も考えないで発言したわけではないと思われます。
「ナチスに学べ」と偉い人が言いましたが、自分で「突撃隊」を演じたあげく、はしごを外されたようですね。
「十勝の活性化を考える会」会員K