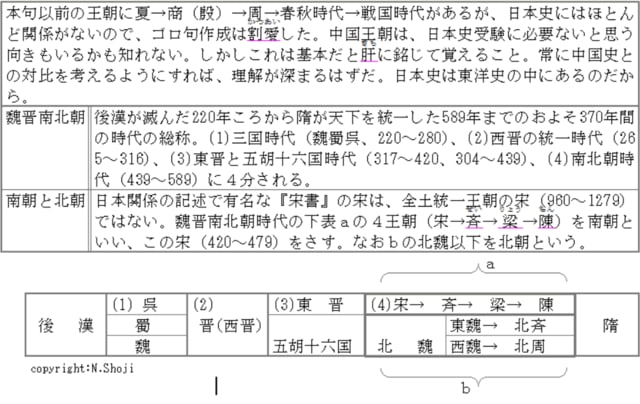◇古代21.応神朝の渡来人の覚え方(4~5世紀3氏)◇B
[ゴロ]西のワニが/東のあっちで/弓の果たし/に応じ
(西文氏・王仁)(東漢氏・阿知使主)(弓月君・秦氏)(応神朝)
[句意]西のワニが、東のあっちで、弓の果たし合いに応じた、という句。つまり弓で決闘したということ。「西文氏」「東漢氏」「弓月氏」などの読みは混乱を避けて無視して作りました。試験では漢字で出題するでしょうから、これで区別はつくと思います。たまに「読み」を聞いてくるので、そこは抜かりなく。
[point]
1.応神期(4~5世紀)の主な渡来人は阿知使主(東漢氏の祖)・弓月君(秦氏の祖)・王仁(西文氏の祖)の3人である。
[解説]
1.東漢氏(やまとのあやうじ)の祖の阿知使主(あちのおみ)は、応神朝に帯方郡(たいほうぐん)を経て渡来したという説話がある。後漢の霊帝の曾孫(そうそん)だという。文筆に秀でており、史部(ふひとべ)を管理した。
2.秦氏(はたし)の祖の弓月君(ゆづきのきみ)は応神朝に百済から渡来したという説話がある。秦の始皇帝の曾孫という。養蚕(ようさん)・機織(はたおり)を伝えた。
3.西文氏(かわちのふみうじ)は祖の王仁(わに)は、応神朝に百済から渡来したという説話がある。漢の高祖の末裔(まつえい)という。論語10巻・千字文(せんじもん)(書道の手本となった漢字の初級教科書)1巻を伝えた。
〈2017関西学院大・済国際総合2/4:「
6世紀に入ると、e百済から儒教や仏教が伝えられた。
問5 下線部eに関して、正しいものを下記より選びなさい。なお、すべて誤っている場合は「エ」をマークしなさい。
ア.百済から五経博士が渡来して仏教を伝えたほか、易・暦・医の諸博士も渡来し、その知識を伝えた。
イ.百済が伝えた仏教は、西域・中国を経て伝えられた南方仏教の系統である。
ウ.『古事記』や『日本書紀』には、東漢氏の祖の王仁が仏教を伝えたと記されている。」
___________________
(答:問5エ ※ア×仏教を伝えていない、イ×北方仏教、ウ×王仁(わに)は西文氏(かわちのふみうじ)の祖)〉
このつづきは「NOTE]を見てください。東海林直人のゴロテマ日本史◇古代3(渡来人~重祚天皇)* | 記事編集 | note