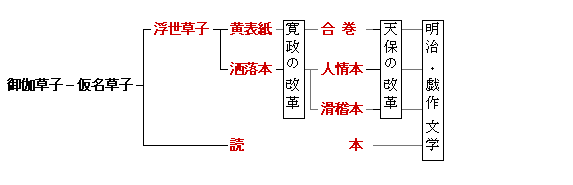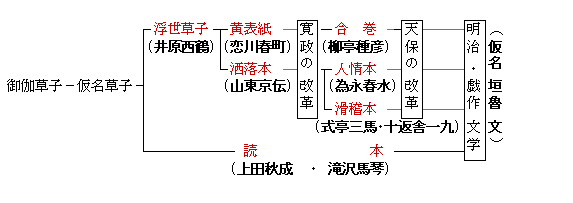◇近現§61.満韓交換論の覚え方(日露協商論主唱者)◇C
[ゴロ]日露協商/一等いいのか/満韓交換
(日露協商論)(伊藤博文・井上馨(かおる))(満韓交換論)
[句意]日露協商の満韓交換の考え方がいちばんいいのか、という句。
[point]
1.日露戦争前の外交で満韓交換論(日露協商論)を主張したのは伊藤博文・井上馨の2人。
[解説]
1.日本政府内には伊藤博文をはじめロシアと妥協して「満韓交換」を交渉でおこなおうとする日露協商論があった。
2「満州」とは中国東北部を占める東北三省をさす旧称である。ロシアに満州経営の自由をあたえるかわりに、日本が韓国に対する優越権を獲得しようという考えであった。
3.しかし、ロシア軍は韓国国境沿いの満州で展開、閔妃虐殺事件により韓国政府が親露に傾いており、ロシアは同論を無視した。
〈2019関西大・外済商人間政策2/3:「
(B)日清戦争後、ロシアは朝鮮への影響力を強めるとともに、北清事変を契機に中国東北部(満州)を占領した。韓国(1897年に朝鮮から大韓帝国へ国号を変更)における権益の確保を重視する日本は、勢力を拡大するロシアへの対応を迫られた。政府の中では、「満韓交換」についてロシアと交渉を行おうとする日露協商論が伊藤博文などにより主張されたが実現せず、時の( 3 )内閣により、イギリスと同盟することでロシアに対抗する方針がとられた。
_________________
(答:3桂太郎 ※原問には選択肢30項あり)〉
〈2019中央大・文2/10:「
問6 史料(『万朝報』1903年6月30日号に掲載された内村鑑三が執筆した記事)は、日露開戦に反対して書かれたものである。日露戦争に関する記述として誤っているものを次のア~オの中から一つ選べ。
ア.開戦前、日本が占拠していた満州をロシアヘ引き渡すかわりに 日本の韓国での優越権を認めさせようとする「満韓交換」をとなえる政治家もいた。
イ.1902年、日本はロシアの極東進出に備え、韓国における日本の権益を守るべくイギリスと同盟を締結した。
ウ.1904年、日本とロシアの交渉は決裂して戦争が勃発し、日本は旅順での戦闘や奉天会戦及び日本海海戦に勝利した。
エ.1905年、アメリカのポーツマスにて日本全権小村寿太郎とロシア全権ウイッテは講和条約に調印した。
オ.ロシアから賠償金をとれなかった講和条約に一部の国民の不満が爆発し、講和条約調印の日に暴動事件が発生した。」
_________________
(答:問6ア×日本が占拠→ロシアが占拠)〉
この先は「NOTE」でご覧ください。東海林直人のゴロテマ日本史◇近現7(満韓交換~器械製糸) | 記事編集 | note