さて、昨日まで、記紀にみる「仁徳天皇」の御聖徳について記してみました。
天皇の大御心(おおみこころ)は、古代の昔話なのでしょうか?
今日は、あるエピソードを交えてご紹介いたします。
時は昭和20年12月。大東亜戦争敗北により、GHQが占領政策を強化していた頃のお話です。
宮城県栗原郡の60人の青年が皇居清掃(草刈りなど)のお手伝いを志願して上京したのです。
その時代を知らない私ですが、終戦から半年も経たない時期です。一面焼け野原にされた国土の中、食糧事情も交通事情もままならないことは想像できます。 しかし彼等は、こういいます。
…二重橋前の 広場に雑草が生い茂って、大変あれていると聞き、草刈りやお掃除のお手伝いのために上京しました。どうかお手伝いをさせて下さい…
実は、事前に彼等のリーダーが上京して、宮内省の担当者と協議をしたそうですが、占領政策のまっただ中、GHQがいつどのような仕打ちをしてくるか予想も出来なかったため、この担当者は「一切の責任を負う」覚悟で、独断で受け入れを決意したそうです。
彼等は「みくに奉仕団」と名乗り、男性55名、女性7名の計62名。
ほとんどが23~23歳の若者でした。
過酷な占領下のこと、GHQがどんな対応をするかも予想が付かないわけですから、「娘っこのうちには、両親兄弟と永い別れの水杯を交わしてきた者もいる」(木下道雄侍従次長=当時=談)そうです。
昭和天皇は、昭和21年にこのような御製を詠んでおられます。
〈皇居内の勤労奉仕者〉
をちこちの民のまゐ来てうれしくぞ宮居(みやゐ)のうちに今日もまたあふ
戦(たたかい)にやぶれし後の今もなほ民のよりきてここに草とる
皇居が雨漏りしているときいて、我先に資材を担いで修理に向かった、と言う1400年以上前の仁徳天皇と国民の関係と、このエピソードは、天皇と国民の関係に、今も尚通じるものがあると強く感じられる内容ではないですか。
昭和天皇は、七十歳になられた昭和45年に、
よろこびもかなしみも民とともにして年はすぎゆきいまはななそじ
との御製を詠んでおられますが、私はこの御製の「…よろこびもかなしみも民とともに」という部分に強く心を打たれます。
話をもどしますが、みくに奉仕団のニュースは全国に流れ、自分たちも皇居の清掃をお手伝いしたい、という人々が続々と手を挙げたそうです。
昭和21年には188団体、約1万人が、ピークの昭和26年には831団体、約4万人もの国民が、皇居の清掃奉仕に参加したといいます。
GHQは、この動きを怪しんで、「背後に強力な組織がいて、巨額の資金を投じて、GHQにとってよからぬ策謀を巡らせているのでは?」という疑念を抱き、独自の調査を試みた、という話もあるそうですが、これはやはり「通常の国では考えられない」事なのです。
戦後の昭和天皇全国ご巡幸も、当初GHQは積極的に進めさせたと言います。
敗戦国の元首はどの国でも必ず悲劇を迎えているからです。例えば第一次世界大戦敗戦後のドイツ皇帝、第二次世界大戦敗戦後のイタリアの国王も廃位となっているように、滅びてしまうのが他国の常識だったため、「天皇も国民に石など投げられるだろう」とGHQは考えていたと言います。
しかし、ご存じの通り、昭和天皇が足を運ばれた各地では、当時の先輩達が元気と勇気を得て、戦後復興に更に邁進してくださって、現在の経済大国・日本の基礎を築いて下さいました。
戦後の「絶望的」な時にあっても、国民の身の上を案じて下さる天皇のご存在、そして、「皇居が草に覆われて忍びない」と、自分たちの生活も顧みず自らの意志で奉仕作業に向かう国民の姿…
我が国にしかない、天皇と国民の「民をいつくしみ、皇室を尊敬する」関係は今も続いているのですね。
(文責:横畑雄基)















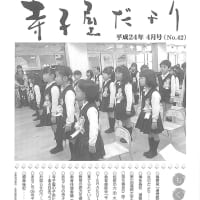




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます