昨日に続きます。
仁徳天皇のご聖徳としては、「三年間の租税免除」が有名です。
ご即位された天皇が、高殿から民の暮らしを御覧になると、かまどの煙が立っていないことに気づかれます。そこで、三年間、租税を免除されたのです。
この間、皇居は屋根も吹き替えることが無く、雨が降ればあちこちに雨漏りがしたと言うことです。
日本書紀によれば、次のような記述があります。
・・・それ天(あめ)の君(きみ)を立つるに、これ百姓(おおみたから)のためなり。然ればすなはち君は百姓をもって本(もと)となす。是をもって古の聖王(ひじりのおおきみ)は、一人も飢え寒(こごゆ)ればかえりみておのれを責む。今百姓貧しきはすなはち朕が貧しきなり、百姓富めるはすなはち朕が富めるなり・・・
百姓と書いて「おおみたから」と当てておりますが、実は、初代神武天皇がご即位にあたって発せられた「橿原建都のおことば」にも、
・・・夫(そ)れ大人(ひじり)の制(のり)を立て、義(ことわり)必ず時に従う。苟も民(おおみたから)に利(くぼさ)有らば、何んぞ聖造(ひりぞのわざ)に妨(たが)わん…
と、同じく「民」と書いて「おおみたから」と読んでいます。
他国の為政者が人民を支配するという構図とは違い、建国以来、天皇は、神の思し召しにしたがい、民を「たからである」という思想で慈しまれていることがわかります。
仁徳天皇の話に戻りますが、三年を待たずして、民の生活も大変改善したのでしょう、諸国の諸々により、次のような懇願があったそうです。
・・・若し此の時に当たりて、税(おおみちから)・調(みつぎ)を貢(たてまつ)りて、宮室(おほみや)を修理(つくろ)ふに非ずは、おそるらくは、其れ罪を天に獲(は)むか・・・
つまり、こんなに豊かになったのに、まだ租税を免除していただいたままで、皇居の修理もできないようならば、天から罰をうけてしまいます・・・(だから租税を納めさせて下さい)・・・という意味でしょう。
それでも、三年間は免除というお考えを貫かれたのが仁徳天皇です。
さて、三年後、租税の徴収が始まるとともに、次ような記述もあります。
・・・是に百姓、うながされずして、老を扶(たす)け幼を携へて、材を運び簣(こ)を負ひ、日夜を問はず力をつくして争(きほ)ひ作る・・・
つまり、老若男女とわず、誰に言われることもないのに、材料を担いで皇居の修復に向かった、と記してあるのです。
思い起こせば、小学校の歴史の授業で、「仁徳陵古墳」を習った際、「世界で一番大きなお墓」と学びましたが、その教科書の挿絵は、鞭を持った役人が、人々を酷使して作らせていたというイメージをわかせるものでした。
記紀を学び、こうした文章に出会ったとき、その事実のとらえ方が正反対であることに気づかされます。
さて、「記紀」はあくまで神話であり、「為政者」側が都合良く正当性を示すために残したものであり、信頼できない、という方も多くいらっしゃいます。
しかし、果たしてそうなのか…明日は、天皇の大御心と、国民の関係について、仁徳天皇から百代以上後の昭和・平成の私たちの時代と重ねて考えてみたいと思います。
(文責:横畑雄基)
仁徳天皇のご聖徳としては、「三年間の租税免除」が有名です。
ご即位された天皇が、高殿から民の暮らしを御覧になると、かまどの煙が立っていないことに気づかれます。そこで、三年間、租税を免除されたのです。
この間、皇居は屋根も吹き替えることが無く、雨が降ればあちこちに雨漏りがしたと言うことです。
日本書紀によれば、次のような記述があります。
・・・それ天(あめ)の君(きみ)を立つるに、これ百姓(おおみたから)のためなり。然ればすなはち君は百姓をもって本(もと)となす。是をもって古の聖王(ひじりのおおきみ)は、一人も飢え寒(こごゆ)ればかえりみておのれを責む。今百姓貧しきはすなはち朕が貧しきなり、百姓富めるはすなはち朕が富めるなり・・・
百姓と書いて「おおみたから」と当てておりますが、実は、初代神武天皇がご即位にあたって発せられた「橿原建都のおことば」にも、
・・・夫(そ)れ大人(ひじり)の制(のり)を立て、義(ことわり)必ず時に従う。苟も民(おおみたから)に利(くぼさ)有らば、何んぞ聖造(ひりぞのわざ)に妨(たが)わん…
と、同じく「民」と書いて「おおみたから」と読んでいます。
他国の為政者が人民を支配するという構図とは違い、建国以来、天皇は、神の思し召しにしたがい、民を「たからである」という思想で慈しまれていることがわかります。
仁徳天皇の話に戻りますが、三年を待たずして、民の生活も大変改善したのでしょう、諸国の諸々により、次のような懇願があったそうです。
・・・若し此の時に当たりて、税(おおみちから)・調(みつぎ)を貢(たてまつ)りて、宮室(おほみや)を修理(つくろ)ふに非ずは、おそるらくは、其れ罪を天に獲(は)むか・・・
つまり、こんなに豊かになったのに、まだ租税を免除していただいたままで、皇居の修理もできないようならば、天から罰をうけてしまいます・・・(だから租税を納めさせて下さい)・・・という意味でしょう。
それでも、三年間は免除というお考えを貫かれたのが仁徳天皇です。
さて、三年後、租税の徴収が始まるとともに、次ような記述もあります。
・・・是に百姓、うながされずして、老を扶(たす)け幼を携へて、材を運び簣(こ)を負ひ、日夜を問はず力をつくして争(きほ)ひ作る・・・
つまり、老若男女とわず、誰に言われることもないのに、材料を担いで皇居の修復に向かった、と記してあるのです。
思い起こせば、小学校の歴史の授業で、「仁徳陵古墳」を習った際、「世界で一番大きなお墓」と学びましたが、その教科書の挿絵は、鞭を持った役人が、人々を酷使して作らせていたというイメージをわかせるものでした。
記紀を学び、こうした文章に出会ったとき、その事実のとらえ方が正反対であることに気づかされます。
さて、「記紀」はあくまで神話であり、「為政者」側が都合良く正当性を示すために残したものであり、信頼できない、という方も多くいらっしゃいます。
しかし、果たしてそうなのか…明日は、天皇の大御心と、国民の関係について、仁徳天皇から百代以上後の昭和・平成の私たちの時代と重ねて考えてみたいと思います。
(文責:横畑雄基)















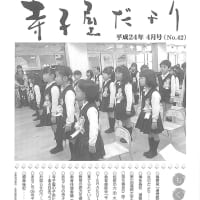




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます