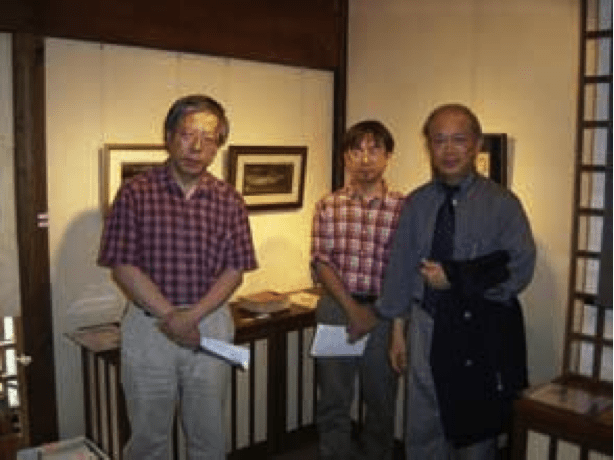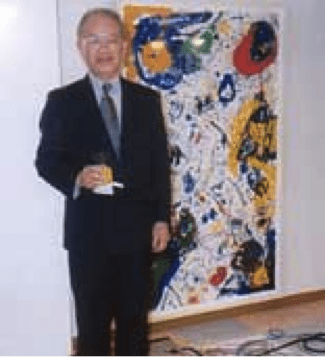10月2、3、4日と「李禹煥回顧展」鑑賞のためソウルに行って来た。今すぐということではないが、いずれアジアの国々とのネットワーク化も検討したいので参考までに情報提供します。参加者は美術評論家峯村敏明氏を中心に、シロタ画廊白田貞夫御夫妻、月刊ギャラリー編集長本多隆彦氏、なびすギャラリー真倉光子さん、鎌倉画廊中村路子さん、作家の藤岡冷子さんなどで、韓国美術界に詳しい峯村さんや白田さんのおかげで充実した旅となった。
オープニングレセプシヨンには美術関係者や作家、愛好者達など大勢の招待客が参集、日本か らは神奈川県近代美術館館長の酒井忠康氏、美術評論家の中原祐介氏の姿も見え、盛大に行われた。作品展示はホアン美術館とロダン美術館の2ヶ所が使われたが、初期の石と鉄の立体から近年の照応Correspondenceに至る作品群が広々した空間で鑑賞することができた。李禹煥のこれだけの回顧展は韓国においてもはじめてのことである。しかし、日本においてアーティストとしての活躍がはじまった歴史や“もの派”の中心的存在であったことからすると、韓国より先に日本の国立美術館において回顧展があってもおかしくないと思うが、どうなっているのだろう。
李禹煥さんを囲んでの昼食会が、私も長いお付き合いの珍画廊の柳珍さんの音頭で実現したが、 パリやドイツでの個展に使う石探しの苦労話や現代美術への思いなど伺いながら、韓国焼肉の味を楽しんだ。李さんは穏やかなお人柄である一方なかなかの理論家で、若い頃哲学を学んだその経歴通りアーティストである以上に哲学者を感じさせる。来年はイギリスでの展覧会が予定とのこと。
韓国現代美術の第一人者である朴栖甫氏は李さんのいわば兄貴格の作家であるが、アトリエ訪 問や素晴らしい夜景の見えるご自宅で美味なワインをご馳走になりながら韓国現代美術の現状やここに至る歴史、トップアーティストとしての誇りや怨念など、他では聞くことができない興味深い話を伺うこととなった。LAでの発表予定の作品は、私が知っている黒やグレーなどモノトーンのものからカラフルなものに大きく変化しつつあり驚かされた。これらの作品は、“鉛筆による繰り返しの線引きという修身のごとき無心の作業に没頭するところから生まれる”という話も印象的であった。ソウル市立美術館館長河鍾甫氏との会食会も有意義であった。河さんは朴栖甫氏に次ぐ韓国現代美術の代表的作家で、日本においてもConjunctionなどの作品を発表しているが、実に温厚で人間的な深みを感じさせる。
韓国現代美術については、改めてそのエネルギーに驚かされた。宿泊したウェスティン朝鮮ホテルのロビーにはリチャード・セラ作品が何枚もさりげなく飾られ、現代美術が生活のなかに定着していることを感じさせる。作家も画廊もコレクターも現代美術への思い熱く、日本より一歩も二歩も先を行っているように見受けられた。なお、KIAF事務局長でもあるKeumsanギャラリーの黄達性氏にご案内いただいた画廊で目に止まった若手作家達は・・ParkHyunjoo、KimMyungsook、そして珍画廊のChaouhi・・などであった。
*関連記事が月刊ギャラリー11月号に掲載