
希望の牧場
2016年1月17日 園田 淳
2015年6月11日、福島第一原発事故から4年3ヶ月。福島市から車で浜通りへと向かいました。2011年6月に市内の128世帯が「特定避難勧奨地点」に指定され、わずかな放射線量の違いが地域を分断した「伊達市」。「避難指示解除準備区域」「居住制限区域」「帰還困難区域」の3つの地域に分断され、住む人がいなくなった村内を除染作業の車両が行き交う「飯舘村」。放射能汚染が人びとや土地に及ぼす惨状を目に焼き付けながら県道12号線を東へ。八木沢峠を超え南相馬市に入りました。
一転して一般車両や人々が行き交う南相馬市の中心部、原町区。ここからは陸前浜街道と呼ばれる県道を南下。福島第一原発に近づくほど汚染がひどくなっていきます。「避難指示解除準備区域」に入ると道の両側の至る所で住宅除染がおこなわれ、耕作されない田畑が延々と広がっていました。この奇妙な風景も原発事故が生み出してしまったものなのです。暗澹たる想いの中、小高区中心部で右折。開通した常磐自動車道をくぐり、県道34号・相馬浪江線をさらに南下すると、森の中に黄色いバリケードが見えてきました。ここから先は「居住制限区域」。南相馬市小高区と浪江町の境界にあたる小さな峠にはバリケードが設置されていました。
この小さな峠の左手の小高い丘に草原が広がっています。「希望の牧場」です。牧場の入り口からゆるい坂道を上って行くと、「3.12 浪江町 無念」と書かれた大きな貯水タンクと赤いプレハブ小屋が見えてきます。草原では何十頭もの牛たちが、ときおり鳴き声をあげながらもくもくと草を食んでいました。
アポイントなしの訪問でしたので、どうしたものかと少々思案しましたが、思い切ってプレハブのドアのところに書いてある吉沢さんの携帯に電話することにしました。「しばらくしたら行けるから、ちょっと待ってて欲しい」と吉沢さん。この日、浜通りは真夏を思わせる天気で日差しが強く、白い雲がぽかりと浮かぶ晴れ渡った空のもと、元気そうな牛たちを眺めながら待つことにしました。ここは第一原発から北西へわずか14キロ。牧場の南端からは放射性物質の排気塔が望める位置にあります。吉沢さんが代表を務める「希望の牧場」は、旧警戒区域内に取り残された被ばく牛、約300頭を飼育しているのです。
2011年、放射能汚染により立ち入り禁止となった地域では、たくさんの動物たちが餓死、生き残っていた家畜たちには殺処分指示がだされるという悲惨な出来事が起こってしまいました。吉沢さんは国・農水省の殺処分指示に抵抗し、被ばくした牛を飼い続けています。牛たちは一個約300キロもある牧草ロールを一日に8~10個も食べます。一日の牧草代だけでも3万円!これだけでも年間1000万円以上もかかってしまいます。ここの牛たちは肉牛として出荷されることはないのです。これだけのお金をかけてでも牛を飼い続ける理由はなんなのでしょうか?
やがてブルドーザーに乗って現れた吉沢さんに、プレハブの中に入るように誘われ、「いまちょうど暇だから」と、いただいた缶ジュースを飲みながら、お話を伺うことができました。
牛たちの中には、白い斑点が浮き出ているものが何頭か見えました。ここには約20頭の牛に現れ、農水省も調査に乗り出していますが、原因は今のところ判っていません。2013年8月からは、東北大学加齢医学研究書の福本学教授(病理学)のチームが被ばく牛の継続的な調査を始めました。その意義について福本教授は、「汚染された土地で、汚染された牧草や水を摂取し続けた牛にどんな影響が現れるのか。世界的にも貴重なデータが得られるはずだ」としています。吉沢さんも「周囲からは金にもならないことを、いつまでばかやってるんだと言われてさ、毎日考えるんだよ。牛を生かす意味を。被ばく牛は原発事故の生きた証だ。生かし続けることで、いつかきっと人の役に立つことができると信じている。」と。
私は屠蓄場に勤務しています。肉牛は通常2年ほどで食肉となりますが、幸か不幸かここの牛たちは「いま」生きているのです。原発事故が起きていなければ、この牛たちはもうすでにこの世にはいなかった存在なのです。「希望の牧場」という命名には、「生きてさえいれば、希望はある」という気持ちが込められていると吉沢さんは言います。私が職場で毎日見ている牛たちに比べ「希望の牧場」の牛たちは、活き活きとしていて眼が輝いています。きっと牛たちも明日への希望を感じ取っているのだと思いました。
吉沢さんは約一時間にわたり、いろんな応援グッズや写真が展示されているプレハブの中で、事故のときの状況や避難命令後の当局の動き。その後の牛の飼料を確保することの難しさや殺処分を押し付けようとする役人との戦いなどなど、いろんな話を交えながら滔々と語ってくれました。
自分も住んでいた浪江町の将来については、「大人なら1マイクロ(シーベルト/毎時)くらいならなんてことはない。高齢者は帰してやったらどうか。仮設は過酷だ。暑いし寒いし狭い。息が詰まる。だから自殺者が出るんだ」と。さらに、「浪江にはもう未来はない。老人だけの町にして、寂しいけど孫に会いたい人はこっちから会いに行くしかない」と、悲しい表情で嘆いていました。
そして、これからの反原発運動につて、「福島と沖縄の問題は根っこは同じだ。これからはアメリカ軍の基地問題なども絡め、若者たちに訴え続け、反原発への指示を拡げていきたい。地方での粘り強い運動も大事だ。園田さんも四日市で頑張ってください」とエールをいただきました。
その吉沢さんが被ばく牛を模した「ベトコラ号」に乗ってやってきます。「3・6さようなら原発三重パレード」への参加を快諾していただきました。全国各地を精力的にまわる吉沢さん。いつも独特でユーモラスな語り口でイベントを盛り上げます。初の三重県入りで、3月6日も「吉沢節」が炸裂すること間違いなし!私も再会するのが楽しみです。ぜひ皆さんお集まり下さい!!
注: 文は3月6日のイベントに向け寄稿したもので、「原発おことわり三重の会」の「はまなつめ」No36(2月1日発行)に掲載されました。










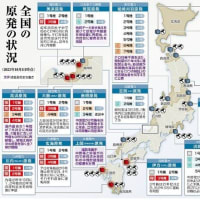
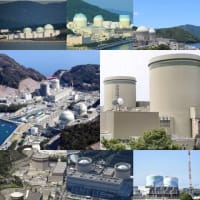








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます