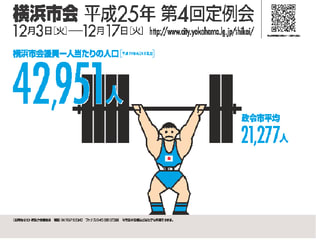◎横浜の駅の中で、昔ながらの駅舎は「奇跡」の駅舎。

写真は、私の事務所から3分程にあるJR横浜線の大口駅西口の駅舎です。古いし、快速も通過してしまうローカルなイメージ感だけを強くしていました。しかし、実はこの「駅舎」の存在は、横浜というタイトルの本に紹介をされていましたが大都市に「奇跡」のように残るとされていました。

大口駅の駅舎は、昭和22年の駅開業と同時に建てられた建造物。戦後に流行した直線を基調にしたモダニズム建築で、建物を覆う大屋根をスマートな片流れにしたお洒落なものだそうです。
現在、横浜市内のほとんどの駅が、橋上化や商業施設と合体しているので、指摘されると確かに珍しいものであると思います。

線路挟んだ大口駅東口にも、小ぶりの駅舎が残っています。こうした風情は、大切にしたいと思いますしローカル一転、「誇り」となりました。

写真は、私の事務所から3分程にあるJR横浜線の大口駅西口の駅舎です。古いし、快速も通過してしまうローカルなイメージ感だけを強くしていました。しかし、実はこの「駅舎」の存在は、横浜というタイトルの本に紹介をされていましたが大都市に「奇跡」のように残るとされていました。

大口駅の駅舎は、昭和22年の駅開業と同時に建てられた建造物。戦後に流行した直線を基調にしたモダニズム建築で、建物を覆う大屋根をスマートな片流れにしたお洒落なものだそうです。
現在、横浜市内のほとんどの駅が、橋上化や商業施設と合体しているので、指摘されると確かに珍しいものであると思います。

線路挟んだ大口駅東口にも、小ぶりの駅舎が残っています。こうした風情は、大切にしたいと思いますしローカル一転、「誇り」となりました。