素数と無限の話:その2で、背理法という証明方法を扱いました。
今回はその背理法について話そうと思います。
【背理法】とは
ある命題Pについて、Pの否定を仮定すると矛盾が起こることを示すことで、元の命題Pを証明する方法です。"Pではない"が間違っている=Pは正しい、ということです。
例えば、【アライは170cm以上である】という命題を背理法を使って証明してみましょう。
まずは、証明したい命題の否定である【アライは170cm未満である】という事を仮定します。
仮定すると言うことは、ここから先の議論ではアライは170cm未満の人間として扱います。
今、アライは自分が170cm未満だと思って生活しています。ある日、高さが170cmの位置にある物干し竿をくぐろうとします。アライは自分の身長が170cm未満だと思っているので、普通に歩いてもぶつからないと考えてます。しかし実際、物干し竿に頭をぶつけてしまいました。
"170cm未満のアライが、高さ170cmの位置にある物干し竿に頭をぶつける"というのは、明らかにつじつまが合わない、つまり矛盾しています。
ここで、物干し竿が170cmの位置にあること自体は間違いが無いとすると、間違いなのはアライが170cm未満ということのです。
よって【アライが170cm未満である】という命題は間違っているということがわかったので、【アライは170cm以上である】という命題が証明されました。めでたしめでたし。
以上が背理法の証明方法の流れです。流れ自体はいたって簡単で
Step1 証明したい命題の否定を仮定する。
Step2 「命題の否定」を仮定した状況で、矛盾を導く。
という2ステップで終わりです。
前回示した【素数は無限個存在する】や【は無理数である】という命題は、背理法を使う有名な証明方法です。とくに後者は大学受験数学の参考書でもかなりの頻度で出現する問題です。
大学レベルの数学でも、背理法は頻繁に出てきます。背理法っていう言葉を書くのを省略するくらい、頻繁に出てきます。数学的帰納法と並んで、数学においてはかなり強力な証明方法と言って良いでしょう。(帰納法についてもそのうち書きたい…)
ところで、今のところ当たり前のように背理法について話をしてきましたが、この背理法という証明方法は、本当に正しいんでしょうか?
もちろん教科書にも書いてありますし、授業でも習いました。でもそれは本当に正しいことですか?
地球は丸いと教わりました。地球が球体である理屈も習いました。宇宙から撮影した写真や映像で、地球が丸いことも見ていると思います。
でも自分の目で確かめてもいないのに、自分の頭で考えてもいないのに、本当に地球は丸いと言えるんですか?
現代の技術を用いれば、写真や映像の加工は簡単に出来ます。もし情報操作が行われていて、真実が弾圧されていて、実は天動説が正しかったなんてオチは、本当にありえない話なんでしょうか?
話が逸れました…
背理法を支えているのは、"Pではない"が間違っている=Pは正しいという論理です。
この論理は言い換えると、【"Pの否定"の否定=P】ということになります。
そして、この論理を支えているのが排中律です。
次回はこの排中律について、話をしていこうと思います。











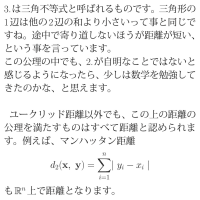

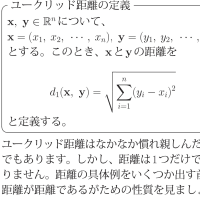
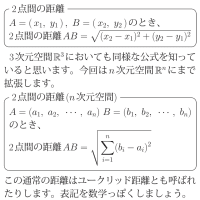

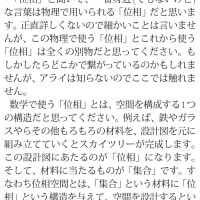
もうちょいすごくなれるように、精進します。