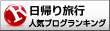祇園祭山鉾巡行が近づいた7月10日頃より各山鉾町で山鉾の組み立てが始まります。

山鉾建(やまほこたて)は大きな筐体を複雑に組み立てる鉾や曳山、簡単に組み上げられる傘鉾などそれぞれ工程が異なるので組み立てが始まる日は異なります。

昔から伝わる「縄がらみ」と呼ばれる手法で、専門の大工方が釘を一本も使わずに重さが12トンもある鉾を組み上げます。
大きな鉾の組み立てには3日程も要するそうです。

20メートルほどもある長い真木(しんぎ)を空に向かって立ち上げる場面は圧巻です。
真木をつけた櫓(やぐら)を道路に寝かせ、太く長い綱を人力で引き垂直に起こします。
立ち上がった瞬間には見物の人達からいっせいに拍手が湧き上がります。
形態の異なる船鉾は鉾建ての方法も異なるようです。

組み上がった鉾や山は飾り付けをして、それぞれの定められた日に曳初が行われます。
前掛、胴掛、見送、水引などの豪華な織物の飾り物は17日の巡行本番に使われる物と、それまでに飾られているものとは異なることが多いので、興味のある方は14日、15日頃の昼間にも各鉾町を見物されることをおすすめします。

山鉾の縄
祇園祭の山鉾(やまほこ)の組み立てに使われるわら縄作りが、福知山市三和町友渕の田尻製縄所で急ピッチで進められている。

今週末までに約120メートルを巻いた束500個を作るという。

詳細は公式サイトをご確認下さい。
(http://www.gionmatsuri.or.jp/)

前祭 鉾建て:7/10~/14
後祭 鉾建て:7/18~/21
(※毎年同じ日程です)
※写真は全て過去のものです。